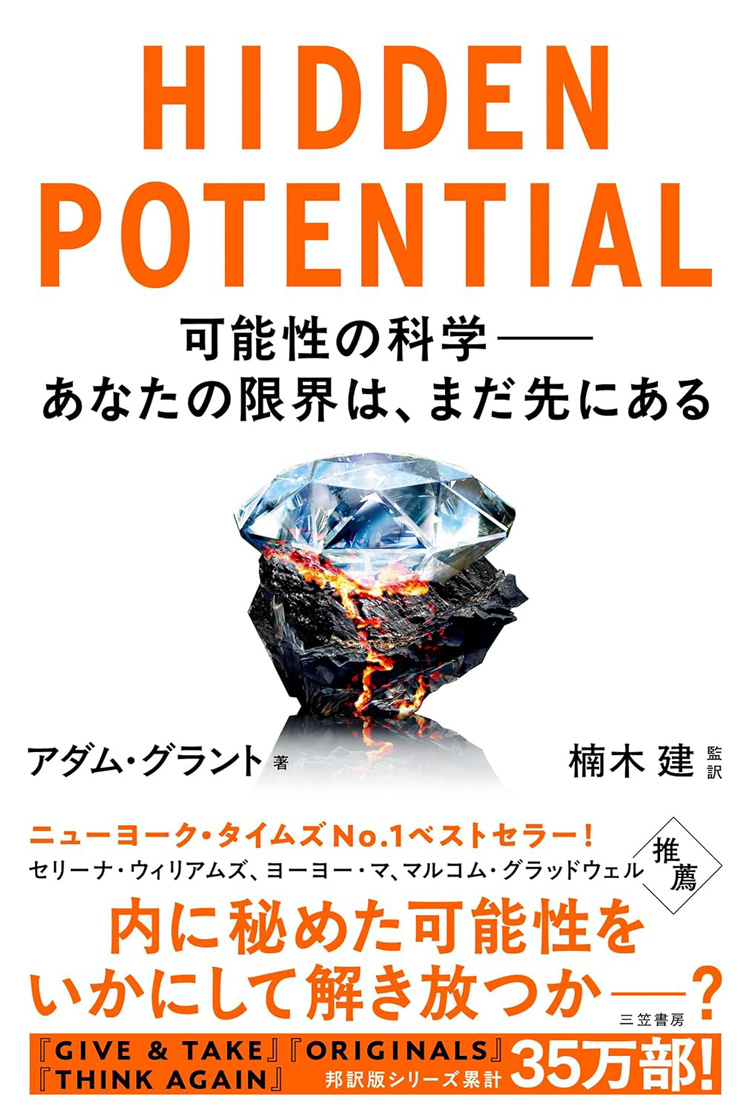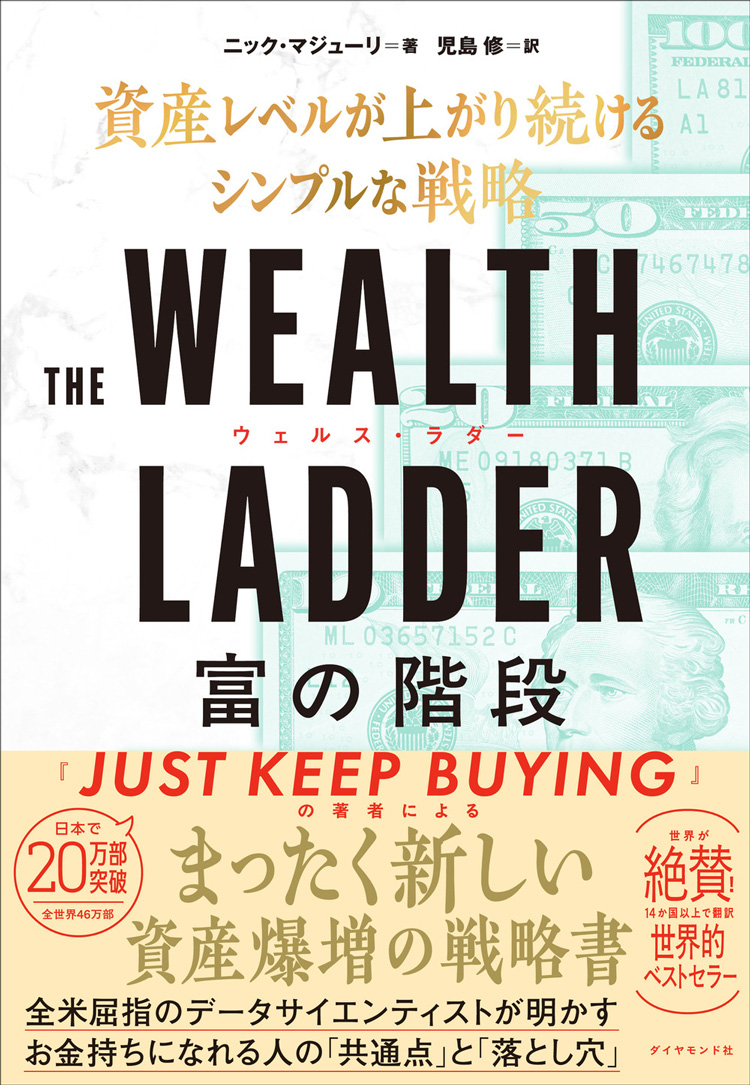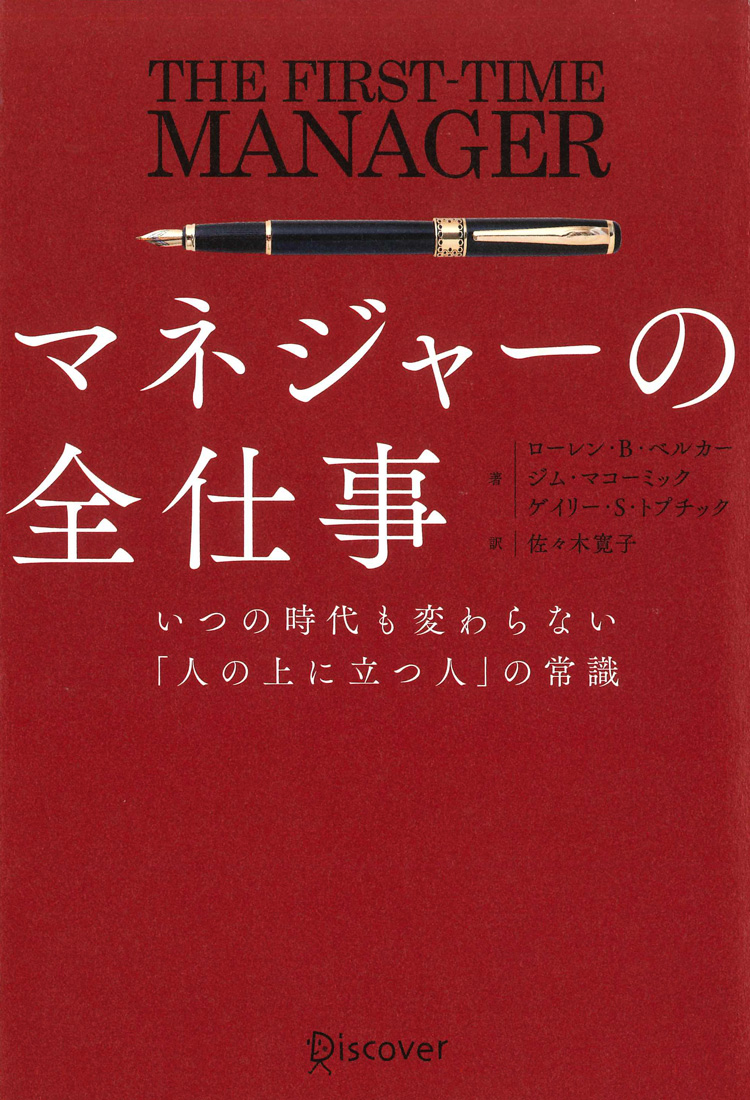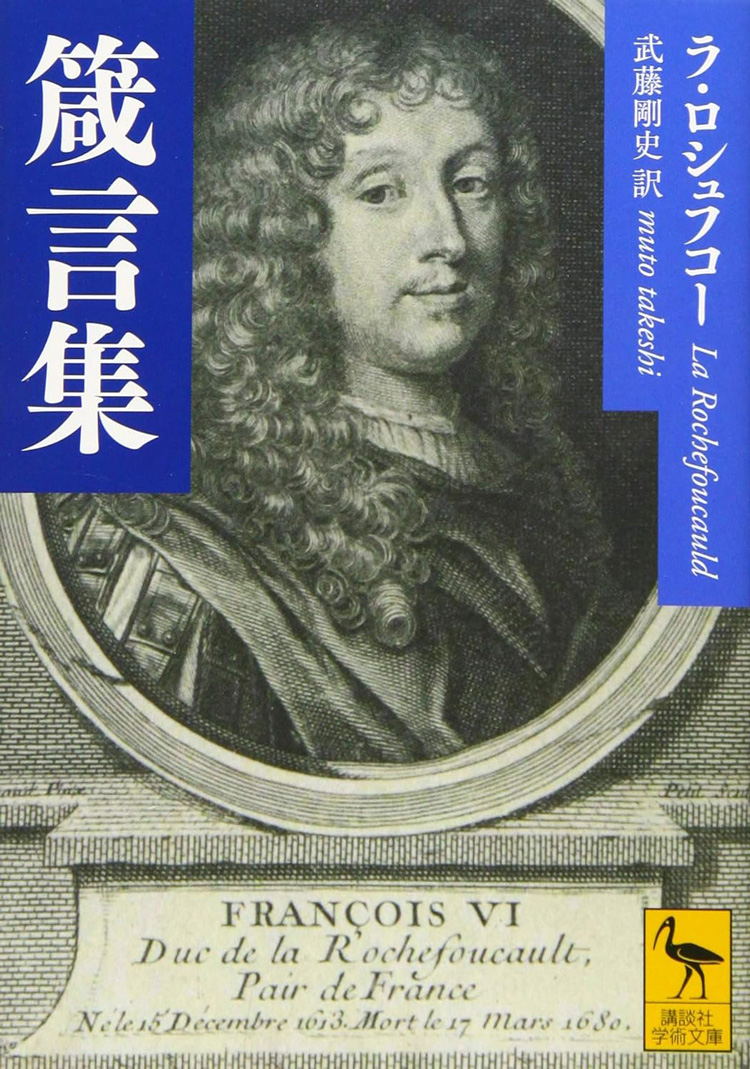全ての厳選書・要約
-
最新号の10冊
最新号に掲載している“一読の価値ある新刊書”10冊の内容をご覧いただけます。
-
おすすめの特集
編集部が独自のテーマを設定し、5冊程度の良書を選出して紹介します。
-
TOPPOINT NOTE
編集部員が思わず読書メモを取った、良書の中の“一節”や“物語”を紹介します。
-
今週のPick Up本
編集部員が「いま改めてお薦めしたい本」「再読したい名著」をPick Up!
-
オールタイムベスト
各ジャンルにおける必読の名著10冊を編集部が選定。選書は随時更新します。
-
TOPPOINT大賞
1万人以上の定期購読者を対象とした読者アンケートで決定された、半年ごとのベストビジネス書です。

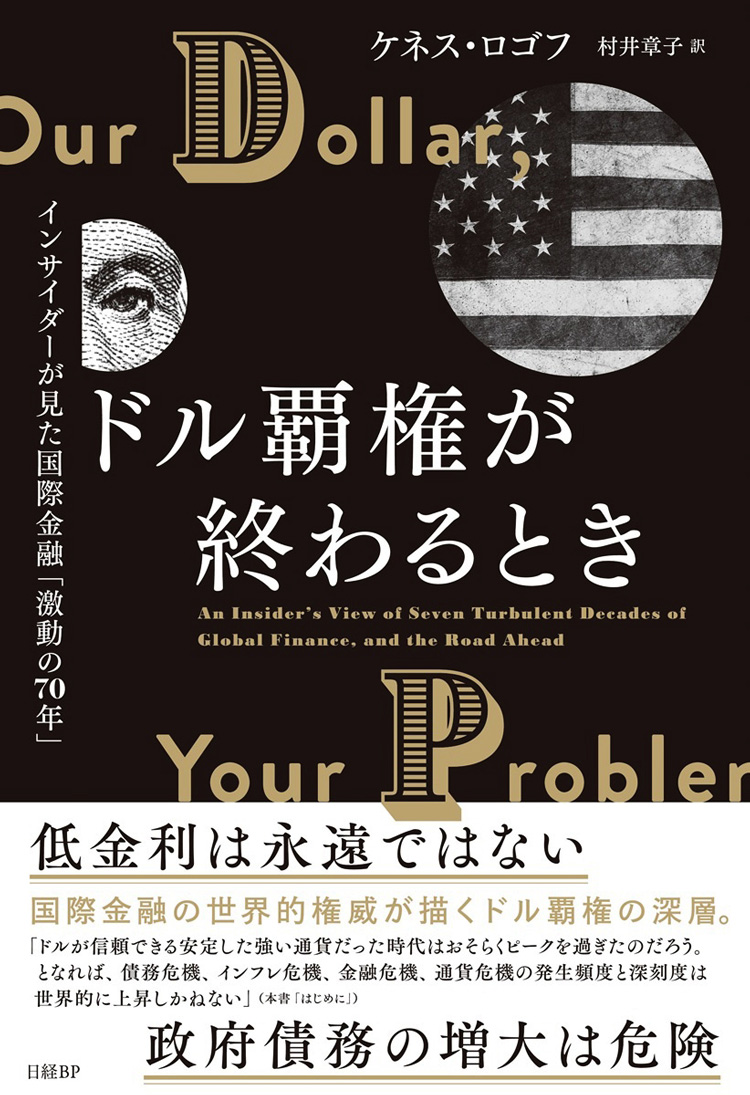









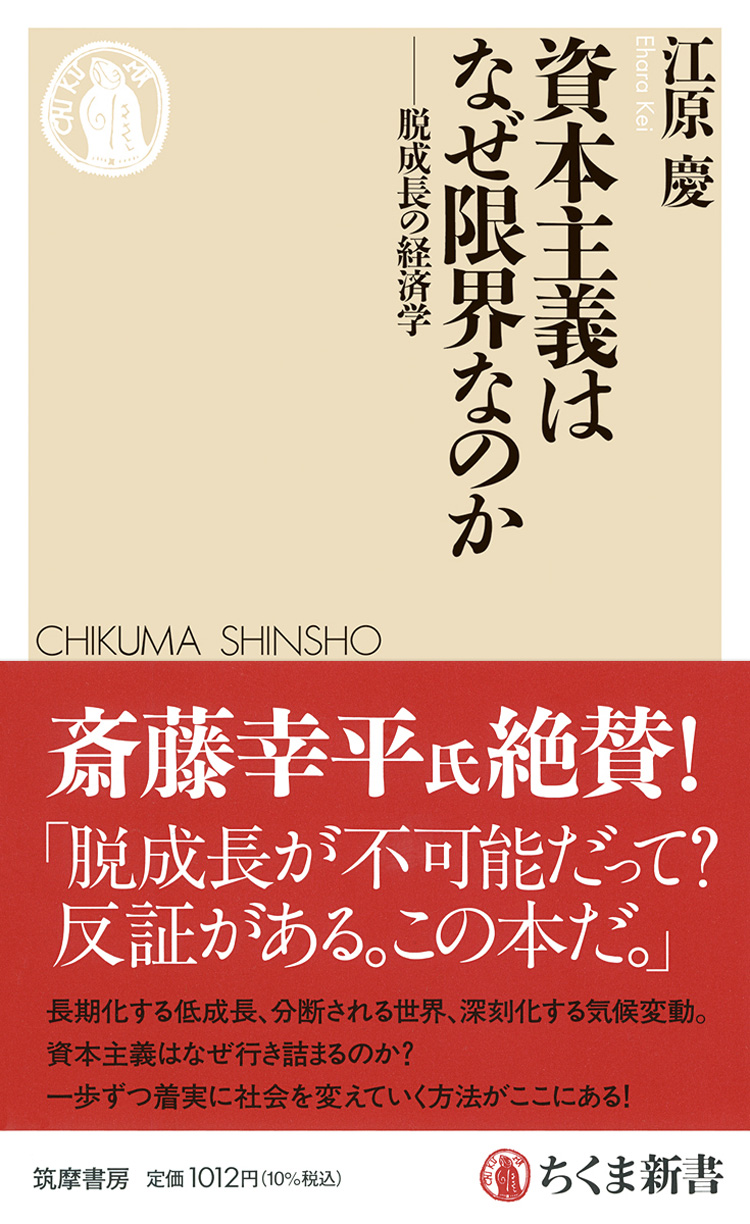
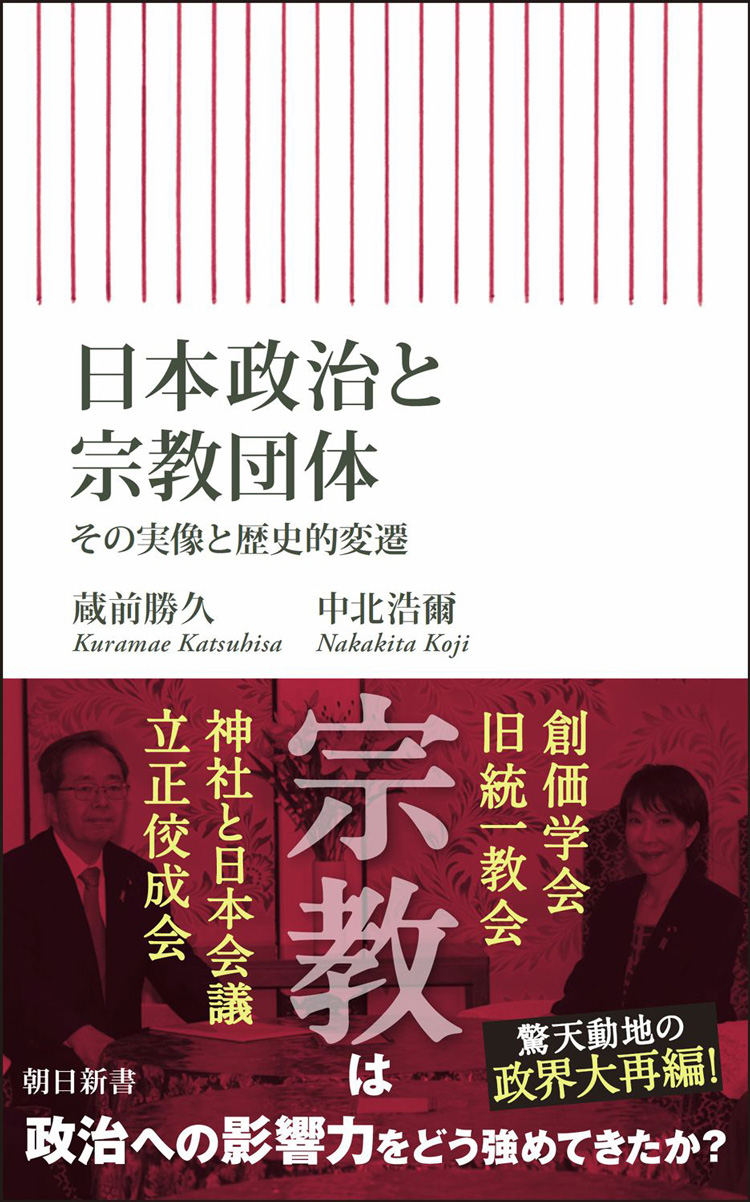
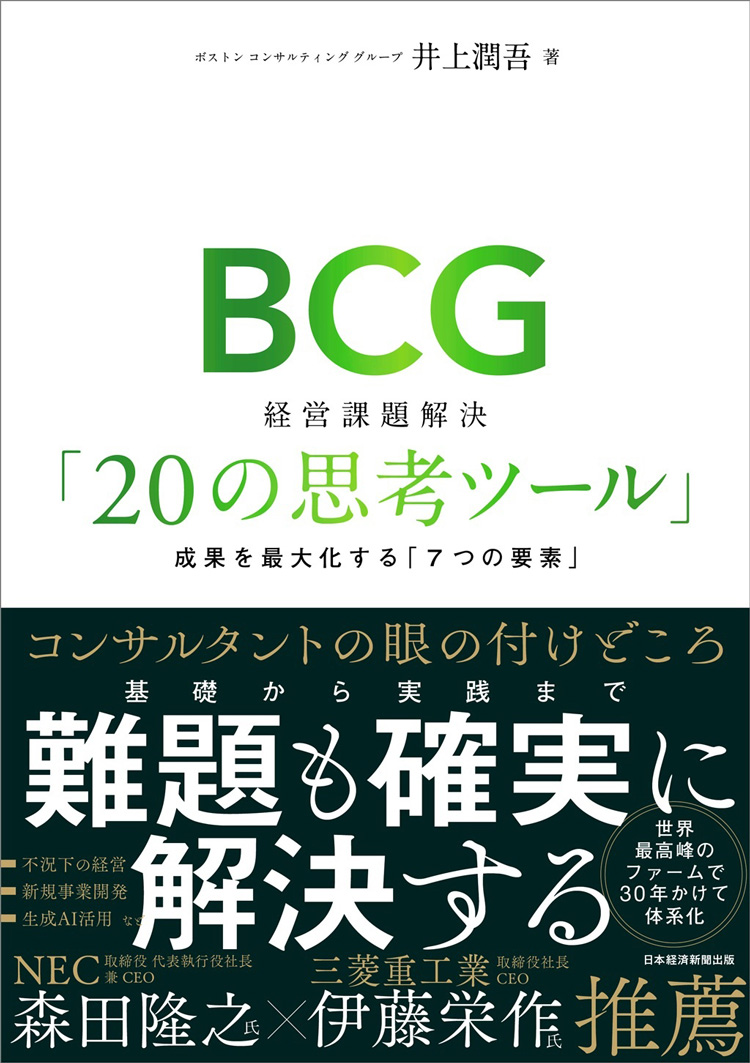
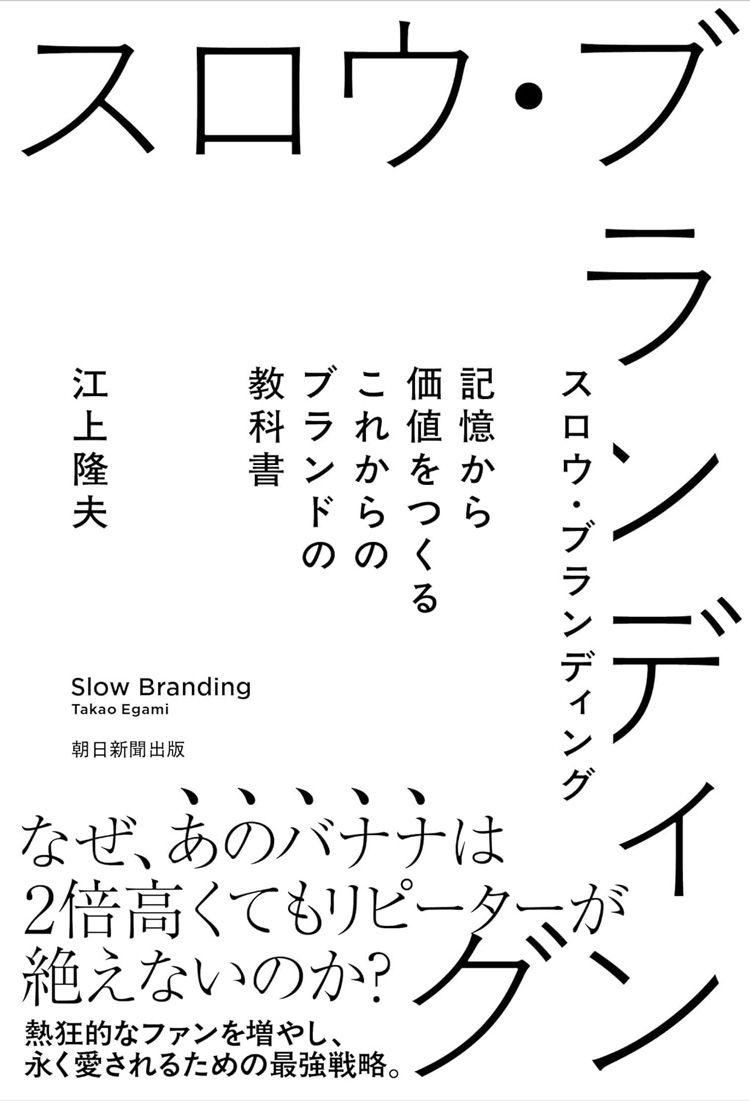
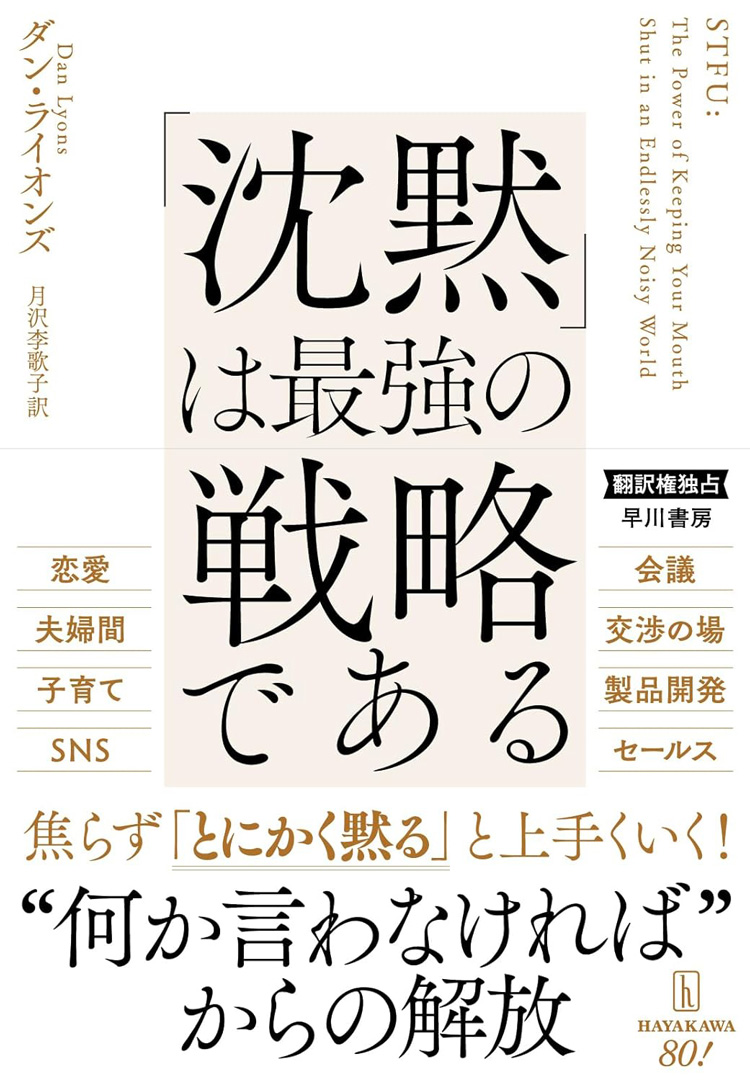
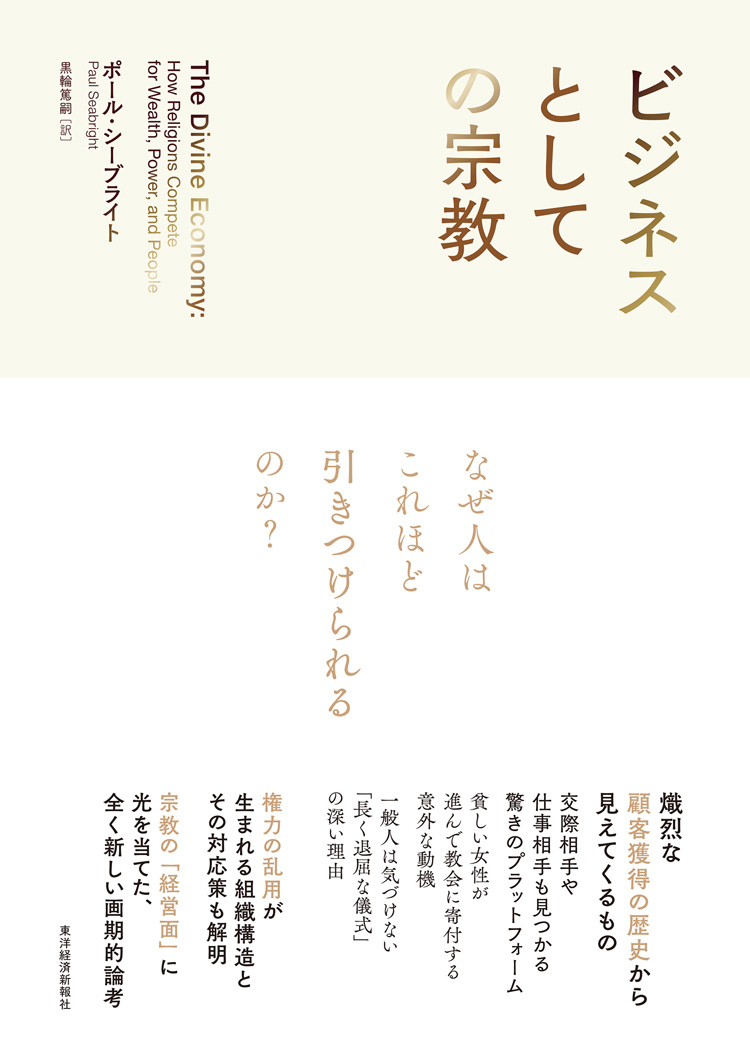
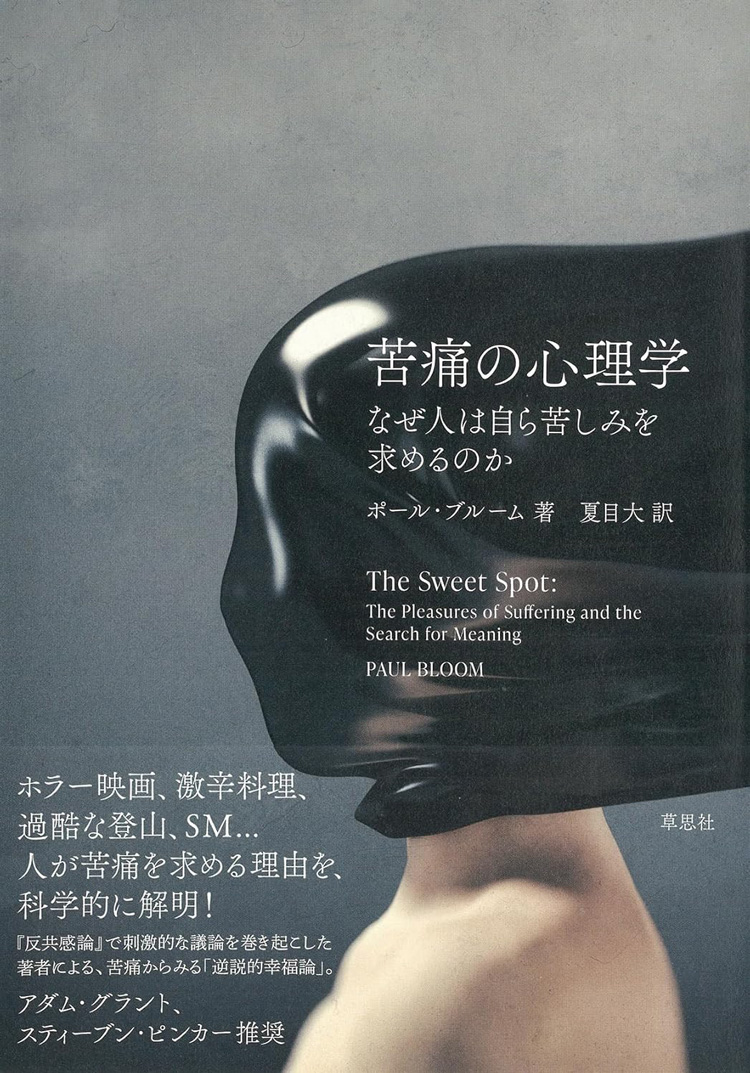
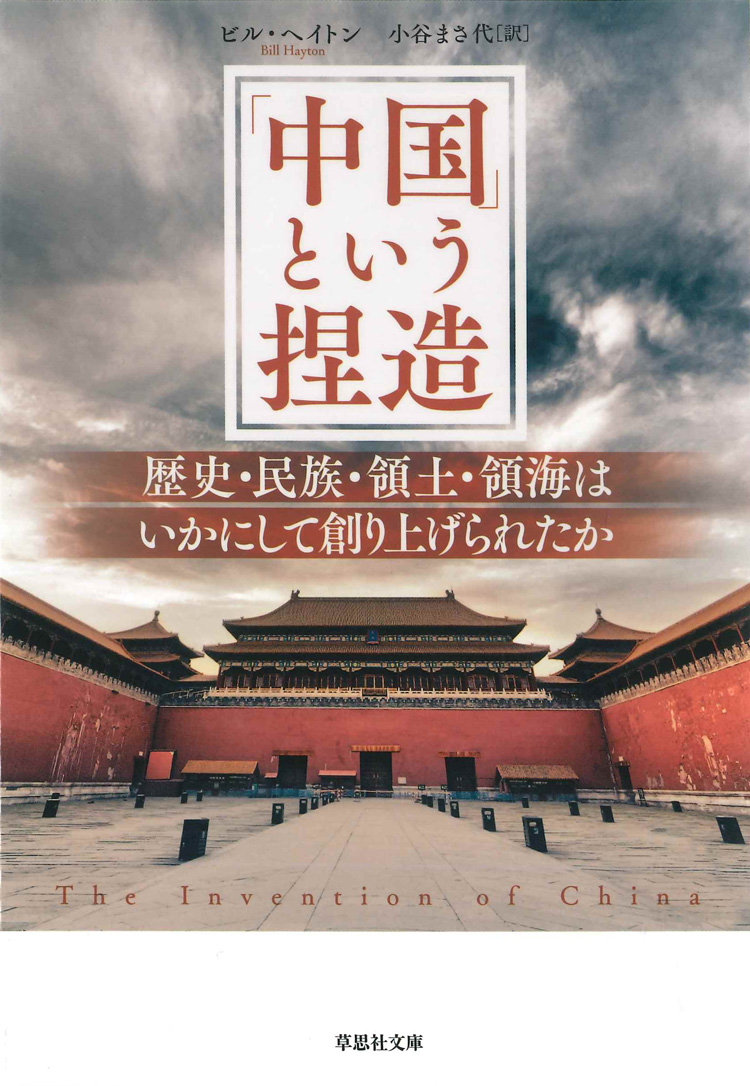
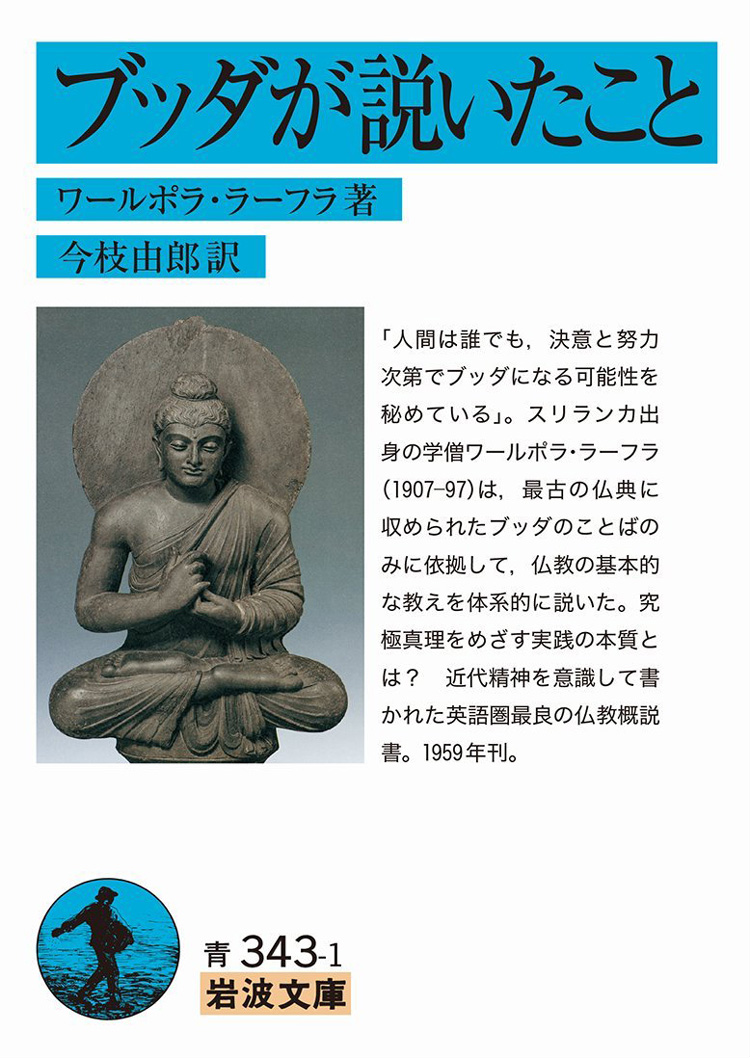

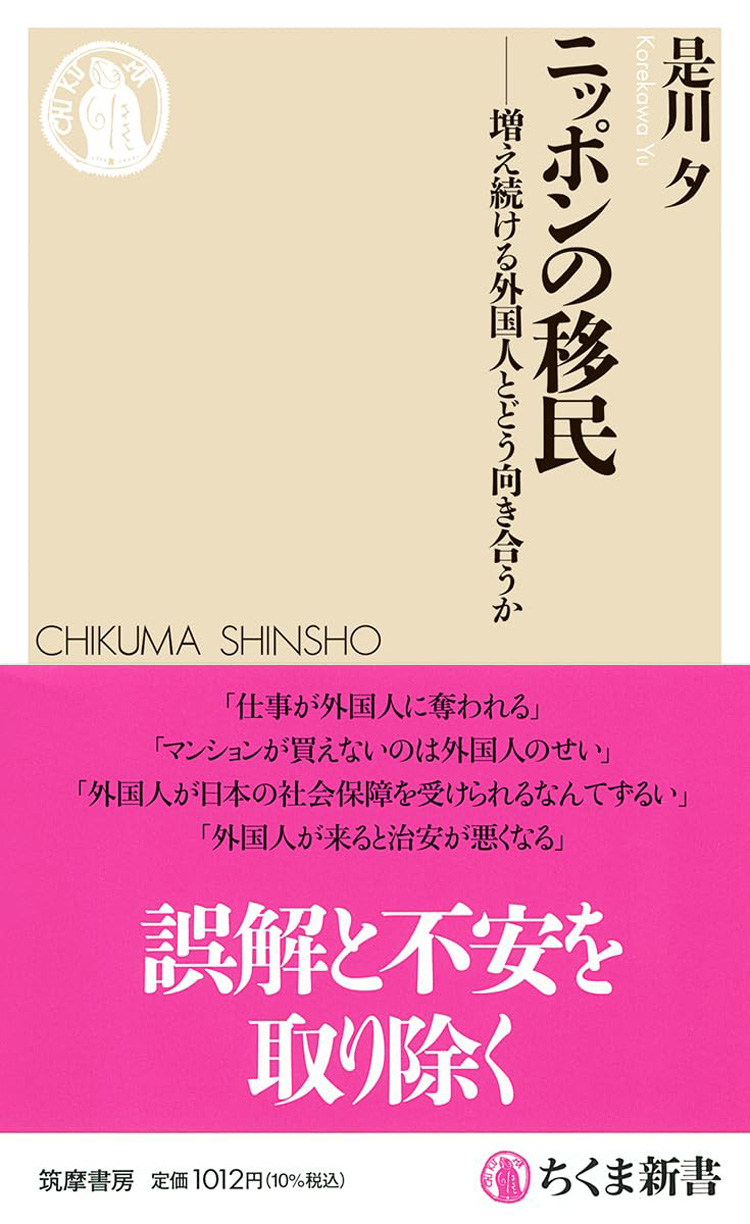


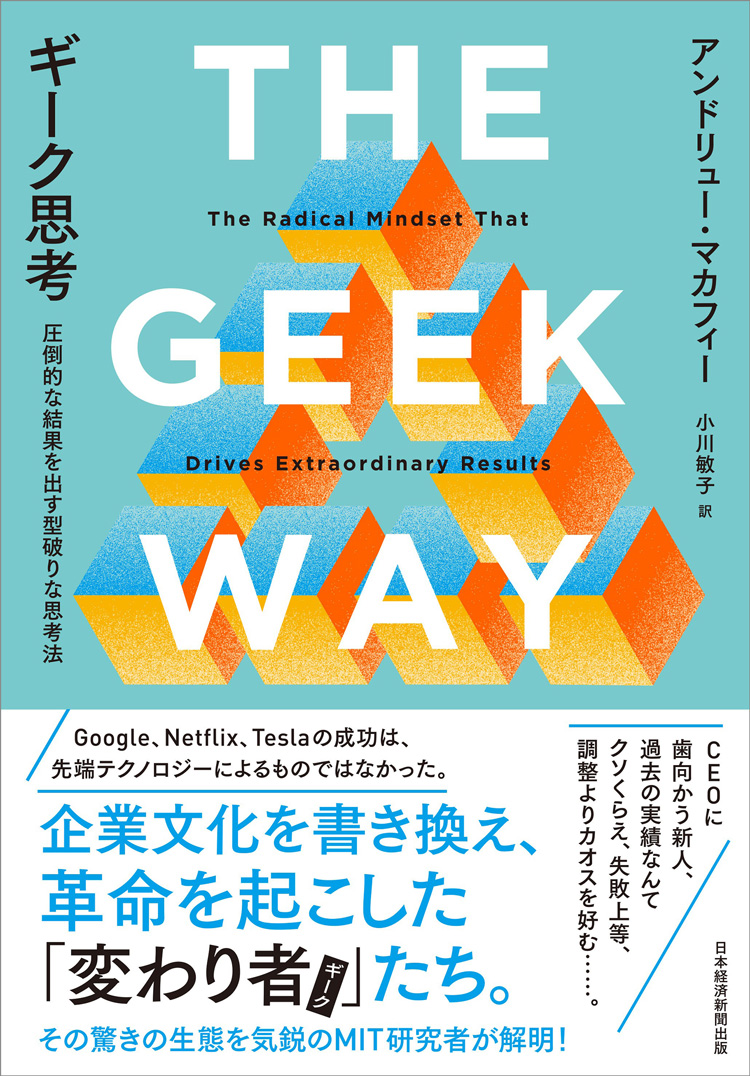
![WHYから始めよ! [改訂版] インスパイア型リーダーはここが違う](https://www.toppoint.jp/uploads/cover/20251218085614-20260106.jpg)