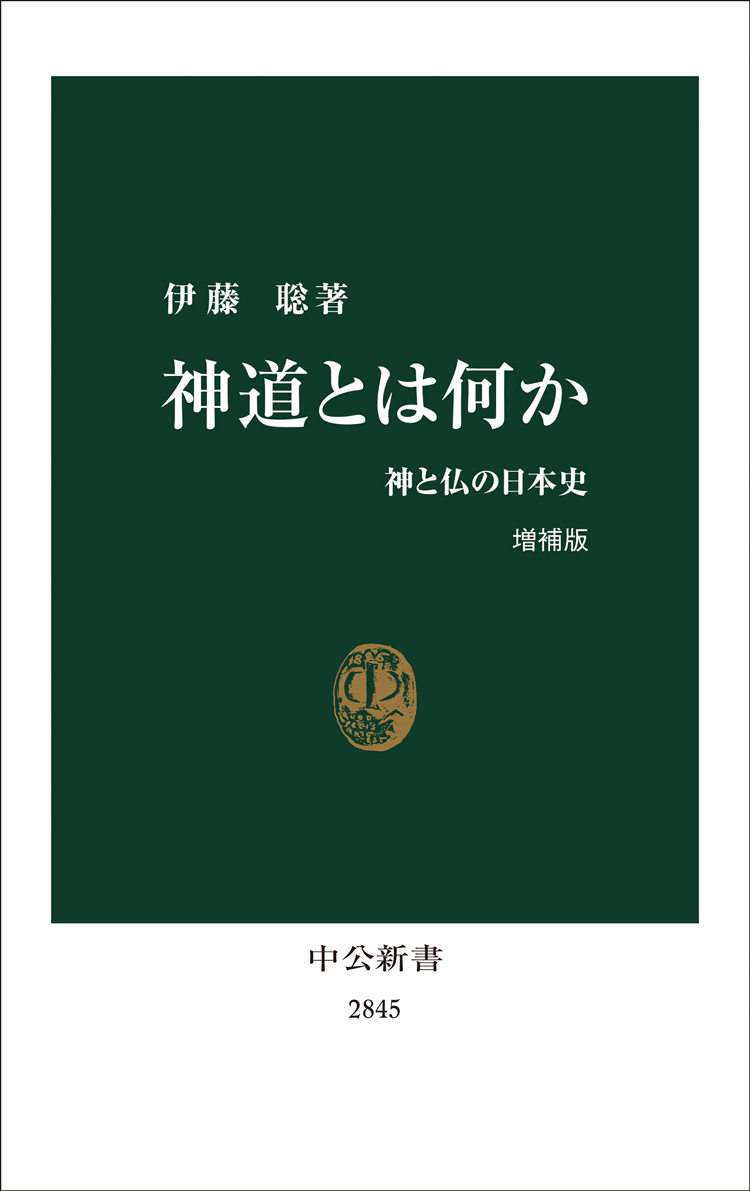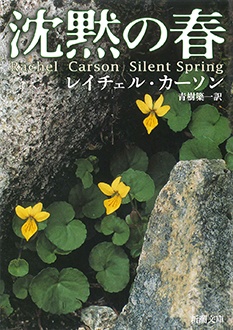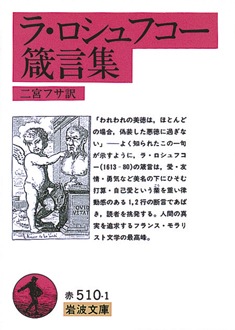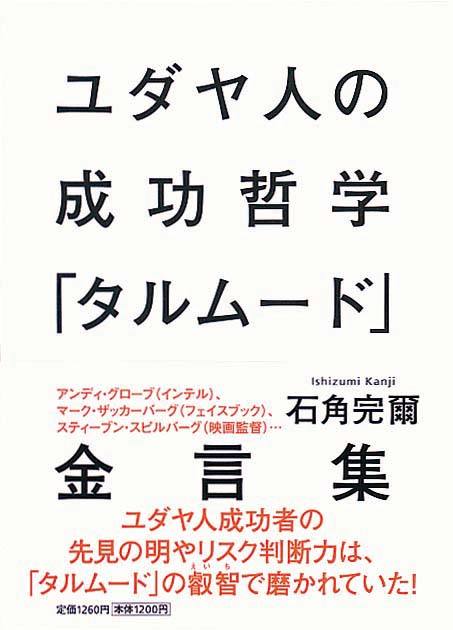2025年8月号掲載
神道とは何か 増補版
- 著者
- 出版社
- 発行日2025年2月25日
- 定価1,210円
- ページ数343ページ
※『TOPPOINT』にお申し込みいただき「月刊誌会員」にご登録いただくと、ご利用いただけます。
※最新号以前に掲載の要約をご覧いただくには、別途「月刊誌プラス会員」のお申し込みが必要です。
著者紹介
概要
「神道」の歩みについて、わかりやすく説いたロングセラーの増補版。古代~近世、仏教と関わりながら展開してきた、日本の民族宗教の成り立ちをたどる。その形成史から浮かび上がるのは、明治初年の廃仏毀釈以前の神社・祭式の姿は、今日とは大きく異なるということ。日本の“神(カミ)信仰”の通史が概観できる好著だ。
要約
日本の「神」とは
現代に生きる我々は、「神道」という言葉を「日本の民族宗教」を指す言葉として使っている。だが、それは正しい認識だろうか ―― 。
明治政府が進めた「神道の国教化」
慶応3年12月9日(西暦1868年1月3日)、「王政復古」の大号令が布告され、明治国家の歩みが始まった。この“復古”とは、神武天皇の時代の「祭政一致の政体」に回帰することであり、そのために新政府が目指したのが「神道の国教化」である。
神道国教化の目的は、外に向けてはキリスト教の流入阻止、内においては神道を純粋な姿に復すること、つまり、神仏習合的信仰(日本古来の神信仰と仏教が融合した現象)の排除(神仏分離)にあった。そして、社僧(神社に所属する僧侶)の還俗が命ぜられ、寺院の廃合などが進められた。その結果、多くの堂舎・経巻・仏像が破却された。
現在、我々が目にする神社・祭式は、この時以来のもので、たかだか百数十年を経たに過ぎない。
「カミ」の語義
漢字の「神」は「カミ」と読まれ、日本の神霊的存在の総称として定着している。では、カミは、元来どのような意味を持つ語だったのであろうか。
近世の神道家や国学者たちは、カミの語源を様々に解釈した。「かがみ(鏡)」「かみ(上)」「かしこみ(畏)」「かみ(彼霊)」…。
国学者の本居宣長(1730~1801)は、天地・自然の何ものであっても「すぐれた徳」があるものをカミと呼ぶ、とした。すぐれた徳とは、善いことだけではない。凡人より優れた力を持ち畏怖すべき存在がカミであり、貴賤・強弱・善悪にかかわりなく様々なカミがあるとした。
この定義は、現在においても、日本の神の性格を的確に示したものとして、しばしば取り上げられる。善悪にかかわらず、何であれ「カミ」になる可能性があるとしていることは重要な指摘だ。
カミと「マツリ」
そして、カミを招き、供物等を捧げる行為が「マツリ」である。その場所(祭場)は、神霊が依り付くところで、岩や樹木であることが多い。また、鏡や剣のこともある。さらに、特定の山や島が、ご神体と見なされる場合もある。このような祭場が「ヤシロ」であり、神社の原型である。
あるカミを祭るのは、祟りを恐れるがゆえである。正しくカミに仕え祭ることが、古い時代においては政治そのものであった。だから、政治を「マリツゴト」というのである。