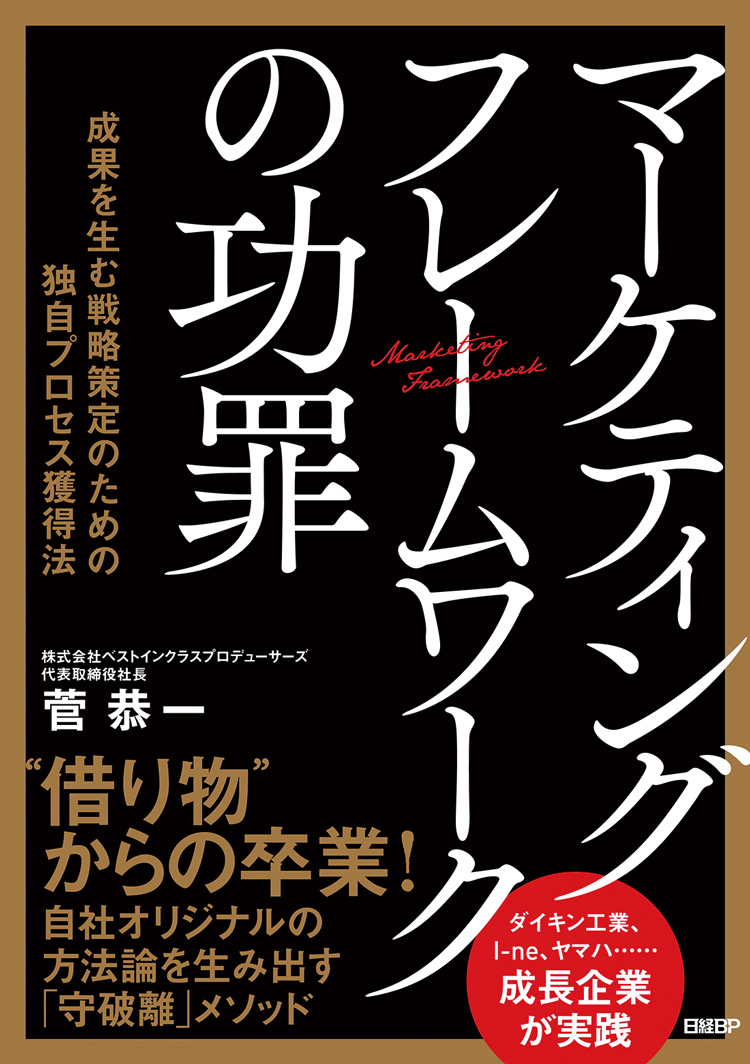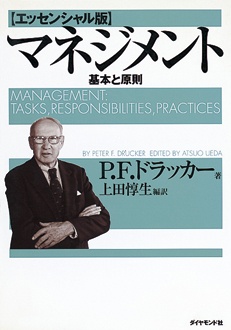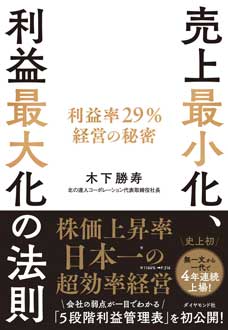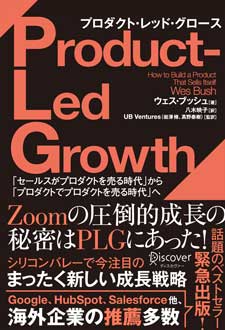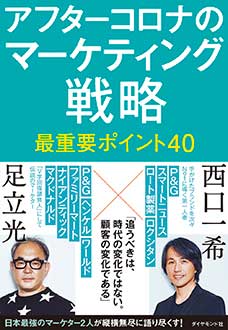2025年8月号掲載
マーケティングフレームワークの功罪 成果を生む戦略策定のための独自プロセス獲得法
著者紹介
概要
近年、「マーケティングフレームワーク」を導入する企業は多い。しかし、効果がないと嘆く企業もまた多い。本書は、つまずく原因を明らかにするとともに、適正に機能させるためのプロセス、「守破離」を紹介。“型”を学び(守)、改良を加え(破)、自在に使いこなす(離)。このメソッドを取り入れれば、組織の競争力が高まる!
要約
幻滅に陥るケース
マーケティングのフレームワークは、効率的に成果を上げるための強力なツールであるはずだ。しかし、現実には、フレームワークを導入しても成果が上がらず、期待外れに終わるケースが多い。
なぜ、うまくいかないのか? その背景として、次のようなケースが挙げられる。
自社のビジネスモデルにフィットしない
企業の中で、フレームワークを導入した後に「自社のビジネスモデルにフィットしない」という声が挙がることがある。この場合、柔軟な運用が十分に考慮されていないことが背景にある。
電通が提唱した「AISASモデル」は、その一例だ。これは「Attention(注意)、Interest(興味)、Search(検索)、Action(行動)、Share(共有)」の頭文字を取ったフレームワークだ。
このモデルは、デジタル時代の消費者行動を捉えるための有効な枠組みとして、多くの企業で採用された。だが、実際には全てのビジネスモデルに適用できるわけではない。例えば、洗剤などの日用品では、消費者は価格等によって意思決定することが一般的で、AISASが示す「検索」「共有」といった行動が発生しないケースが多い。つまり、AISASが示す一連のステップを全てたどらない。
フレームワークは、「型にはめるための枠組み」ではない。自社のビジネスモデルや消費者の行動特性に合わせて柔軟にアレンジすることこそが、その有用性を最大限に引き出すポイントだ。
特定の部署やチームに閉じた活用にとどまっている
フレームワークが組織全体で共有されず、期待された成果が得られずに「役に立たない」と評価されるケースも少なくない。
例えば、事業の主体となる部署と、宣伝・デジタルマーケティングなどの支援部署で、異なるフレームワークを活用している現場をよく見かける。
こうした場合、事業部が重視する戦略とのずれが生じ、思うように実行に落とし込めないだけでなく、部署間での摩擦が起きやすくなる。その結果、期待通りに機能しないと感じられるのである。
フレームワークの誤用と課題
マーケティングの現場では、フレームワークの誤用もよく発生する。