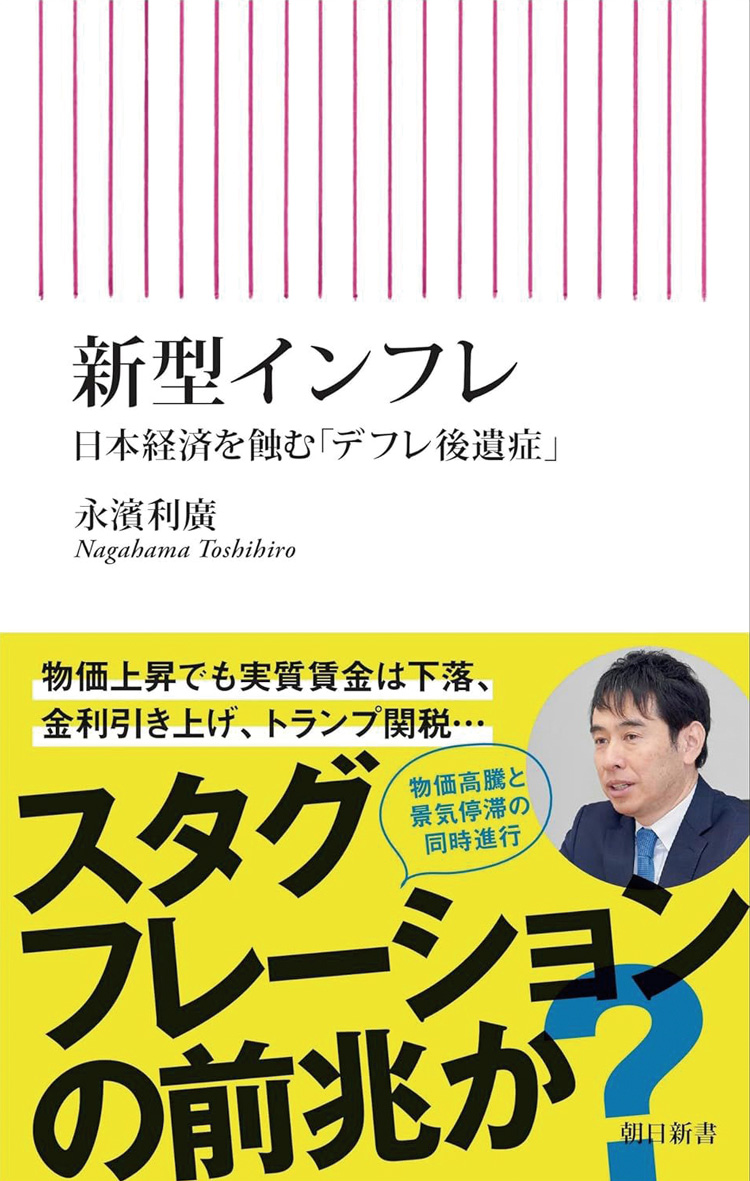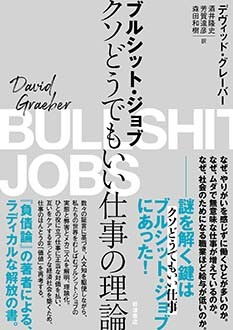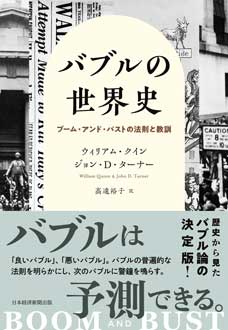2025年8月号掲載
新型インフレ 日本経済を蝕む「デフレ後遺症」
- 著者
- 出版社
- 発行日2025年5月30日
- 定価1,045円
- ページ数221ページ
※『TOPPOINT』にお申し込みいただき「月刊誌会員」にご登録いただくと、ご利用いただけます。
※最新号以前に掲載の要約をご覧いただくには、別途「月刊誌プラス会員」のお申し込みが必要です。
著者紹介
概要
長年のデフレから脱却して、インフレに転じた日本経済。賃上げの報道も目にするが、生活の豊かさを実感している声はそう多く上がってこない。なぜか? 今のインフレは、通常とは異なる“歪なインフレ”だからだ。こう喝破するエコノミストが、物価、賃金、金利の関係が複雑に絡み合った、「新型インフレ」の正体を解き明かす。
要約
影響を与え合う「賃金と物価」
2025年の春闘で、大幅な賃上げを行う企業が相次いだ。企業業績は好調で、億ションが飛ぶように売れているといった好景気を感じさせるニュースも連日報道されている。
しかし、そんなニュースにもピンと来ず、物価上昇で生活が苦しくなっている人が大半ではないだろうか。こうした歪みはなぜ生じているのか?
「経済のエンジン」 ―― 個人消費が停滞中
日本の個人消費はGDPの5割以上を占める。まさに「経済の原動力」と言っても過言ではない。しかし日本では、ずっと個人消費が抑制されている。人々が「買わない、使わない」のだ。
最新データでは、個人消費の金額は増加しているものの、これは物価上昇によるものである。というのも、2023年度以降、名目個人消費は増えているが、実質個人消費は減っているからだ。つまり、購入する量は減っているのに、物価上昇でより多くの支出を強いられている状況といえる。
個人消費を増やすポイントの1つは「賃金の上昇」である。だが、それほど単純な話ではない。
大企業の「労働分配率」は過去最低に
日本の実質賃金は一時的にプラスに転じたものの、実情は厳しく楽観視できない。名目賃金は確かに上昇し、物価上昇率を上回る月も出てきたが、これはボーナス支給によるものだ。毎月支払われる給与は依然、物価上昇率を下回っている。
企業収益は絶好調なのに、なぜ賃金は低いままなのか? その大きな要因の1つが、「労働分配率」の低下だ。これは企業が生み出した付加価値のうち、どれだけが人件費として従業員に分配されているかを示す。
企業の規模別に見ると、中小企業の労働分配率は大企業より高いものの30年前の水準まで低下している。さらに驚くべきことに、大企業の労働分配率は過去最低水準にまで落ち込んでいるのだ。
これは企業の収益が改善しているにもかかわらず、それが従業員の賃金に還元されにくくなっていることを意味する。
大企業以上に賃上げしている中小企業
一般的には「賃上げしているのは大企業だけだ」と言われている。しかし、2023年の厚生労働省「賃金構造基本統計調査」によれば、実態は逆だ。
というのも、賃金上昇率を見ると、「小企業>中企業>大企業」の順となる。