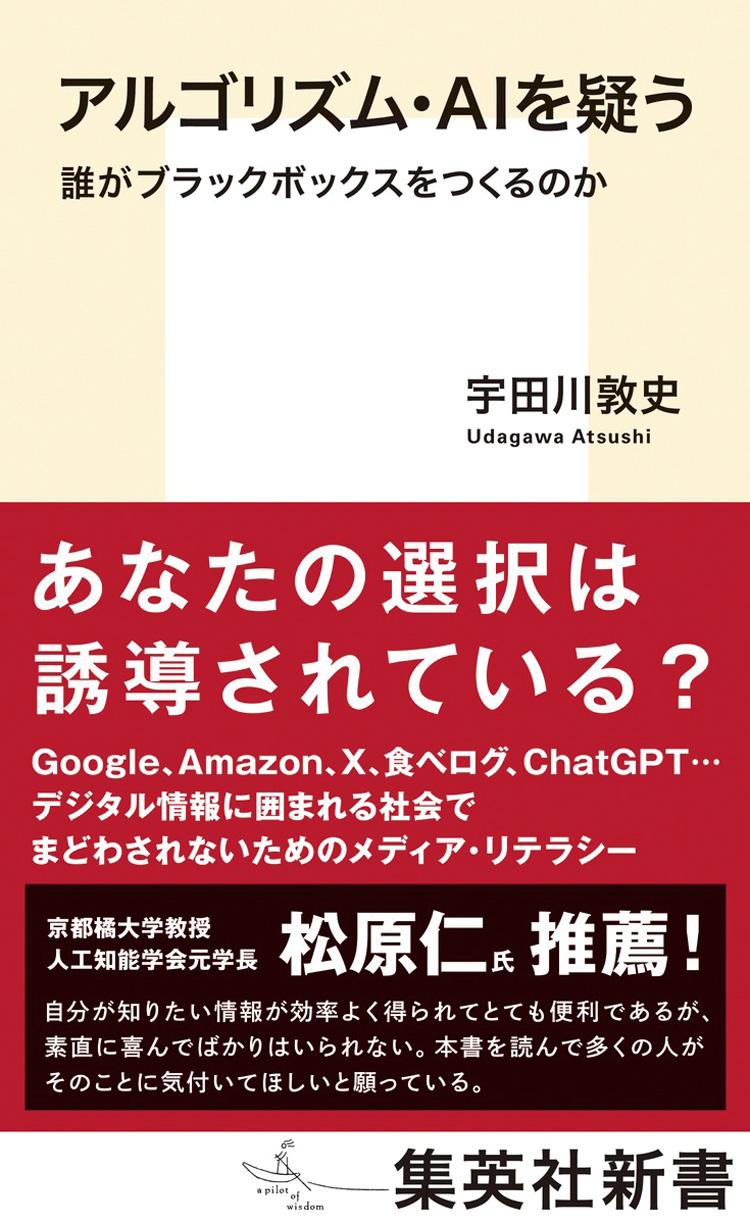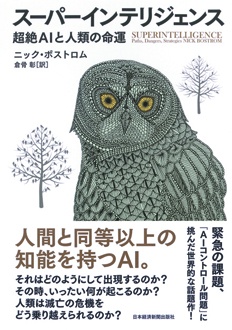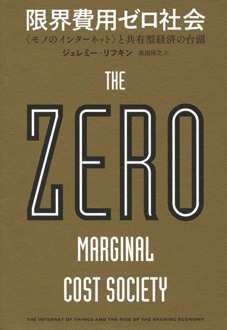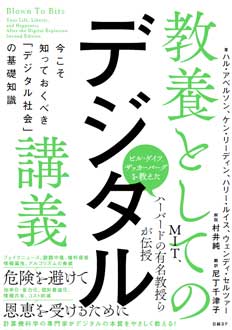2025年8月号掲載
アルゴリズム・AIを疑う 誰がブラックボックスをつくるのか
- 著者
- 出版社
- 発行日2025年5月21日
- 定価1,100円
- ページ数237ページ
※『TOPPOINT』にお申し込みいただき「月刊誌会員」にご登録いただくと、ご利用いただけます。
※最新号以前に掲載の要約をご覧いただくには、別途「月刊誌プラス会員」のお申し込みが必要です。
著者紹介
概要
SNSや検索エンジンなど、あらゆるメディアで情報の選別に関わっている「アルゴリズム」。それなしで現代社会は成り立たないといえる。一方で、その仕組みはブラックボックス化し、利用者には見えづらい。そんなアルゴリズムの内部構造を、メディア論の専門家が分析。併せて、今日必要なメディア・リテラシーのあり方も示す。
要約
アルゴリズムとは
私たちの生活には、デジタル・メディアがあふれている。スマホやパソコン、インターネット…。これらの動作のしくみを理解する上でキーワードとなるのは「アルゴリズム」である。
料理のレシピもアルゴリズムの一種
アルゴリズムとは、本来は何らかの問題を解決するための計算手順や処理手順を広く指し示すものだ。その対象は、必ずしもコンピューター上のプログラムに限定されるわけではない。
例えば、料理のレシピもアルゴリズムの一種といえる。肉じゃがのレシピであれば、じゃがいもを切り、肉を炒めた後に野菜を加える、などの手順がある。そしてレシピに従って調理をすれば、誰でも一定の味を出せる。
出力が「正確」とはいえない
重要なのは、アルゴリズムは誰がやっても同じアウトプットになるよう誘導する手段であり、だからこそコンピューターの処理手順として採用可能な厳密さをもっている、ということだ。ここで注意すべきは、この「厳密さ」の意味である。
アルゴリズムは属人性を排除するための手段だが、どのようなアルゴリズムを採用するのか、については属人性が排除されているわけではない。
すなわち、あるアルゴリズムに従って同一の入力を処理すれば同一の出力になるが、その出力が妥当かどうかは、アルゴリズム自体の設計に依存する。そしてその設計には、設計者の主観や価値観、時には政治的な立場が含まれているのだ。
例えば、「料理研究家○○直伝の肉じゃが」は、そのレシピに従えば誰でも再現できる。だが、それが「正確」な肉じゃがだと主張するのはナンセンスだ。○○の肉じゃがを好まない人もいる。
同じように、「SNS上でどの情報を出力するのが望ましいか」という判断は、SNSのアルゴリズムを考える設計者の主観や価値観に依存して決まるものだ。アルゴリズムが厳密さをもっているからといって、アルゴリズムによる出力そのものが「正確」であるとはいえないのである。
アルゴリズムの実際
現代の社会や生活は、アルゴリズムなしには成り立たない。X(旧ツイッター)のタイムラインやアマゾンのおすすめ商品など、あらゆる情報の選別や分配に、アルゴリズムが介在している。
Xのタイムライン表示アルゴリズム
例えば、Xのタイムラインのアルゴリズムは、大きく3つのステップで構成されている。