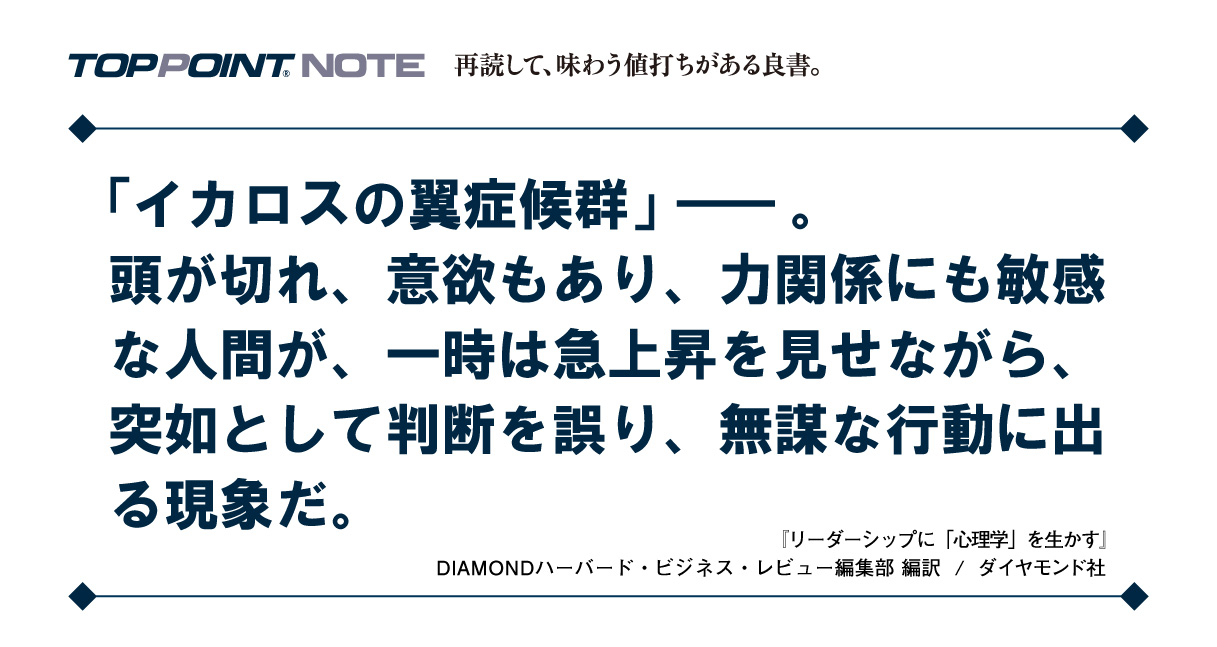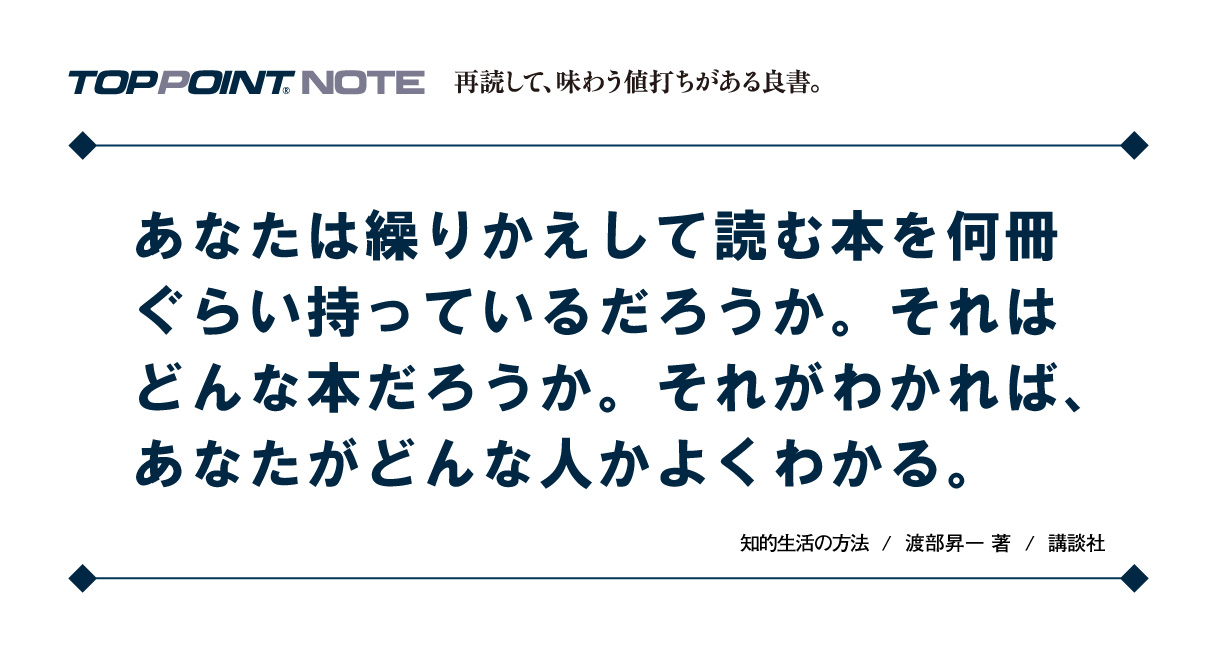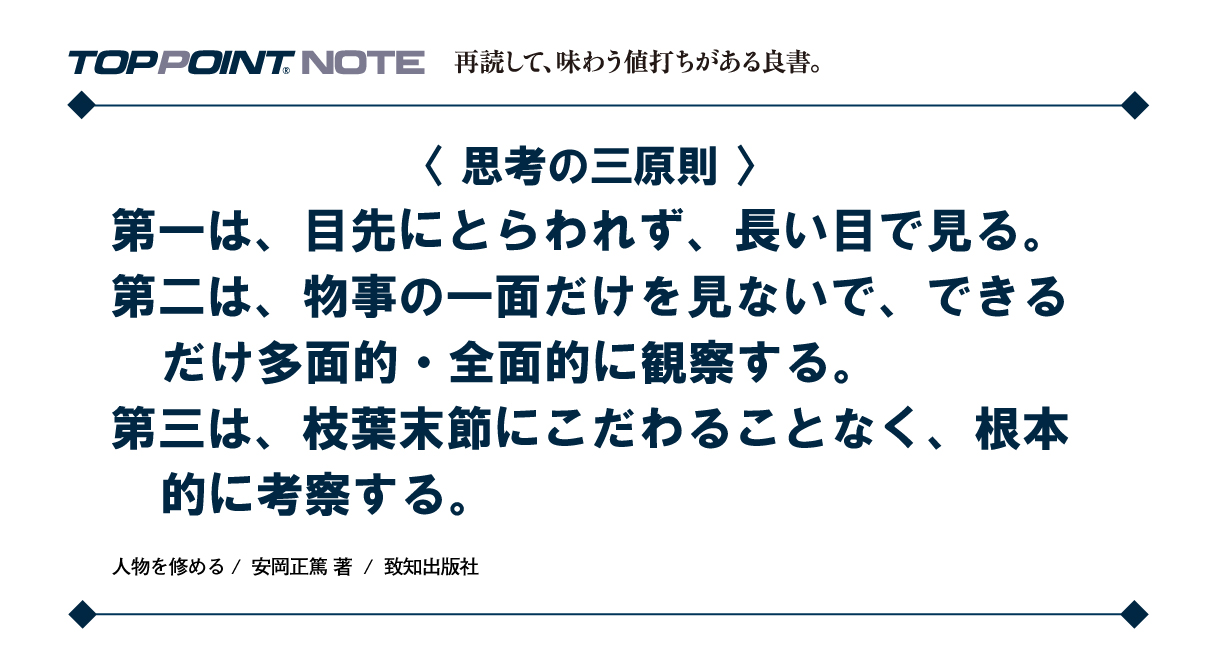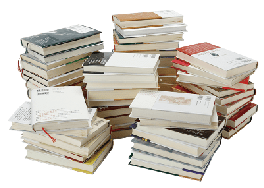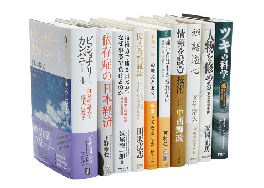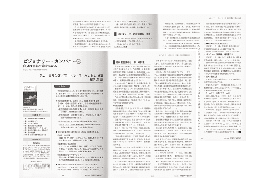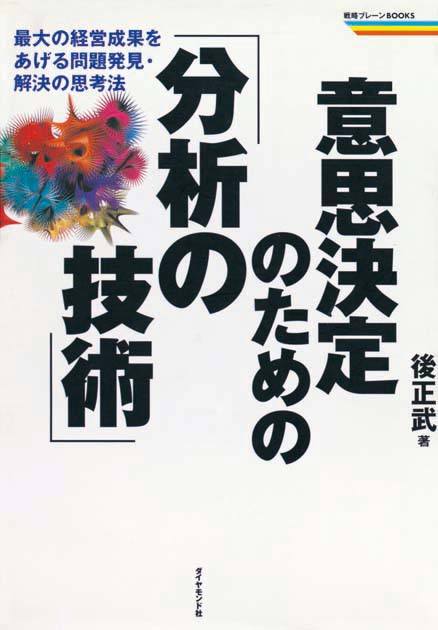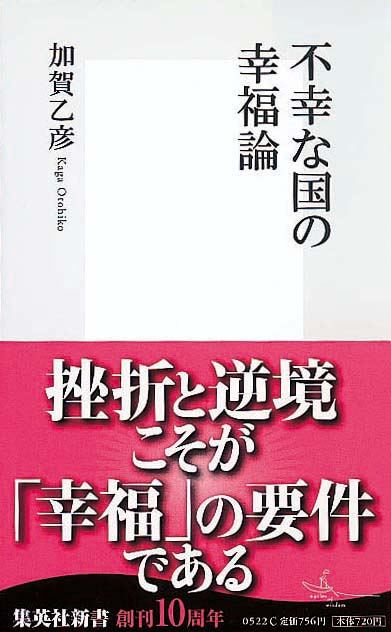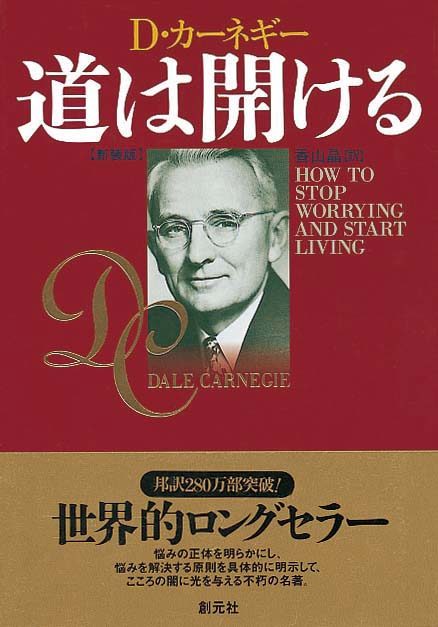妻のエレンが病院で死の床についていた時のことだ。ある時、そばにあった『プレイガール』の男性ヌードの折り込みページを開くと、何を思ったのか出し抜けに、その全裸写真を壁に張ってほしいと言いだした。
「病院にはちょっとどうかな。そうとうきわどいよ」
「平気、平気、お遊びよ」と妻は答えた。
「あそこにある植物の葉っぱを1枚取ってきて、ここを隠せばいいわ」
私は妻の言う通りにした。その日は何事もなかった。次の日も無事だった。ところが3日目、葉っぱがひからびはじめ、隠していた部分がだんだん見えてきてしまったのだ。
その植物というか、ひからびた葉っぱに目をやるたびに私たちは笑った。そのはしたない楽しみはほんの10秒か20秒しか続かなかったが、それでも私たちは気持ちが触れ合うのを感じたし、元気が出たし、暗い海の底からいっ時ふっと抜け出したような気がしたものだった。
解説
妻の病気、そして死という体験を通じて、ユーモアの大切さに気づいた著者は次のように語る。
ユーモアは人々に力を与える。逆境に立ち向かい、乗り越える手助けをしてくれる。
例えば、米国・テキサス州のある病院では、患者にお笑いのビデオを見せて痛みを軽減するのに役立てている。患者が病気のことばかり考えずに済むようにと、手品や曲芸を教えているニューヨークの医師もいる。
たとえ苦境にあっても、笑っている間、人はその境遇を超越している。恐れ、落胆、絶望といった感情から一段高い所へ抜け出している。
ユーモアには、たちまち気が紛れるという効果もある。私たちが苦しいと感じる時は、出来事そのものが苦しいというより、それを苦痛だと思うから苦しくなるというところが大いにある。
つまり、苦痛を呼ぶのは事実そのものではなく、その事実とのつき合い方というわけだ。
苦しい時にユーモアの助けを借りること、それは人生の山坂を上手に越えていくために私たちにできる、最も賢いことの1つといえるだろう。