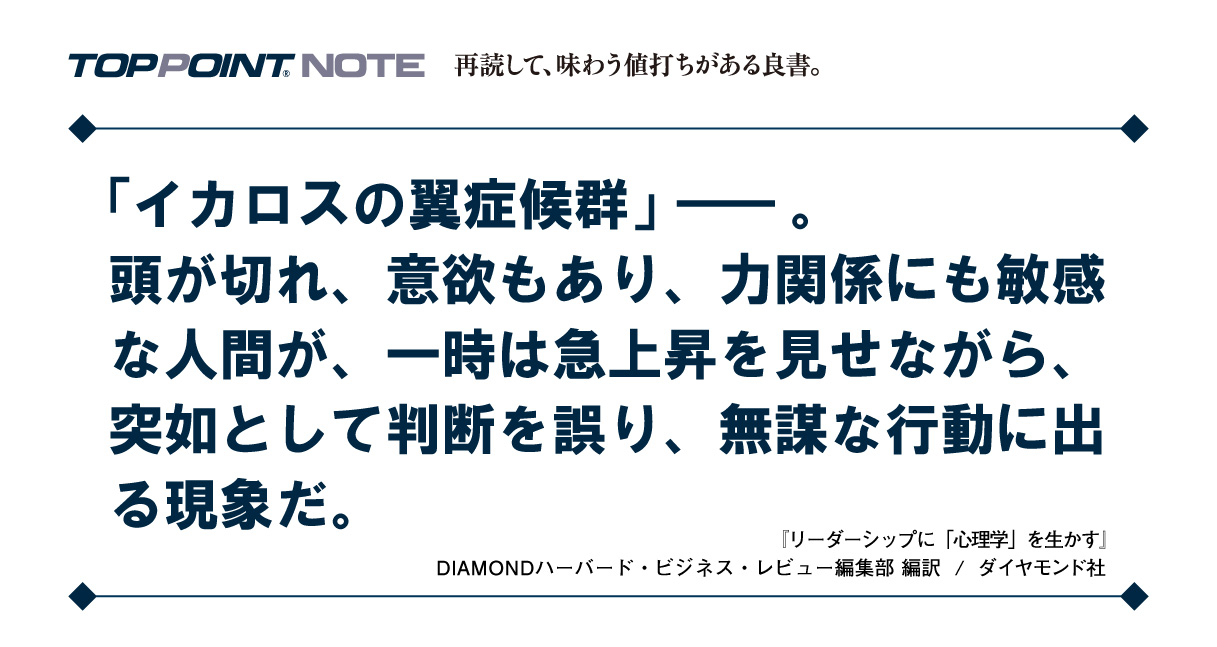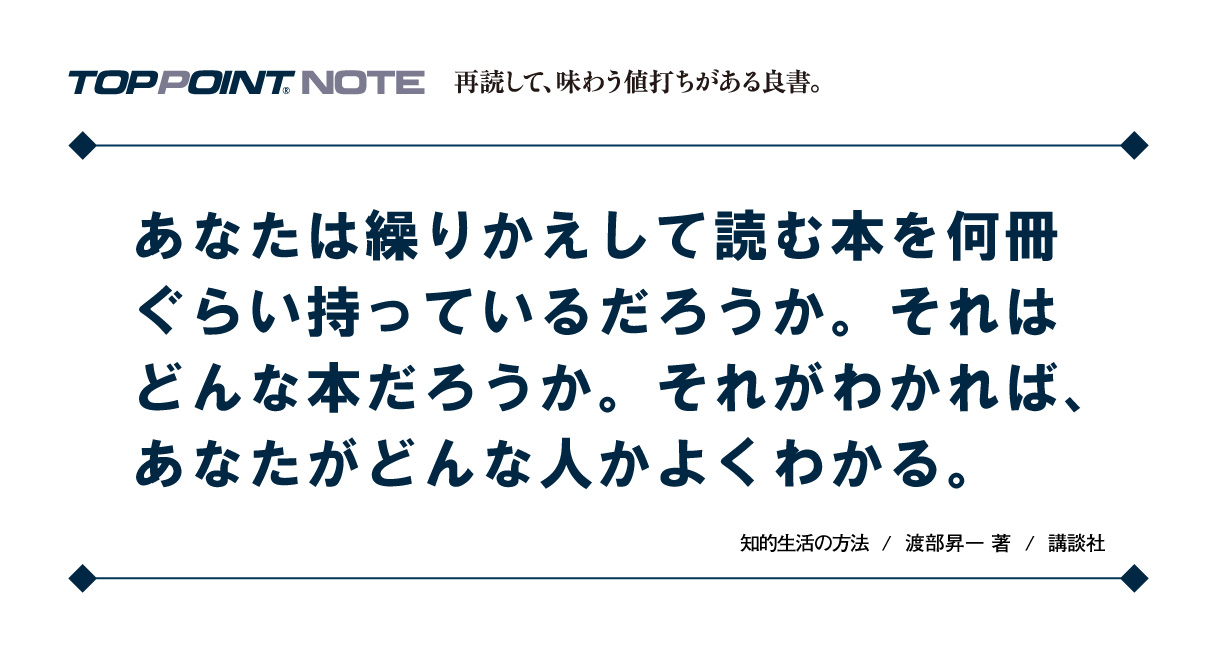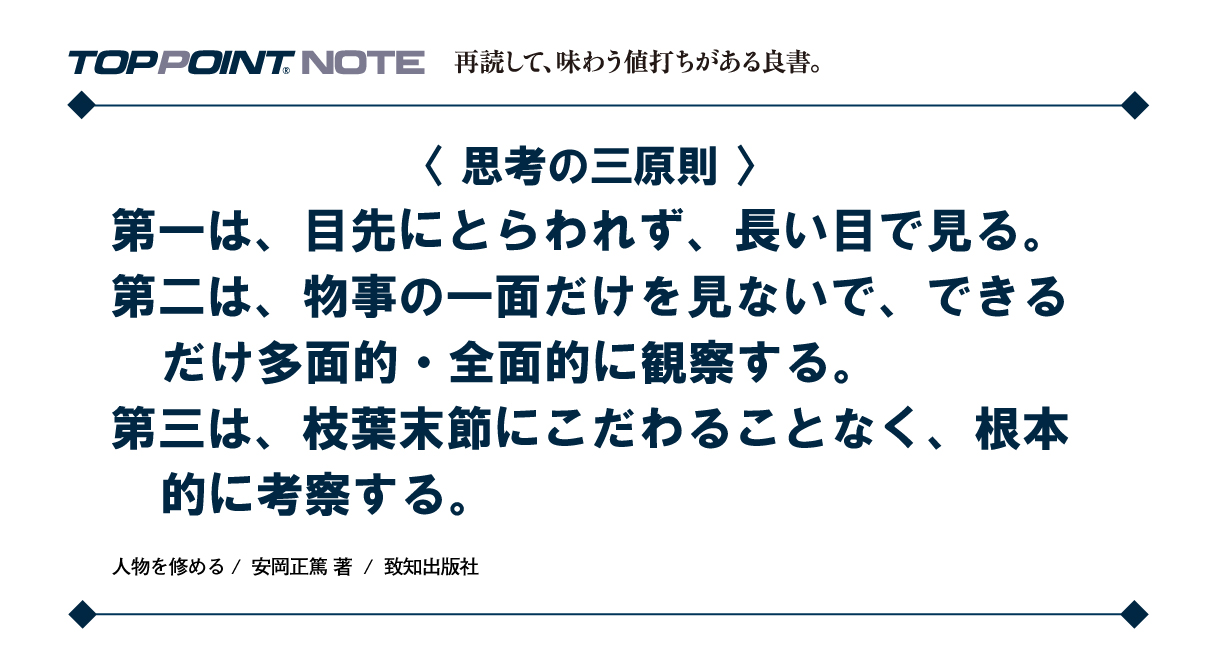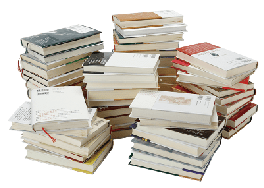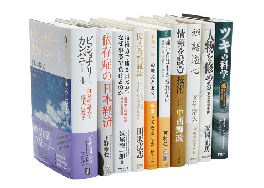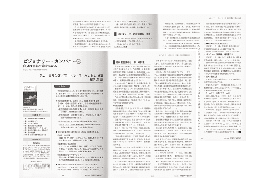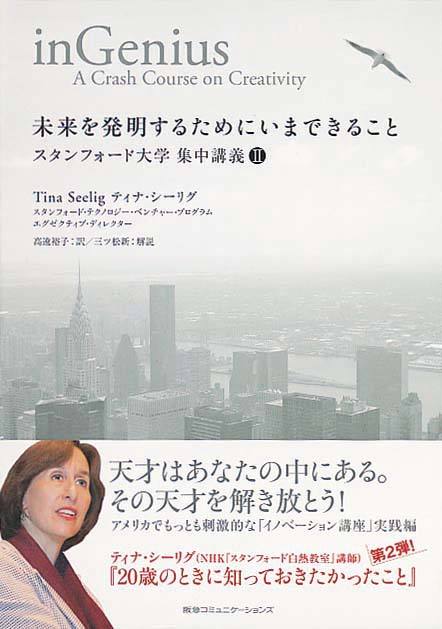将棋には、最善手とそれに近いものが1つか2つあると、一方で悪手が100くらいあるのが普通ですが、人生も同じようなものではないかと思います。
解説
世の中には、「運」や「ツキ」といった、人間の知識や論理では解明できない「不可解な力」が存在する。それはどれほど大きいのか、測ることはできない。しかし、我々は生活するうえで、この不可解な力にずいぶん影響を受けている。
では、どうすれば、そうした力を自分に有利に使うことができるのか?
棋士の米長邦雄氏は、最も大事なのは「大勢判断」だという。すなわち、細部にとらわれず、全体を見る。このような姿勢は、「許容範囲」を大切にするという発想を教えてくれる。
例えば、豊かな人生を送りたいと考えた時、何でもやりたいことをしていいかというと、そうではない。ここまではいいが、ここから先はダメだ、ということを明確にする必要がある。
将棋でいうと、最善手ではないが、指しても問題ない手であれば、さほど思い悩まずに指してよい。しかし、悪手を指さないということには十分配慮をしなければならない。
将棋にしろ、人生にしろ、悪手を指すのは難しいことではない。
例えば、事故を起こす、人を殺すなどということは簡単にできる。横領する、盗むといった悪手はさらに簡単だ。人間が欲望を満たそうと行動すれば、たいてい悪手になる。
要するに、人生とは、悪手の山の中を歩いているようなものなのだ。こういう状況においては、悪手を指さないことほど大切なことはない。