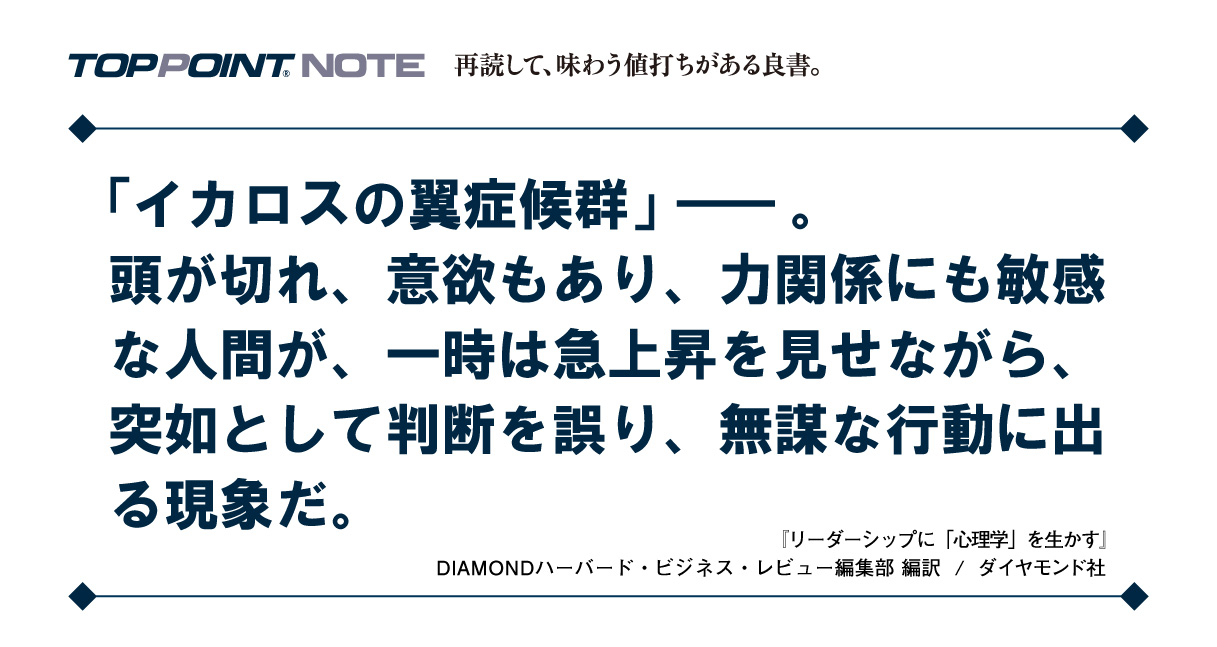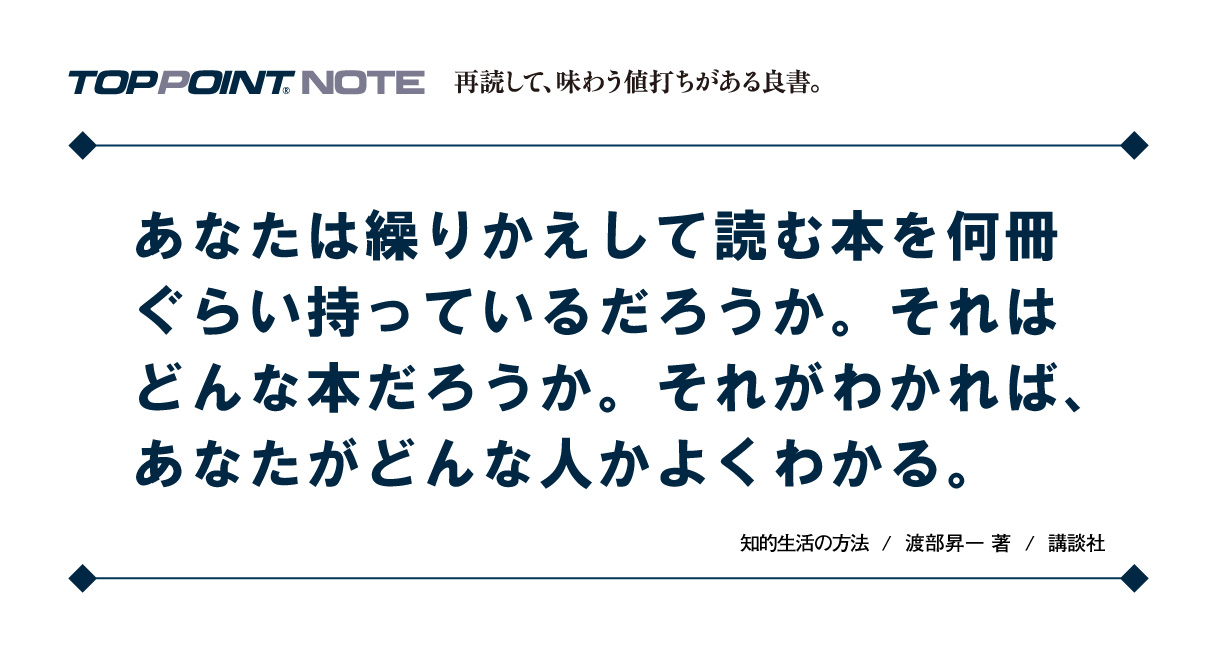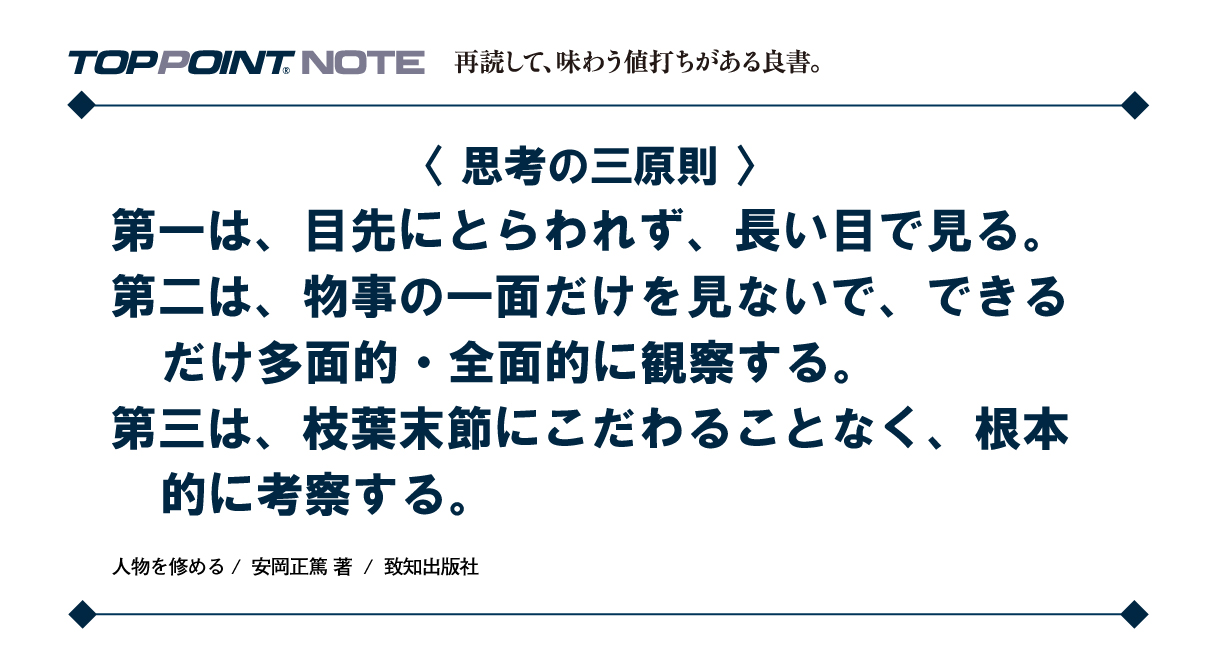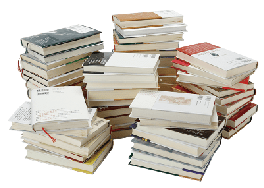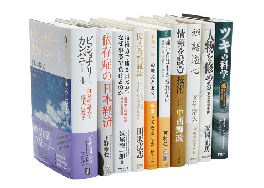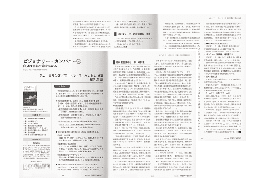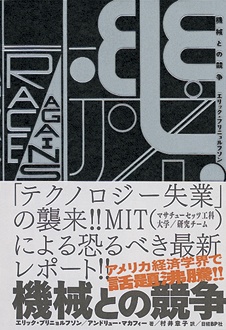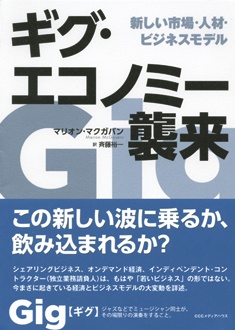比較をする際のまず第一の要件は、「意味ある比較ができるか否か」である。
同じリンゴ同士なら、大きさ・色・形・味などを対等な条件で比較し、優劣をつけられようが、リンゴとミカンを比較しても意味がない。英語では、それは「アップル・ツー・オレンジだから、比較できない」という表現をする。
解説
「比較する」ことは、物事を正しく理解するための最も基本的な分析の手法である。
ただし、比較するといっても、ただ漠然と比較するのでは、有用な結果は得られない。上記のように、重要なのは「意味ある比較ができるか否か」である。
そのための基本姿勢が、「アップル・ツー・アップルを考える」というものだ。同じリンゴ同士なら、大きさ・色・形などを比較して優劣をつけられる。だが、リンゴとミカンを比較しても意味がない。
比較する際のポイントは、次の3点である。
-
- ①できるだけ同じものを比較する
- ②異なるものを比較する時は、意味があり、かつ比較できる指標を探す
- ③似たもの同士を比較する場合も、同じ要素と異なる要素を正しく見分け、異なる部分の影響を勘案しつつ合理的な比較を心がける
例えば、競合他社と開発費の割合を比較する場合。まず、自社と競合他社の規模の差、導入している技術や歴史の差、商品構成や対象とする市場の差などをそれぞれ見極める。
そして、できるだけアップル・ツー・アップルになるよう、場合に応じた妥当な比較のあり方を考えることが必要だ。