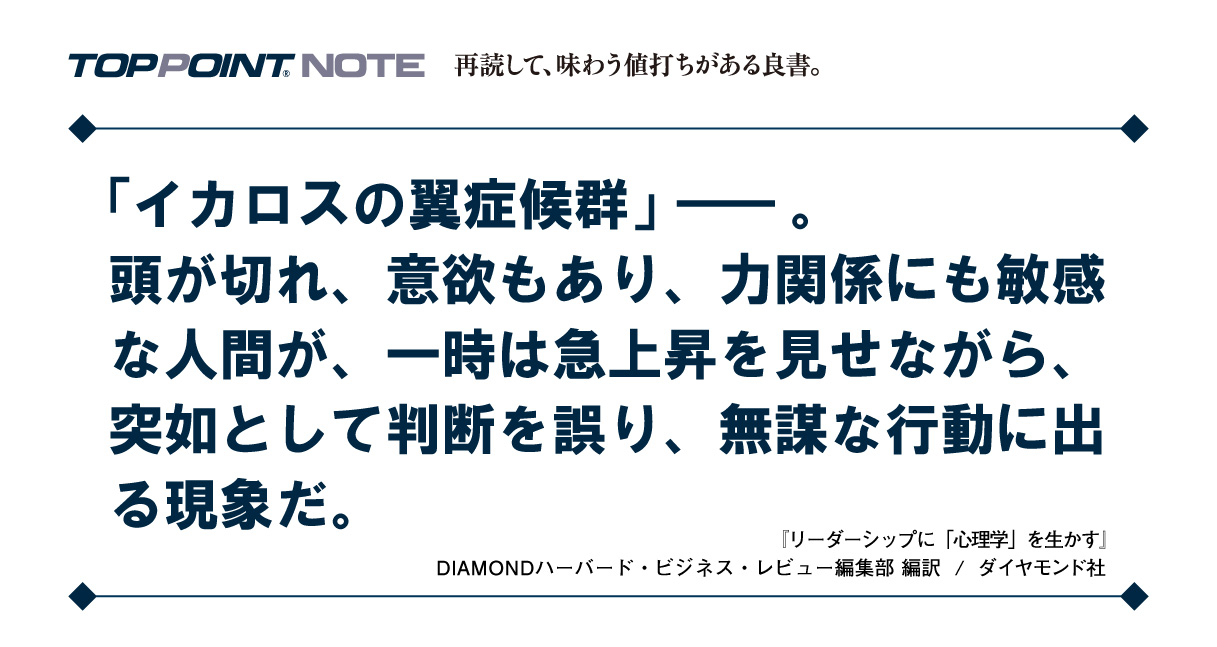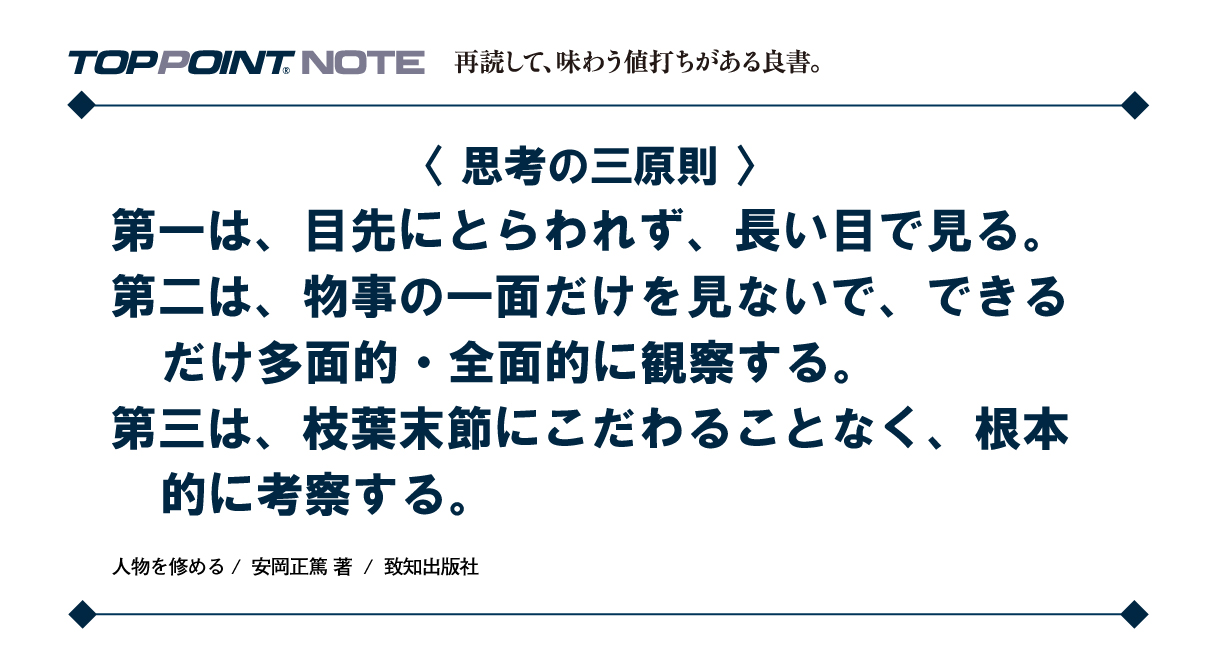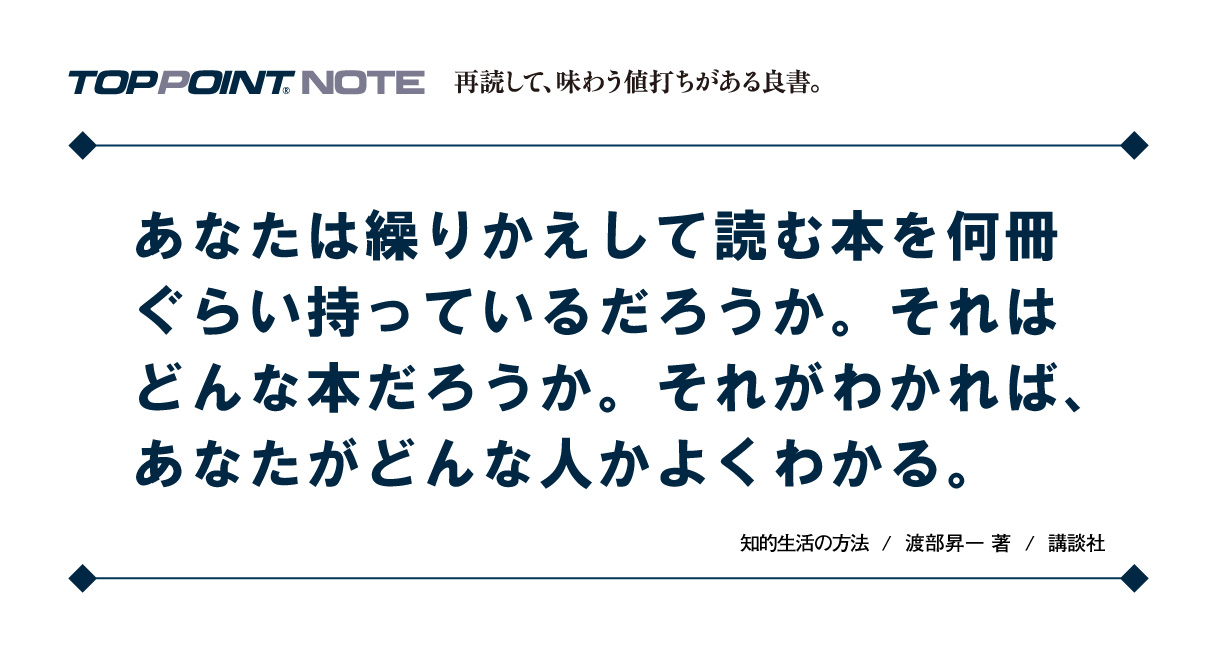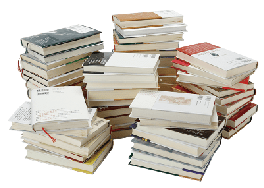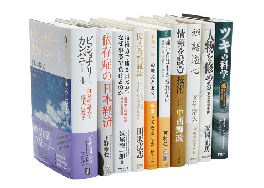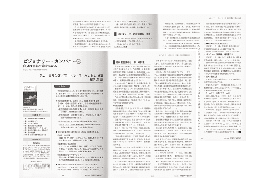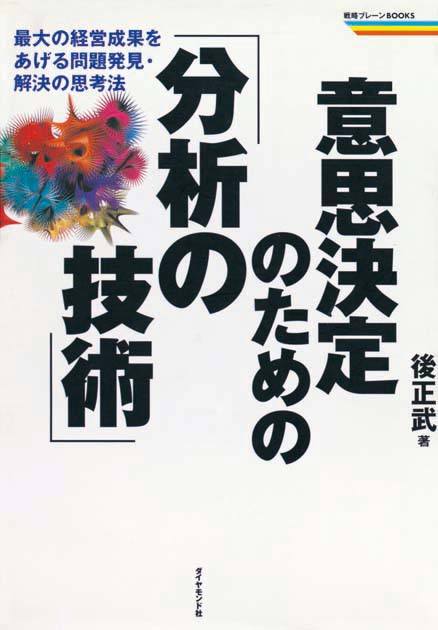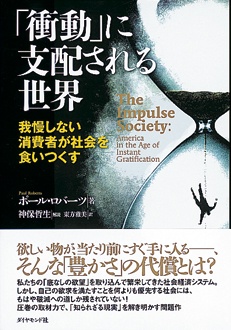人生には三つの坂道があるという。一つは“上り坂”、二つは“下り坂”、三つは、“まさかの坂”である。
上り坂と下り坂は人生の常である。人は、時には上り坂の幸せを味わい、時には下り坂の辛さに落ち込む二面性を経験するのである。それでも人間は上り坂のみを求め、競いながら、下り坂の悲哀を経験していくのである。
従って、人生の重さを体得した人は、上り坂の時には驕らず、感謝と謙虚さを守り、下り坂の時には、自分を駄目にせず、明日を信じて生きることを知っているのである。結局は、人生の安定は、上りでも下りでもない“平常心”を養うことにあるのである。
問題なのは“まさかの坂”との出会いである。人生においては、往々にして想像もしなかった不慮の出来事に遭遇し、なすすべもなく絶望の渦に巻き込まれていくのである。しかも、誰彼の区別なく、私たちは大なり小なり、この“まさかの坂”を越えていかなければならないのである。
だが、そう簡単には乗り越えられない受難の坂道である。逃げ出すことも出来ず、他に押しつけることも出来ず、自分の掌中から放り出すことが出来ず、苦悩し続けるのである。
私も、生き抜くということは、“焼け火箸を握りしめて、離さない経験をすること”だと戒めている。
解説
“日本のヘレン・ケラー”と呼ばれた大石順教尼。17歳の時、気のふれた養父に両腕を切断されるも、この受難を乗り越えて出家し、日本初の身障者更生施設を設立。身障者と苦楽を共にしながら、彼らの自立のために尽力した。
上記の言葉は、そんな順教尼の感動の人生を描いた『無いから出来る』の著者・石川洋氏が序章に綴ったメッセージの一部である。