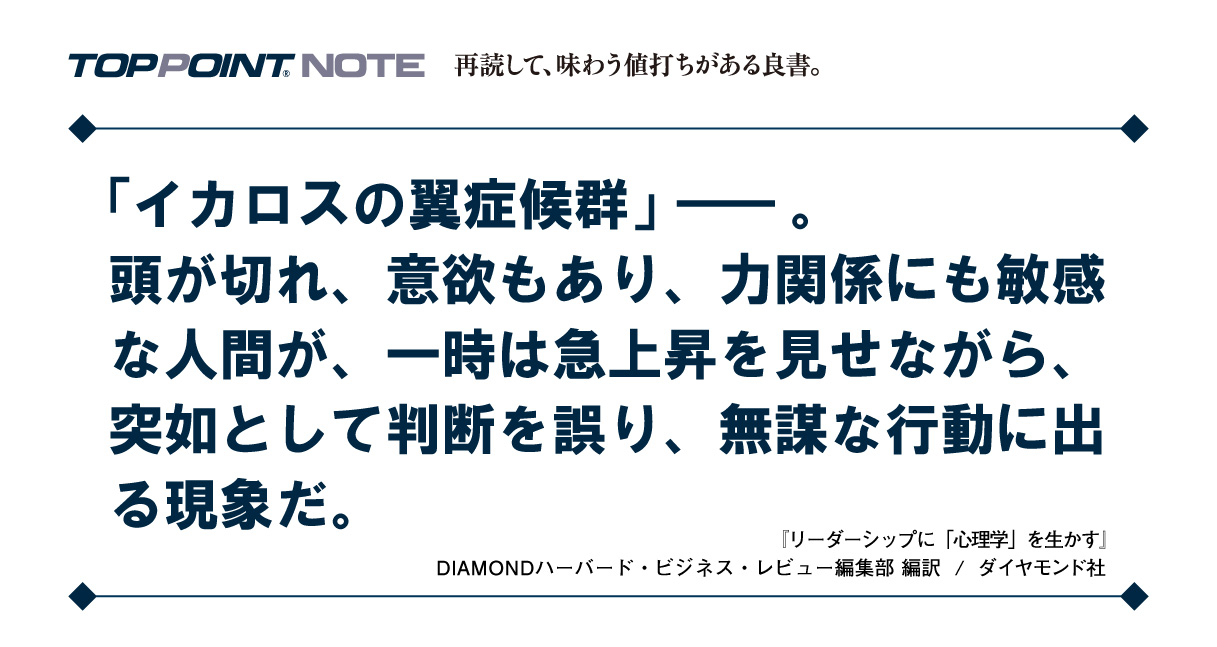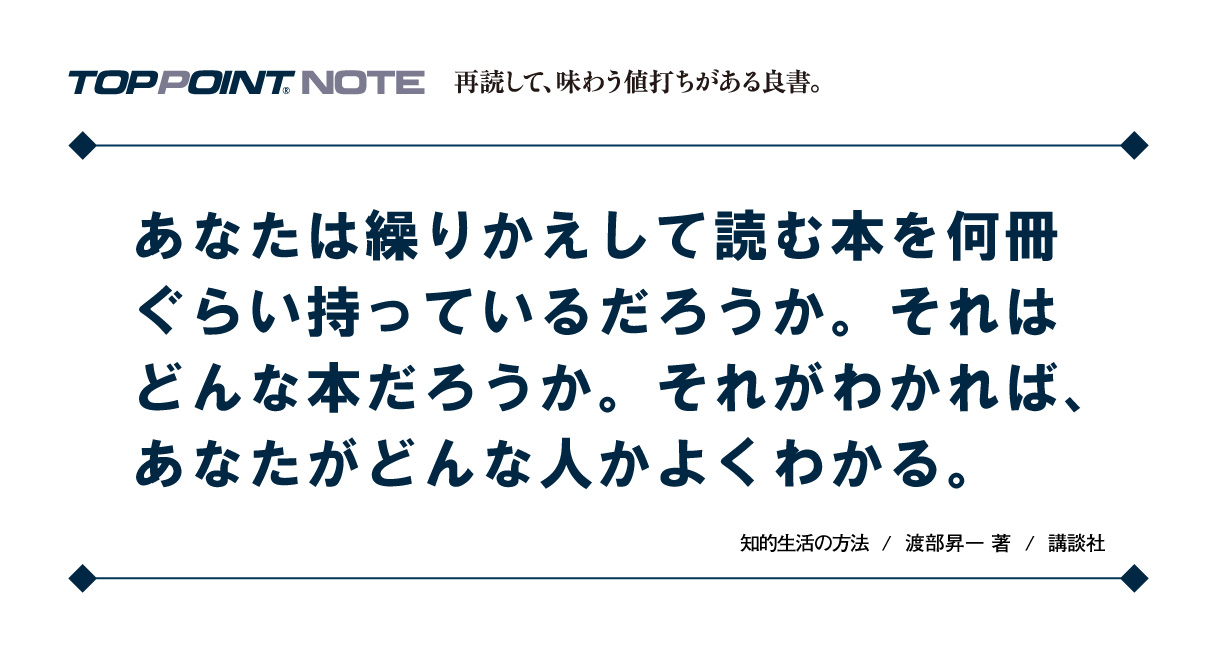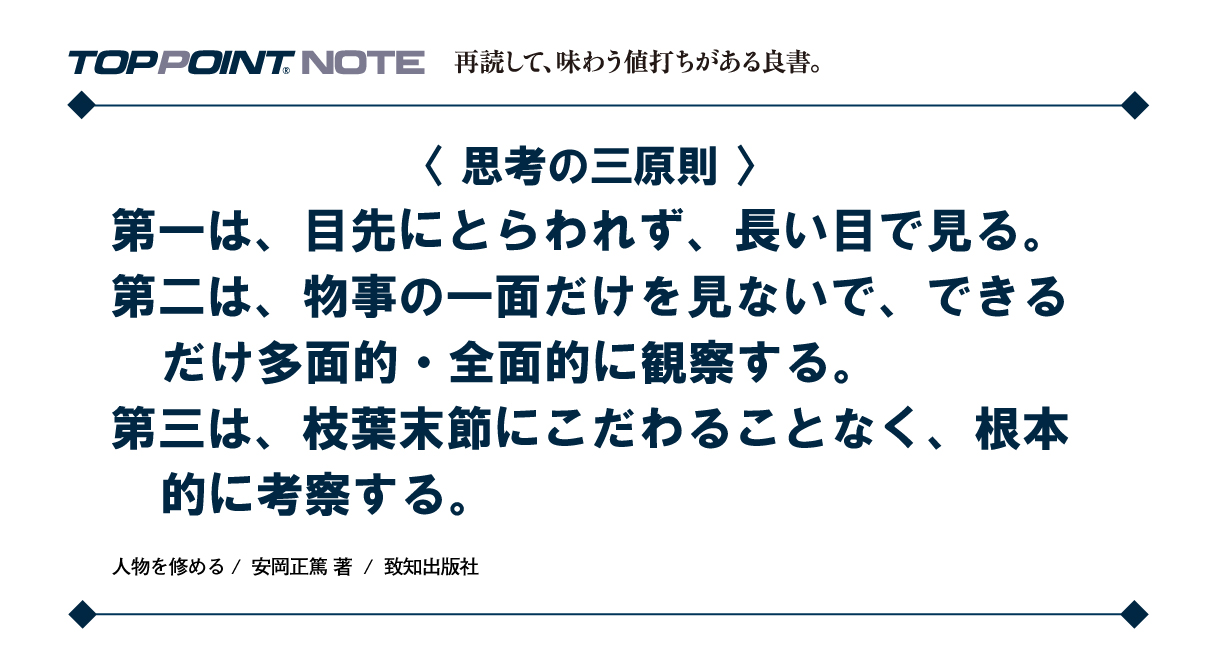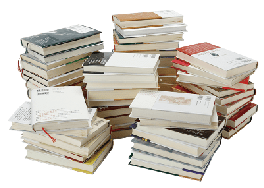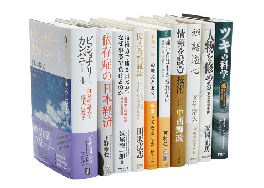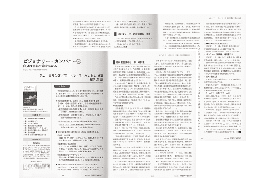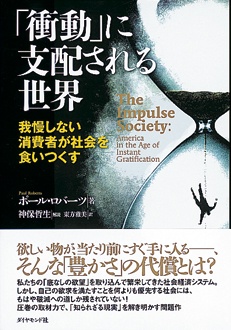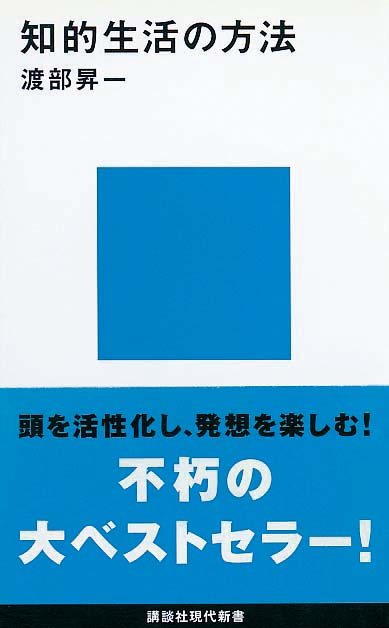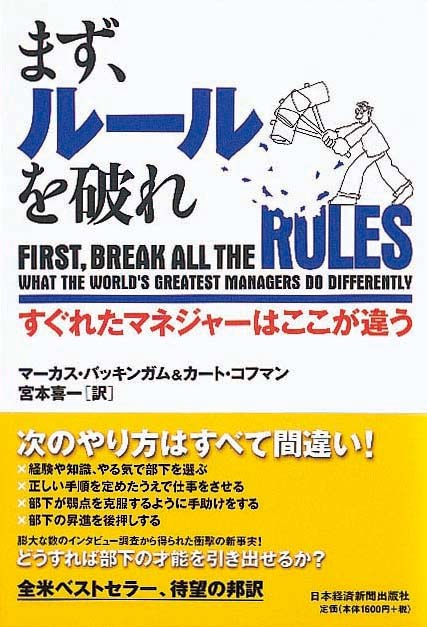「俺は働き盛りの大半を、世のため人のためにつくしてきた。ところが、どうだ ―― 俺の得たものは、冷たい世間の非難と、お尋ねものの烙印だけだ」
と、嘆いたのは、かつて全米をふるえあがらせた暗黒街の王者アル・カポネである。
解説
アル・カポネほどの極悪人でも、自分では悪人だと思っていなかった。それどころか、自分は慈善家だと考えていた。世間は彼の善行を誤解しているのだ、というのである。
人は、たとえ自分がどんなに間違っていても、決して自分が悪いとは思いたがらないものだ。これは悪人だけの話ではない。我々もまた同じである。
心理学者ハンス・セリエは、こう言う。
「我々は他人からの賞讃を強く望んでいる。そして、それと同じ強さで他人からの非難を恐れる」
だから、もし他人を非難したくなったら、アル・カポネの話を思い出すといい。
人の過ちを正したりすると、相手は逆にこちらを恨む。人を非難するのは、天に向かって唾するようなもので、必ずわが身に返ってくる。
人を非難することは、どんな馬鹿者でもできる。そして馬鹿者に限ってそれをしたがるものだ。
人を動かす原則の第1は、「批判も非難もしない」である。人を非難する代わりに、理解するように努めよう。なぜ相手がそんなことをするのか、よく考えてみよう。その方がよほど得策である。