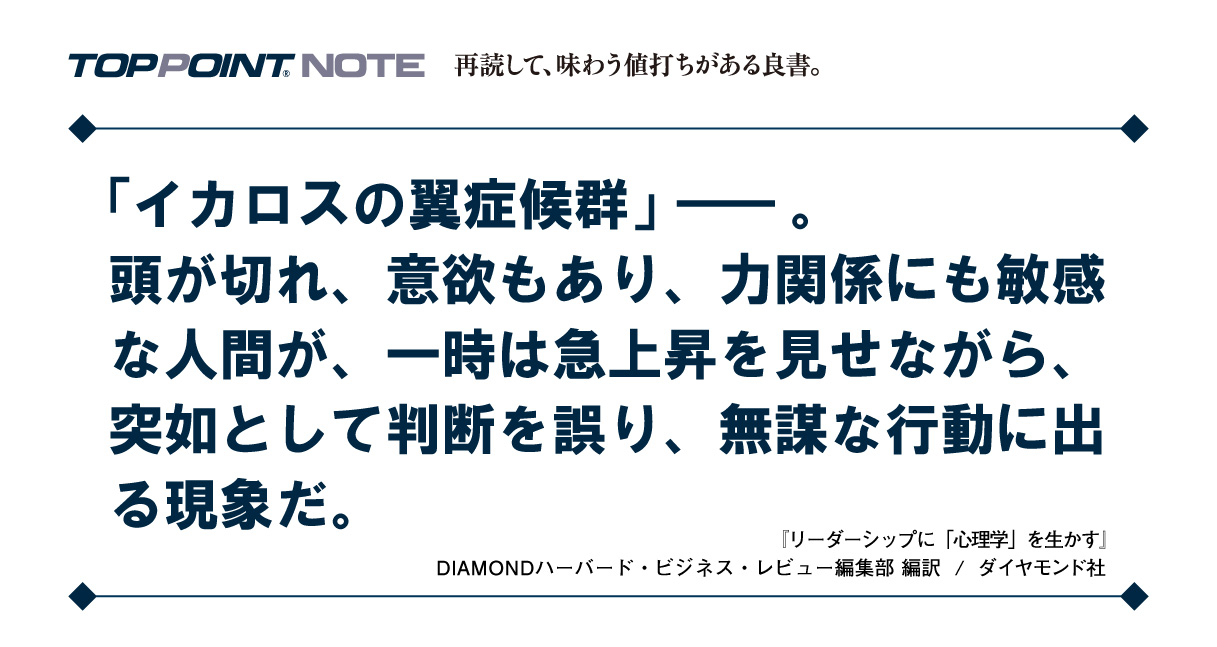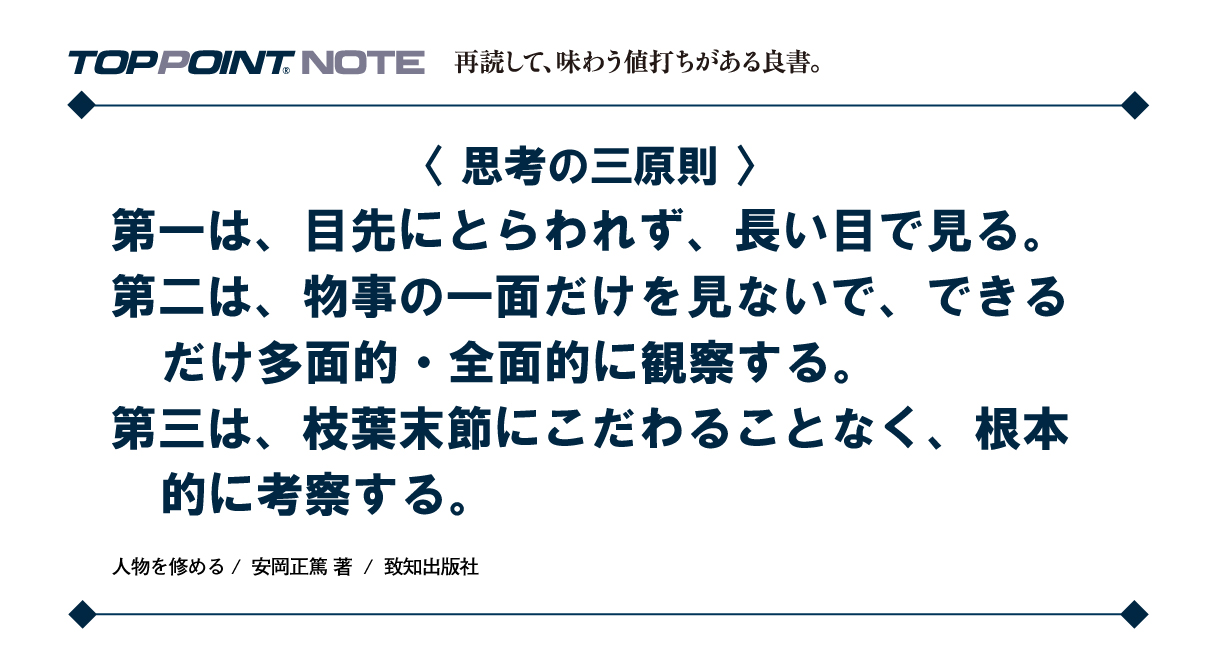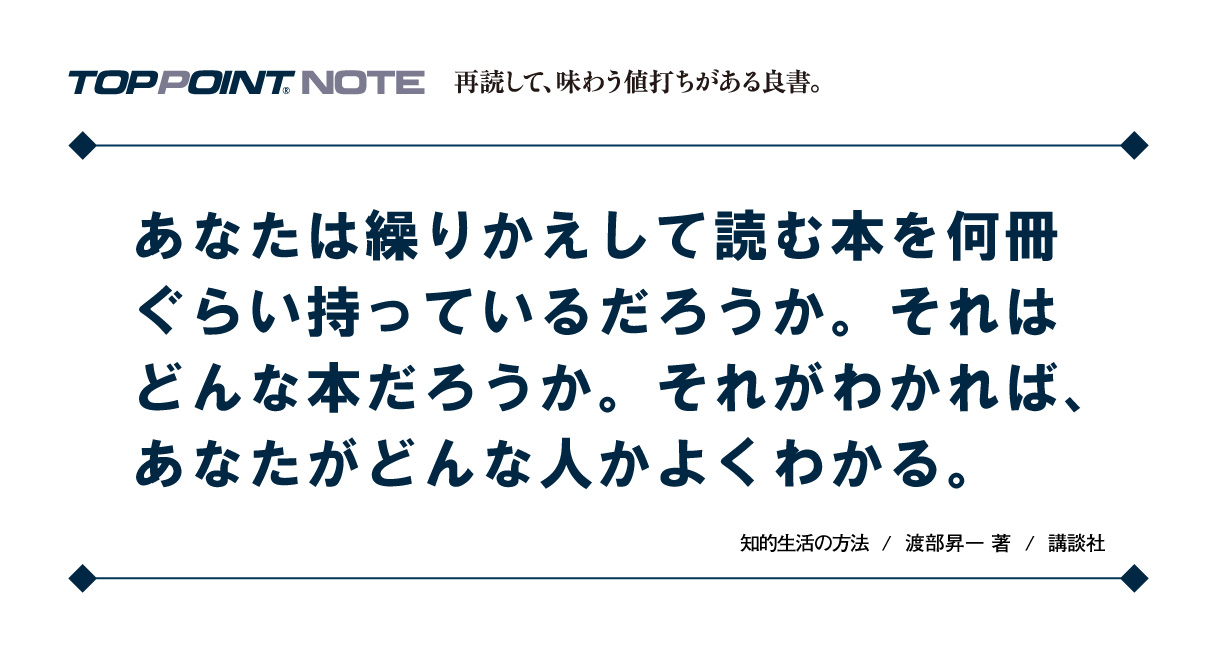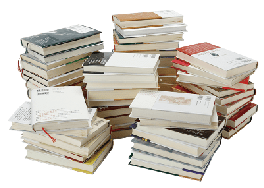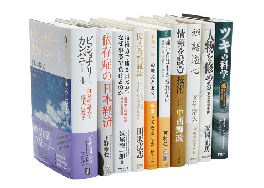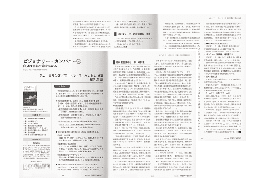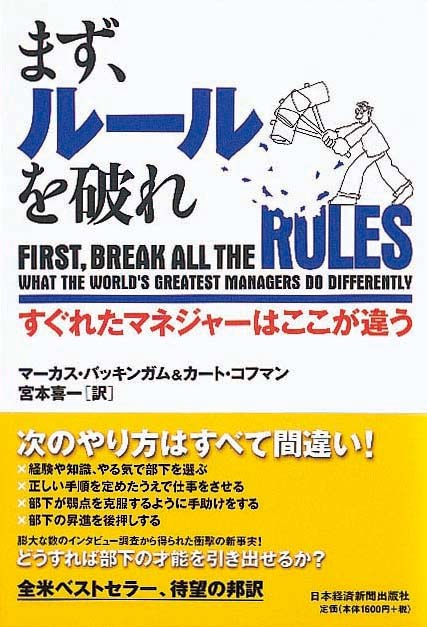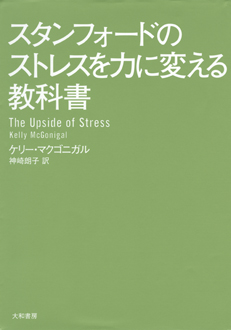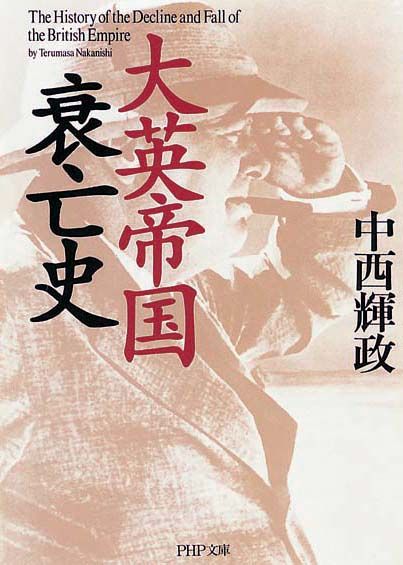退屈に耐える力をある程度持っていることは、幸福な生活にとって不可欠であり、若い人たちに教えるべき事柄の一つである。
解説
英国を代表する思想家のバートランド・ラッセルは、次のように読者に語り掛ける。
“興奮”に対する欲望は、人間、ことに男性においてすこぶる根深い。この欲望は、恐らく狩猟時代には容易に満たされただろう。狩猟には、興奮があったからだ。
しかし、農業の発達とともに、生活は“退屈”なものになった。中世の頃の、冬場の夜を想像してみるがいい。暗くなると、灯りとしてはロウソクしかなかったので、人々は読み書きすらできなかった。手軽に楽しめる娯楽も限られていた。その退屈さたるや、恐ろしいほどだったろう。
今日の私たちは祖先ほど退屈していない。それなのに、彼ら以上に退屈を恐れている。そして、がむしゃらに興奮を追求することで、退屈を避けようとする。
その結果、人々は、絶えずあちらこちらへ移動して、ダンスを、酒を楽しむ。人々は車に乗り、映画を楽しむ。若い男女は、昔よりもずっと簡単にデートができる。
だが結局、退屈を免れることはできない。前の晩が楽しければ楽しいほど、翌朝は退屈になり、より強い刺激が必要になる。
一定の量の興奮は健康によい。しかし、他のほとんどすべてのものと同様、問題は分量である。
少なすぎると渇望を生み、多すぎれば疲労を生む。そして、興奮に満ちた生活は、心身を消耗させることになる。
だから、退屈に耐える力をある程度持っていることは、幸福な生活にとって不可欠である。
古来、偉大な人の生涯は退屈な期間が長かった。
例えば、カントは一生涯、ケーニヒスベルクの町から10マイル以上離れたことはなかった。ダーウィンは世界一周をした後、残りの生涯をずっとわが家で過ごしている。