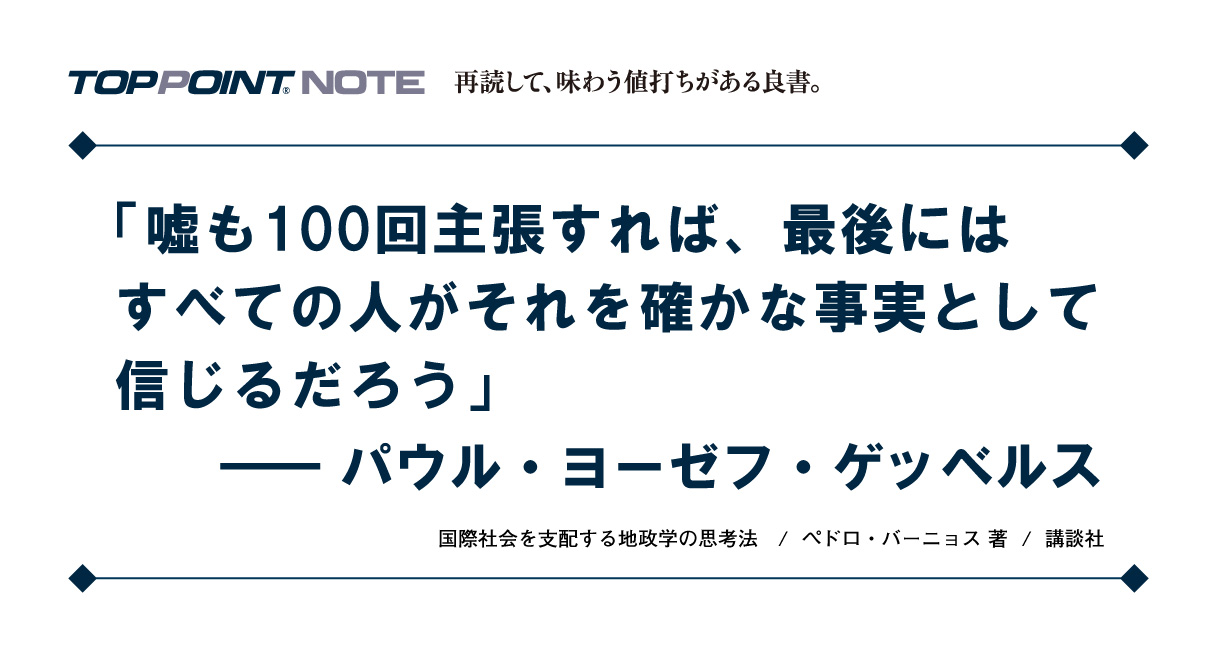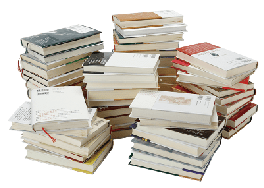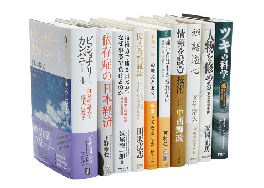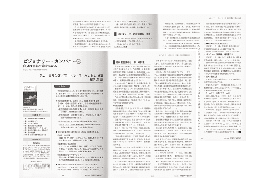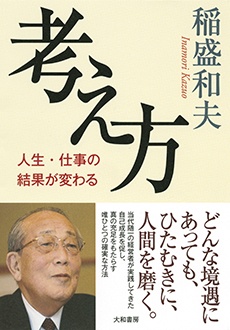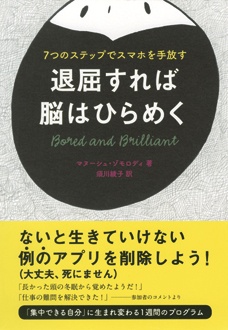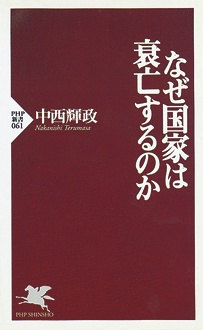国家存亡や独立の危機において、頼みにできるのは自国だけだ。
解説
北欧のフィンランドは、西はスウェーデン、東はロシアと国境を接する、人口600万人の小国である。
今日、同国の国民1人当たりの平均所得はドイツやスウェーデンに並び、最富裕国の1つに数えられる。だが、第2次世界大戦開戦当時は貧しい国だった。
フィンランドには、1939年の苦い記憶がある。この年の10月、巨大な軍事力をバックに、ソ連がバルト海沿岸の4カ国、フィンランド、エストニア、ラトビア、リトアニアにソ連軍駐留と基地建設を認めるよう迫った。この要求に対して、フィンランドだけが激しい抵抗を示し、大きな犠牲を払って独立維持を貫いた。
当時、ソ連侵攻に対し、フィンランドに支援を提供した国はなかった。アメリカもスウェーデンも、ドイツ、イギリス、フランスも、フィンランドを助けようとはしなかったのだ。
フィンランド人はこうした歴史から、国家存亡や独立の危機において、頼みにできるのは自国だけだということを学んでいる。そのため、今も男性には兵役義務があり、女性でも志願者は兵役に就ける。