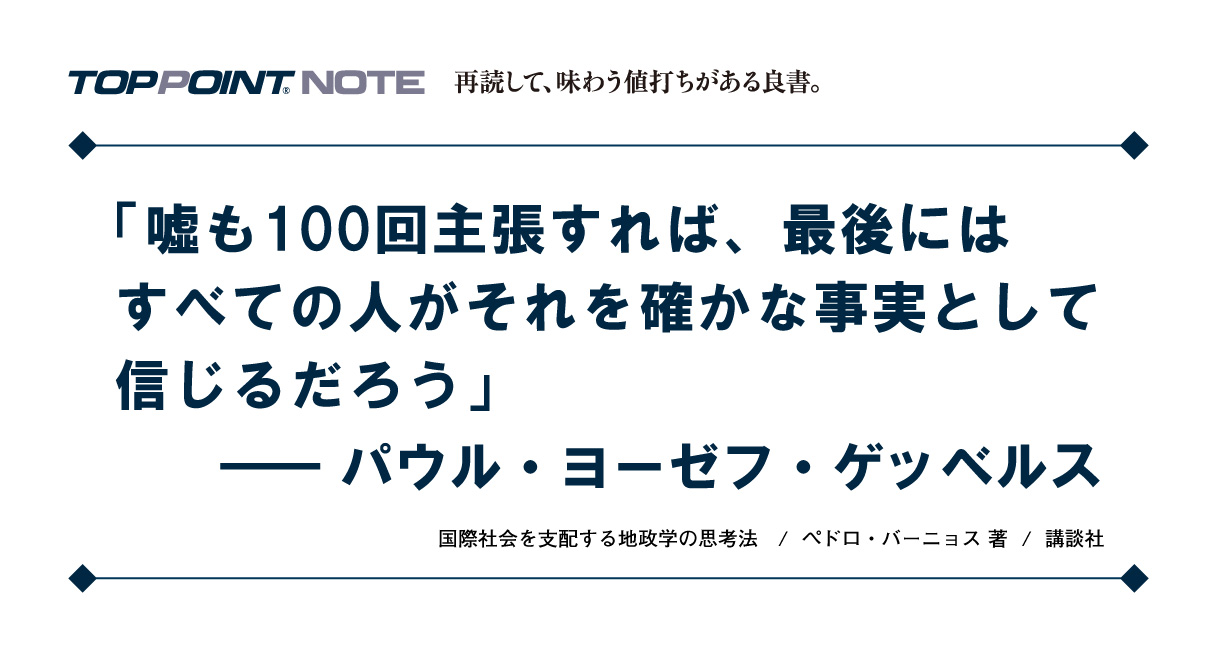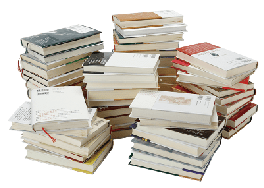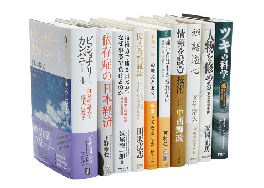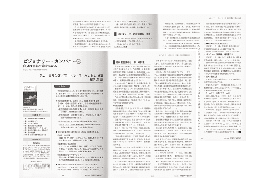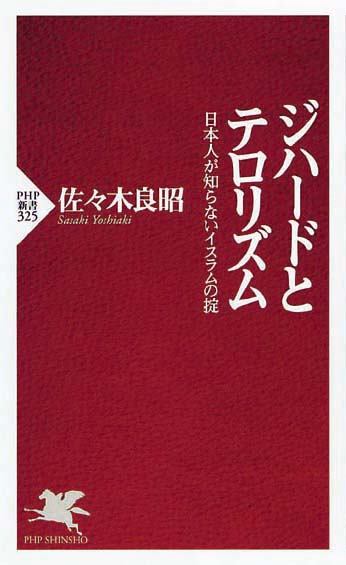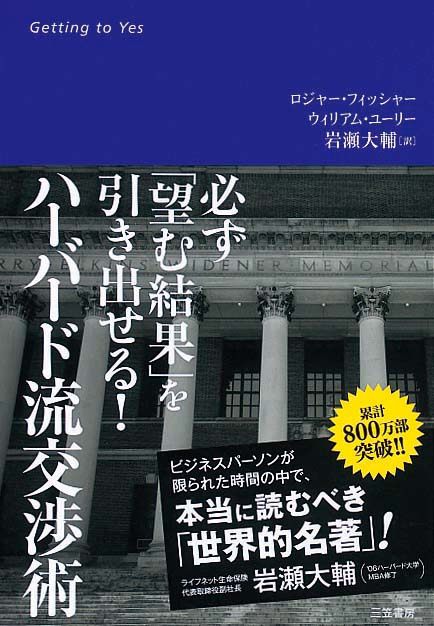歴史認識問題を外交問題化しないことこそが、それまでの日中間および日韓間での二国間関係を維持するための政治的叡智としてしばしば意識されてきた。それにも拘わらず、村山政権で善意から和解を求めて自らの歴史認識を明らかにした結果、むしろこの問題が外交問題化してしまい、関係悪化に道を開いてしまった。
解説
戦後50周年を迎えた1995年。村山富市首相は、この年に歴史を語る必要性を感じていた。そして8月15日、いわゆる「村山談話」が誕生した。
この談話には、植民地支配により多くの悲劇をもたらしたことへの「痛切な反省」と「心からのお詫び」という言葉がある。戦後の首相による談話で、ここまで踏み込んだことはなかった。
村山首相は、国家間の問題でも、誠意を示せば決着がつくと感じていたのかもしれない。だが結果として、それ以降、歴史認識問題が日中間、日韓間での深刻な外交問題へと発展してしまった。
この問題に詳しい神戸大学の木村幹教授は、次のように述べる。「細川政権の選択は正解だった。細川は歴史認識問題に関わる発言を散発的に行う一方で、それを ―― 例えば『談話』のような ―― まとまった形で示すことはなかったからである。だからこそ日韓両国の政府やメディアは細川の散発的に行われる歴史認識問題に関する発言を『玉虫色』に解釈することができ、両者の歴史認識の違いは明確なものにならなかった」。
歴史認識が各国のアイデンティティと深く結びついている以上、そもそも国境を越えた歴史認識の共有は難しいという意識が、村山首相には欠けていた。歴史認識問題という「パンドラの箱」を開けた結果、中国でも韓国でも歴史認識問題を封印しておくことが不可能になってしまったのだ。