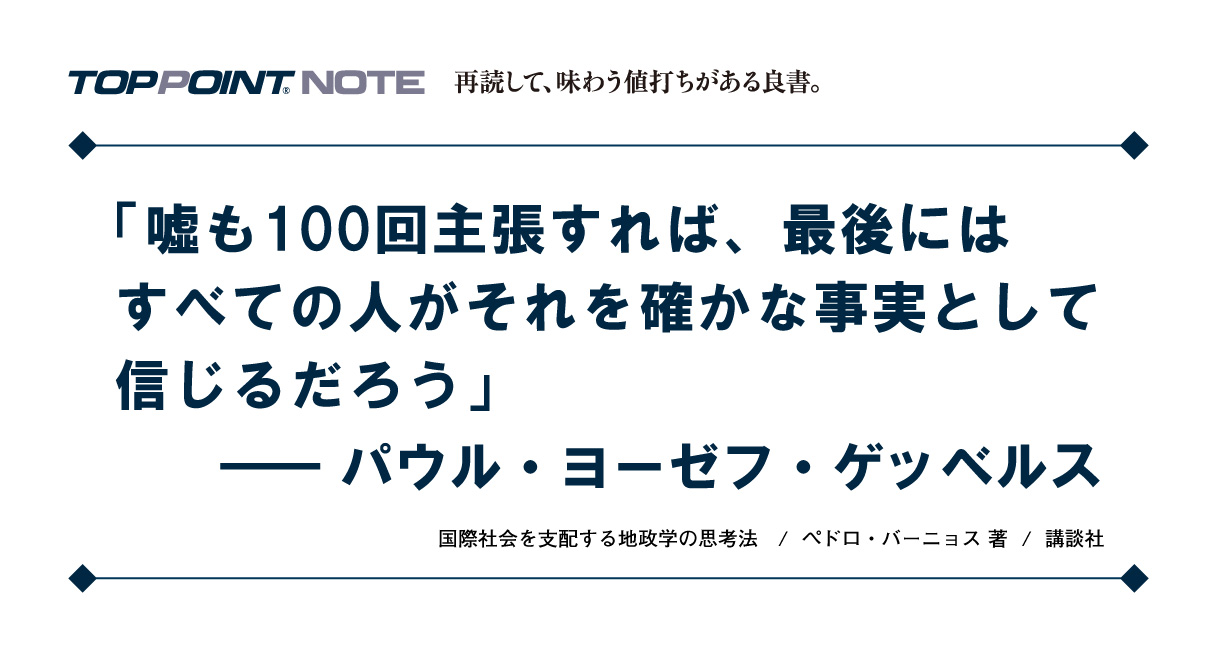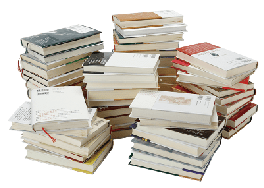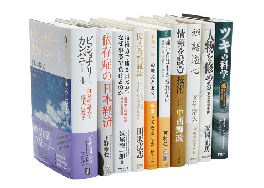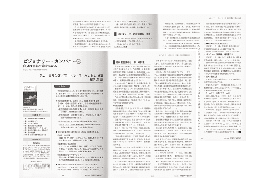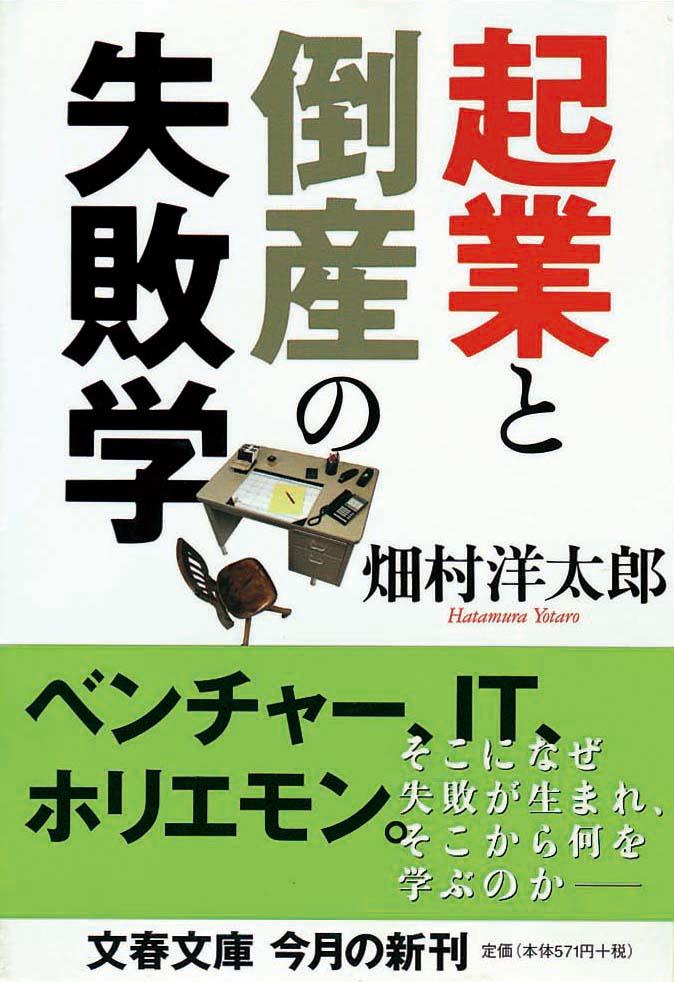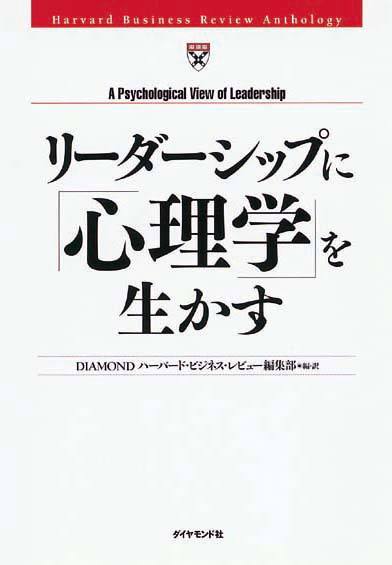「水に流す」とは、今まであったことを、さらりと忘れ去ってしまうことである。過ぎてしまったことを改めて話にもち出したり、とがめ立てたりせず、無かったことにしようとする行為である。
われわれ日本人の行動様式をふりかえると、この「水に流す」傾向が極めて強いことに気づかされる。善くも悪くも、過去に対してわだかまりがなく、済んでしまったことは仕方がないという気分が支配的である。
解説
日本の川には、大きな特徴がある。それは、流れの速い川が多いということだ。
流れが速いことには、清浄さを保つという点で利点がある。土砂で水が濁っても、流れが速い川だと瞬く間に清浄さを取り戻せる。ゴミを捨ててもあっという間に押し流され、目の前の川はきれいになる。
こうした自然環境が、日本人の「水に流す」心情や行動様式を育んだといえる。
過去にこだわらず、責めず、忘れ、許す ―― 。この日本人の行動様式は、おだやかで優しい人間関係を維持する知恵として、また寛容な人間性の美点として、これまで受け容れられてきた。
だが今日は、好むと好まざるとにかかわらず、国際社会の文化、生活習慣に接する機会が増えている。そうなると、何事も「水に流す」という心情や行動様式は、トラブルを生む原因となる。