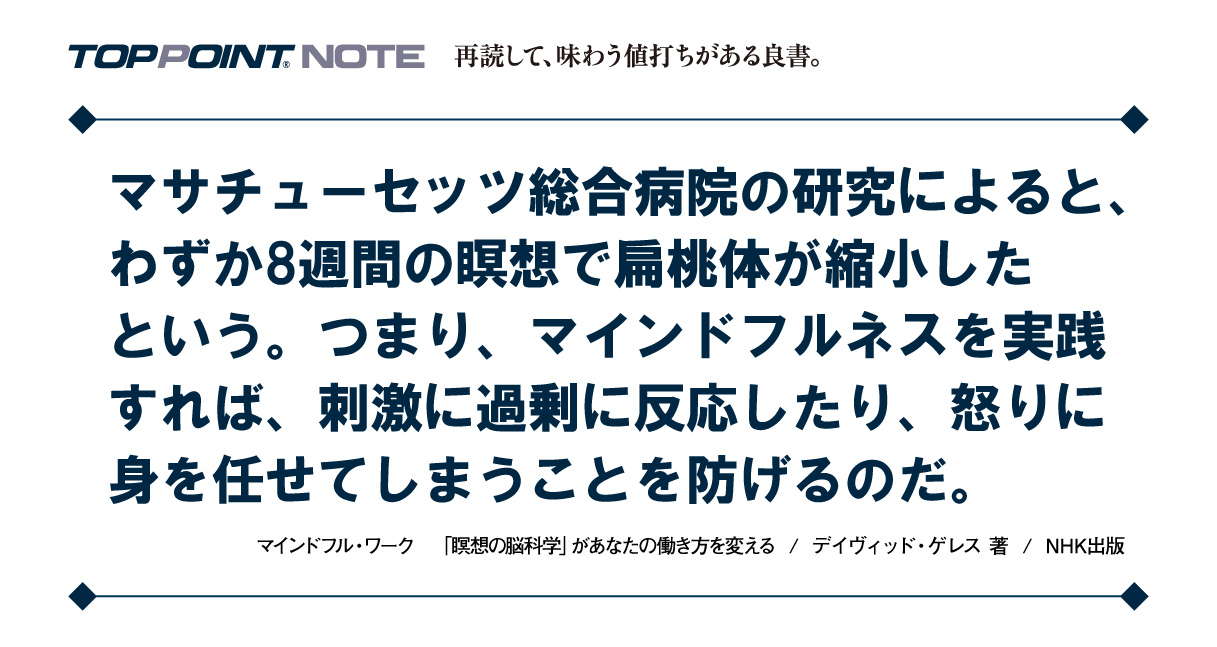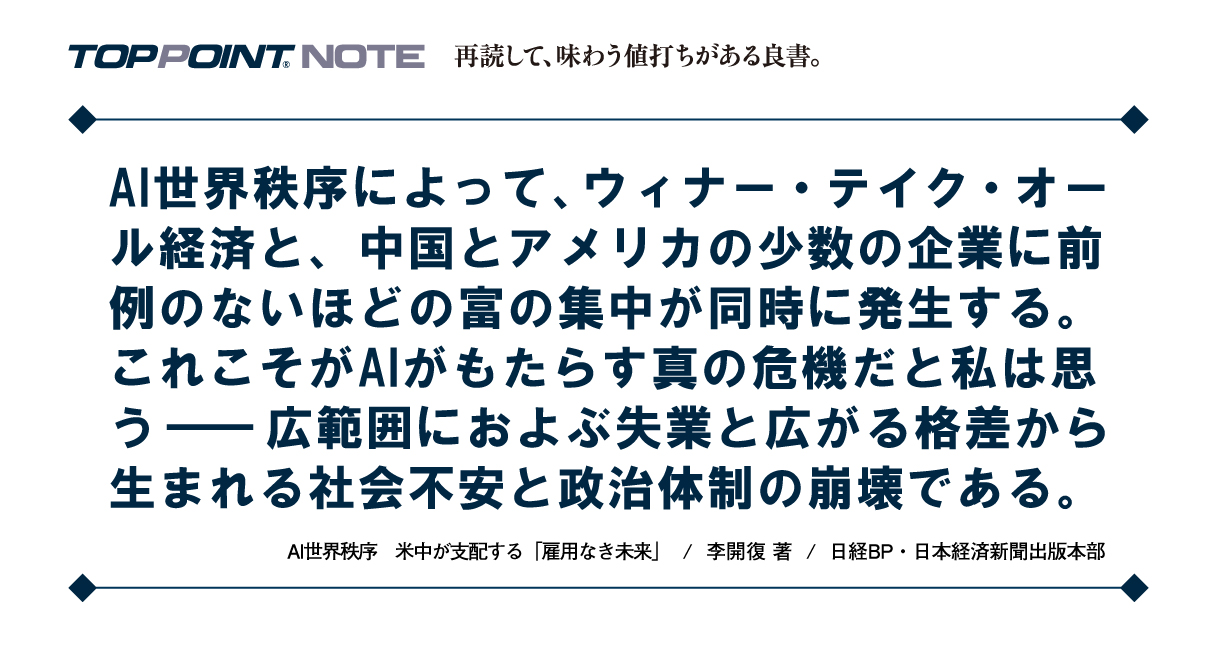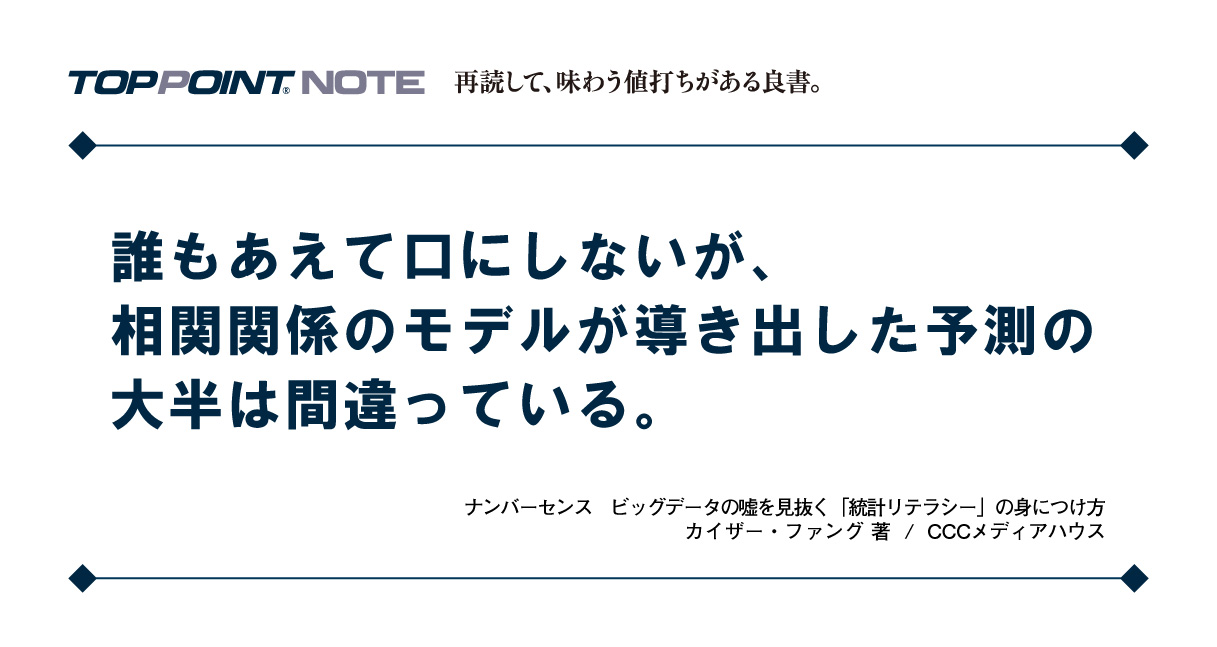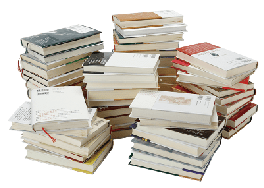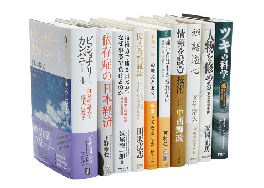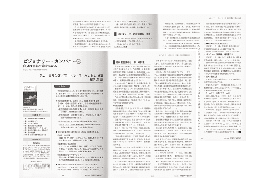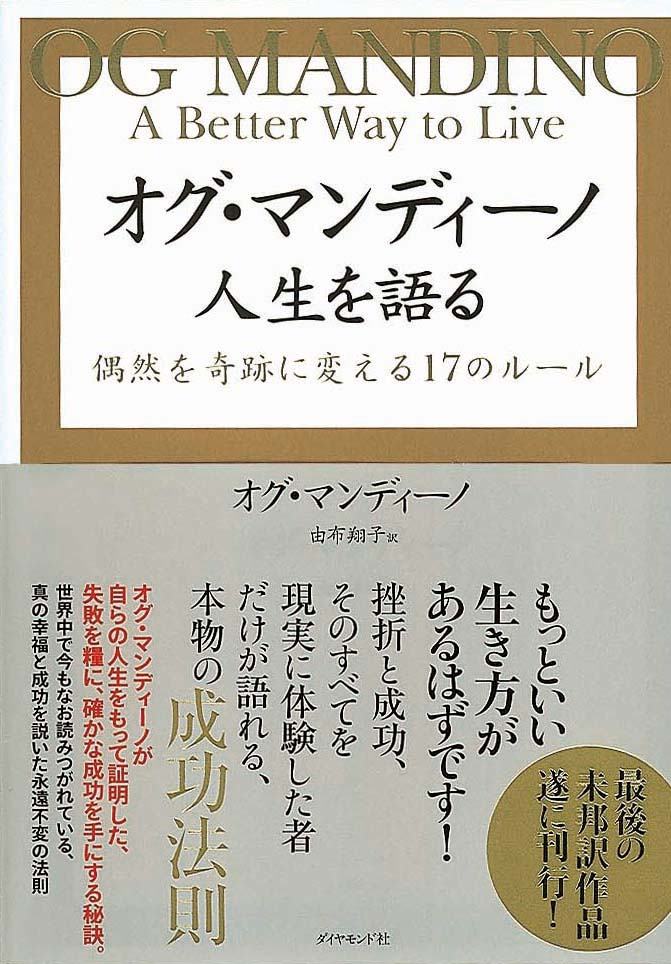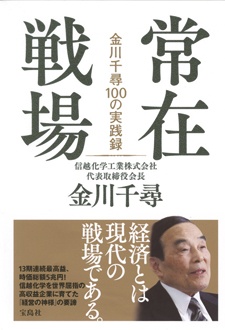チェス盤を発明した男が王様に献呈したところ、王様は大層喜び、望みの褒美をつかわすと言った。そこでこの賢い男は米を所望し、チェス盤の最初のマス目に1粒、2番目のマス目に2粒、3番目に4粒……という具合に、前のマス目の倍の米を置いていき、その合計を賜りたいと申し出た。
王様はたやすいことだと承知したが、実際には倍、倍とただ置いていくだけで米粒は途方もない量になった。最終的には、米粒の数は2の64乗マイナス1粒になったのである。これは、積み上げればエベレスト山よりも高い。
解説
この逸話では、チェス盤の半分(32マス目)に至るまでは、米粒の量はそう多くなかった。それまでに王様が与えた米粒は40億粒。これは大きな競技場程度で、王様が賜る褒美としては妥当だ。だが、チェス盤の残り半分が進行するにつれ、米粒の数は加速度的に増えた。
このように、倍々ゲームでの増加、すなわち指数関数的な増加は人を欺く。始めはありふれた増え方に見えるが、時間の経過とともに、私たちを狼狽させるような増え方に転じるのである。
コンピュータの進化も、これと同じだ。米商務省経済分析局が、設備投資の対象に「情報技術」を加えたのは1958年のこと。ムーアの法則による集積密度の倍増ペースが18カ月ごとだと仮定すると、32回倍増した年は、2006年だ。
2010年、グーグルは完全自動運転車で米国の道路を1600km走破した、と発表した。こうした事例は、チェス盤の残り半分を進むにつれ次々に登場するデジタル・イノベーションの最初の例とみなすことができる。指数関数的な進化が私たちを驚愕させるのは、これからなのだ。