マーケターはよくロイヤルティとか顧客との長期的な関係とかいう話をするが、近年では、ますます多くの消費者が企業との関係をオープン・マリッジ、つまり浮気公認の結婚関係のようなものとみなしている。
解説
現代の消費者は浮気性である。
例えば2012年の調査で、ホテル・ブランドに対するロイヤルティが急激に低下したことがわかった。回答者のうち、「毎回同じブランドのホテルに宿泊する」と答えた人は、わずか8%にすぎなかったのだ。
こうした傾向の根底には、様々な要因がある。
価格比較サイトやレビュー・サイトなど、各ホテルの価値を評価できるツールが増えたのは、その理由の1つである。
顧客ロイヤルティの低下にもかかわらず、いまだに多くのマーケターはロイヤルティを重視する。ロイヤルティは自社の利益に大きく貢献する、マーケティング費用の減少や競合他社参入の阻止など他にも様々なメリットがある、と。
ロイヤルティの重要性については、これまでに多くの専門家が議論してきた。
学者たちは「ロイヤルティが収益性のカギを握る」と繰り返し唱えてきた。コンサルタントは、顧客の生涯価値の計算方法を説いた。顧客生涯価値は、企業が新規顧客の獲得に費やせるコストを測る目安になるとされる。
こうした議論は魅力的だが、その説得力や重要性はますます小さくなっている。
顧客と企業の関係がオープン・マリッジに近くなれば、つまり浮気性の消費者が増えれば増えるほど、生涯価値は理論上の計算にすぎなくなる。特に他社に乗り換えるコストが低い場合、長期的な関係を築くのは困難だ。
長期的な関係が実現しそうもないのであれば、生涯価値の計算に基づいてマーケティング判断を下すのは無意味である。





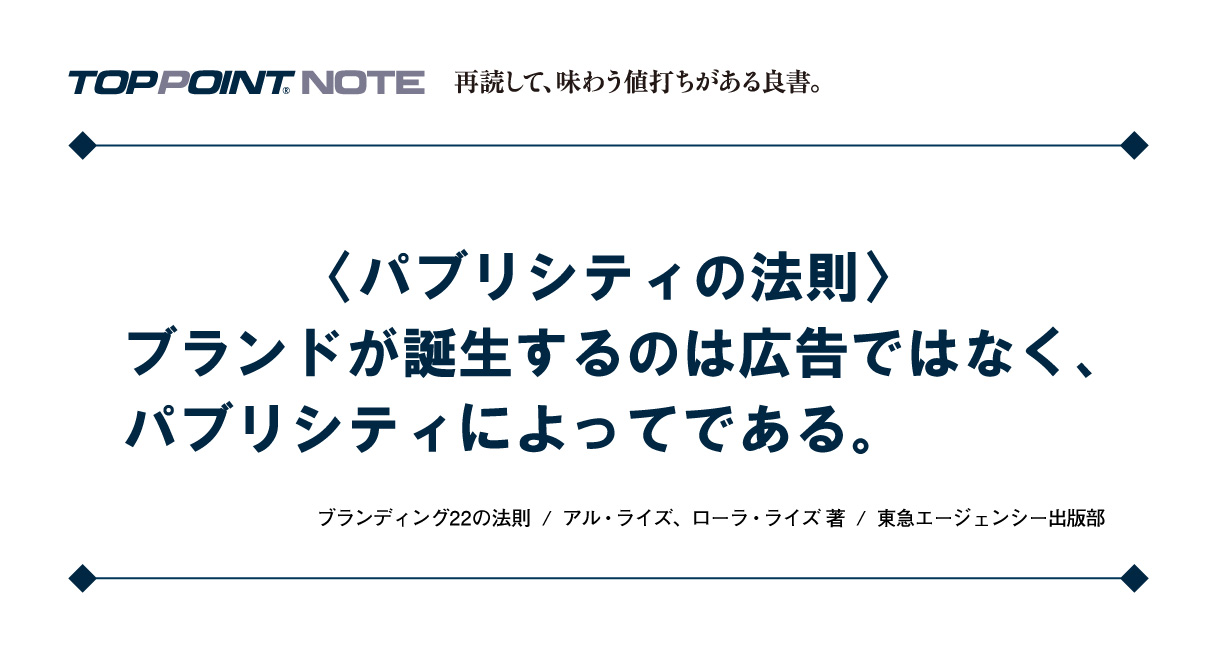
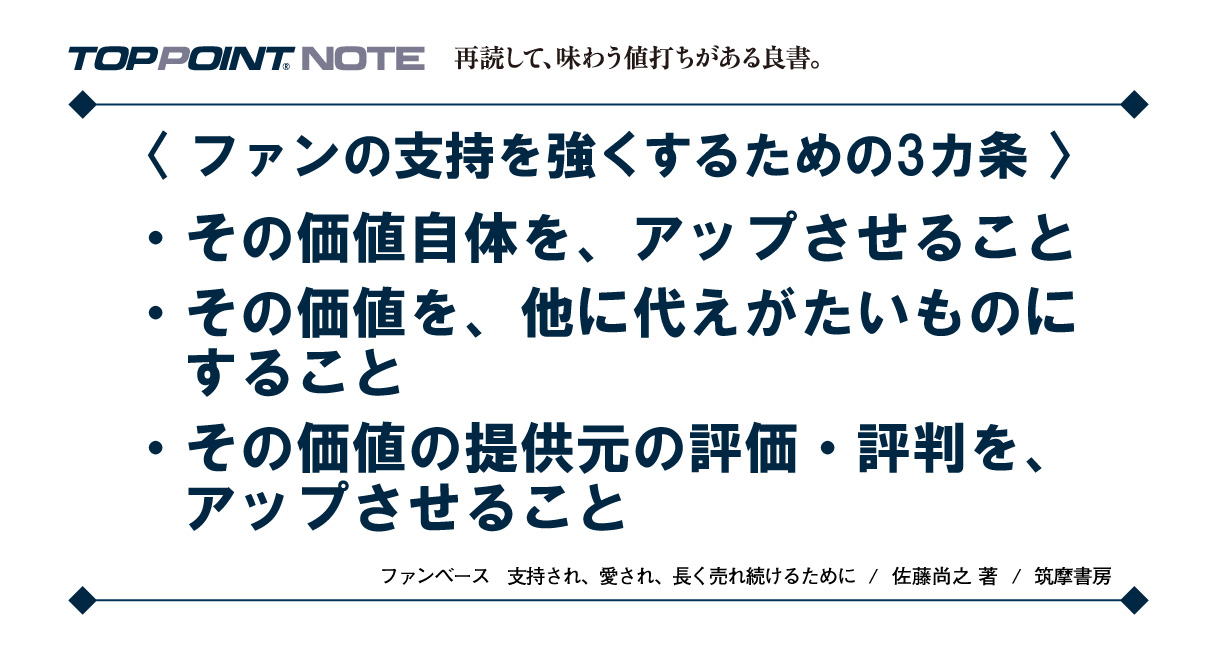
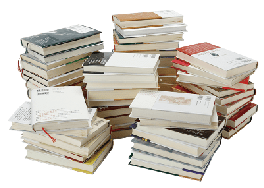
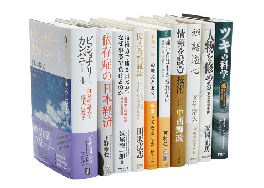
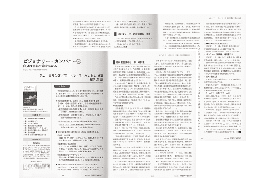


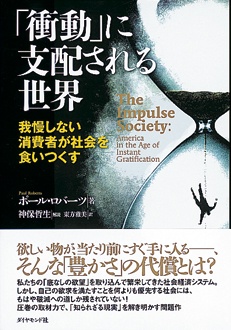
![人を動かす [新装版]](https://www.toppoint.jp/uploads/cover/20200612131136-20090810.jpg)


