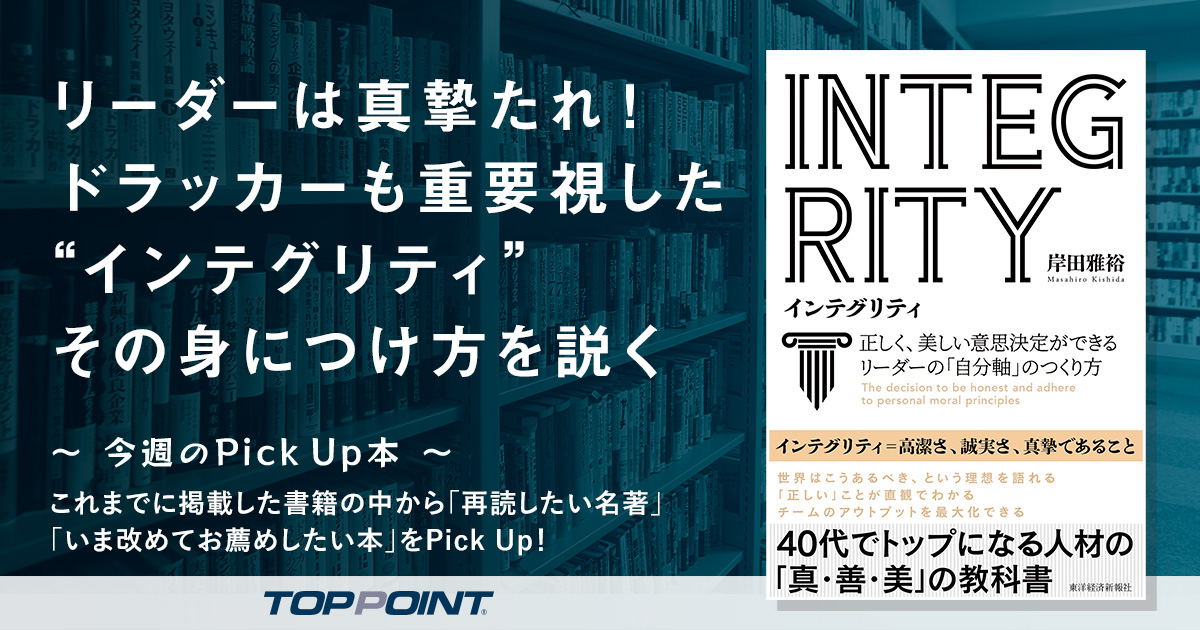
日々、様々な謝罪や釈明の会見が社会を騒がせています。
中でも印象に残りやすいのは、会見によってかえって炎上してしまうケースでしょう。
「現場がやった」と自らの関与を否定する社長。
「記憶にない」とごまかす政治家。
そもそも会見に姿を現さない責任者…。
多くの「残念な会見」に共通するのは、組織を代表する人間の資質の欠如ではないでしょうか。
では、一体リーダーにはどんな資質が求められるのか。
今週Pick Upするのは、その内容を明確化した本、『INTEGRITY インテグリティ 正しく、美しい意思決定ができるリーダーの「自分軸」のつくり方』(岸田雅裕 著/東洋経済新報社 刊)です。
このPick Up本を読んだ方は、
他にこんな記事にも興味を持たれています。
-
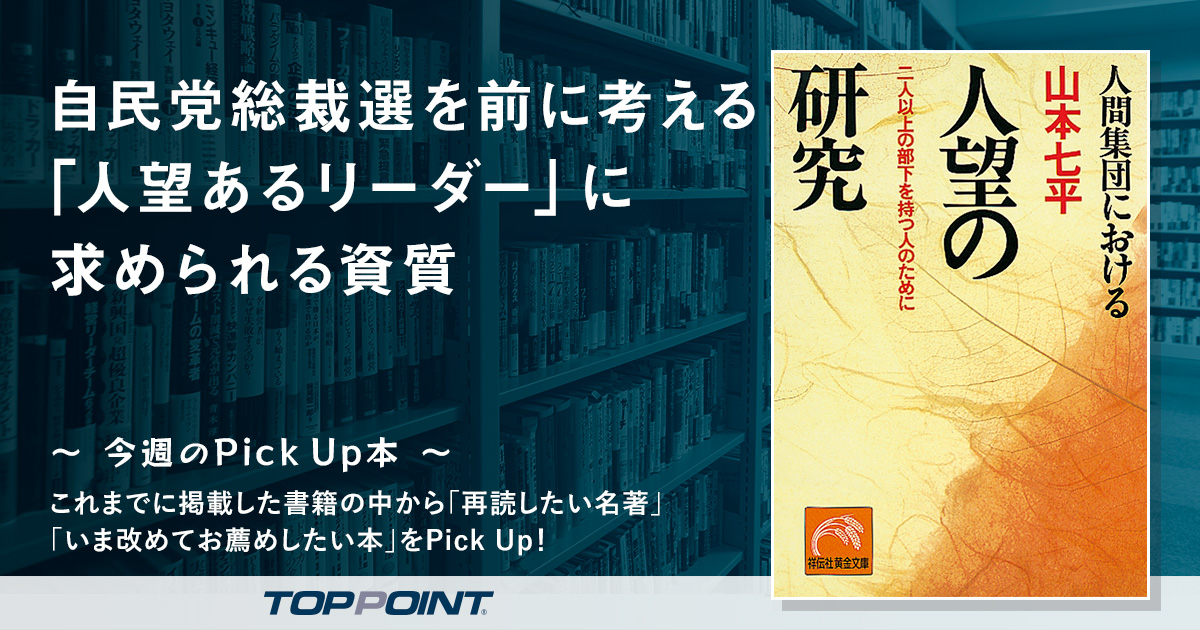
自民党総裁選を前に考える 「人望あるリーダー」に求められる資質
-

行動経済学が教える、人間心理の“クセ”とお金の賢い使い方
-
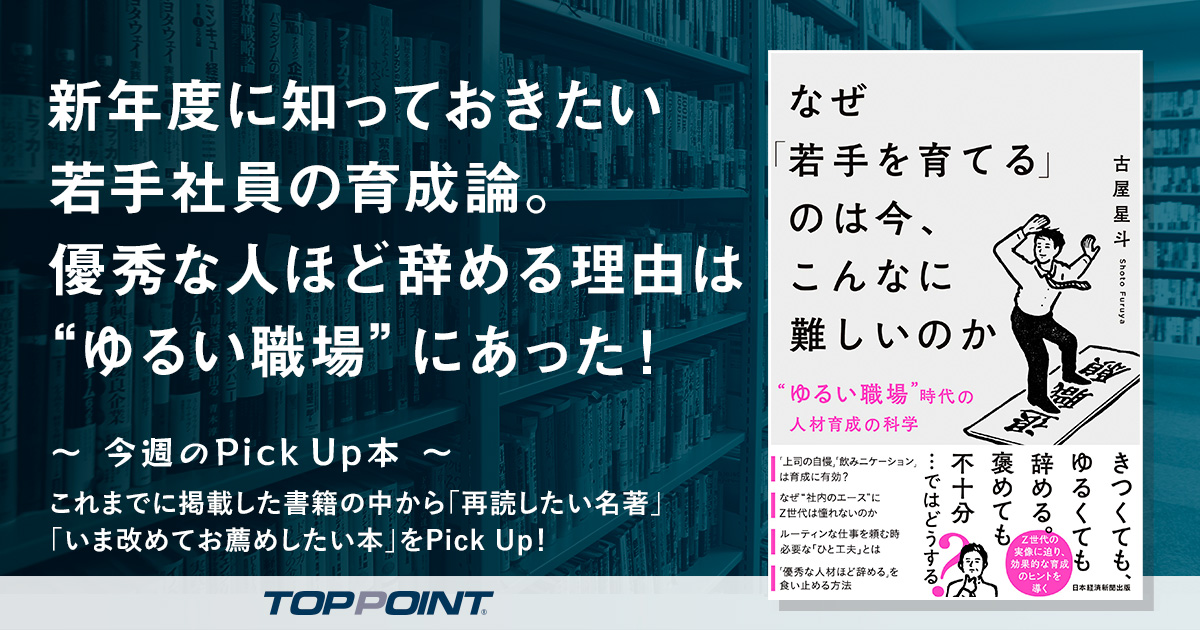
新年度に知っておきたい若手社員の育成論。優秀な人ほど辞める理由は“ゆるい職場”にあった!





