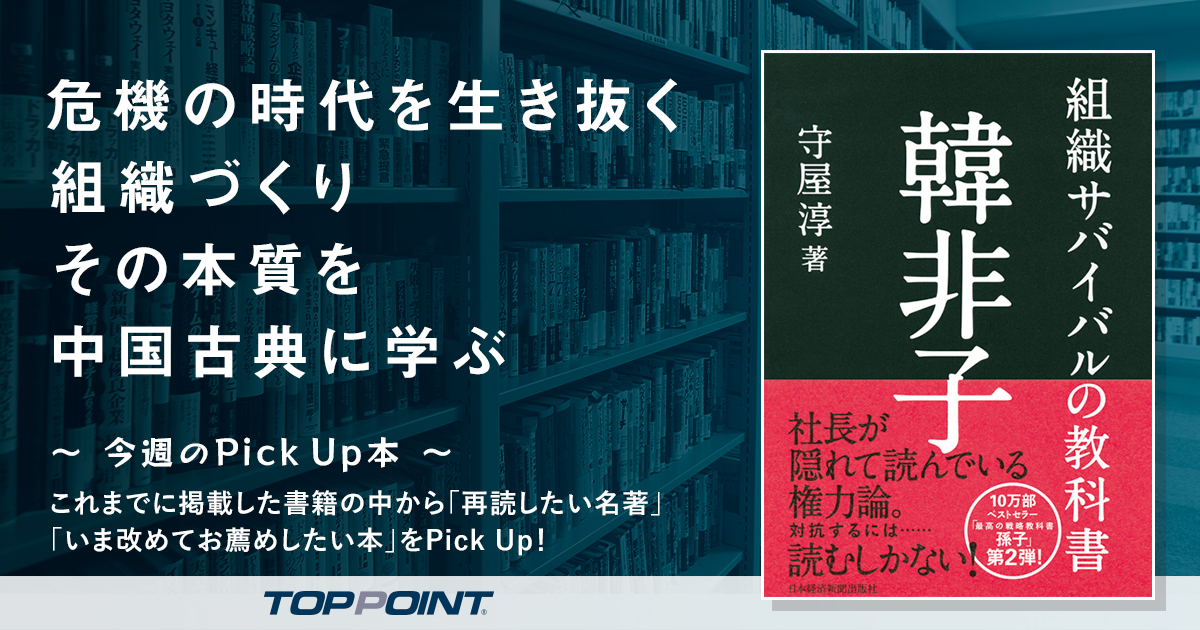
パンデミック、戦争、エネルギー危機、食糧不足、インフレ…。
今日の世界は、これまでの日常を根底から覆すような難題にさらされています。
企業のリーダーたちは、経営にも大きな影響を及ぼすこうした危機を乗り切るために、どう組織を運営すればよいのでしょうか?
今週Pick Upするのは、その悩みへのヒントを、中国古典を通して示してくれる本、『組織サバイバルの教科書 韓非子』(守屋 淳 著/日本経済新聞出版社 刊)です。
『韓非子』の著者とされる韓非が活躍したのは、紀元前3世紀頃の中国。当時は戦国時代の乱世で、彼が暮らしていた韓の国も、当時最強の秦の国に絶えず脅かされていました。
そんな状況で自国が生き延びるために、君主はいかなる統治機構を備えるべきか――。韓非は考え抜き、その結果生まれたのが、『韓非子』の思想です。2000年以上前の書ですが、組織が常に脅かされているという時代背景は、今日にも通ずるところがあります。
このPick Up本を読んだ方は、
他にこんな記事にも興味を持たれています。
-
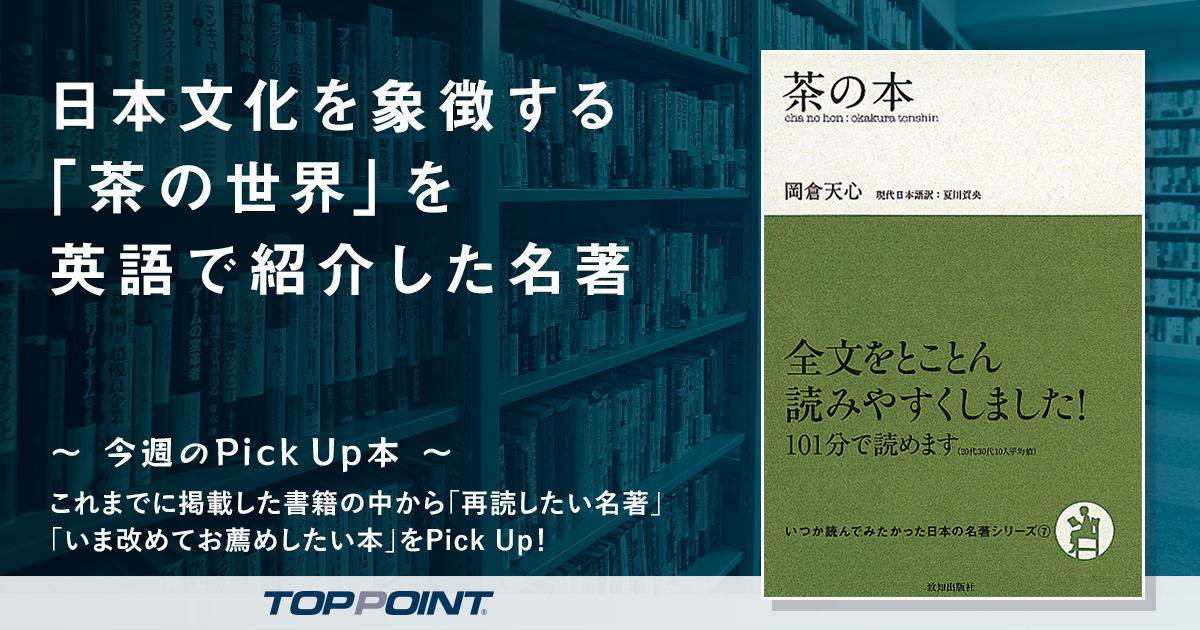
日本文化を象徴する「茶の世界」を英語で紹介した名著
-
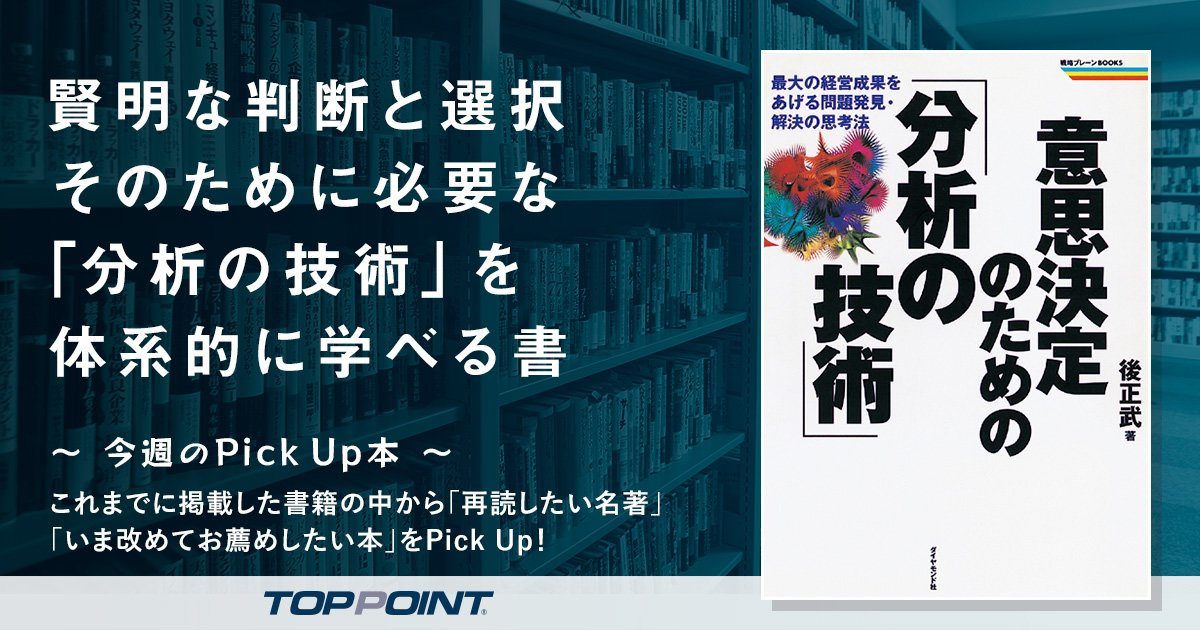
賢明な判断と選択 そのために必要な「分析の技術」を体系的に学べる書
-
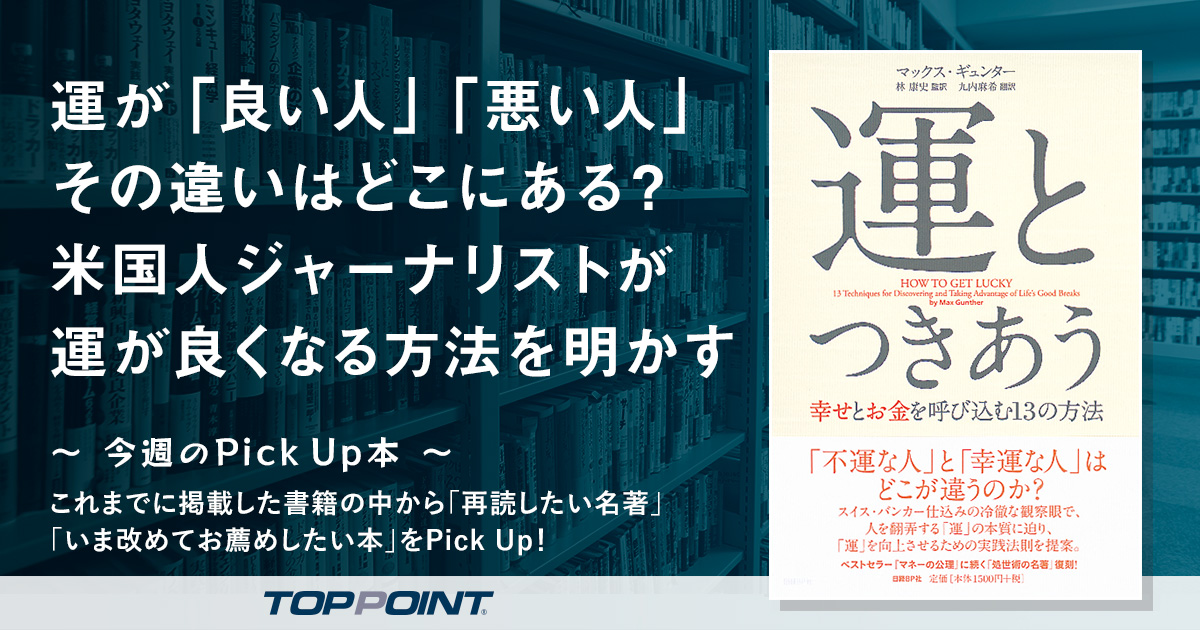
運が「良い人」「悪い人」その違いはどこにある? 米国人ジャーナリストが運が良くなる方法を明かす





