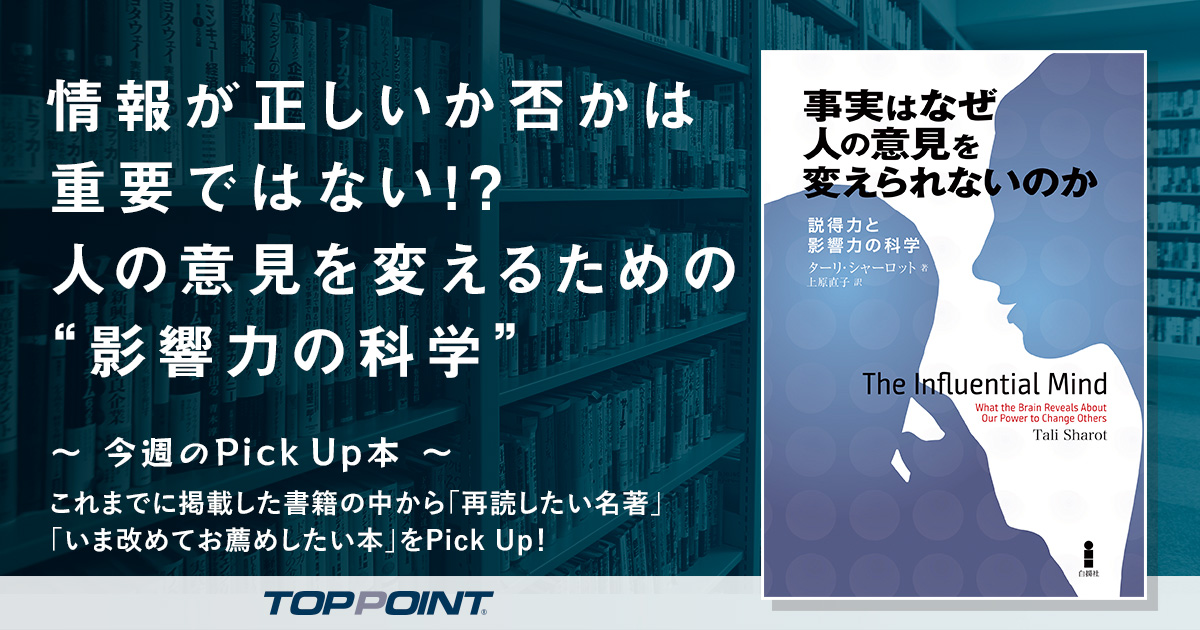
会議やプレゼンの場でのこと。
データを揃え、ファクトに基づいて論理的に自分の正しさを説明した。当然、相手も納得してくれると思っていたが、実際は何やかやと理屈をつけられ、結局こちらの意見は採用してもらえなかった…。
そんな経験をしたことはないでしょうか。
疑いようのない事実をもとにした説得が、まるで成果につながらない。そうしたことは、日常生活やビジネスシーンで珍しくありません。
一方で、私たちは生きていくうえで、そして仕事を進める中で、「人の意見を変える」必要に迫られることが多々あります。
特にリーダー・マネジャーにとって、多様なメンバーの意見をまとめ上げ、チームとして1つの方向性をつくっていくことは、重要な課題です。
このジレンマを、どう解消すればいいのか?
今週Pick Upするのは、この点に1つの示唆を与えてくれる本、『事実はなぜ人の意見を変えられないのか 説得力と影響力の科学』(ターリ・シャーロット 著/白揚社 刊 )です。
このPick Up本を読んだ方は、
他にこんな記事にも興味を持たれています。
-
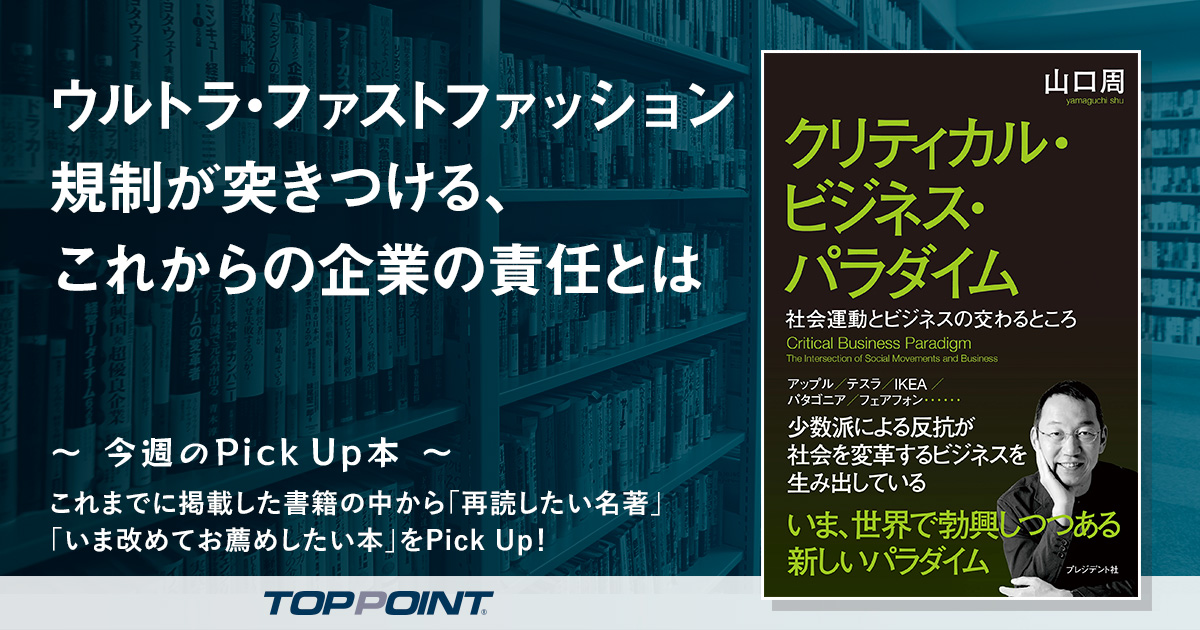
ウルトラ・ファストファッション規制が突きつける、これからの企業の責任とは
-
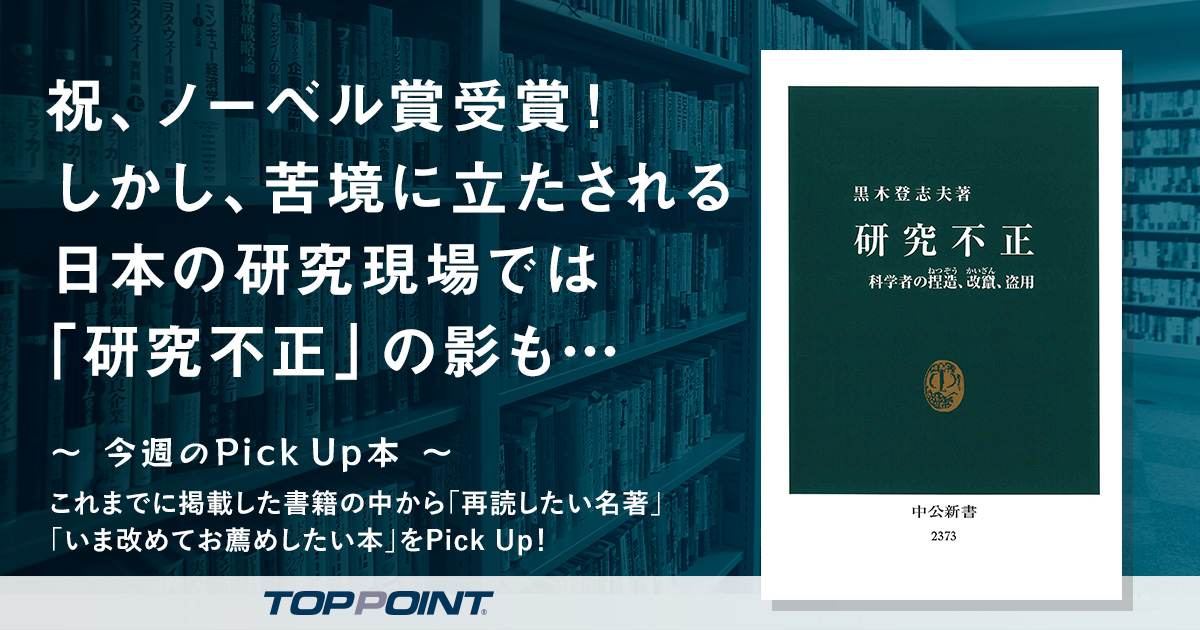
祝、ノーベル賞受賞! しかし、苦境に立たされる日本の研究現場では「研究不正」の影も…
-
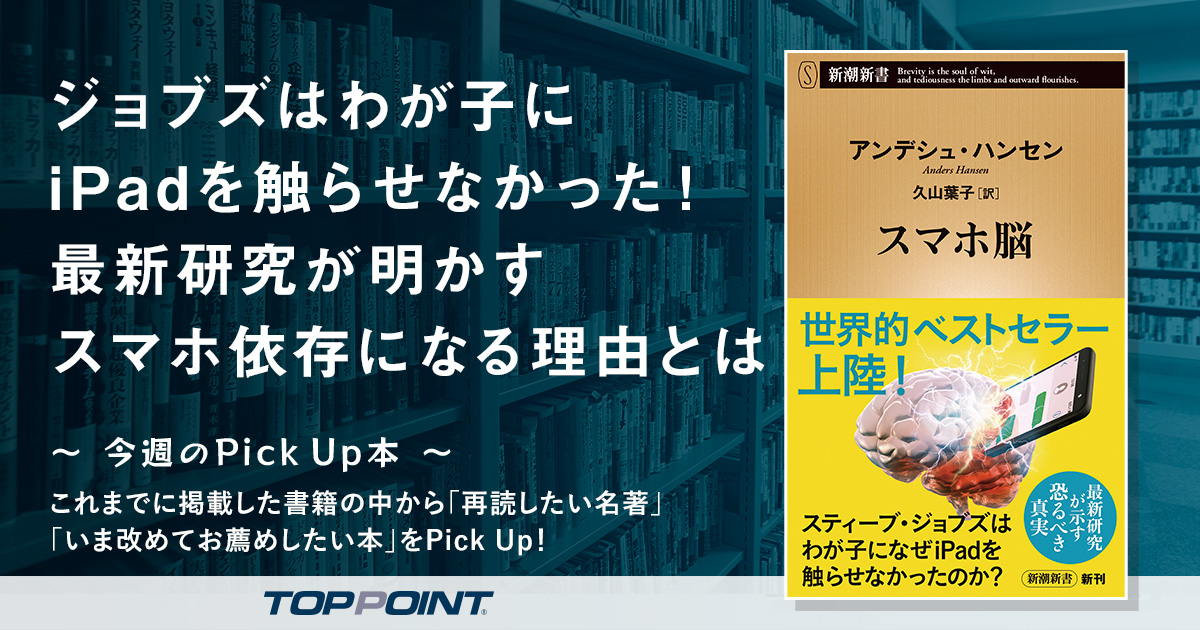
ジョブズはわが子にiPadを触らせなかった! 最新研究が明かすスマホ依存になる理由とは





