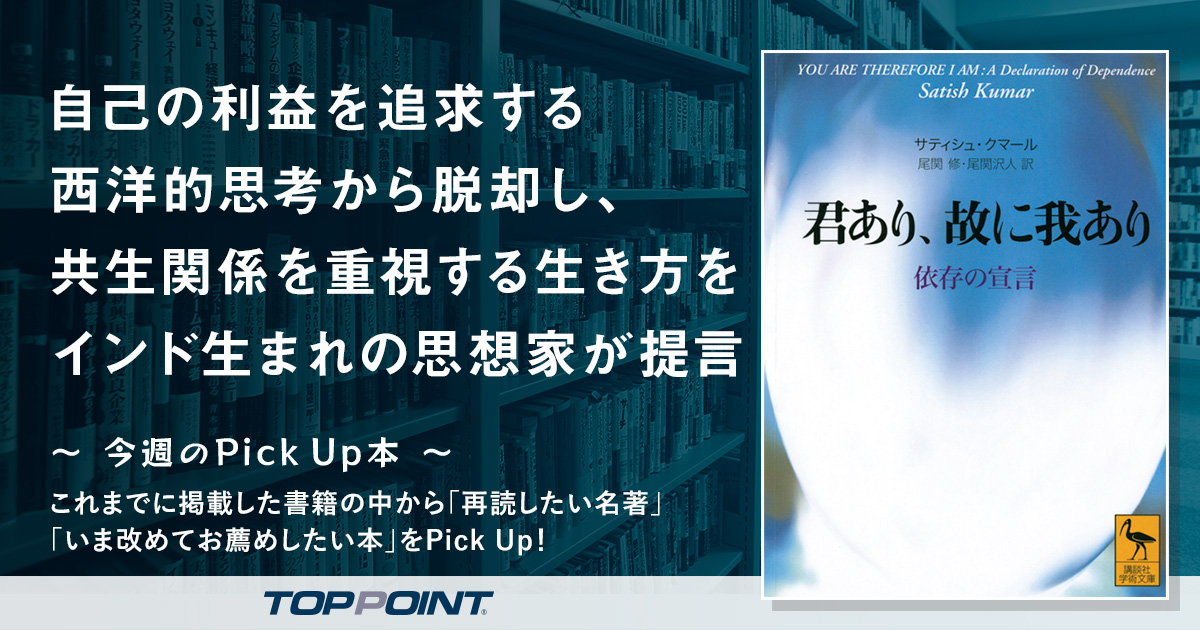
先週木曜日、11月16日は国際寛容デーでした。1996年に国連で制定されたこの日は、前年に採択された「寛容に関する原則の宣言」に基づいています。
宣言では、「寛容」という言葉を次のように定義しています。
「豊かな多様性に富む世界の文化、表現の手段、人間としてのあり方を尊重し、受け入れ、享受すること」(ユネスコスクールHP)
残念ながら、今の世界は寛容とはほど遠い状態にあります。国家間の争いのみならず、宗教間や人種間の不寛容が原因となり、様々な軋轢が生じています。日本でもSNSなどを中心に、他者の誤りや失敗に対する容赦ない攻撃など、不寛容な動きが広まっています。
このPick Up本を読んだ方は、
他にこんな記事にも興味を持たれています。
-

宇宙を味方にする「そ・わ・か」の力。掃除・笑い・感謝で人生はもっと輝く!
-
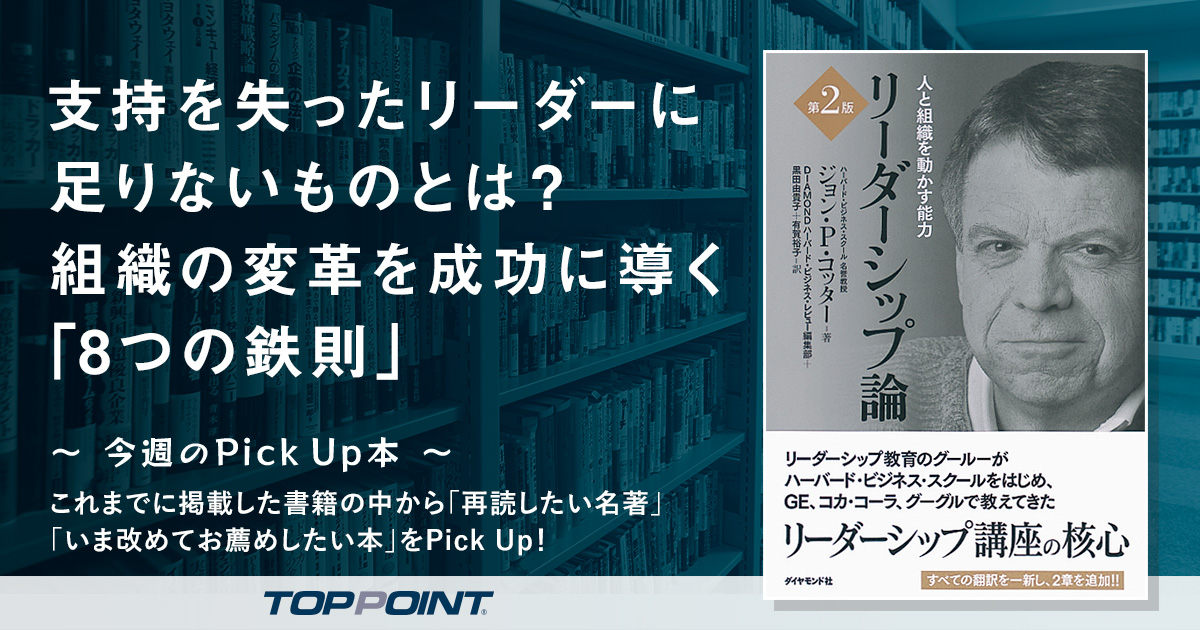
支持を失ったリーダーに足りないものとは? 組織の変革を成功に導く「8つの鉄則」
-
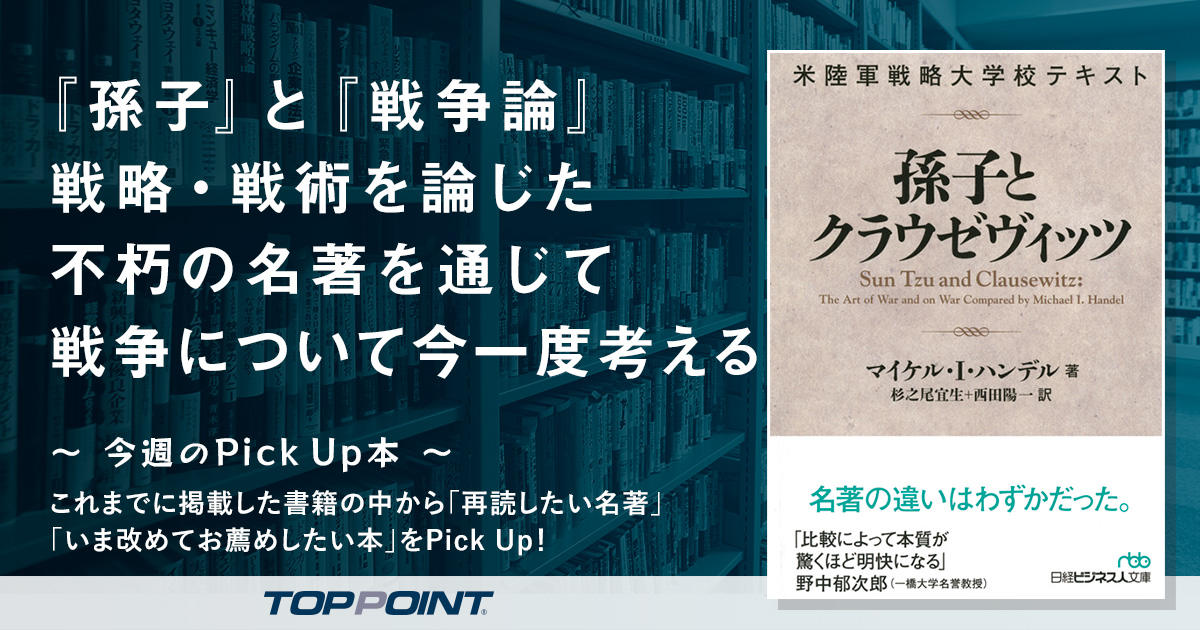
『孫子』と『戦争論』 戦略・戦術を論じた不朽の名著を通じて戦争について今一度考える





