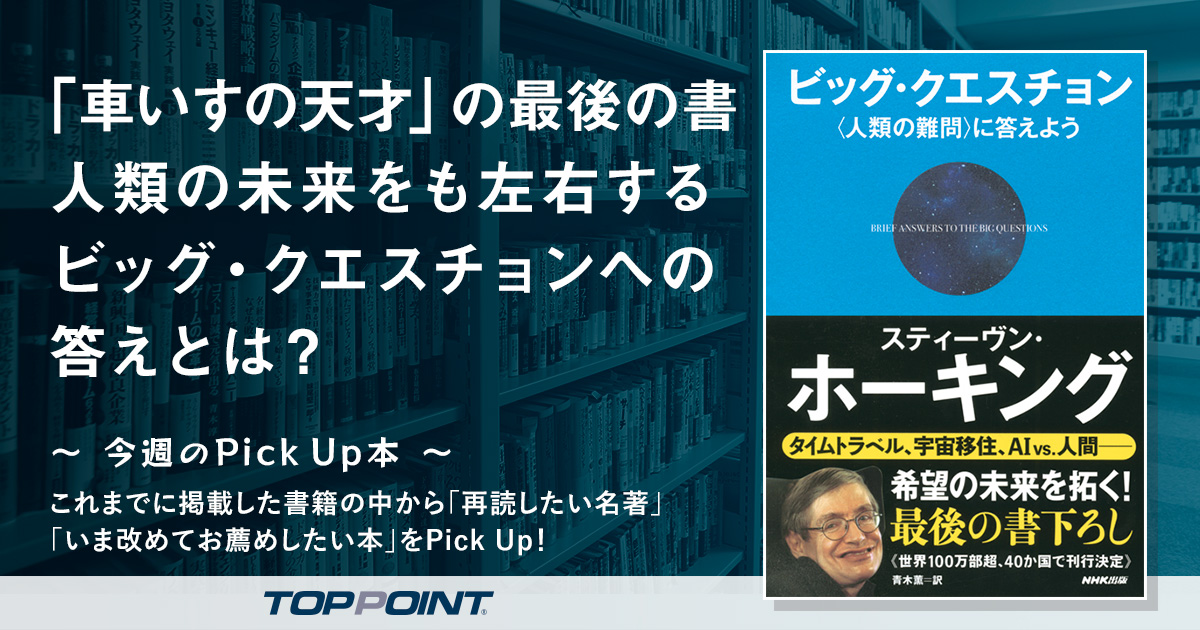
2023年2月28日、宇宙航空研究開発機構(JAXA)は、宇宙飛行士候補者の募集結果を発表しました。募集が行われたのは13年ぶりで、応募者の数は過去最多となる4,127人。JAXAは「これから宇宙飛行士の活動の場が月周回や月面に広がることを見据え」募集を行ったとしており、今後、一般の人々にとっても宇宙がより身近なものになっていくことが期待されます。
さて、そんな宇宙について、「銀河系の果てまで行ったこともあるし、ブラックホールの内部に入ったことも、時間の始まりにまで遡ったこともある」と語った人物がいます。――「頭と物理法則を使って」、宇宙をまたにかける旅をしてきた、と。
その人物の名は、スティーヴン・ホーキング。特にブラックホールの研究で有名で、「車いすの天才」としても知られる偉大な科学者です。
2018年3月14日にこの世を去ったホーキング博士。その命日を前に、今週は博士の最後の著書である『ビッグ・クエスチョン 〈人類の難問〉に答えよう』(スティーヴン・ホーキング 著/NHK出版 刊)をPick Upしたいと思います。
本書の魅力の1つは、世界最高峰の宇宙物理学者が、誰も解き明かしていない究極の問いについて、わかりやすく、時にユーモアを交えながら語っている点でしょう。
本書で取り上げられる「ビッグ・クエスチョン」は10あります。そのうち「ブラックホールの内部には何があるのか?」「タイムトラベルは可能なのか?」など6つは、ホーキング博士の研究分野に関わる問いです。
当然、きわめて専門性の高い内容ですが、本書では難解な数式をほぼ用いず、平易に語られています。加えて、博士一流の「お茶目さ」が随所に見受けられ、読む者を飽きさせません。
例えば、「タイムトラベルは可能なのか?」という章の最後で、博士はこんなエピソードを明かしています。
このPick Up本を読んだ方は、
他にこんな記事にも興味を持たれています。
-
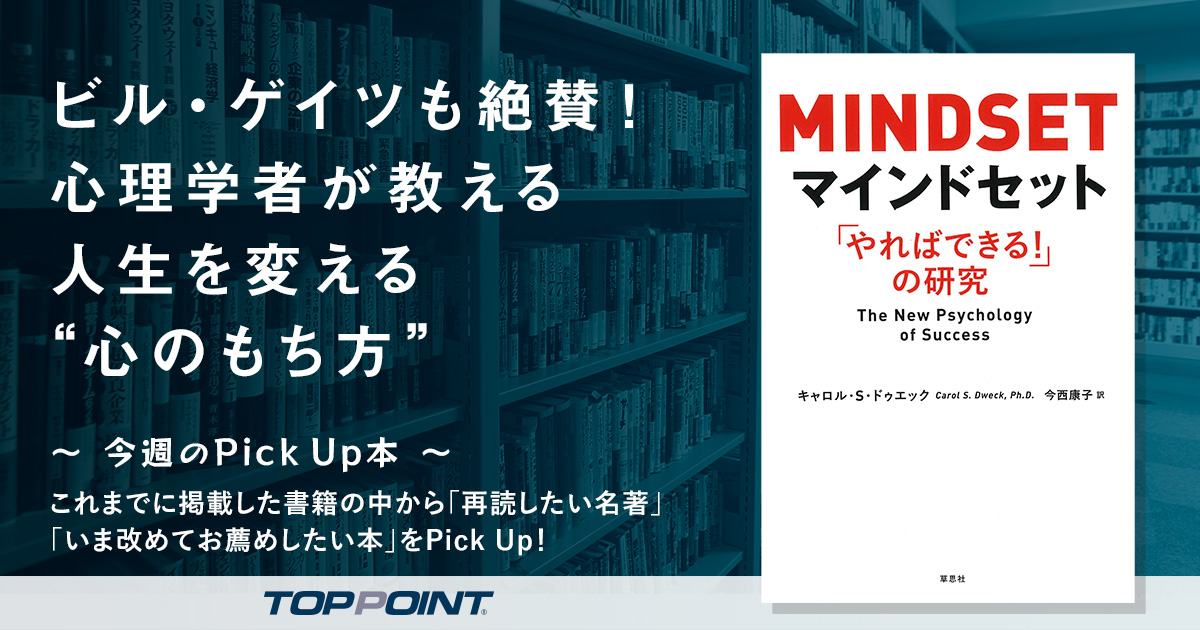
ビル・ゲイツも絶賛! 心理学者が教える 人生を変える“心のもち方”
-
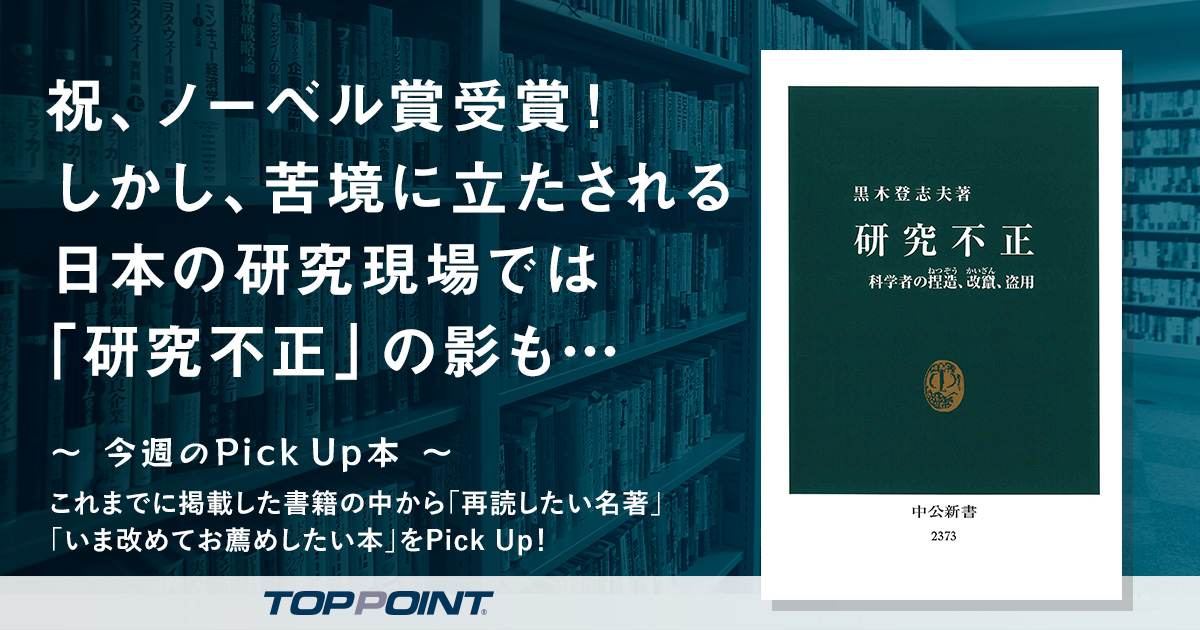
祝、ノーベル賞受賞! しかし、苦境に立たされる日本の研究現場では「研究不正」の影も…
-
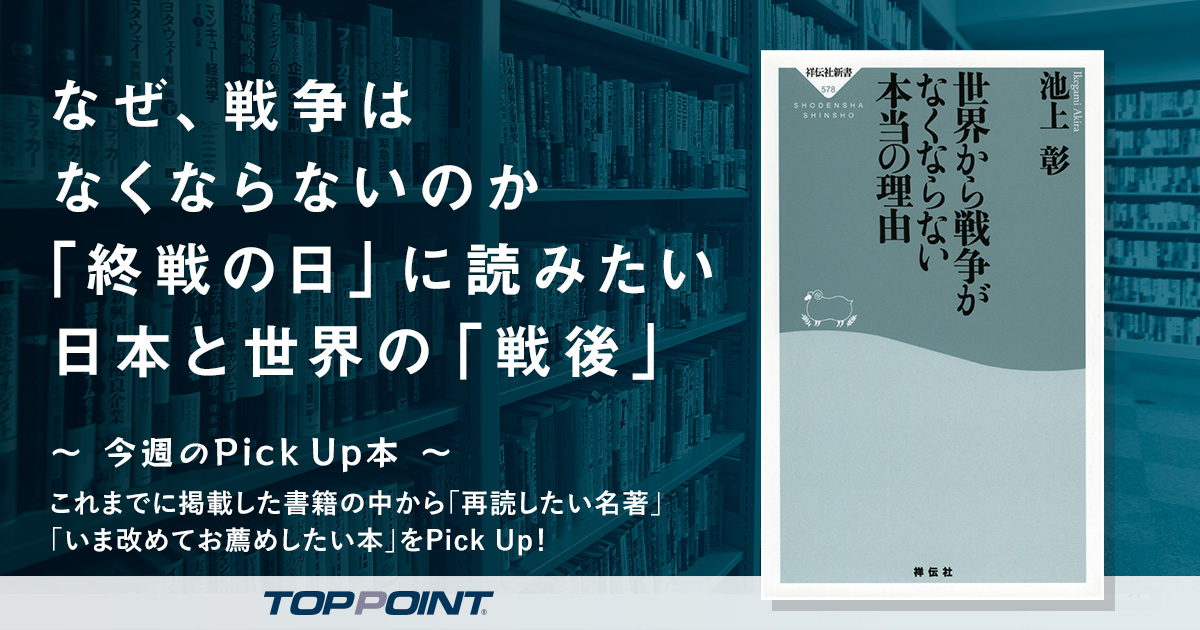
なぜ、戦争はなくならないのか 「終戦の日」に読みたい日本と世界の「戦後」





