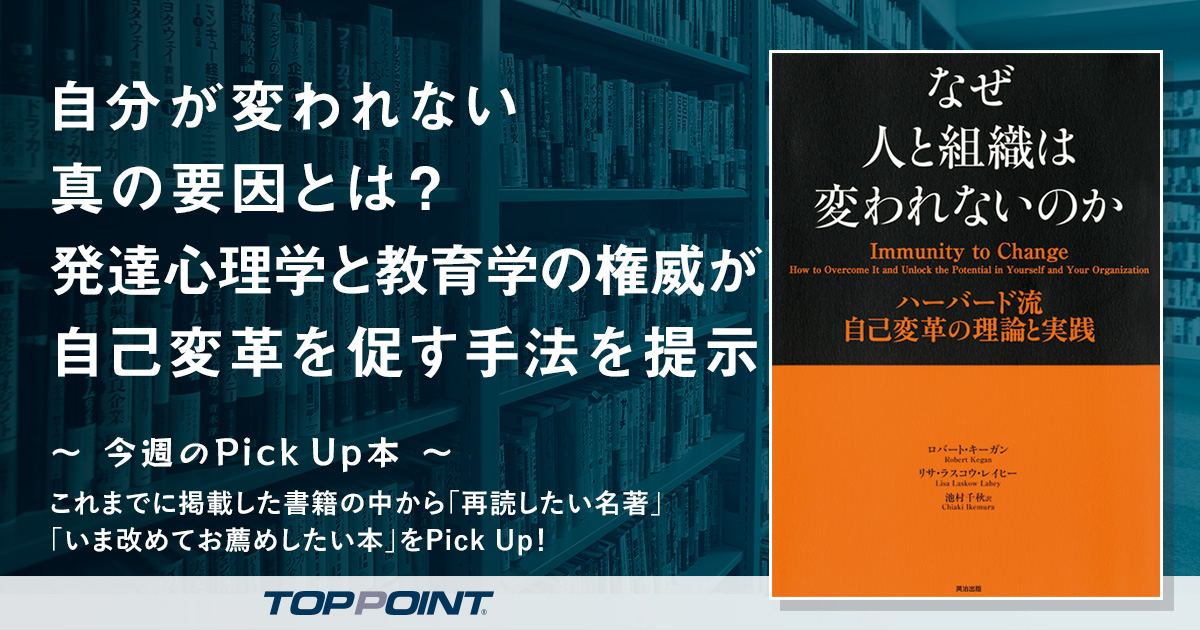
あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。
さて、新しい年を始めるにあたり、「新年の誓い」を立てられる方は多いのではないでしょうか。「今年こそは資格を取りたい」「リーダーシップを発揮できる人間になりたい」「ダイエットに成功したい」…。私も毎年、誓いを立てる1人です。しかし、1年後に振り返ってみると、あの誓いはどこにいったのかと思うこともしばしば。自分の実行力のなさ、意志の弱さを痛感します。
自分を変えるにはどうすればよいのか ―― 。そんなことを考えている時に目に留まった本が、今週Pick Upする『なぜ人と組織は変われないのか ハーバード流 自己変革の理論と実践』(ロバート・キーガン、リサ・ラスコウ・レイヒー 著/英治出版 刊)です。発達心理学と教育学の権威による本書は、意志を強くするだけでは自分を変えられないということを教えてくれました。
なぜ、自分を変えることが難しいのか。もし、本当に変えようとするならば、どのようなところに目を向ければよいのか。この点について、本書は次のように説きます。
このPick Up本を読んだ方は、
他にこんな記事にも興味を持たれています。
-
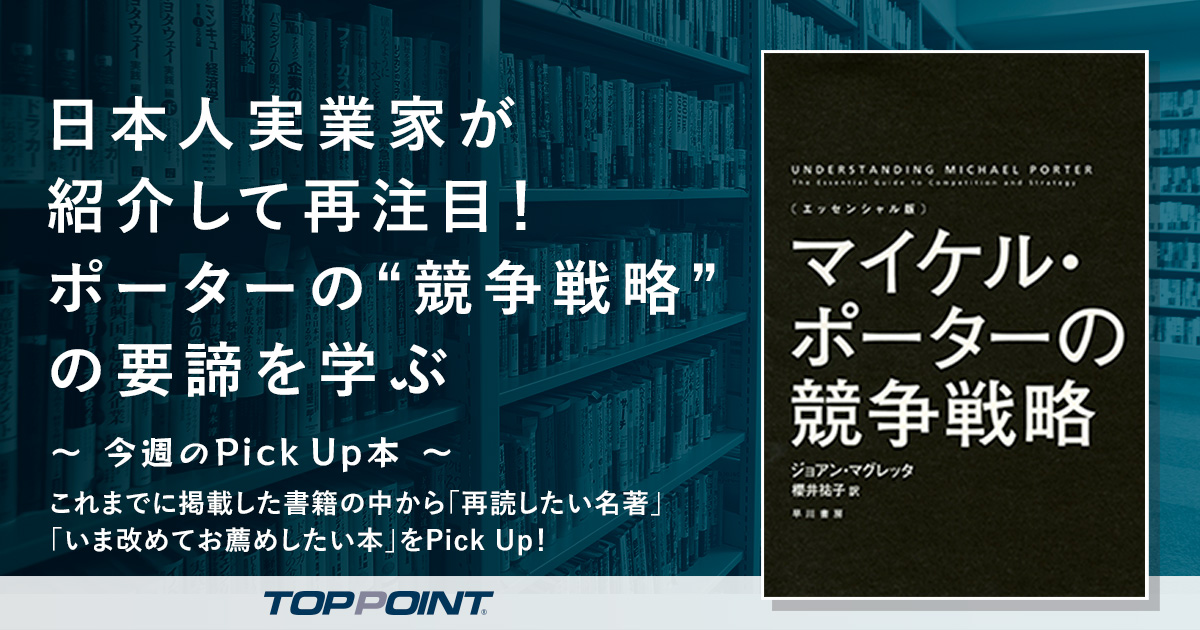
日本人実業家が紹介して再注目! ポーターの“競争戦略”の要諦を学ぶ
-
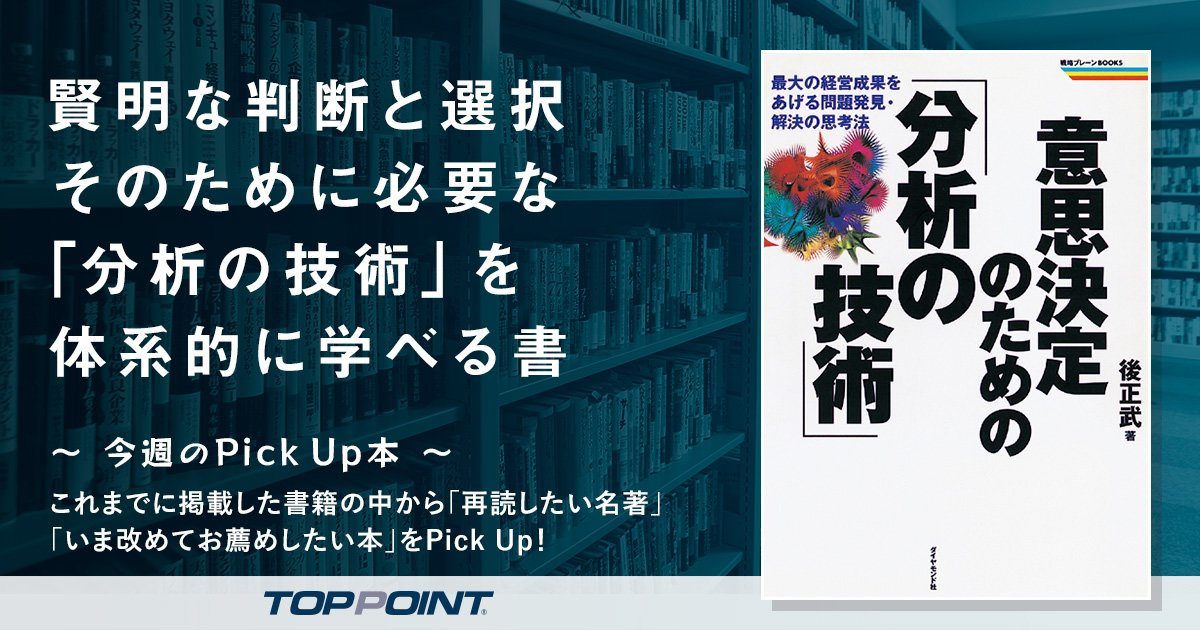
賢明な判断と選択 そのために必要な「分析の技術」を体系的に学べる書
-
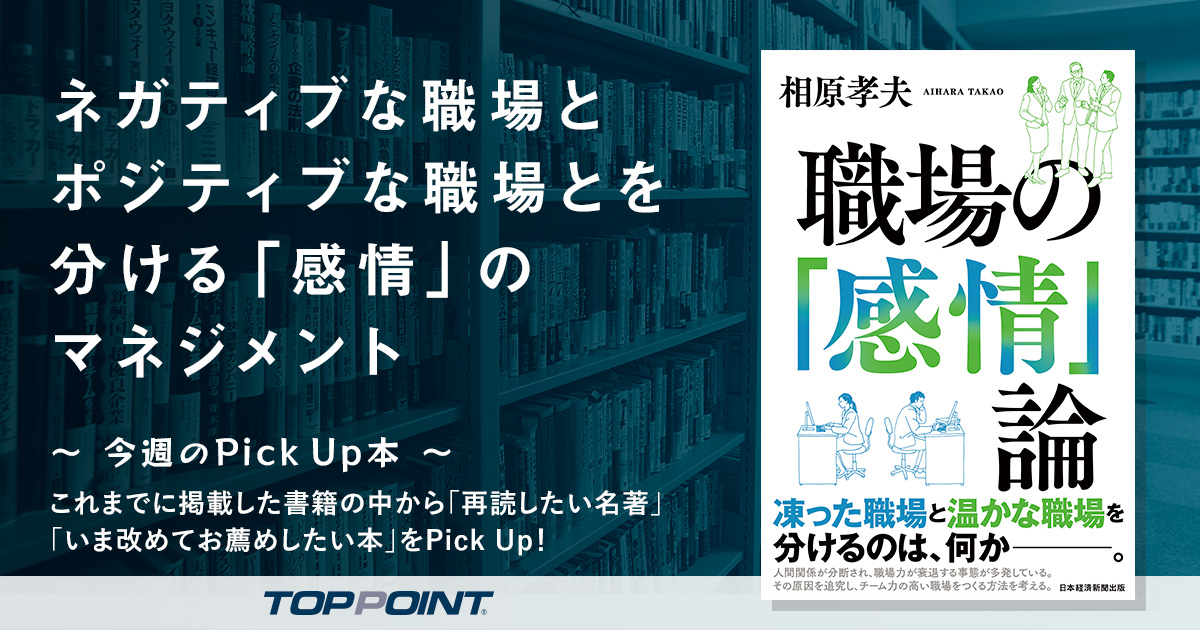
ネガティブな職場とポジティブな職場とを分ける 「感情」のマネジメント





