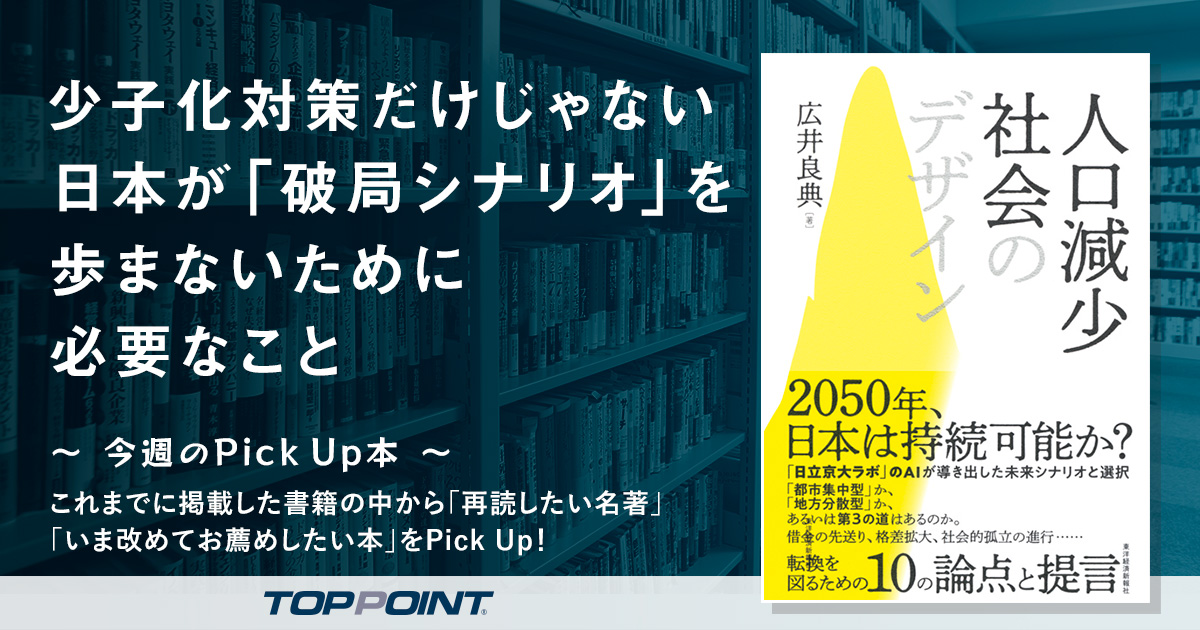
2023年6月13日、政府は少子化対策の強化に向けて、「こども未来戦略方針」を閣議決定しました。
この方針の冒頭では、近年少子化が加速していることや、急速な少子化・人口減少に歯止めをかけなければ日本の経済・社会システムの維持が難しいといった状況を述べた上で、次のように書いています。
若年人口が急激に減少する2030年代に入るまでが、こうした状況を反転させることができるかどうかの重要な分岐点であり、2030年までに少子化トレンドを反転できなければ、我が国は、こうした人口減少を食い止められなくなり、持続的な経済成長の達成も困難となる。
このPick Up本を読んだ方は、
他にこんな記事にも興味を持たれています。
-
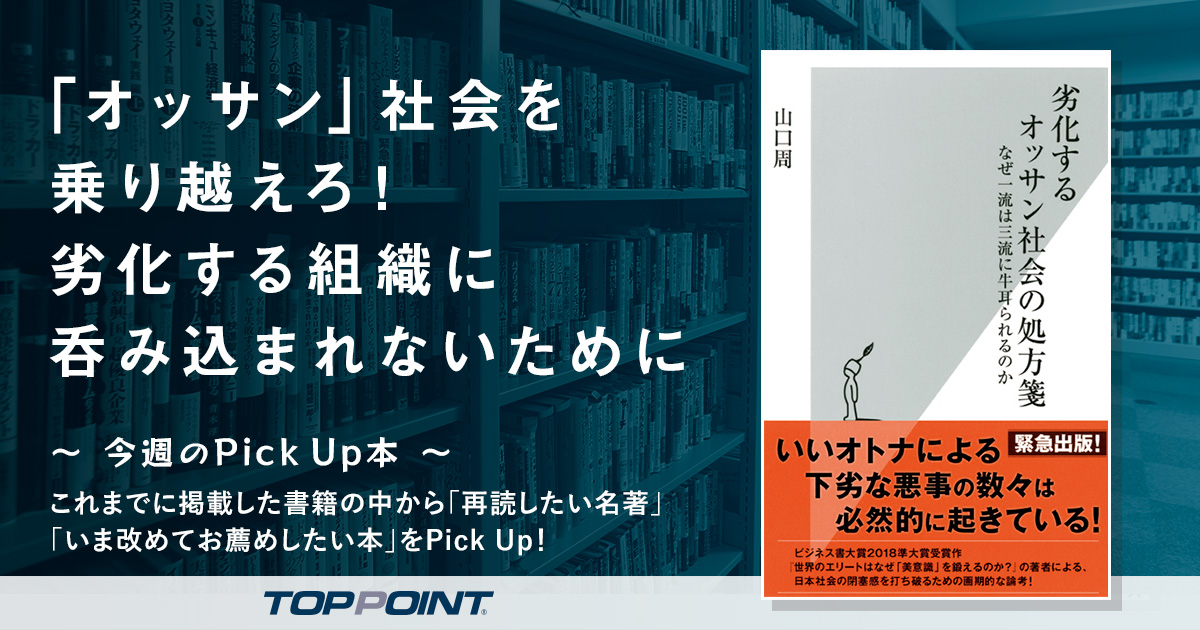
「オッサン」社会を乗り越えろ! 劣化する組織に呑み込まれないために
-
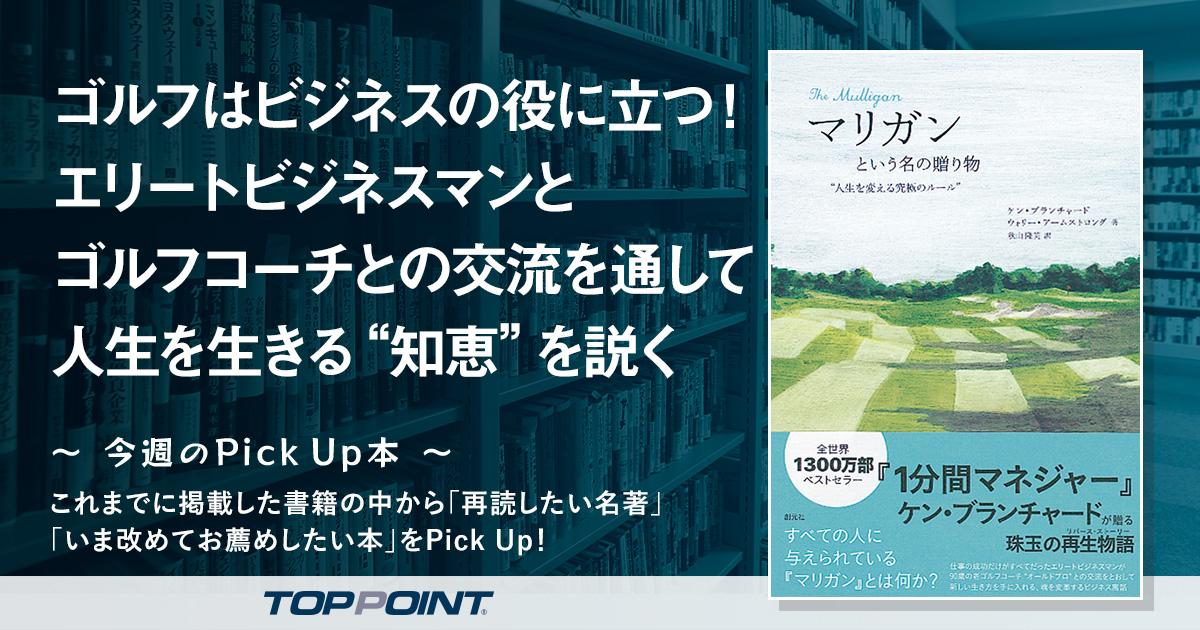
ゴルフはビジネスの役に立つ! エリートビジネスマンとゴルフコーチとの交流を通して人生を生きる“知恵”を説く
-
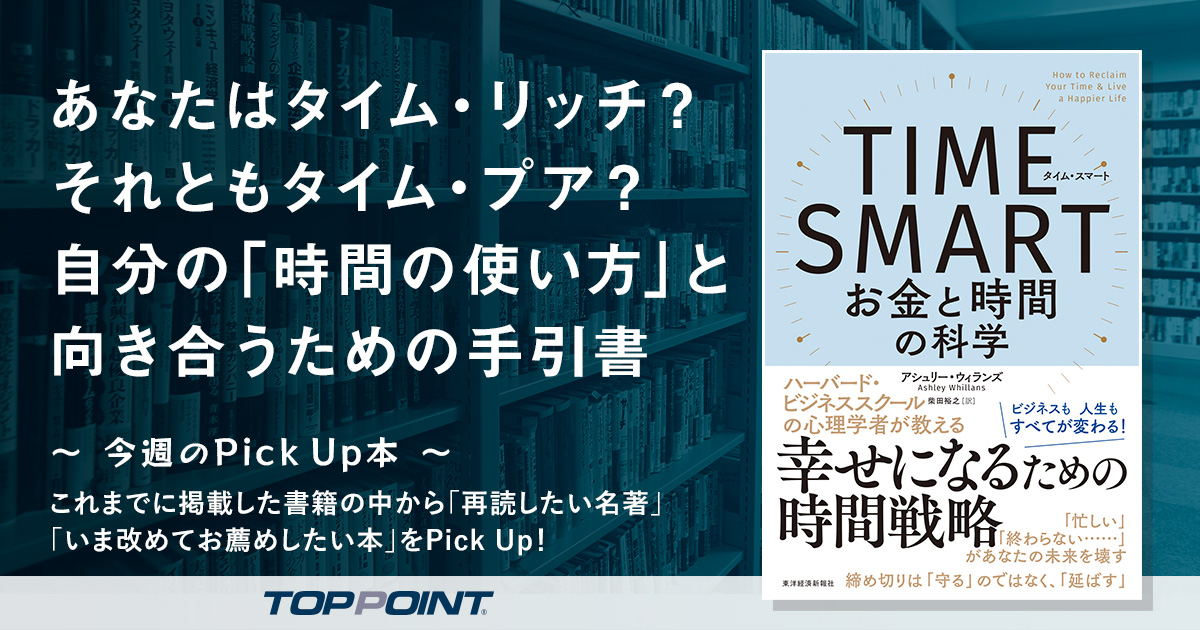
あなたはタイム・リッチ? それともタイム・プア? 自分の「時間の使い方」と向き合うための手引書





