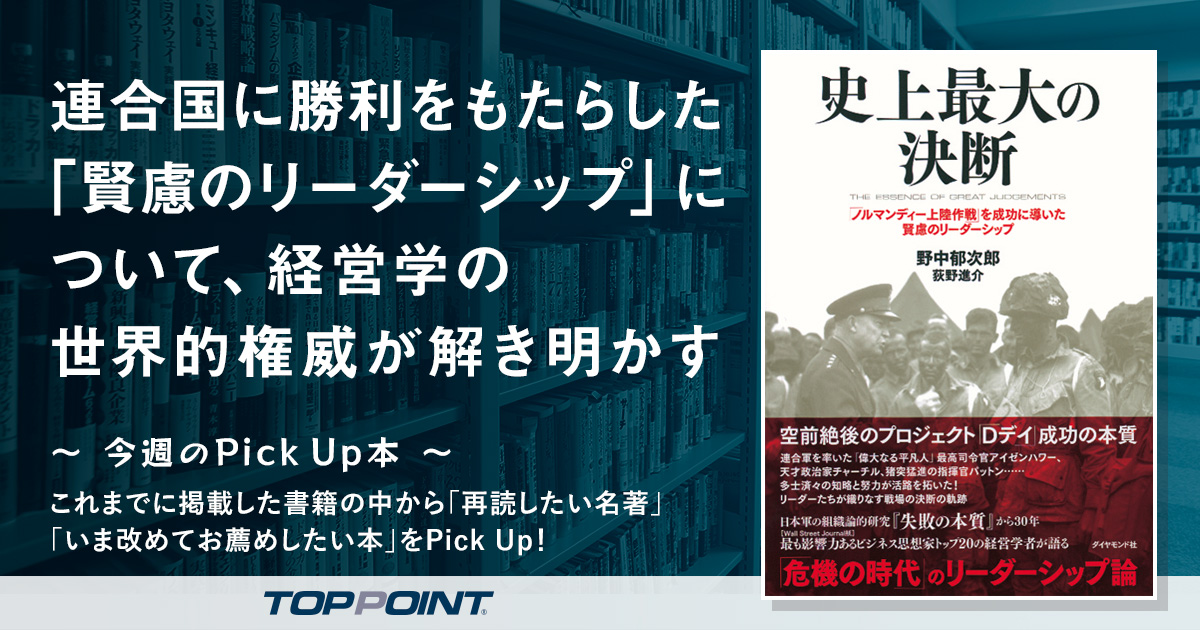
本日8月15日は終戦記念日です。第2次世界大戦の終結から77年がたった今なお、ロシアによるウクライナ侵攻など、世界では戦争・紛争の火は消えていません。1日も早く平和が訪れることを願うばかりです。
先週、編集部・西田が「今週のPick Up本」で紹介した『敗戦真相記』(永野 護 著/バジリコ 刊)は、第2次世界大戦がなぜ起こったのか、なぜ日本が破れたのか、その“真相”を明かす名著でした。
今回は視点を変えて、英米をはじめとした連合国が第2次世界大戦で勝利した要因にスポットを当てたいと思います。紹介する本は、『史上最大の決断 「ノルマンディー上陸作戦」を成功に導いた賢慮のリーダーシップ』(野中郁次郎、荻野進介 著/ダイヤモンド社 刊)です。
なお、著者の野中郁次郎氏は、第2次世界大戦における日本軍の敗因を分析した名著『失敗の本質―日本軍の組織論的研究』(戸部良一、寺本義也、鎌田伸一、杉之尾孝生、村井友秀、野中郁次郎 著/中央公論新社 刊)の執筆者の1人でもあります。
副題にある「ノルマンディー上陸作戦」(別名オーバーロード作戦)とは、1944年6月6日に連合軍がドイツ支配下のフランス・ノルマンディー海岸に反攻上陸した、史上最大の上陸作戦です。連合軍はD・アイゼンハワー元帥の指揮下に、艦艇約4000隻、重爆撃機2500機、戦闘爆撃機7000機、上陸部隊17万5000人を投入しました。
ノルマンディー上陸作戦は成功し、連合国側が勝利を収めます。その要因の1つとして、本書では「実践知」に長けたリーダーの存在を挙げています。実践知とは、次のようなものです。
このPick Up本を読んだ方は、
他にこんな記事にも興味を持たれています。
-
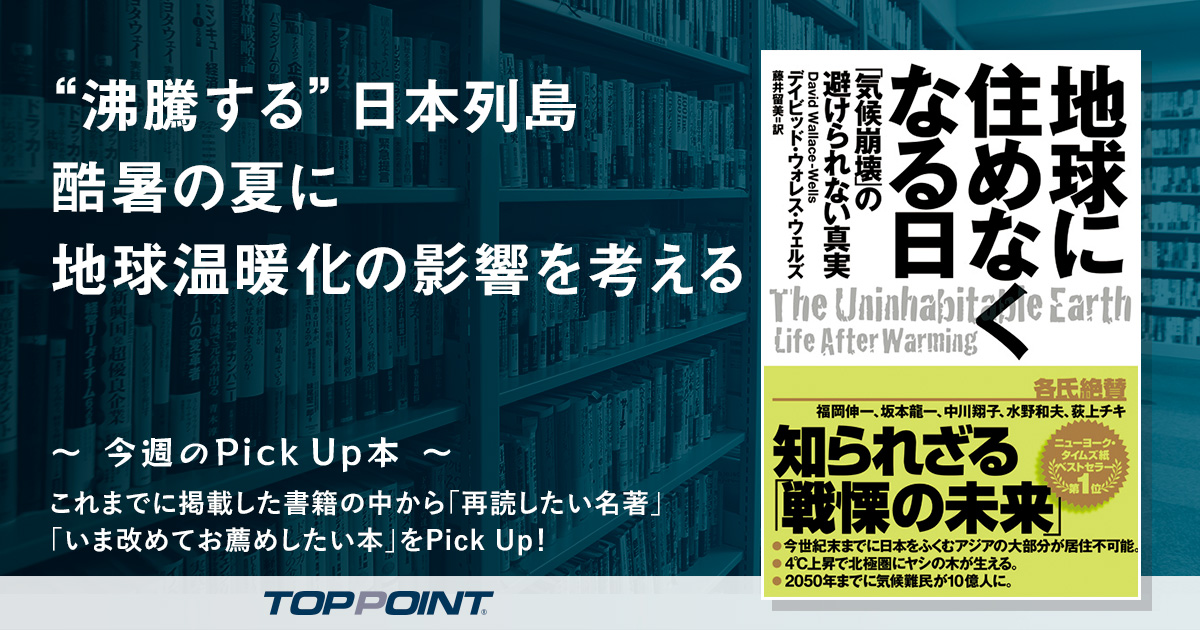
“沸騰する”日本列島 酷暑の夏に地球温暖化の影響を考える
-
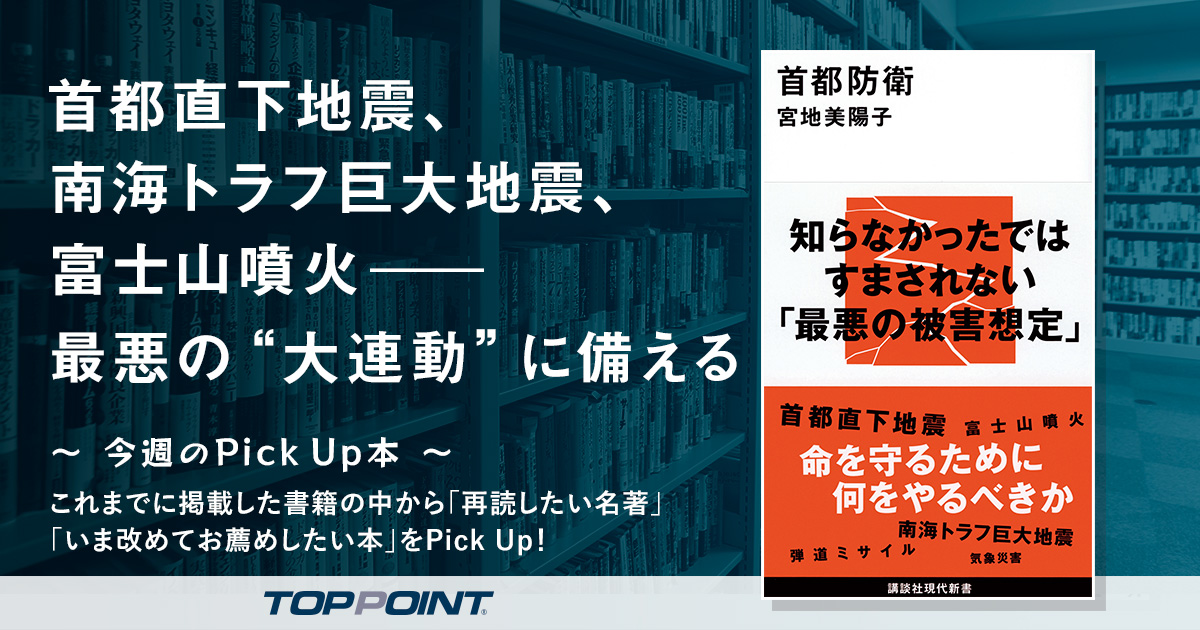
首都直下地震、南海トラフ巨大地震、富士山噴火―― 最悪の“大連動”に備える
-
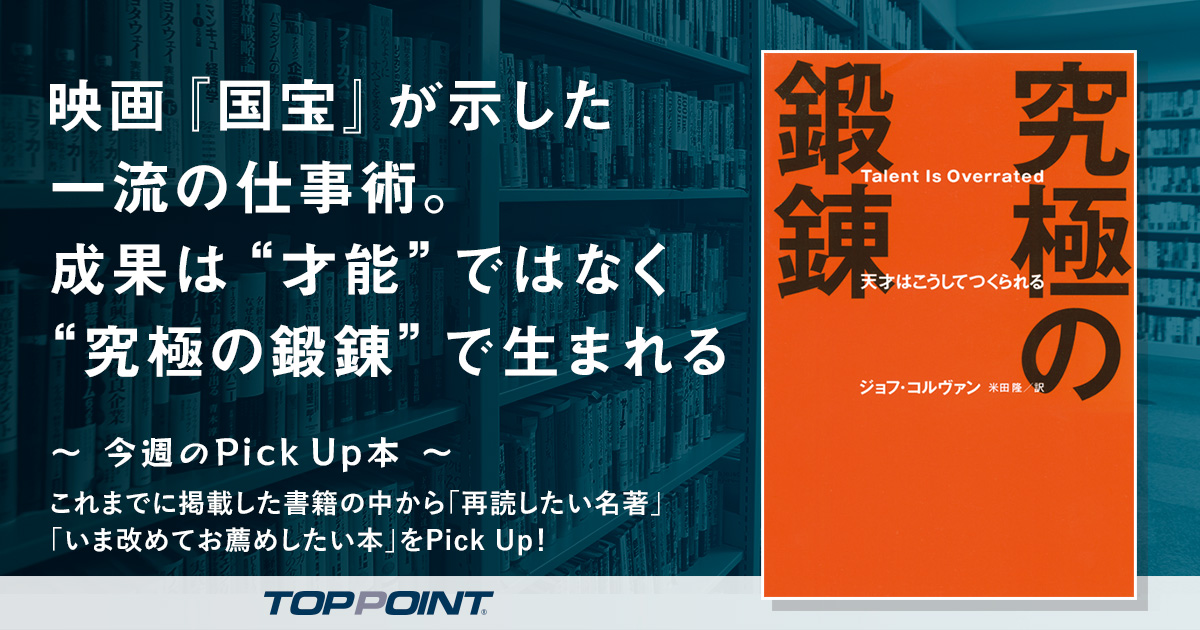
映画『国宝』が示した一流の仕事術。成果は“才能”ではなく“究極の鍛錬”で生まれる





