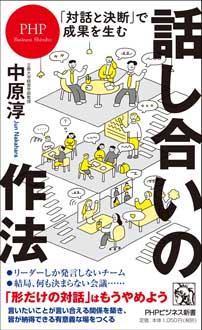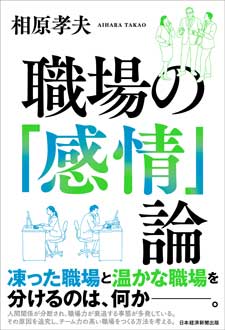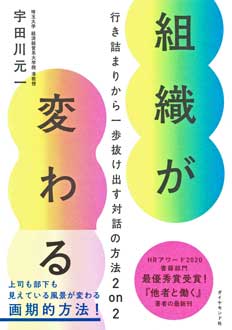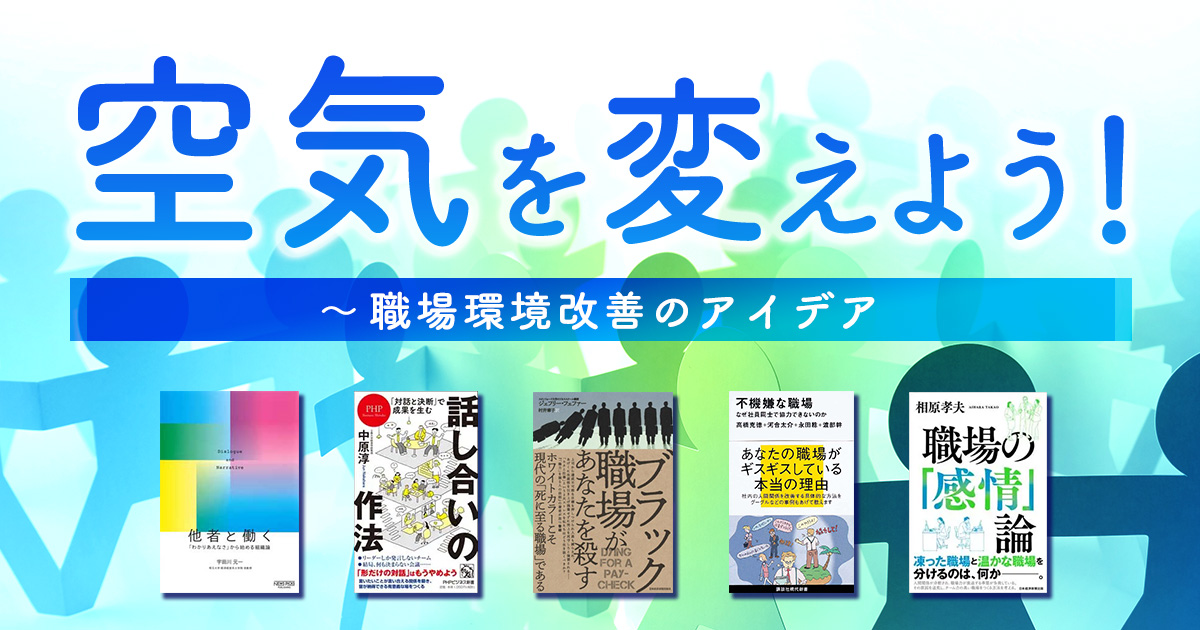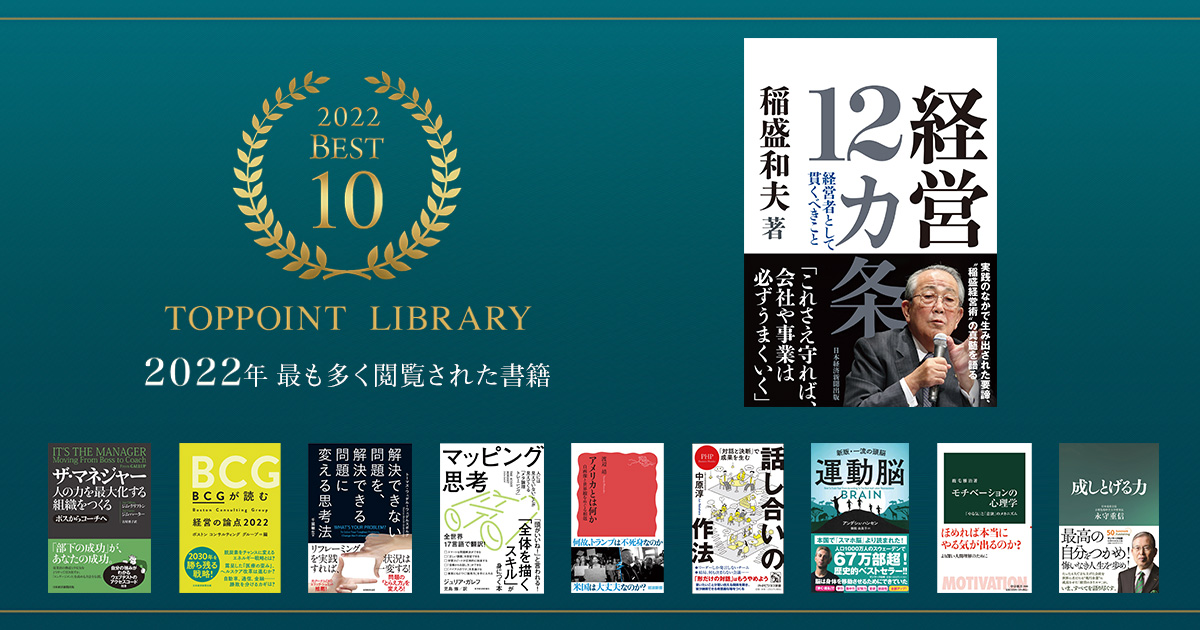2022年11月号掲載
「対話と決断」で成果を生む 話し合いの作法
- 著者
- 出版社
- 発行日2022年9月6日
- 定価1,155円
- ページ数301ページ
※『TOPPOINT』にお申し込みいただき「月刊誌会員」にご登録いただくと、ご利用いただけます。
※最新号以前に掲載の要約をご覧いただくには、別途「月刊誌プラス会員」のお申し込みが必要です。
著者紹介
概要
よい“話し合い”には、「対話」と「決断」が欠かせない ―― 。参加者が人の話を聞かず、何も決まらない長時間の会議が多くの組織で頻発している。そんな残念な話し合いを有意義な場に変えるためのヒントを、人材開発の研究者が説いた。本書で示される“作法”を実践すれば、相互理解が深まり、納得感ある結論を導けるはずだ。
要約
話し合い=対話+決断
今、企業では「話し合い」が機能不全に陥っていることが少なくない。
例えば、「リーダーが権力を用いて結論に誘導し、自由な意見交換を妨げる」「参加者が人の話を聞かず、自分の意見をかぶせて発言する」…。このような残念な話し合いが頻発している。
では、よい話し合いのプロセスとは何か?
「対話」と「決断(議論)」
話し合いは、2つのフェイズから成立する。「①対話する」フェイズと、「②決断(議論)する」フェイズである。
「①対話する」の「対話」とは、お互いの意見のズレや違いを表出させ、認識し合うようなコミュニケーションのことだ。
対話の効果とは、「この問題については、Aという意見とBという意見がある。この2つはこういう部分で違いがある」ことを明らかにして、いったん、メンバーの間で共有することである。まずは相互の「違い」の理解を深めるコミュニケーションを、対話というのである。
2つ目のフェイズは、「②決断(議論)する」である。メンバーの間で、どんなに対話を重ねても、最終的に「決めること」ができなければ、物事を前に進めることはできない。それでは、決めるためには、何が必要か。それが「議論」だ。
議論とは、もともと「勝ち負け・白黒をはっきりさせる」という意味を持つ。AとB、どちらかの意見が「優れている(マシである)」かを理性的に比較検討し、最後に決めることである。対話の後、議論をするからこそ、決断ができるのだ。
対話と決断のバランス
それでは、「対話する」フェイズから「決断(議論)する」フェイズへの移行は、どのようなプロセスを経て行われているのか。
対話するフェイズでは、お互いの意見の違いを表出しながら、共通の部分やわかり合えない部分を探っていく。対話が進んでいくと、意見の違いを表出する量が減り、「共通認識」が増えていく。こうして対話量が減っていった段階で、決断(議論)するフェイズに移り、最終的に決断する。
だから、話し合いをする時には、次の2つの意識をメンバーが共有して進めていくことが大切だ。