2017年3月号掲載
意思決定の心理学 脳とこころの傾向と対策
- 著者
- 出版社
- 発行日2017年1月11日
- 定価1,430円
- ページ数205ページ
※『TOPPOINT』にお申し込みいただき「月刊誌会員」にご登録いただくと、ご利用いただけます。
※最新号以前に掲載の要約をご覧いただくには、別途「月刊誌プラス会員」のお申し込みが必要です。
著者紹介
概要
本を読むか、読まないか。何をもって善とし、悪とするか ―― 。生きるということは、意思決定の連続だ。ある時はうまく決められ、ある時は失敗する。なぜか?本書は、情動と理性という2つの「こころの働き」に着目。これを軸に、心理学と脳科学の最新の研究成果を紹介しながら、意思決定のメカニズムを探っていく。
要約
二重過程理論
私たちの様々なこころの働きは、多様な機能を持つ脳の働きによって実現されている。
例えば街を歩いていて、菓子屋のショーケースに美味しそうなケーキがあるのを見つけたとする。甘いものが好きな人なら、食べたいと思うだろう。
しかし、ダイエットをしている人にとっては、カロリーオーバーになることが気になる。ケーキは食べたいけど我慢しないといけない、と自制心を働かせてその行動を制御しようとする。
このように、意思決定の多くの場面では、素早く湧きあがる情動や欲求と、時間をかけた思考に基づく理性や自制心が、意思決定に作用する別々のシステムとして機能しているのである。
意思決定において、こうした2種類のこころの働きを想定する理論を「二重過程理論」と呼ぶ。
二重過程理論と2つの「こころ」の呼称
2つのこころの働きについて、学術的によく使われる表現の1つが「システム1」「システム2」という分類の仕方である。
・情動的・直感的な「システム1」
システム1は、直感的な反応や情動的な反応、本能的な欲求の発現を支えるシステムだ。自動的に働き、努力を必要とせず、論理性よりも直感に依存する。知能や処理能力とは、あまり関係がないとされる。本書では「速いこころ」と呼ぶ。
ケーキを見てすぐに「食べてみたい!」という欲求が芽生えるのは、システム1の働きによる。
・理性的・統制的な「システム2」
システム2は、合理的判断や論理的思考、自制心といった、意志の力によるこころの働きを支えている。システム1の働きに、ブレーキをかけようとする存在といってもよいだろう。
システム2を働かせるには努力が必要で、時間もかかる。学習によって獲得された論理性や特定のルールに基づいて思考が展開されるのも、知能や処理能力と関係しているのも、システム2の大きな特徴である。システム1の速いこころと対をなすものとして、本書では「遅いこころ」と呼ぶ。
先のケーキの例でいえば、「ダイエット中だから食べるわけにはいかない」と判断する際には、システム2がフル稼働している。もちろん、うまく制御できる場合もあれば、できない場合もある。




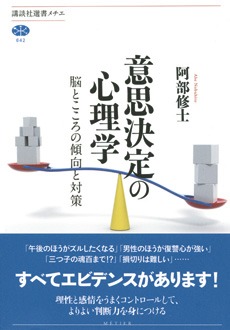









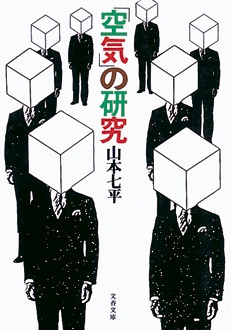
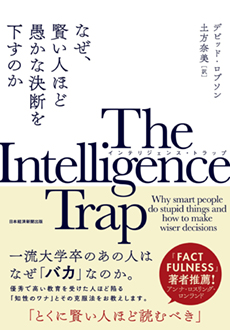



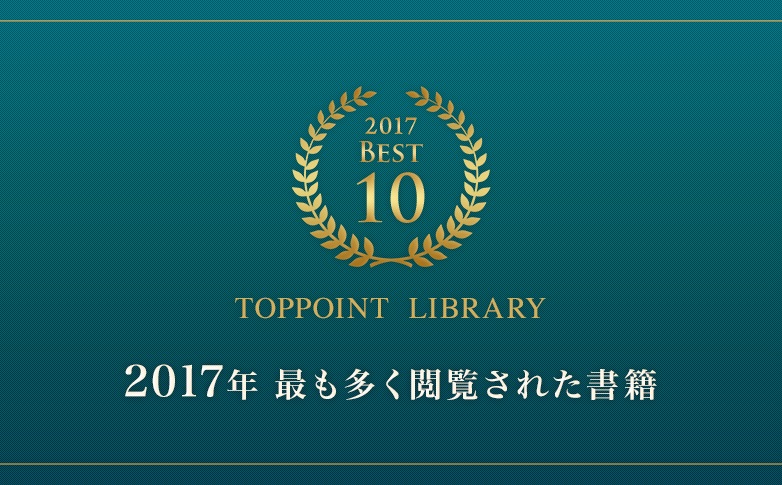
![「失敗」を研究して、そこから学ぼう [個人編]](/uploads/20200528122311-2017_5%E6%9C%88%E5%A2%97%E5%88%8A%E5%8F%B7.jpg?1603790314)

