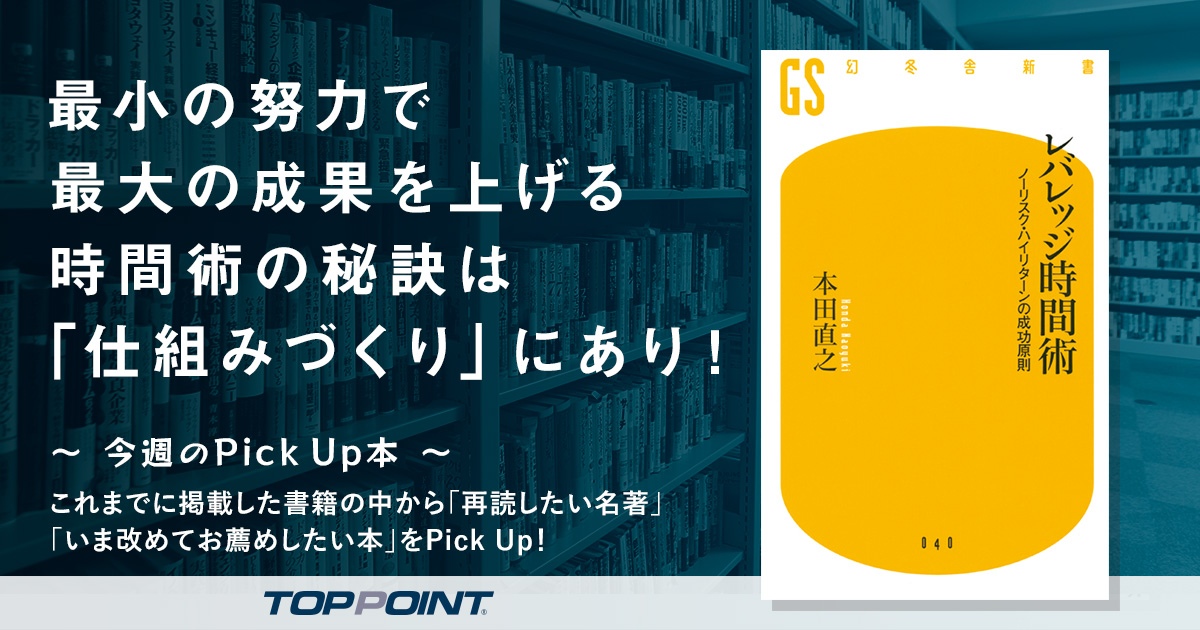
明日は「時の記念日」
明日、6月10日は「時の記念日」です。
この日を記念日とする由来について、『時間の日本史 日本人はいかに「時」を創ってきたのか』(佐々木勝浩 他著/小学館 刊)は次のように解説しています。
日本書紀には、飛鳥時代、天智天皇が漏刻(水時計)を用いて、日本で初めて時を知らせた故事が記されている。現代の暦に直すと6月10日で、これが時の記念日の由来となっている。
(『時間の日本史』 22ページ)
同書によれば、時の記念日が制定されたのは1920年(大正9年)のこと。そのきっかけは、東京で開催された「時」をテーマとした展覧会、「『時』展覧会」でした。
そもそも、この展覧会が開催されたのは、当時の人々が「時間にルーズ」だったことによります。明治時代、日本にも1日24時間の「定時法」が導入されましたが、江戸時代の日の出と日没を基準として昼と夜をそれぞれ6等分する「不定時法」(時間の単位である「一時」の長さは昼と夜とで異なり、季節的にも変わる)の感覚が抜け切れていなかったようで、人々の時間感覚はゆったりしていたそうです。
しかし、郵便や鉄道など、近代的な制度や技術が日本に導入されるに従い、時間励行の意識が求められるようになりました。
人々に時間励行を促すために開催された「『時』展覧会」は大盛況。それを受けて、「時の大切さを宣伝するセレモニー」として時の記念日が制定されたといいます。
このPick Up本を読んだ方は、
他にこんな記事にも興味を持たれています。
-

なぜ年越し蕎麦? なぜ冬至にカボチャ? 日本の食文化の由来を専門家に学ぶ
-
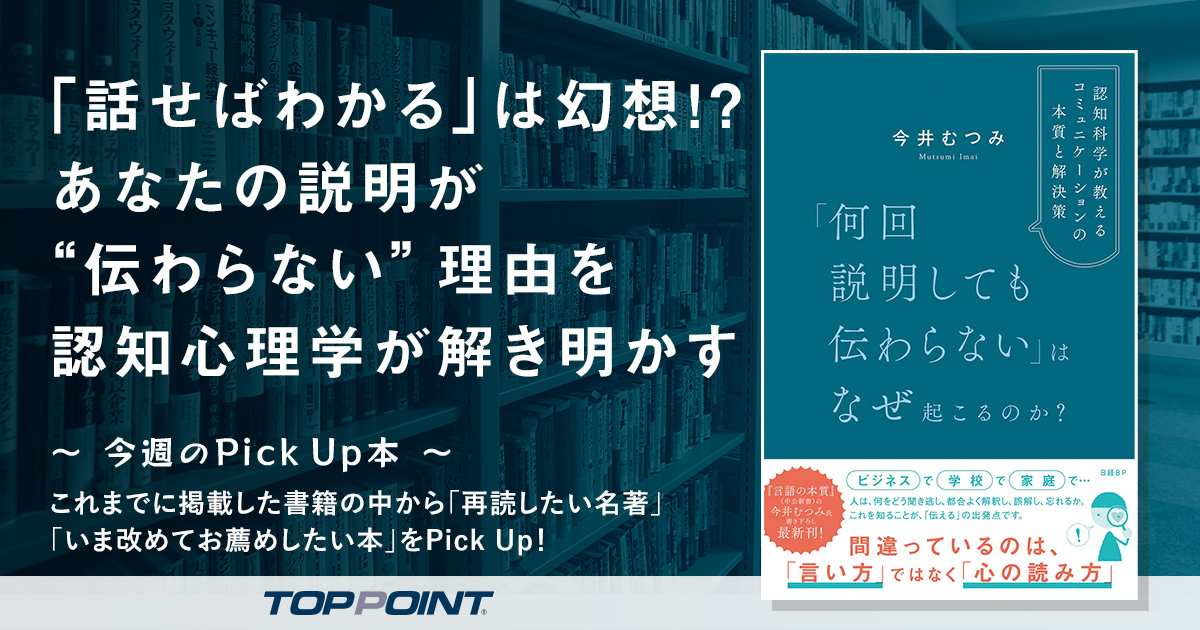
「話せばわかる」は幻想!? あなたの説明が“伝わらない”理由を認知心理学が解き明かす
-
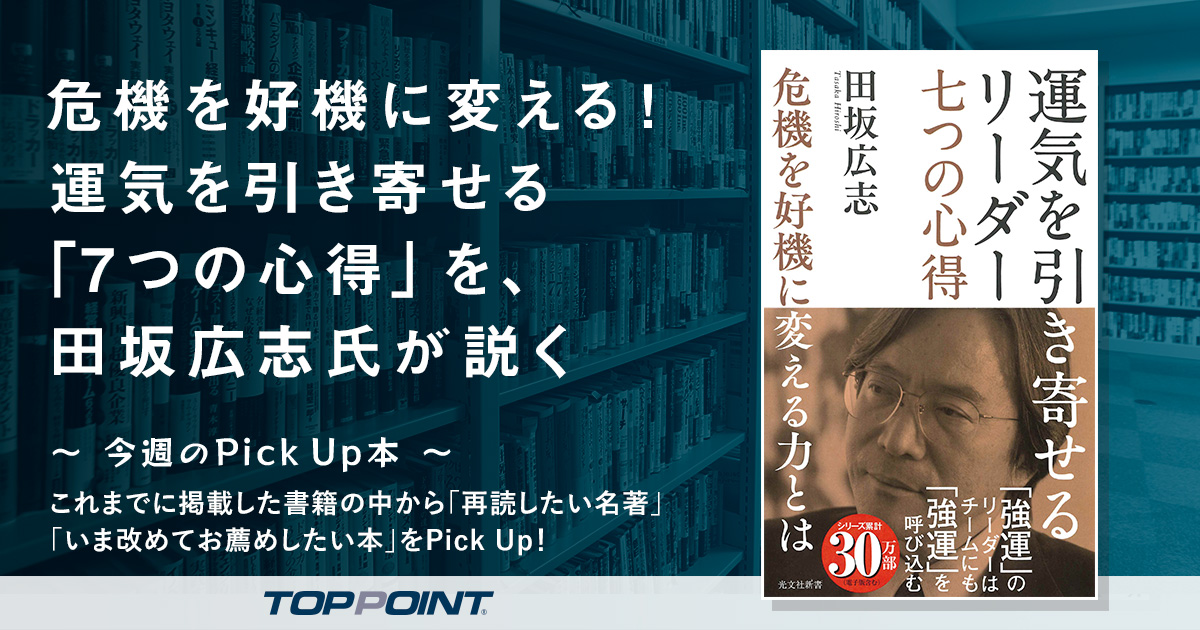
危機を好機に変える! 運気を引き寄せる「7つの心得」を、田坂広志氏が説く





