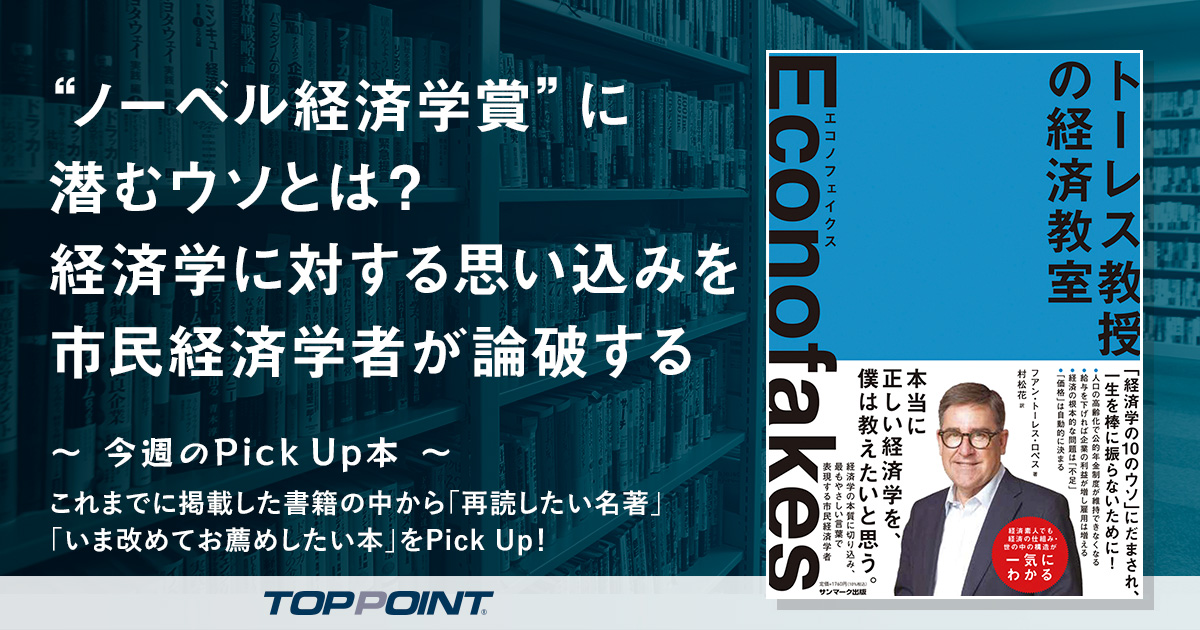
今年も、ノーベル賞の受賞者が発表されました。
10月2日(月)の生理学・医学賞を皮切りに、物理学賞、化学賞、文学賞、平和賞、そして10月9日(月)の経済学賞と、6つの賞で計11人が選ばれました。
受賞理由を見ると、新型コロナウイルスのワクチン開発への貢献やナノテクノロジー発展の礎の構築など、圧倒される実績が並んでいます。
ところで、これら6つの賞の中に、1つだけ「仲間外れ」がいることはご存じでしょうか?
『Econofakes エコノフェイクス』(フアン・トーレス・ロペス 著/サンマーク出版 刊)を読むと、その答えがわかります。
このPick Up本を読んだ方は、
他にこんな記事にも興味を持たれています。
-
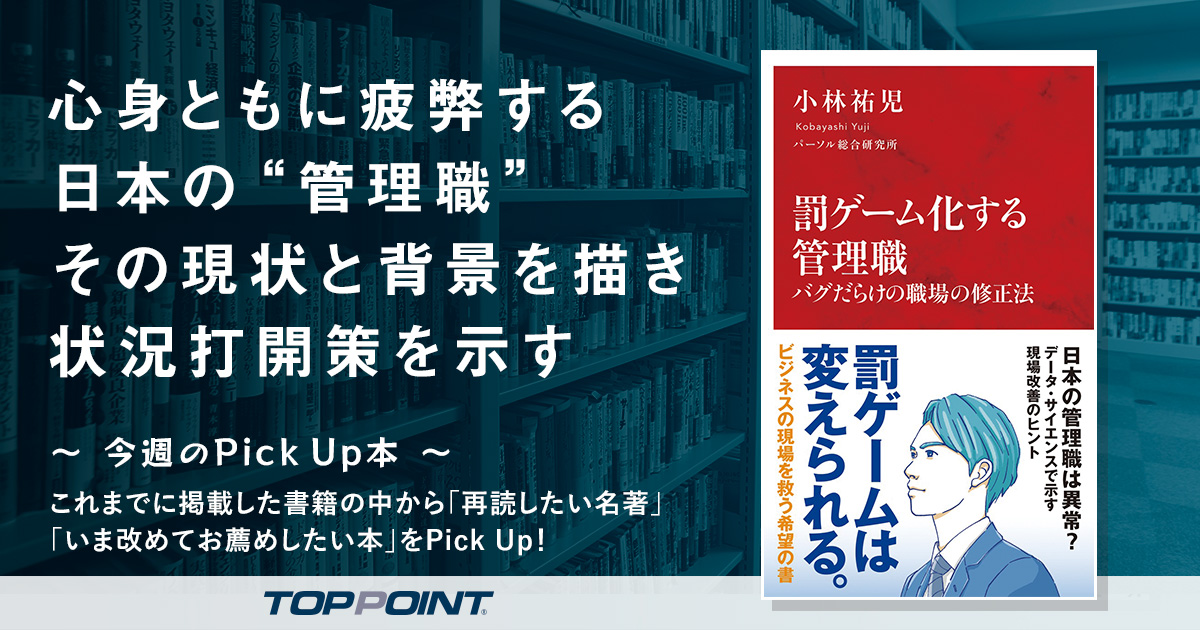
心身ともに疲弊する日本の“管理職” その現状と背景を描き状況打開策を示す
-
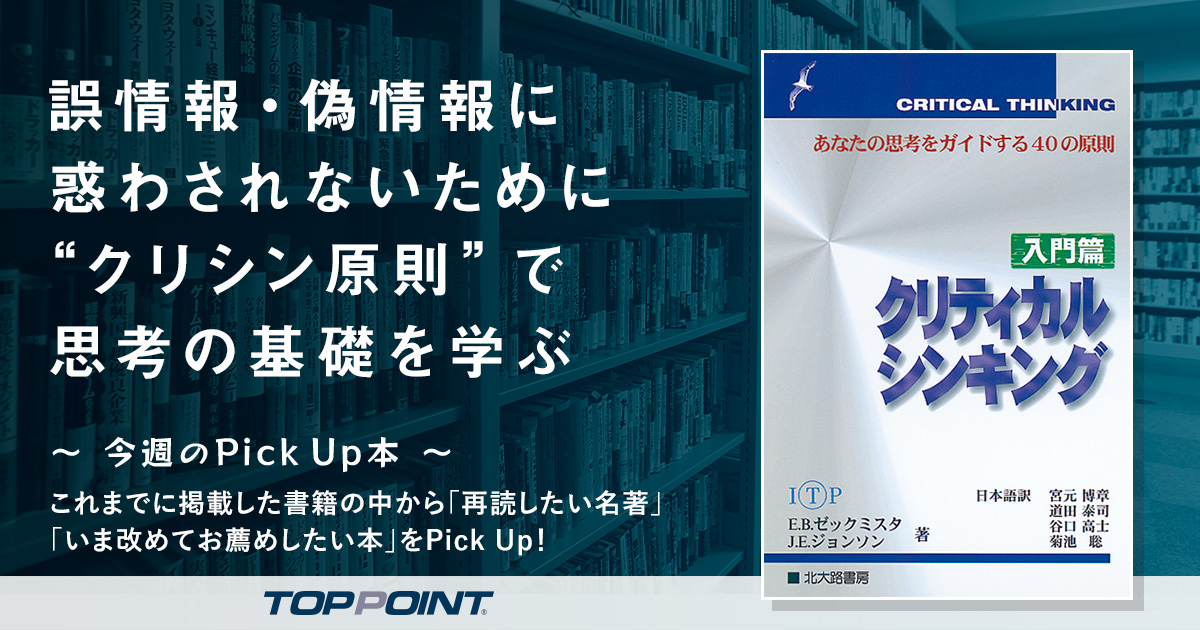
誤情報・偽情報に惑わされないために “クリシン原則”で思考の基礎を学ぶ
-
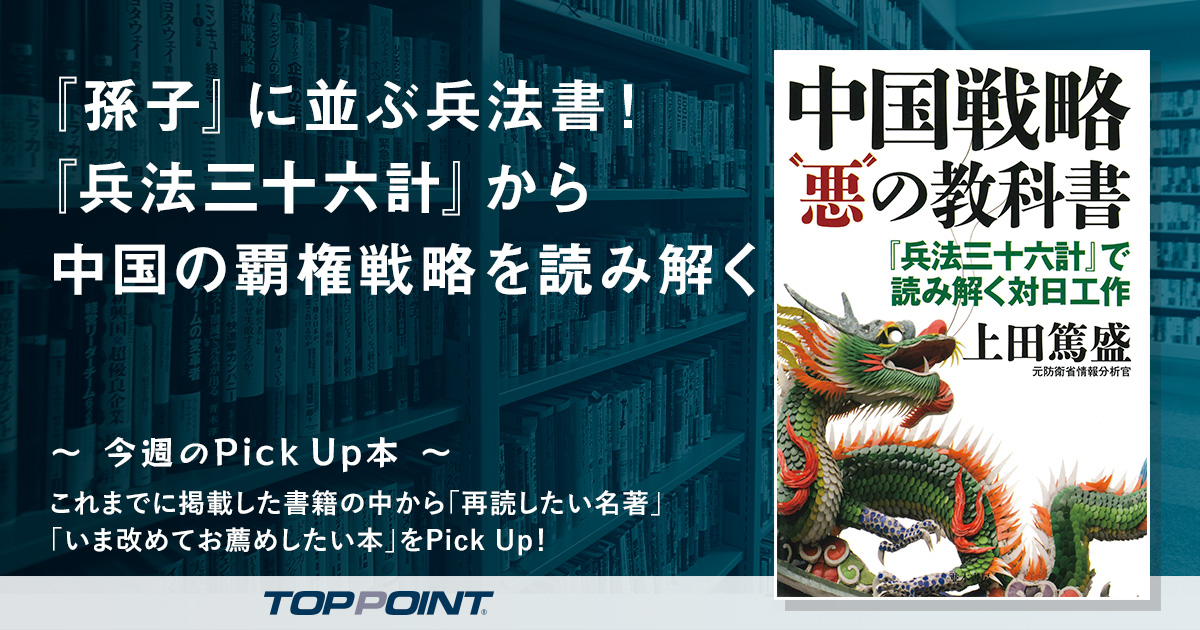
『孫子』に並ぶ兵法書! 『兵法三十六計』から中国の覇権戦略を読み解く





