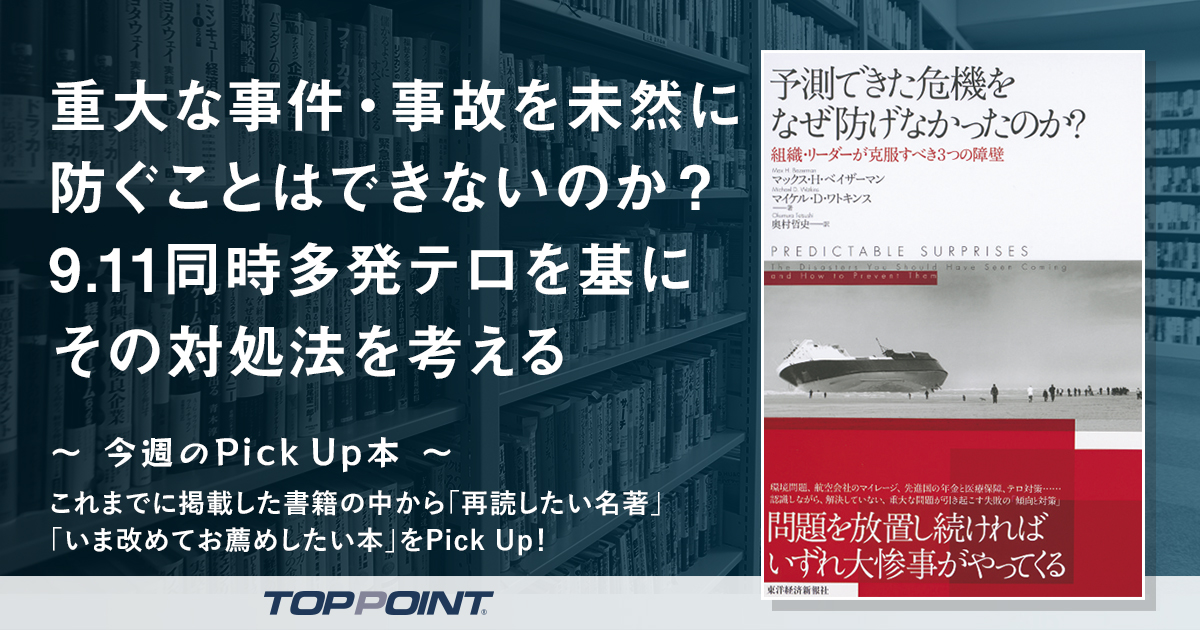
22年前の今日 ―― 2001年9月11日、イスラム過激派のテロ組織アルカイダによって「アメリカ同時多発テロ事件」が引き起こされました。ハイジャックされた旅客機がワールドトレードセンタービルに突撃する映像は、今も私の脳裏に焼き付いています。
3000名にも上る犠牲者を出したこのテロ事件は「予測可能」であった ―― こう指摘する本があります。それが今回Pick Upする、『予測できた危機をなぜ防げなかったのか? 組織・リーダーが克服すべき3つの障壁』(マックス・H・ベイザーマン、マイケル・D・ワトキンス 著/東洋経済新報社 刊)です。
著者は、ハーバード・ビジネススクール教授のマックス・H・ベイザーマンと、リーダーシップ戦略をメインに扱うジェネシス・アドバイザーズの創業者マイケル・D・ワトキンス。彼らは本書で、次のように語っています。
このPick Up本を読んだ方は、
他にこんな記事にも興味を持たれています。
-
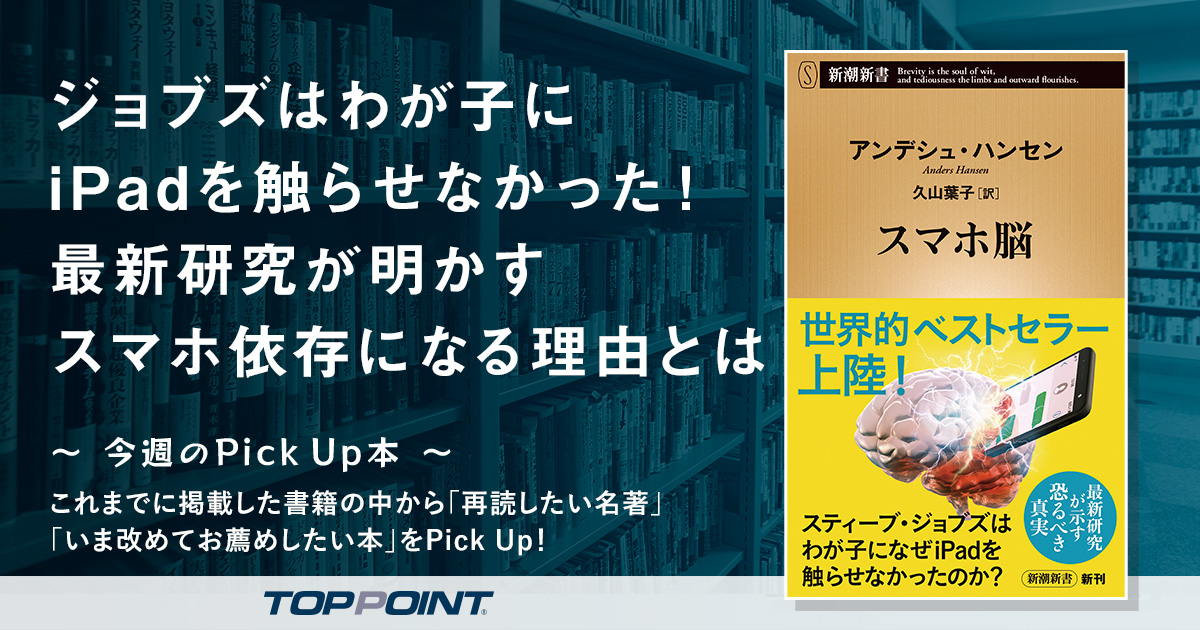
ジョブズはわが子にiPadを触らせなかった! 最新研究が明かすスマホ依存になる理由とは
-
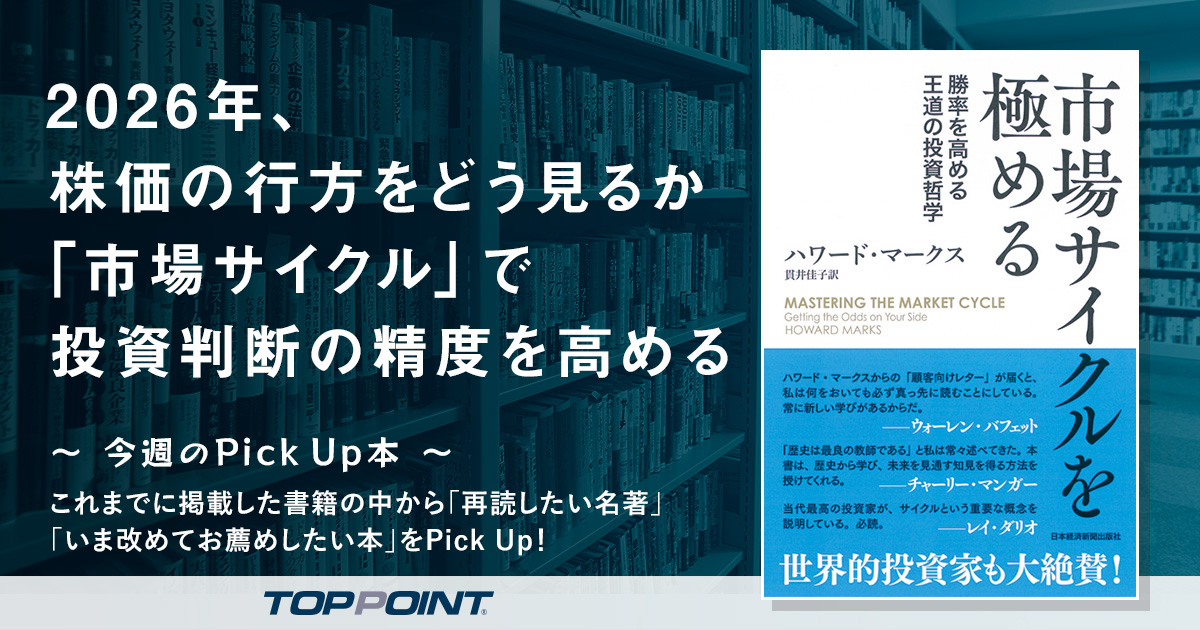
2026年、株価の行方をどう見るか 「市場サイクル」で投資判断の精度を高める
-
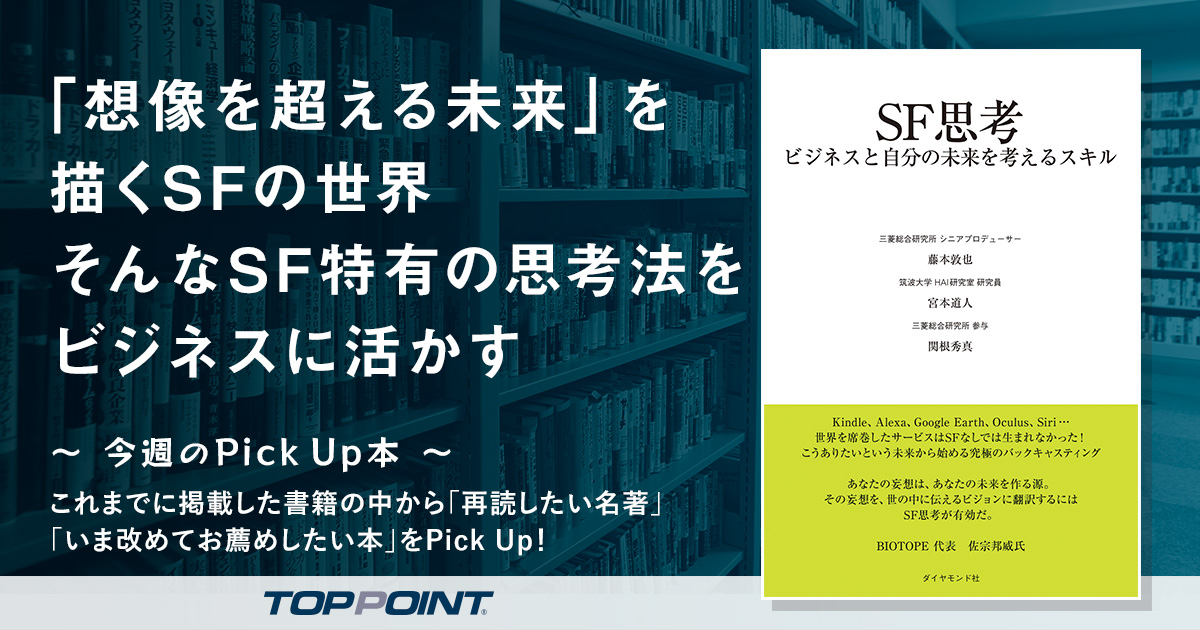
「想像を超える未来」を描くSFの世界 そんなSF特有の思考法をビジネスに活かす





