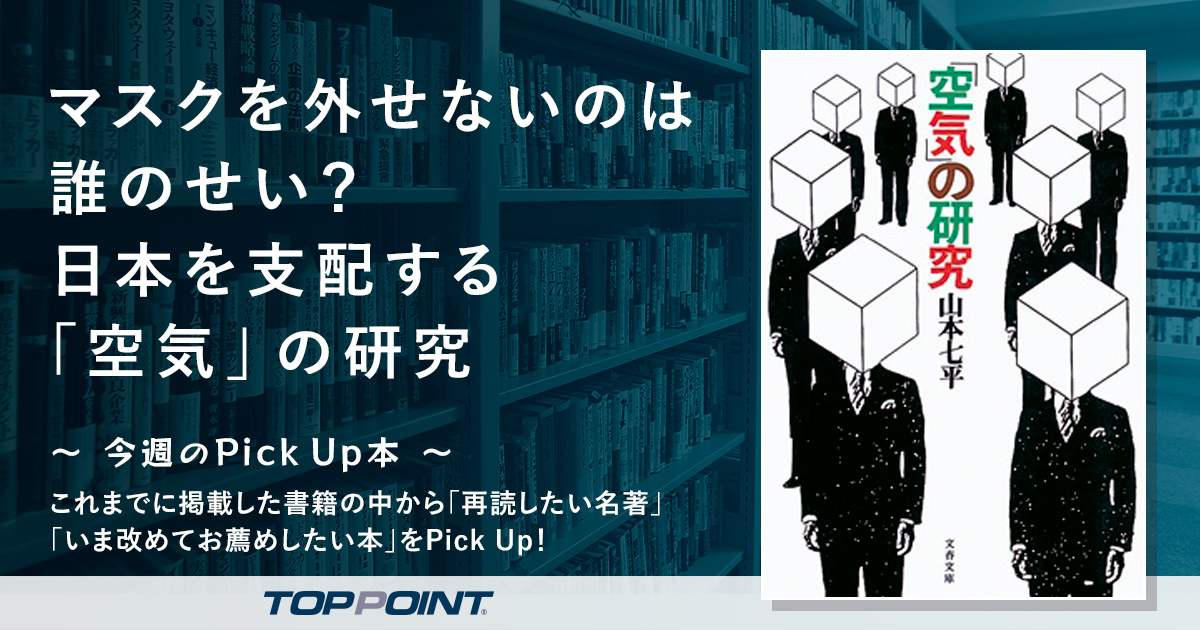
「あの人、空気を読むのがうまいよね」「今はそういう話を持ち出せる雰囲気じゃない」「あの場では断れないムードだった」…。
日本では会議や会話の中などで、“空気”あるいはそれに近い言葉が頻繁に使われます。例えば最近、熱中症のリスクがあるにもかかわらず、ほとんどの人は屋外でもマスクを外しません。それは、「みんながマスクをしているのに、自分だけ外すような“空気”じゃない」と考えるからではないでしょうか。
今回取り上げたいのは、そんな“空気”について考察した名著、『「空気」の研究』(山本七平 著/文藝春秋 刊)です。著者は、作家・評論家として活躍された山本七平氏です。
“空気”とは、一体何なのか ―― 。山本氏は本書で、次のように説明しています。
このPick Up本を読んだ方は、
他にこんな記事にも興味を持たれています。
-
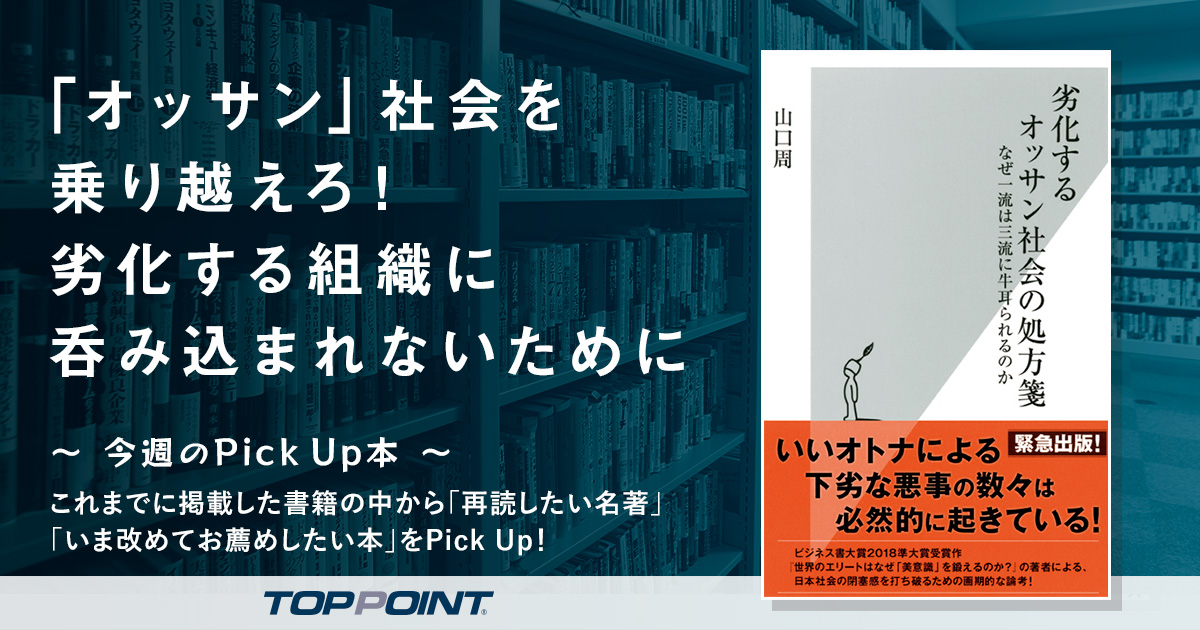
「オッサン」社会を乗り越えろ! 劣化する組織に呑み込まれないために
-
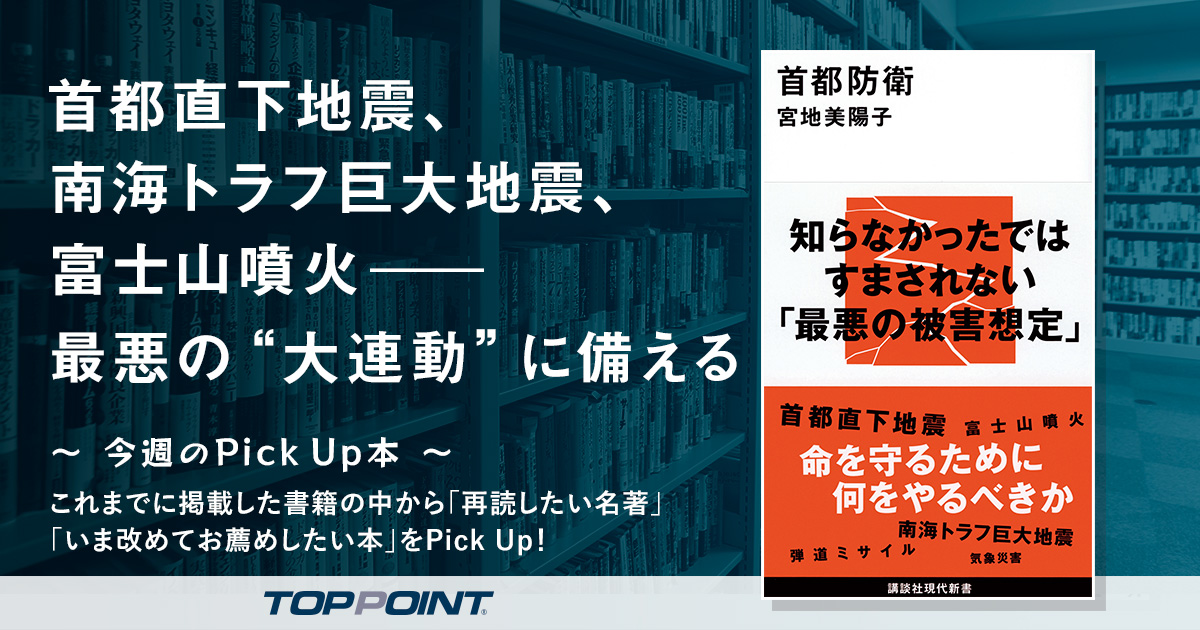
首都直下地震、南海トラフ巨大地震、富士山噴火―― 最悪の“大連動”に備える
-
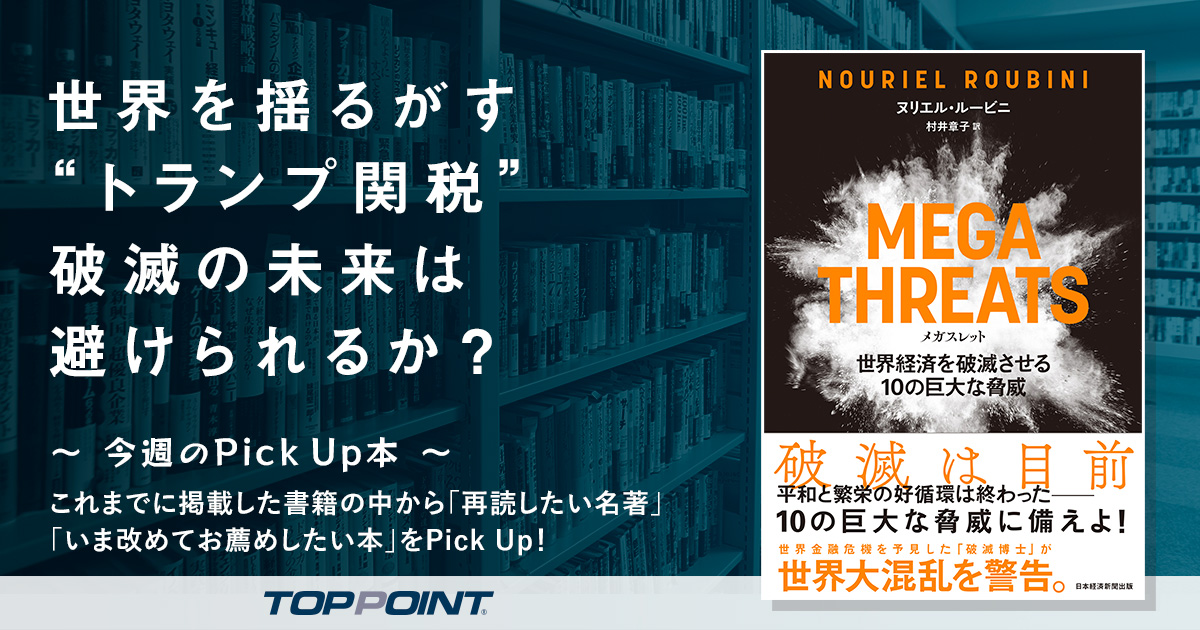
世界を揺るがす“トランプ関税” 破滅の未来は避けられるか?





