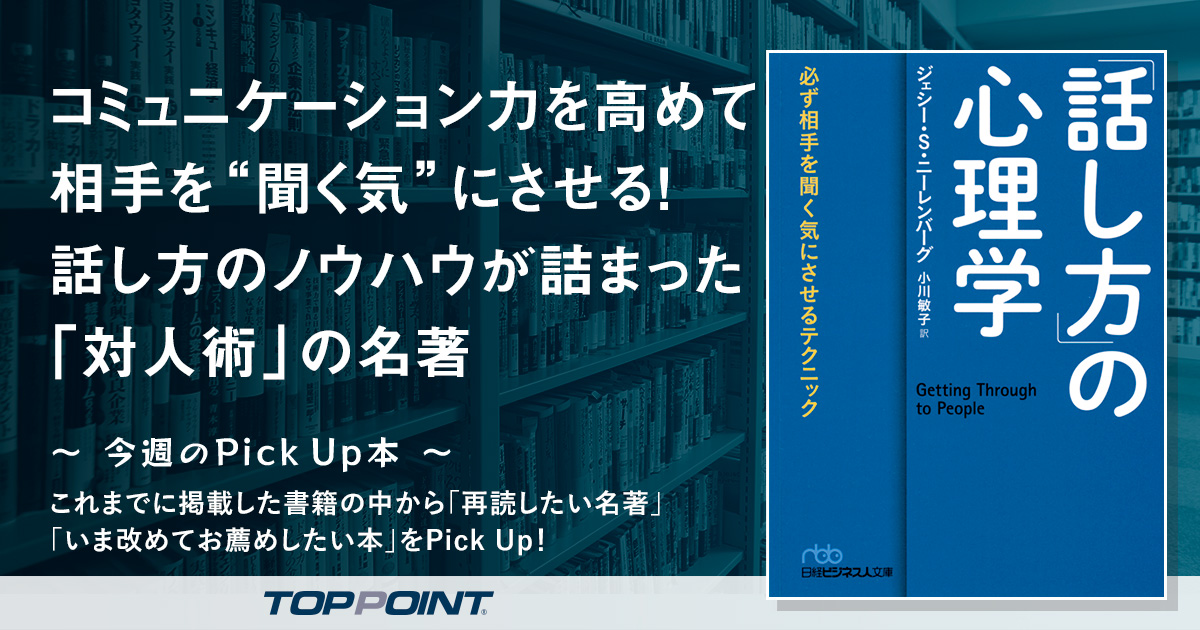
早いもので、間もなく新年度が始まります。
この時期になると、新入社員が自分の部署に来ることがわかったり、異動や転職で新しい職場に向かうことが決まったりします。私はどちらかというと人見知りなので、この時期が少し苦手です。初めての人に会うと、何を話したらいいか悩んでしまうからです。
私と似たような悩みを持つ方も少なくないでしょう。また、初対面の相手でなくとも、人と会話し、意思疎通を図るのは難しいものです。そこで今回は、半世紀にわたってアメリカで読み継がれてきたビジネス&コミュニケーションの古典的名著、『「話し方」の心理学 必ず相手を聞く気にさせるテクニック』(ジェシー・S・ニーレンバーグ 著/日本経済新聞出版社 刊)をご紹介します。
著者は、アメリカの産業心理学者(心理学博士)のジェシー・S・ニーレンバーグ氏。ニューヨーク大学などで心理学の教鞭をとるかたわら、企業人のカウンセラーとしても活躍した人物です。そんなニーレンバーグ氏が1963年に著した『「話し方」の心理学』(日経ビジネス人文庫は2017年刊行)には、コミュニケーション力、対人能力を磨く上で役立つテクニックが詰まっています。
例えば、相手の関心をつなぎとめ、話を聞いてもらいたい時は、次のような方法が効果的だといいます。
このPick Up本を読んだ方は、
他にこんな記事にも興味を持たれています。
-
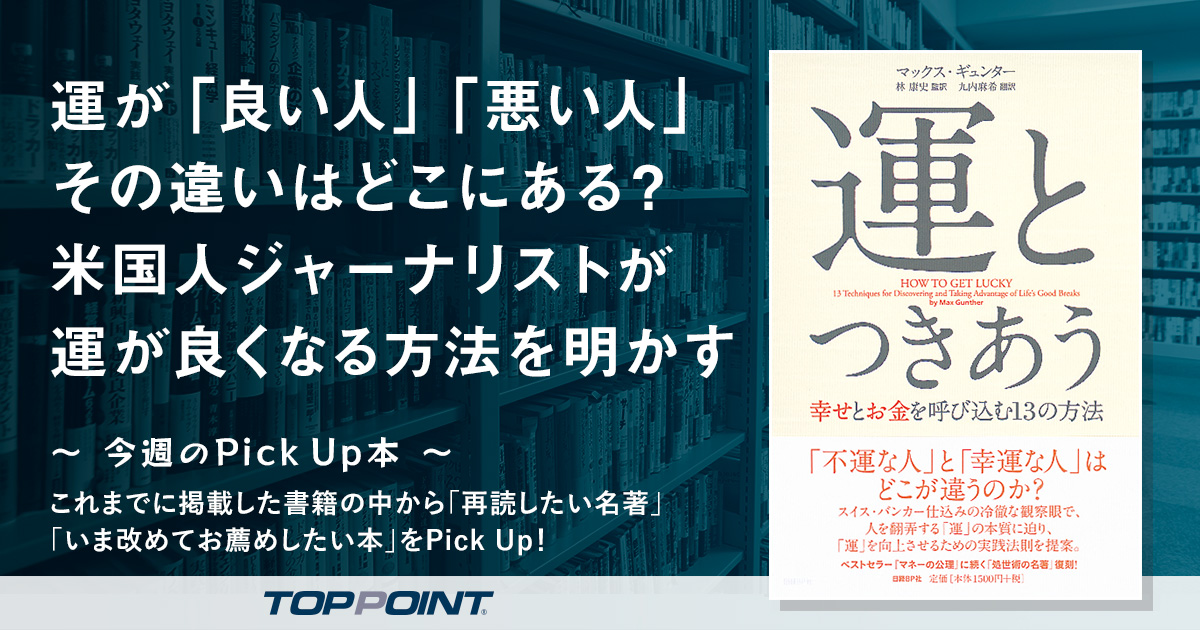
運が「良い人」「悪い人」その違いはどこにある? 米国人ジャーナリストが運が良くなる方法を明かす
-
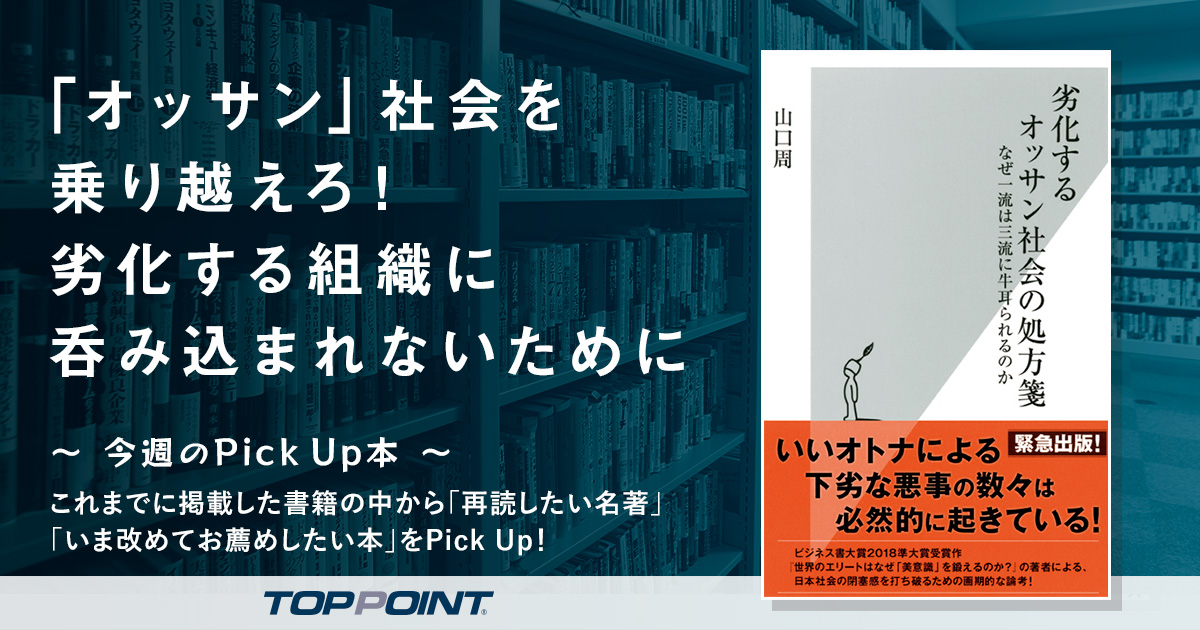
「オッサン」社会を乗り越えろ! 劣化する組織に呑み込まれないために
-
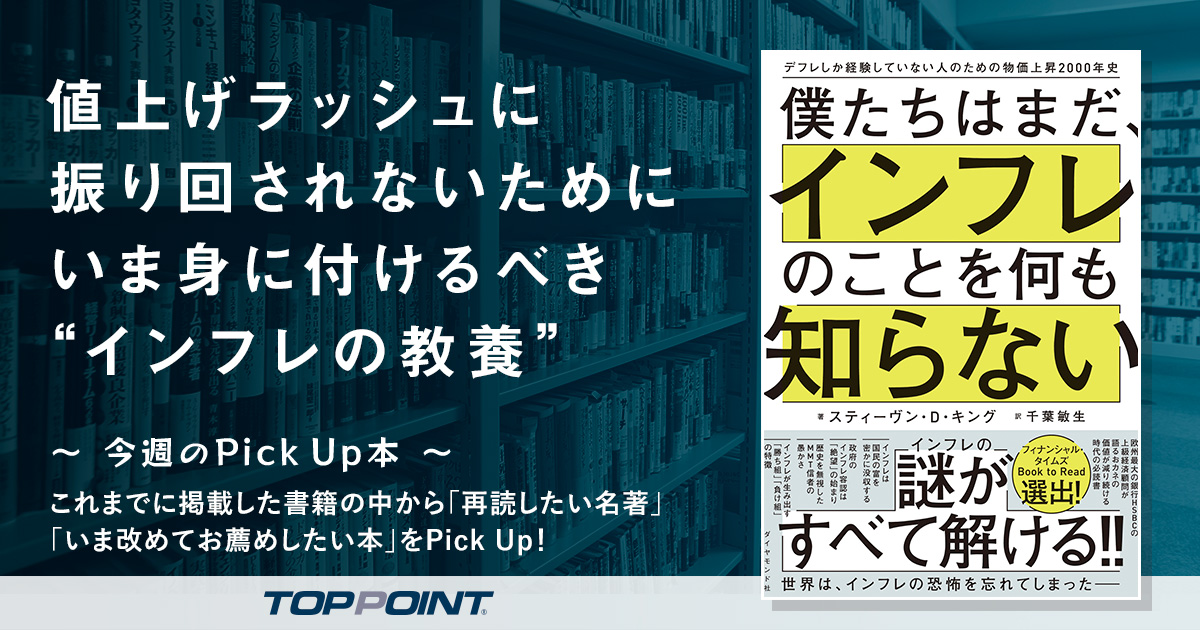
値上げラッシュに振り回されないために いま身に付けるべき“インフレの教養”





