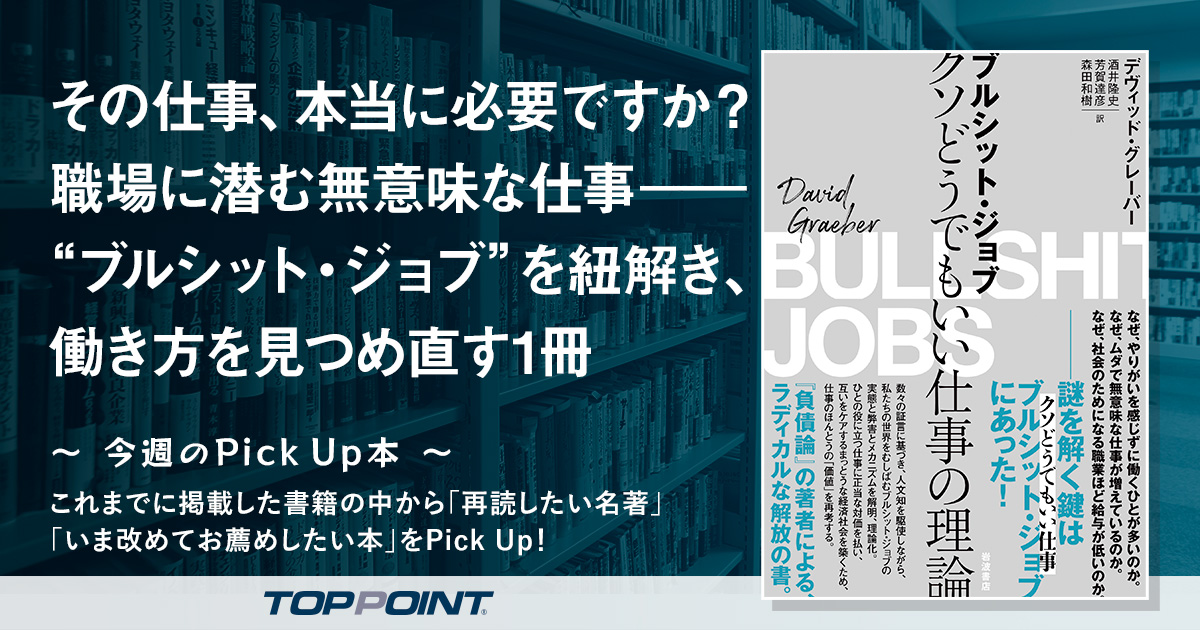
10月も半ば。2025年も残りわずかとなりました。
このあたりで一度、自分の働き方を振り返ってみるのはいかがでしょうか。
仕事にやりがいを感じているか。労働時間が必要以上に増えてはいないか。そして、自分の努力と報酬は見合っているのか ―― 。
そんな問いを投げかけるのに最適なビジネス書として、今回は2020年に急逝した世界的な文化人類学者であるデヴィッド・グレーバー氏の著書、『ブルシット・ジョブ クソどうでもいい仕事の理論』(岩波書店)をPick Upします。
社会に潜む「無意味な仕事」の実態を徹底的に分析し、大きな反響を呼んだこの本は、「2020年下半期TOPPOINT大賞」でランキング1位を獲得。多くのビジネスパーソンに衝撃を与えました。
このPick Up本を読んだ方は、
他にこんな記事にも興味を持たれています。
-
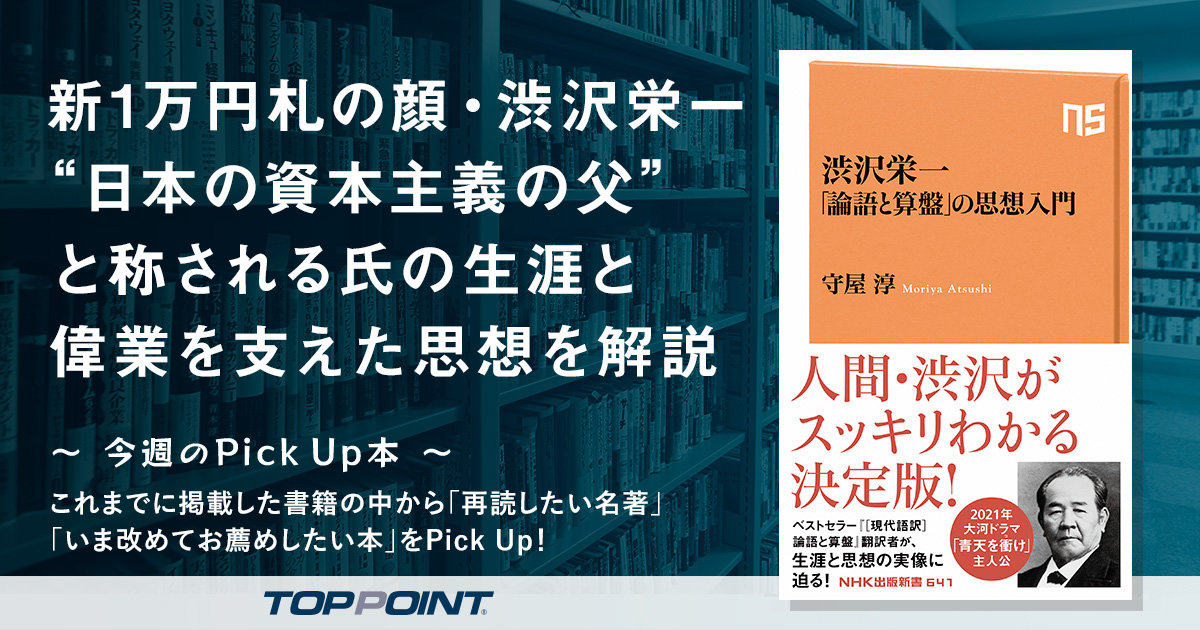
新1万円札の顔・渋沢栄一 “日本の資本主義の父”と称される氏の生涯と偉業を支えた思想を解説
-
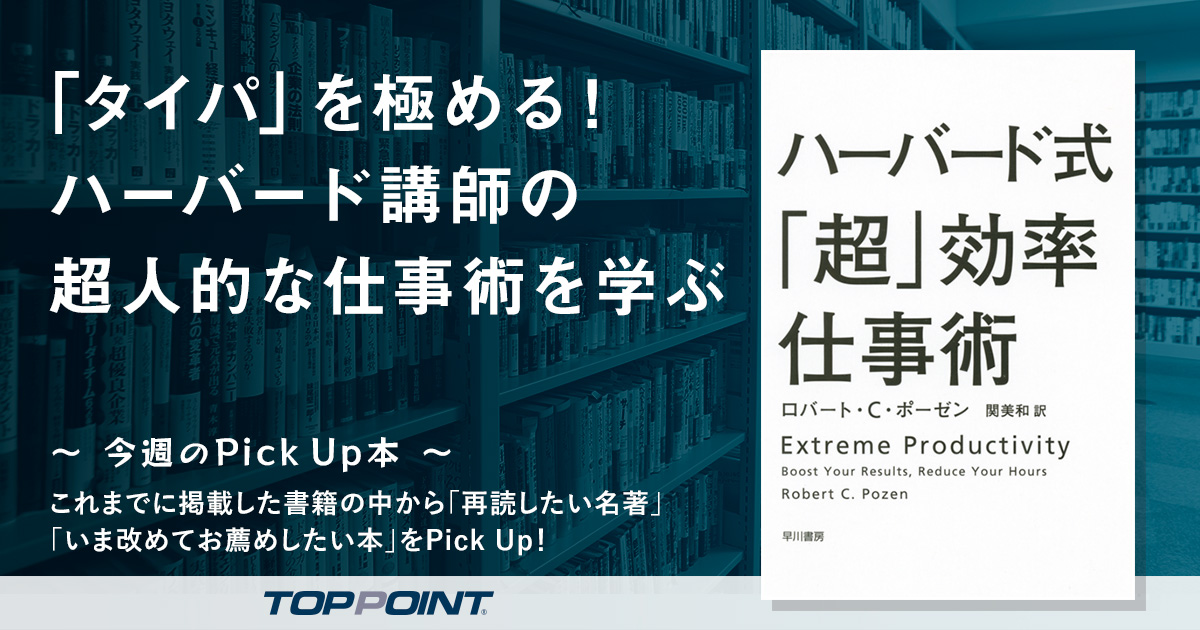
「タイパ」を極める! ハーバード講師の超人的な仕事術を学ぶ
-
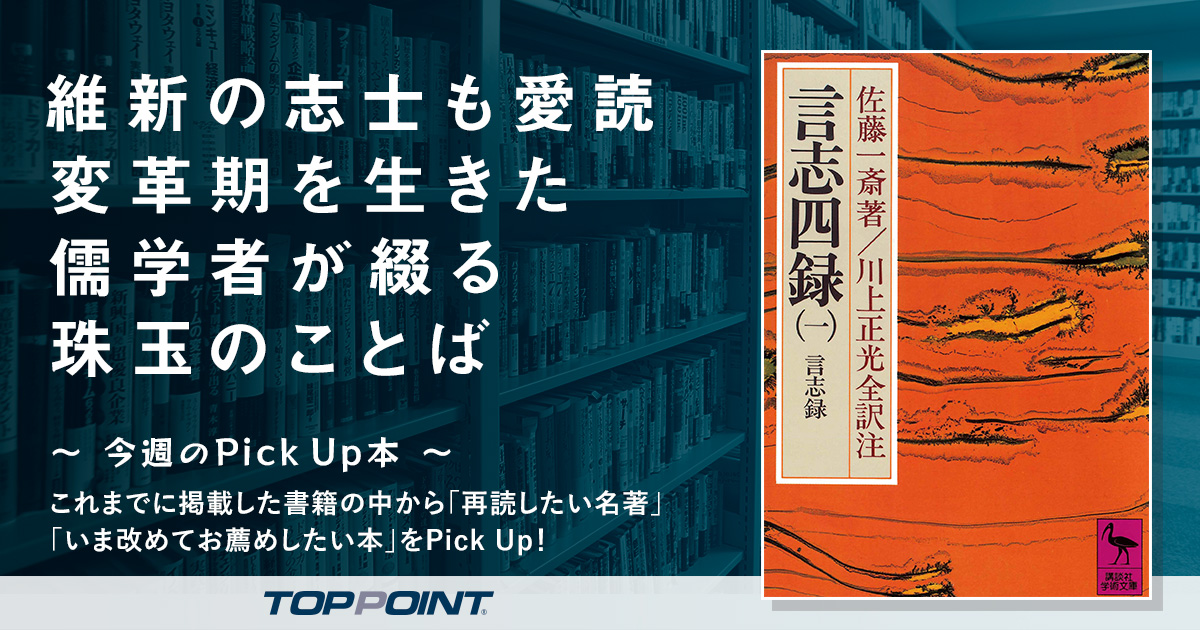
維新の志士も愛読 変革期を生きた儒学者が綴る珠玉のことば





