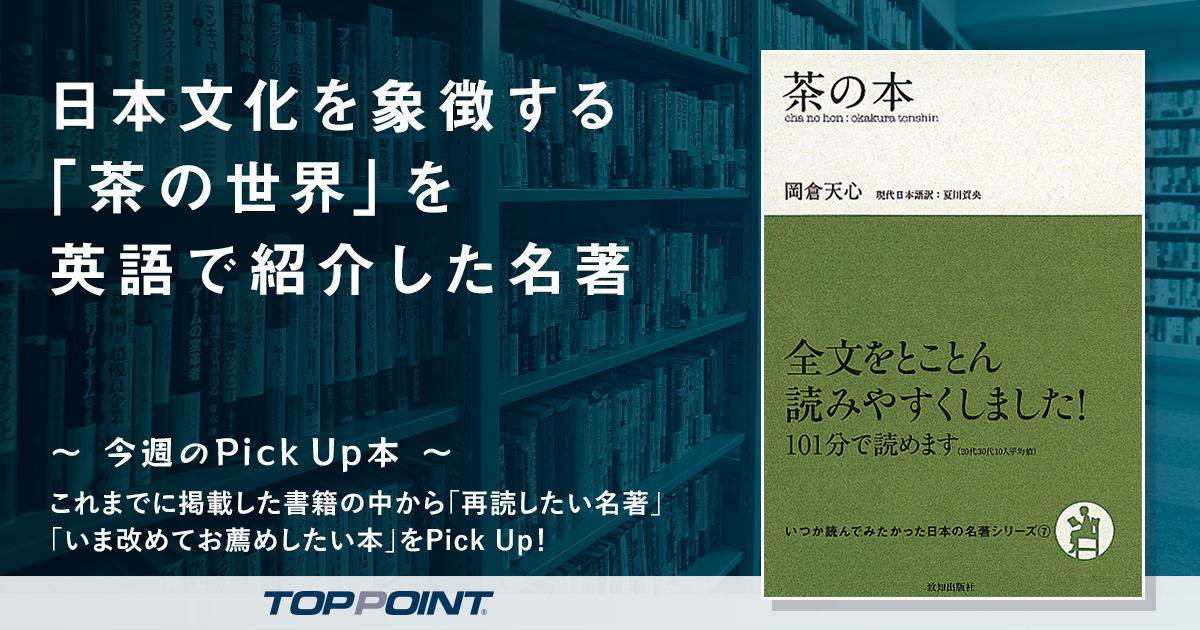
世界で「MATCHA」ブーム
日本茶が海外でブームとなっています。
財務省の貿易統計によれば、緑茶の輸出額は急増。2024年に過去最高の364億円を記録しました。緑茶の中でも特に抹茶の人気が高く、その背景には健康食品としての需要や、「アイス抹茶ラテ」を海外のインフルエンサーがSNSに投稿したことなどがあるといいます(「「MATCHAブーム」世界沸かす ラテ・菓子など商品多彩、国内は品薄」/日本経済新聞電子版2025年6月7日)。
今や世界的な人気を獲得した日本のお茶ですが、日本におけるその歴史は長く、また日本文化にとって重要な地位を占めています。ビジネスパーソンにとって「お茶の文化」を学ぶことは、教養を高めるだけでなく、海外の人々との国際交流のきっかけの1つにもなるでしょう。
このPick Up本を読んだ方は、
他にこんな記事にも興味を持たれています。
-
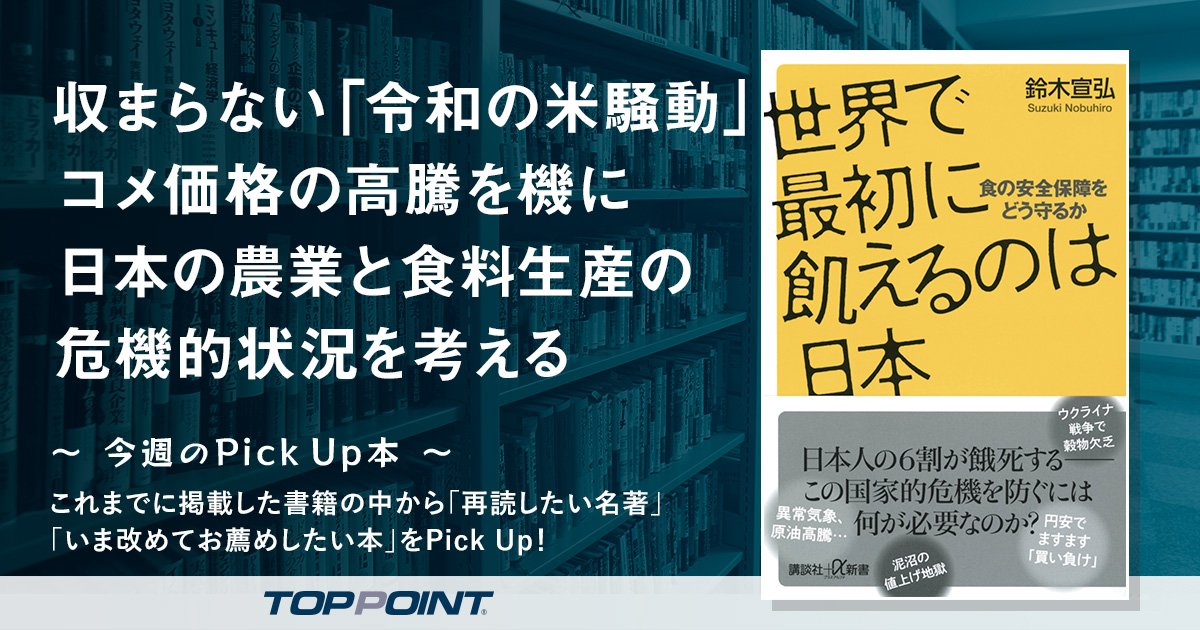
収まらない「令和の米騒動」 コメ価格の高騰を機に日本の農業と食料生産の危機的状況を考える
-

「近代マーケティングの父」が実務家に向けて説いたマーケティングの最重要ポイントとは?
-
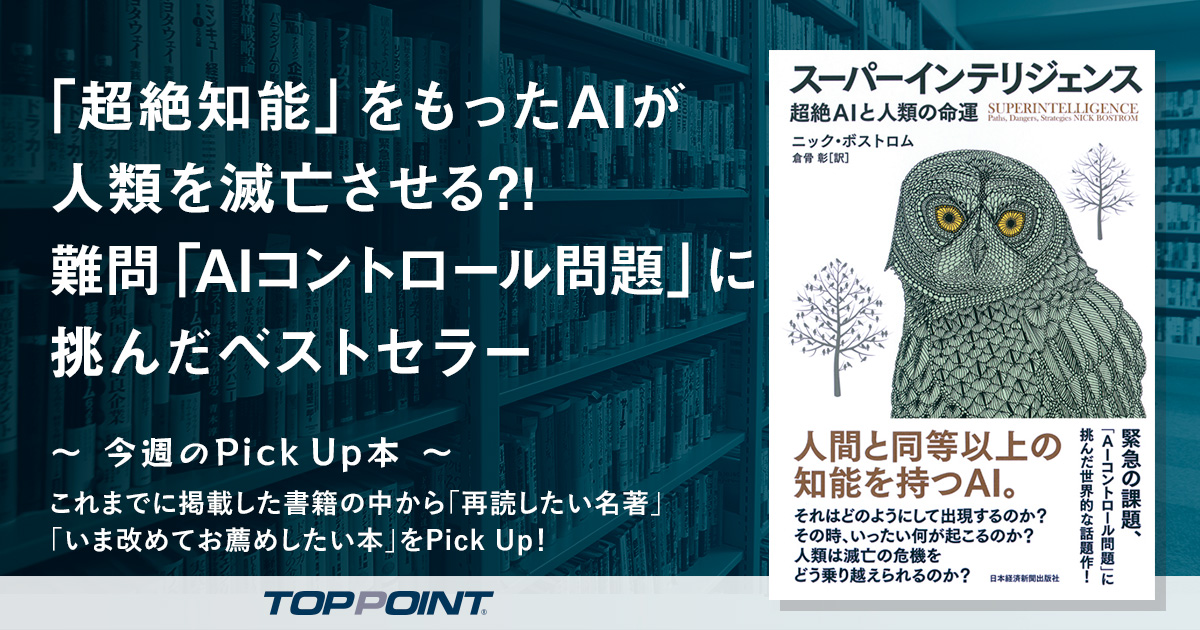
「超絶知能」をもったAIが人類を滅亡させる?! 難問「AIコントロール問題」に挑んだベストセラー





