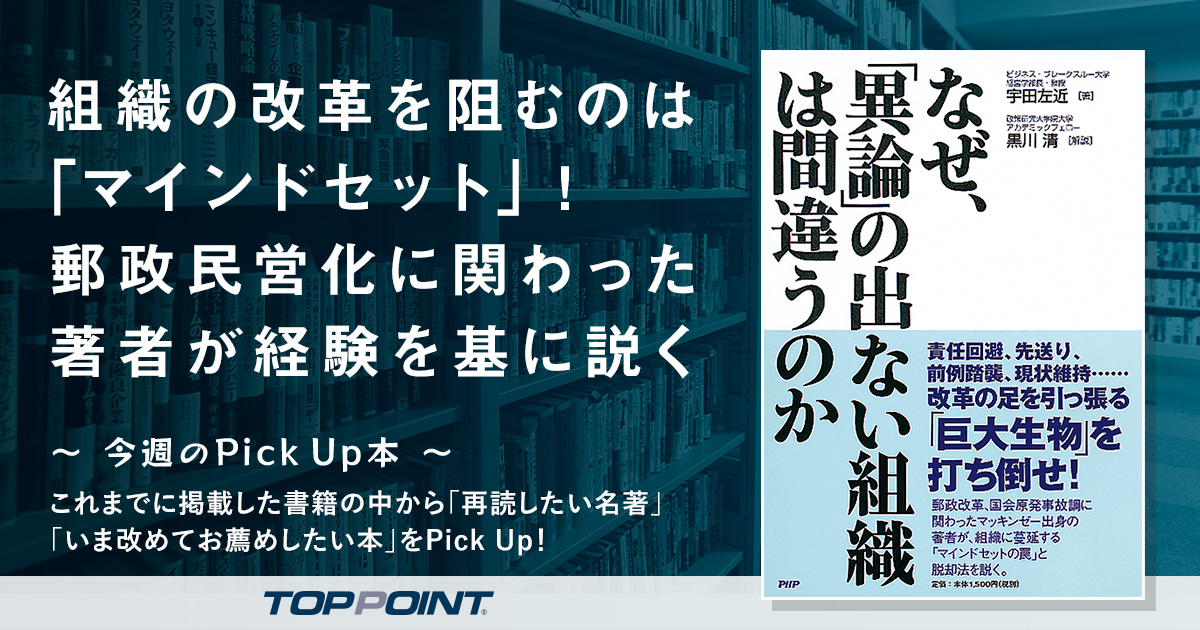
不祥事が続く日本郵便
2025年6月25日、国土交通省は虚偽の点呼記録作成などの違反行為が確認されたとして、日本郵便に対し、トラックなどの車両を使う運送事業の許可を取り消しました(「国交省 日本郵便のトラックなど使った運送事業の許可取り消し」/NHK NEWS WEB 2025年6月25日)。
日本郵便は、2024年10月にも保険商品勧誘のために、155万人に及ぶゆうちょ銀行の顧客情報を不正にリスト化しており、問題となっていました。
こうした報道を目にして、「ダメな組織だな」と他人事のように考えるのは簡単です。しかしビジネスパーソンであれば、「自社にもこうした“緩み”はないだろうか」という視点を持つことが必要ではないでしょうか。
今回はそれを考える上で参考となる1冊をご紹介します。2007年の郵政民営化に関わった著者が、組織に蔓延する問題を鋭く指摘した2014年の本、『なぜ、「異論」の出ない組織は間違うのか』(宇田左近 著/PHP研究所 刊)です。
このPick Up本を読んだ方は、
他にこんな記事にも興味を持たれています。
-
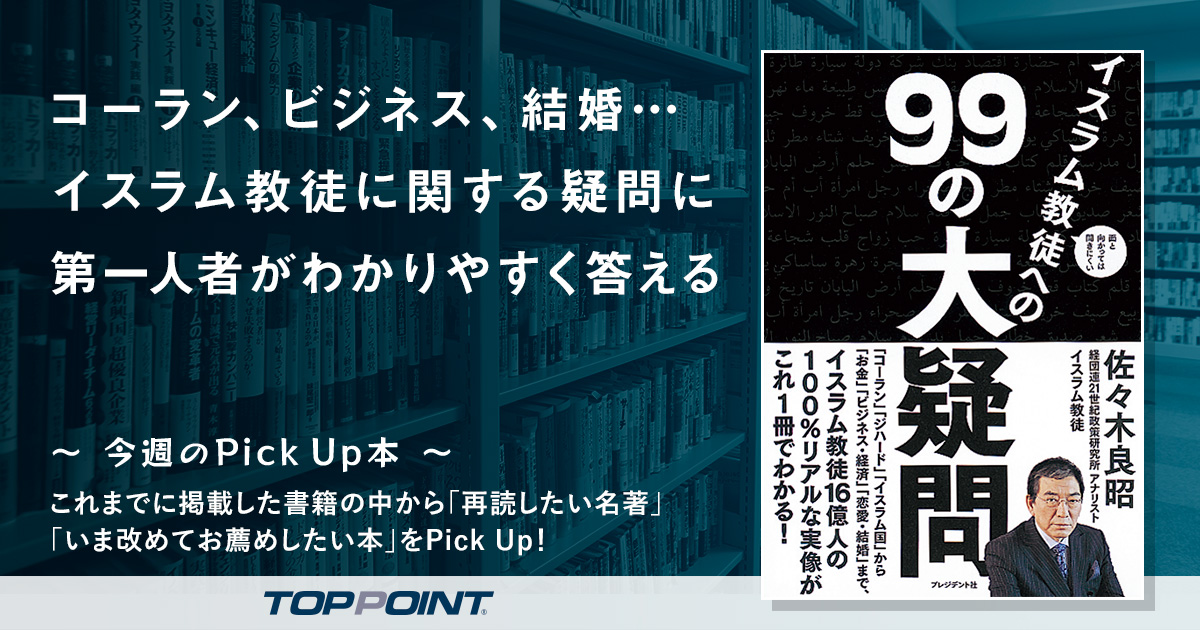
コーラン、ビジネス、結婚… イスラム教徒に関する疑問に第一人者がわかりやすく答える
-
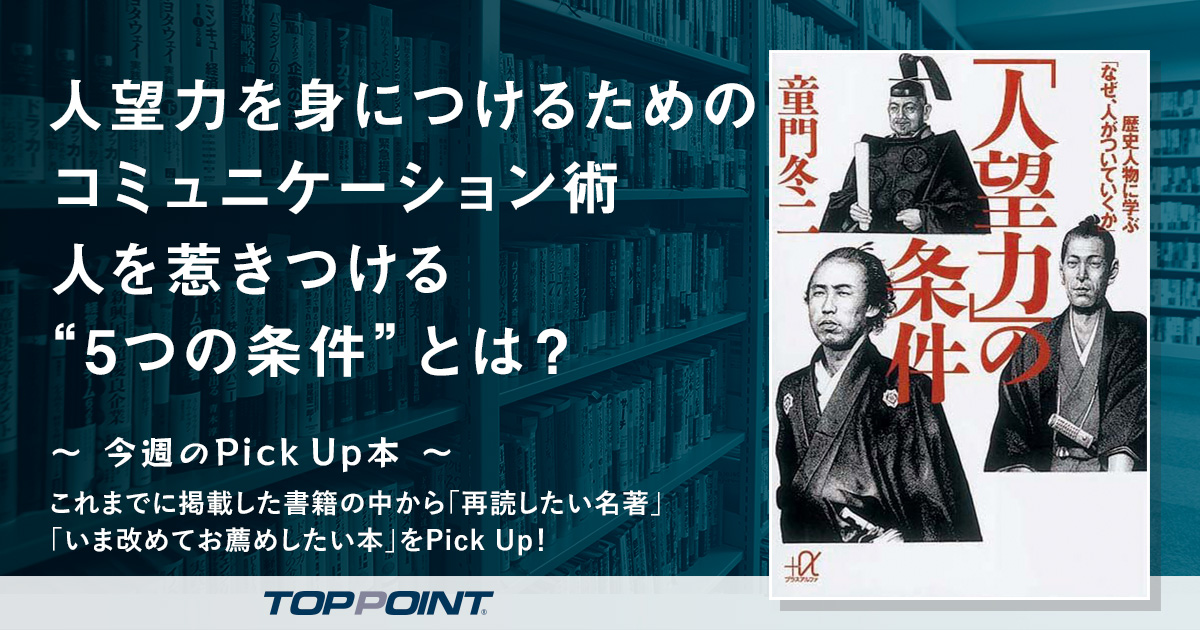
人望力を身につけるためのコミュニケーション術 人を惹きつける “5つの条件”とは?
-
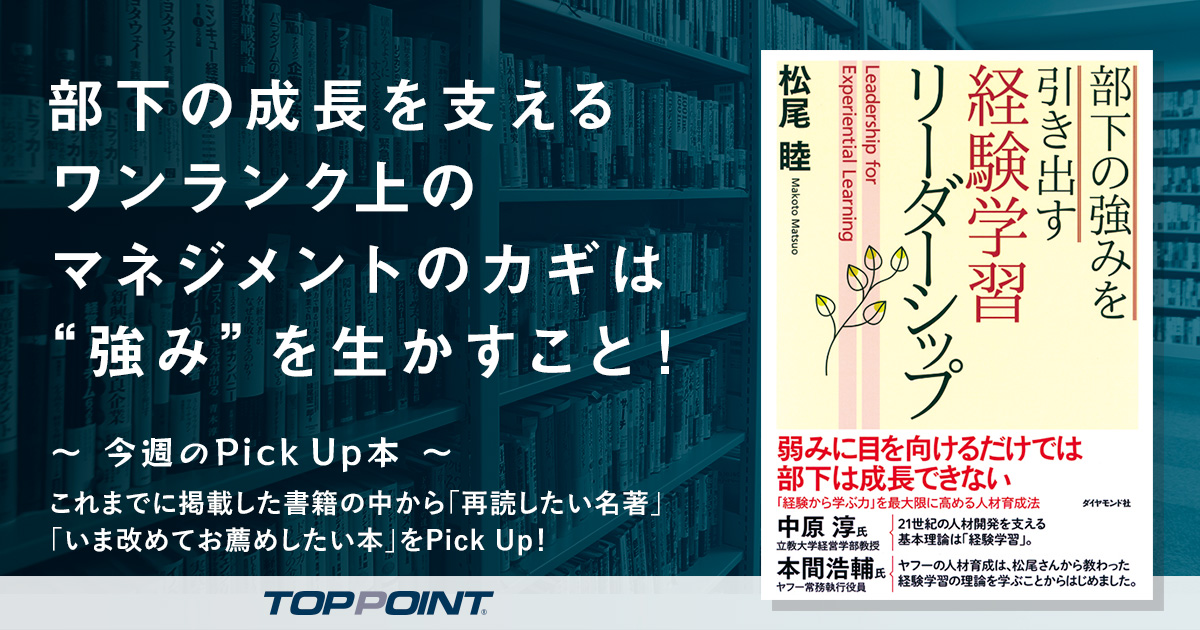
部下の成長を支えるワンランク上のマネジメントのカギは“強み”を生かすこと!





