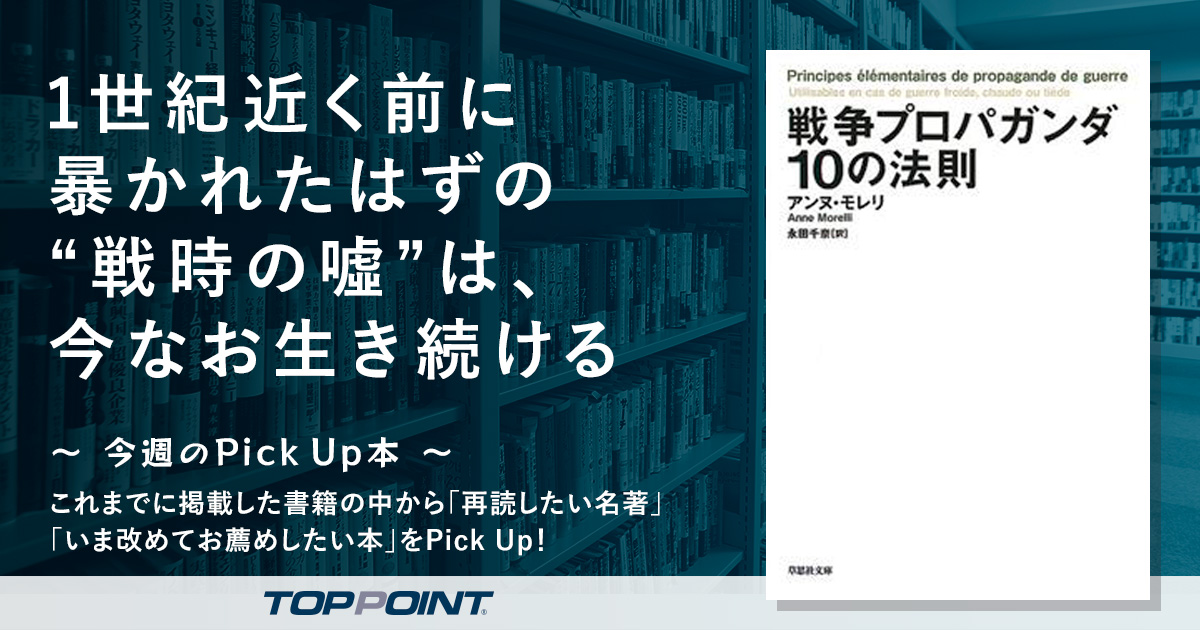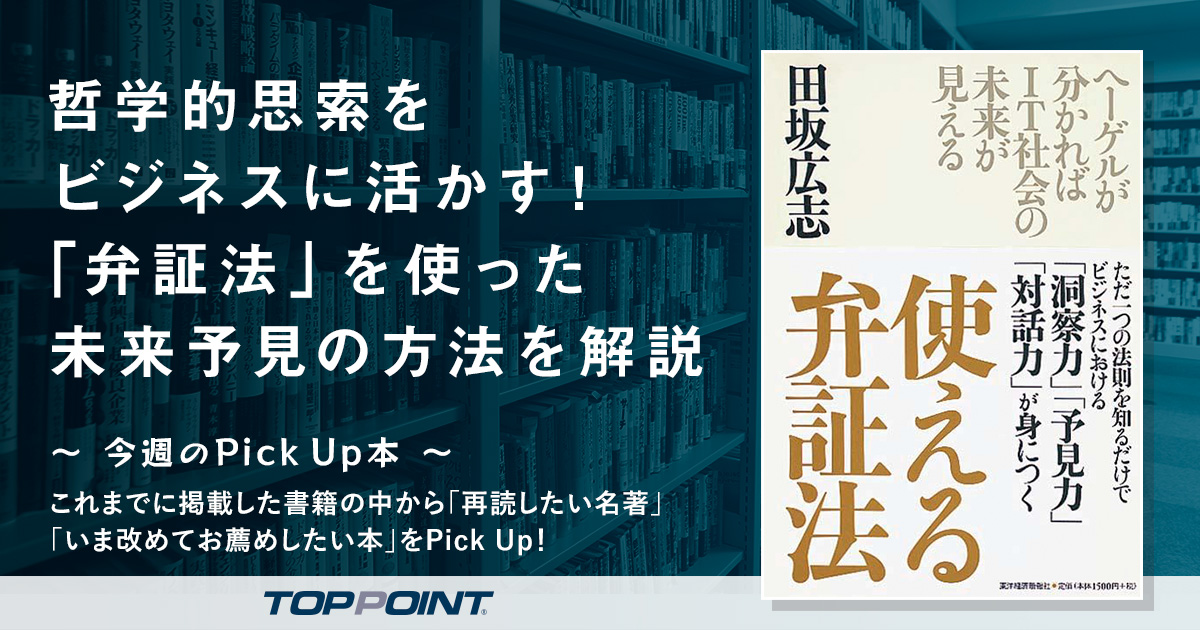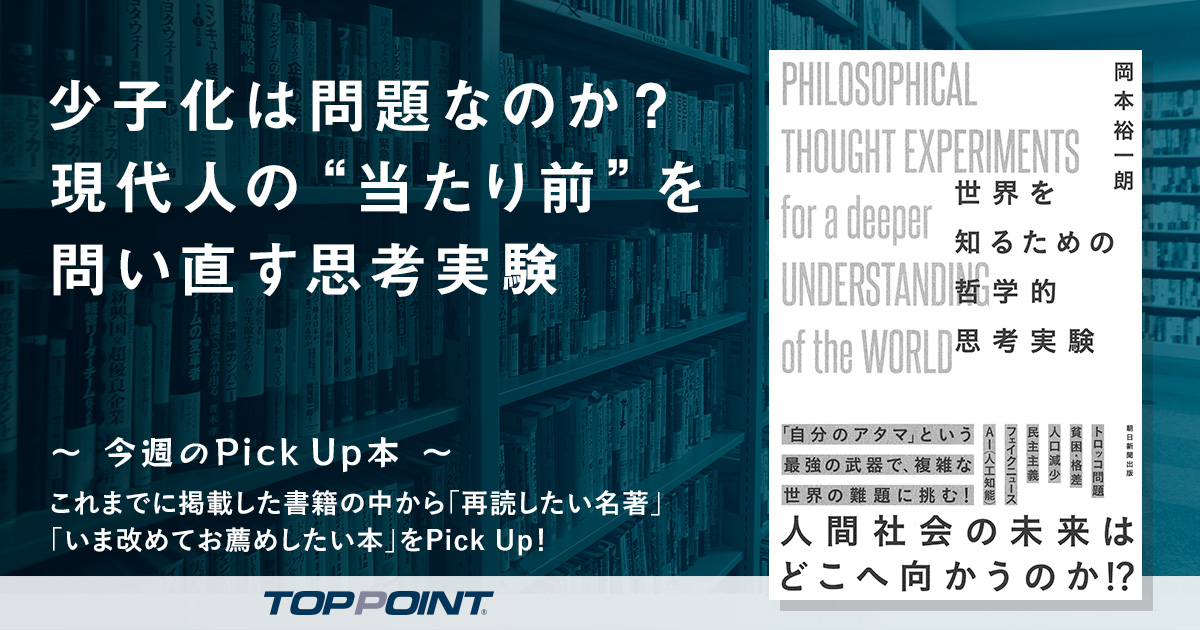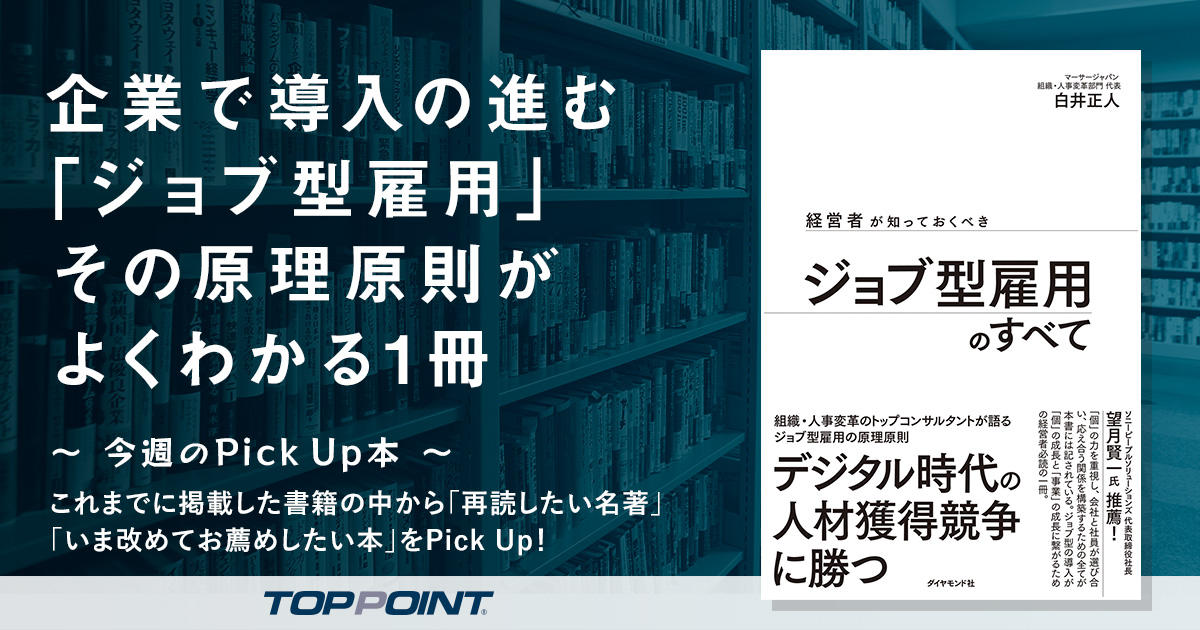
先月、厚生労働省が企業に対し、将来の勤務地や仕事の内容などの就労条件をすべての従業員に明示するよう求める、との報道がありました(「勤務地や職務、全社員に明示 「ジョブ型」へ法改正検討」/日本経済新聞電子版2022年8月31日)。その趣旨は、「ジョブ型雇用」の広がりを受けて、法改正を検討するというものです。
このジョブ型雇用。働く側としては雇用形態をイメージしやすいのですが、導入する組織の側に立つと、これまでの組織形態をどの程度変えればよいのか、わからないことも多くあります。ジョブ型雇用が広がりを見せる中、経営者や管理職の方々にとって、その具体的な知識を得ることは喫緊の課題ではないでしょうか。
そこで今週は、ジョブ型雇用の概要から導入する際のプロセスまで、その全体像がわかる本『経営者が知っておくべきジョブ型雇用のすべて』(白井正人 著/ダイヤモンド社 刊)をPick Upします。著者の白井氏は、約30年間にわたり組織・人事領域の経営コンサルティングに従事してきたトップコンサルタントです。
まず、ジョブ型雇用とはどのような制度でしょうか。改めて本書の記述を見てみると ――