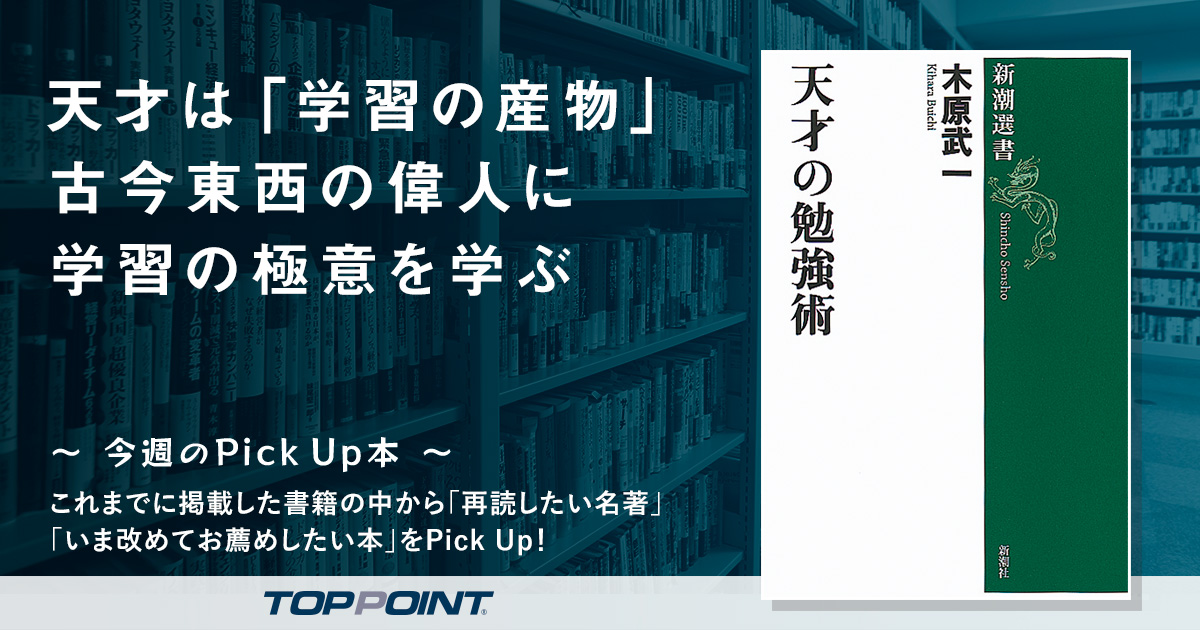
「化学」の試験で『枕草子』
先週の1月18日・19日に、2025年度の大学入学共通テストが行われました。
その試験問題が、ネットを騒がせました。「化学」の問題で古典の『枕草子』が出た、というのです。
「化学発光ではないもの」を選ぶ問題で、選択肢の1つとして『枕草子』の「(蛍が)ほのかにうち光りて」という一節が挙げられており(他の選択肢は、ルミノール反応による光、ケミカルライトの光、ネオンサインの光)、ネットでは戸惑いの声や、面白がる声が聞かれました。
ちなみに答えは、蛍の光ではなくネオンサインの光。そもそも「化学発光」という言葉すら知らなかった身としては蛍だけ化学っぽくないなと思ったのですが、見事に間違えました。
蛍のお尻にある「発光器」には、「ルシフェリン」という発光する物質と、発光を助ける「ルシフェラーゼ」という酵素があり、これらが体内の酸素と反応して光を出すそうです。蛍が光る様子はテレビなどで見たことがあるものの、「なぜ」「どのように」ということを深く考えたことはなかったことに気づかされました。
物理学者のアイザック・ニュートンが、木から落ちるリンゴを見て万有引力の法則を発見した、というのは有名な話ですが(もっとも、これは多分に単純化された話だそうです)、蛍が光るのを見ても深く考えることをしなかった自分は、とてもニュートンにはなれそうにないな、と一抹の寂しさとともに思い知らされました。
では、ニュートンのような歴史に名を残す“天才”たちは、普通の人間とは何が違うのでしょうか? 私たちのような普通の人間が彼らのようになることは、本当に不可能なのでしょうか?
今週は、こうしたことを考える上で参考になる本、『天才の勉強術』(木原武一 著/新潮社 刊)をPick Upします。
このPick Up本を読んだ方は、
他にこんな記事にも興味を持たれています。
-
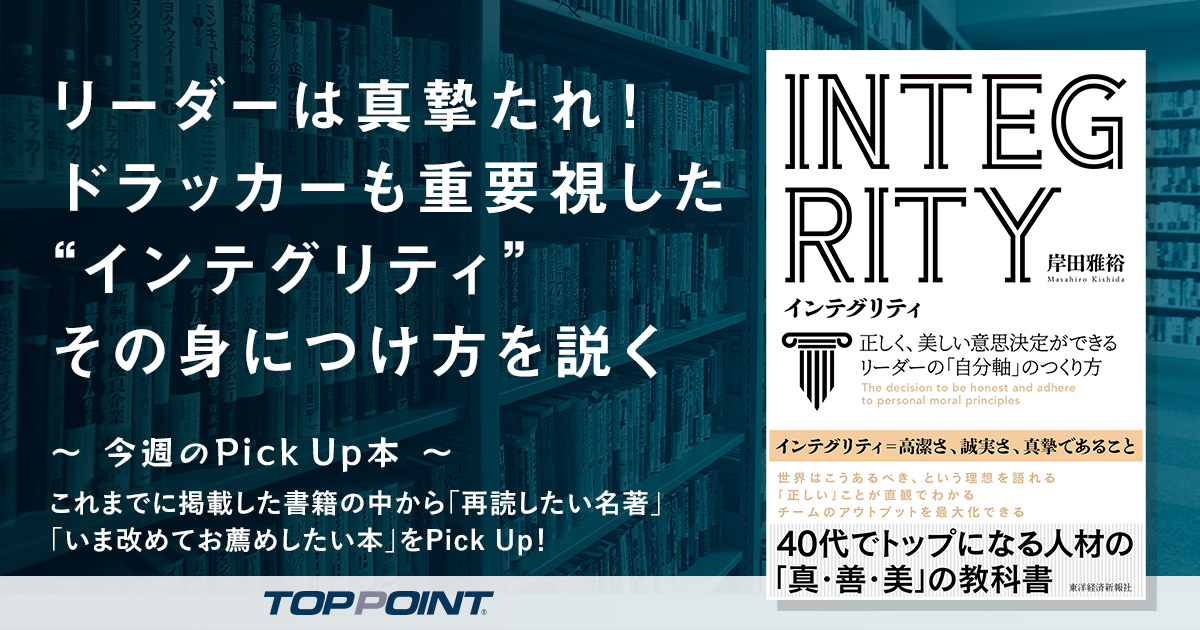
リーダーは真摯たれ! ドラッカーも重要視した“インテグリティ” その身につけ方を説く
-
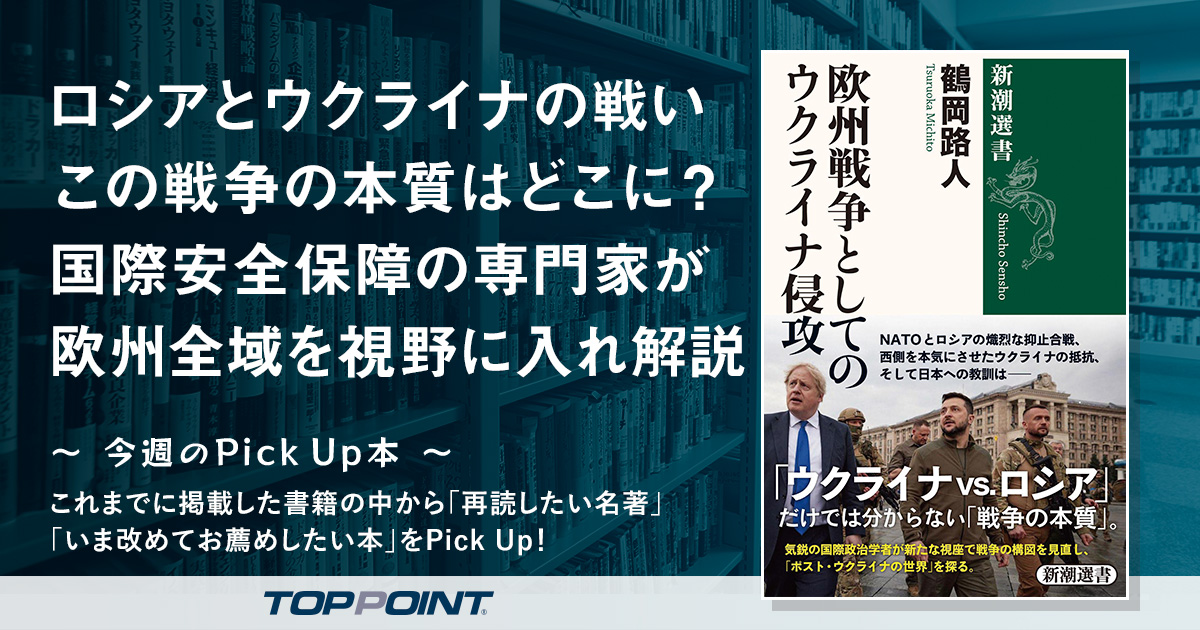
ロシアとウクライナの戦い この戦争の本質はどこに? 国際安全保障の専門家が欧州全域を視野に入れ解説
-
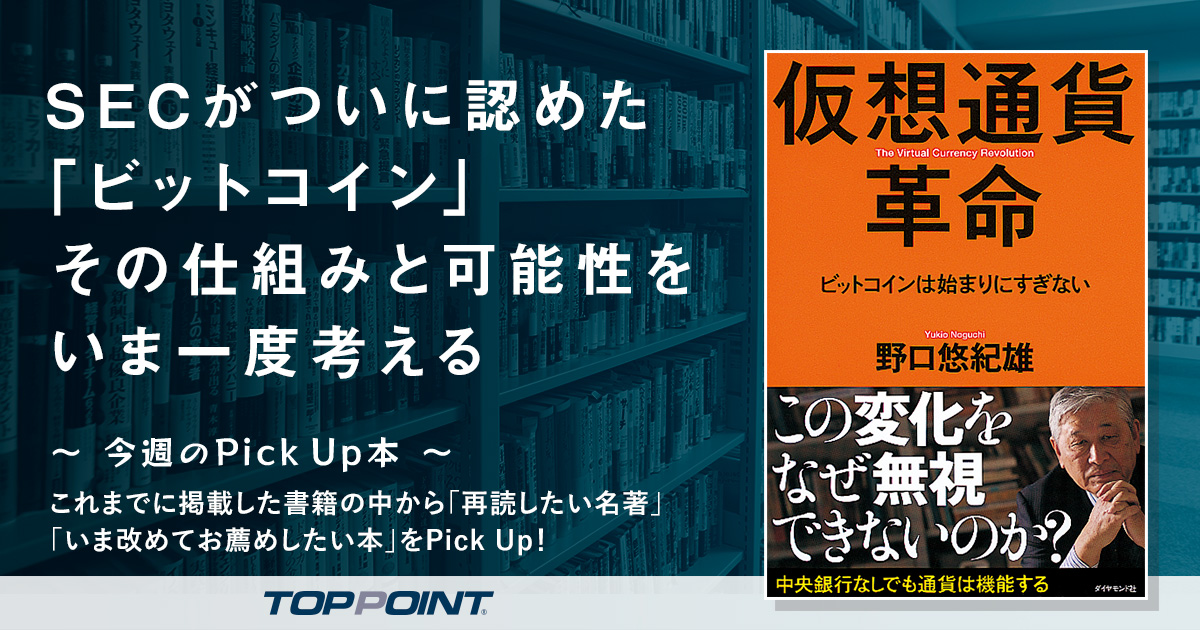
SECがついに認めた「ビットコイン」 その仕組みと可能性をいま一度考える





