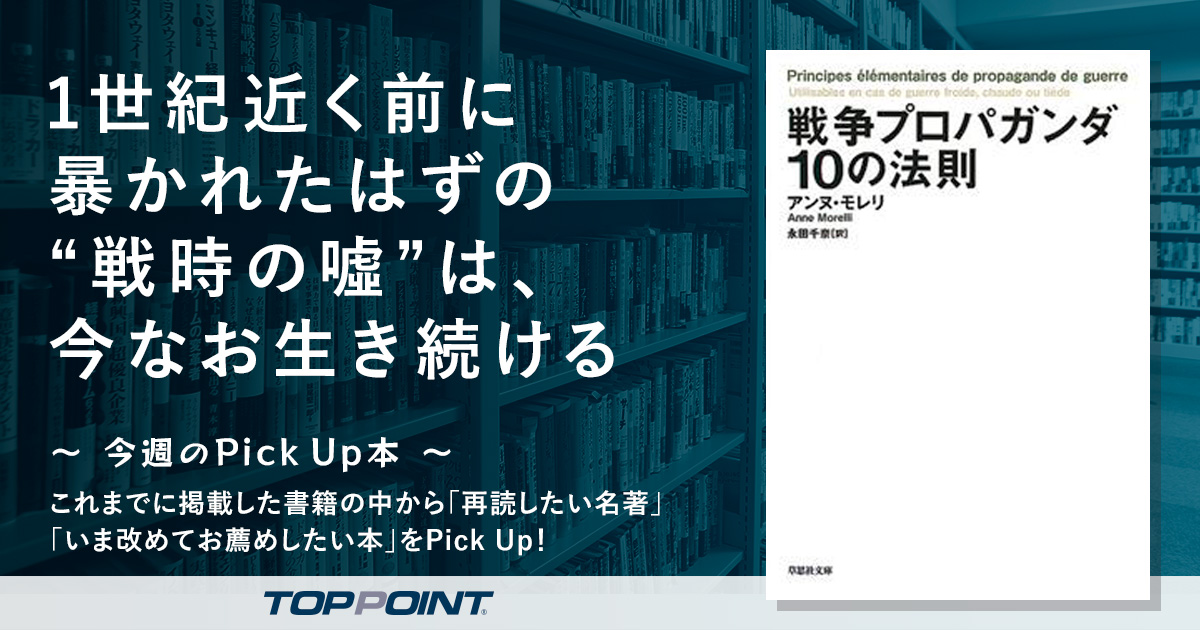
今年5月9日、ロシアの戦勝記念日に演説を行ったプーチン大統領は、ウクライナ侵攻について次のように言及しました。
ネオナチとの衝突は避けられなかった。NATO(北大西洋条約機構)は最新兵器を定期的に提供し、危険は日増しに高まった。攻撃はやむを得なかった。時宜を得た、唯一の正しい決定だった。
(「「祖国防衛は常に神聖」プーチン大統領演説要旨」/日本経済新聞電子版2022年5月9日)
日本で様々な情報に接していると、プーチン大統領の発言は「都合のいい噓」「プロパガンダ」であるように聞こえます。しかし、情報が統制されたロシア国内では事情が異なります。国民はこうした発言を繰り返し耳にすることで、相手国に怒りと憎しみを抱き、強い愛国心を持つようになるのです。
では、私たちがプロパガンダに乗せられないようにするにはどうすればよいのか。そのためには、そこに隠された「噓」がいかなるものかを見極めなければなりません。
そこで今週は、世論を巧みに操る「戦争プロパガンダ」の手法を解説した『戦争プロパガンダ10の法則』(アンヌ・モレリ 著/草思社 刊)をPick Upします。ベルギーの歴史学者である著者は、アーサー・ポンソンビーの古典的名著である『戦時の噓』(1928年刊)が指摘した戦争プロパガンダの「10項目の法則」に基いて持論を展開しています。その法則は、本書では以下のように各章のタイトルとしても用いられています。
このPick Up本を読んだ方は、
他にこんな記事にも興味を持たれています。
-
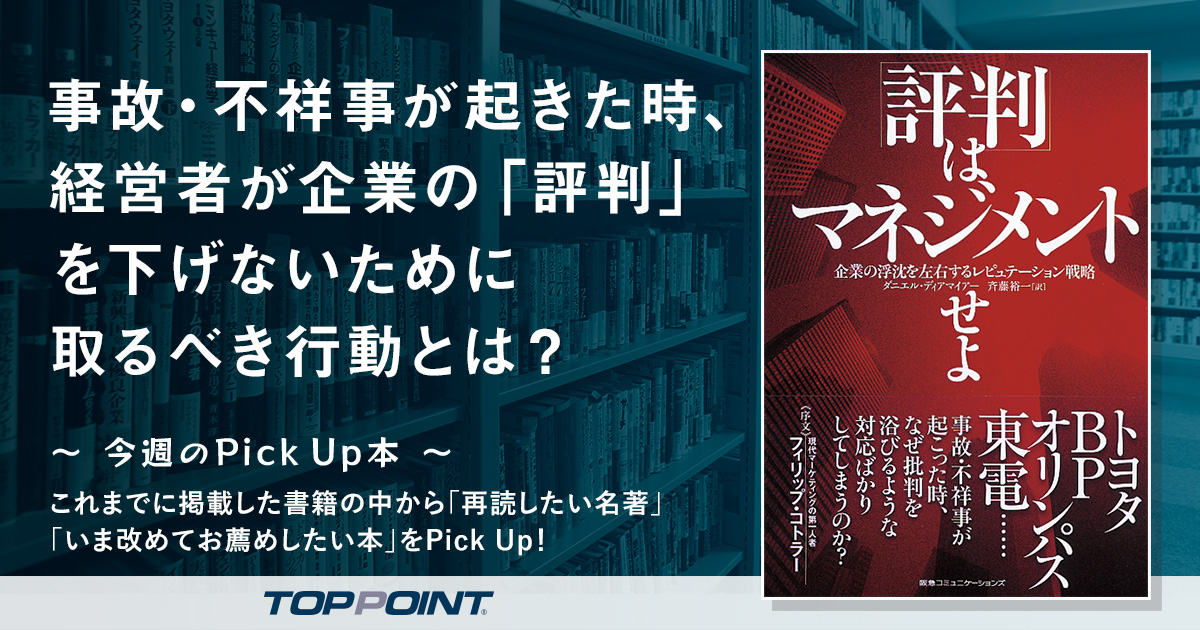
事故・不祥事が起きた時、経営者が企業の「評判」を下げないために取るべき行動とは?
-
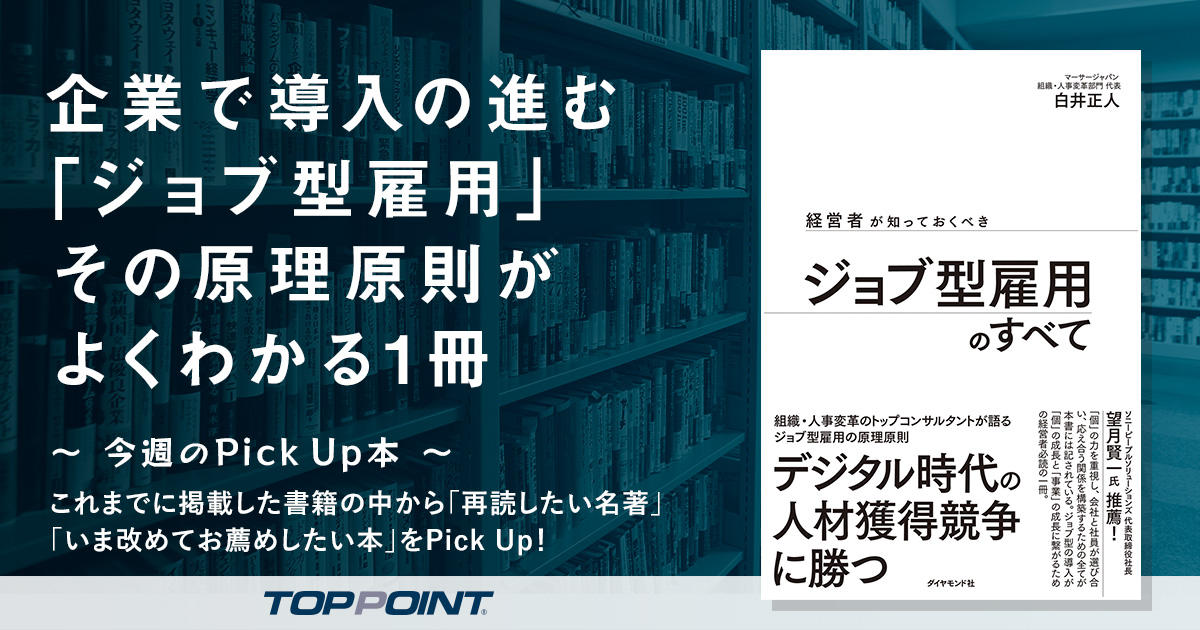
企業で導入の進む「ジョブ型雇用」 その原理原則がよくわかる1冊
-
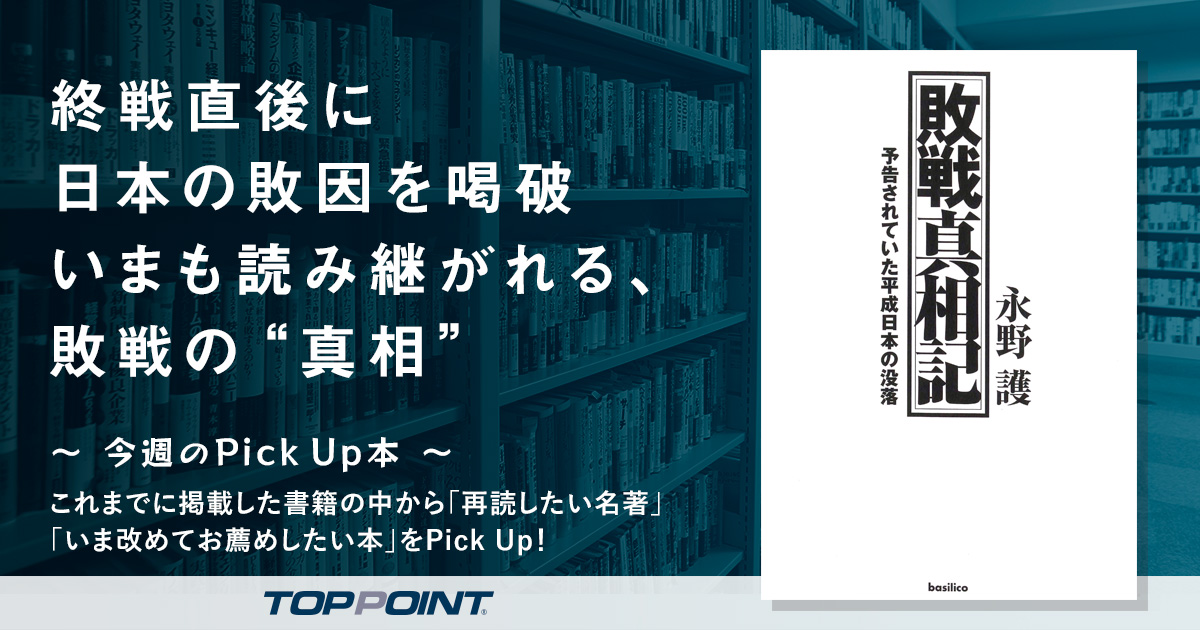
終戦直後に日本の敗因を喝破 いまも読み継がれる、敗戦の“真相”





