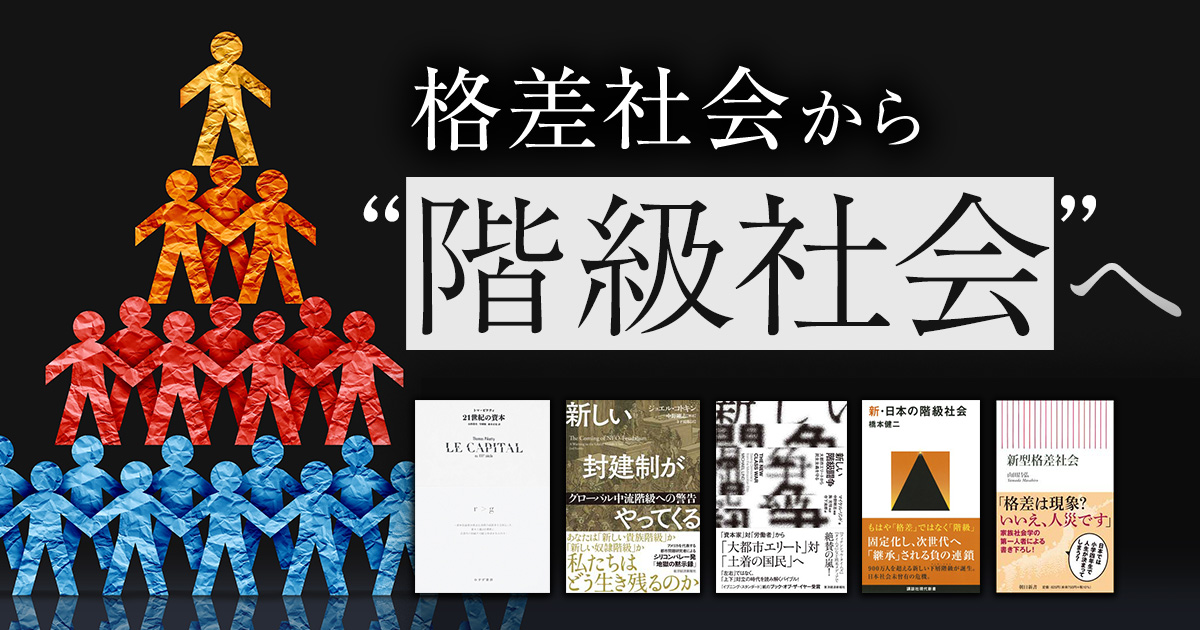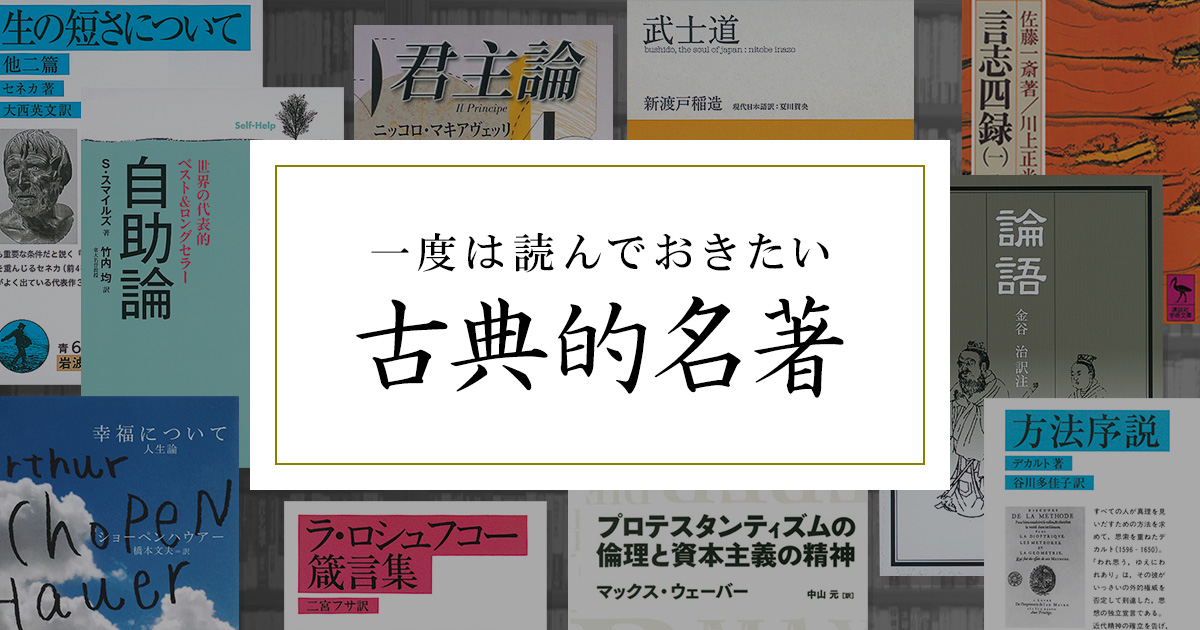
「ふるきをたずね あたらしきをしる」
温故知新という言葉を持ちださずとも、日々、多くの書籍に親しまれている方なら「古典」と称される書籍から、多くの気づきや知見を得た経験をお持ちでしょう。
一般に、古典が“外れのない名著”と言われる理由は2つあります。
1つは、幾多の読者の厳しい眼にさらされた上で、今もなお高い評価を得ていること。もう1つは、数十年、数百年の時を経ても色あせない、普遍的な教訓が記されていること。
「TOPPOINT」でも、Longseller Collectionコーナー(毎号10冊目の書籍)
温故知新という言葉を持ちださずとも、日々、多くの書籍に親しまれている方なら「古典」と称される書籍から、多くの気づきや知見を得た経験をお持ちでしょう。
一般に、古典が“外れのない名著”と言われる理由は2つあります。
1つは、幾多の読者の厳しい眼にさらされた上で、今もなお高い評価を得ていること。もう1つは、数十年、数百年の時を経ても色あせない、普遍的な教訓が記されていること。
「TOPPOINT」でも、Longseller Collectionコーナー(毎号10冊目の書籍)