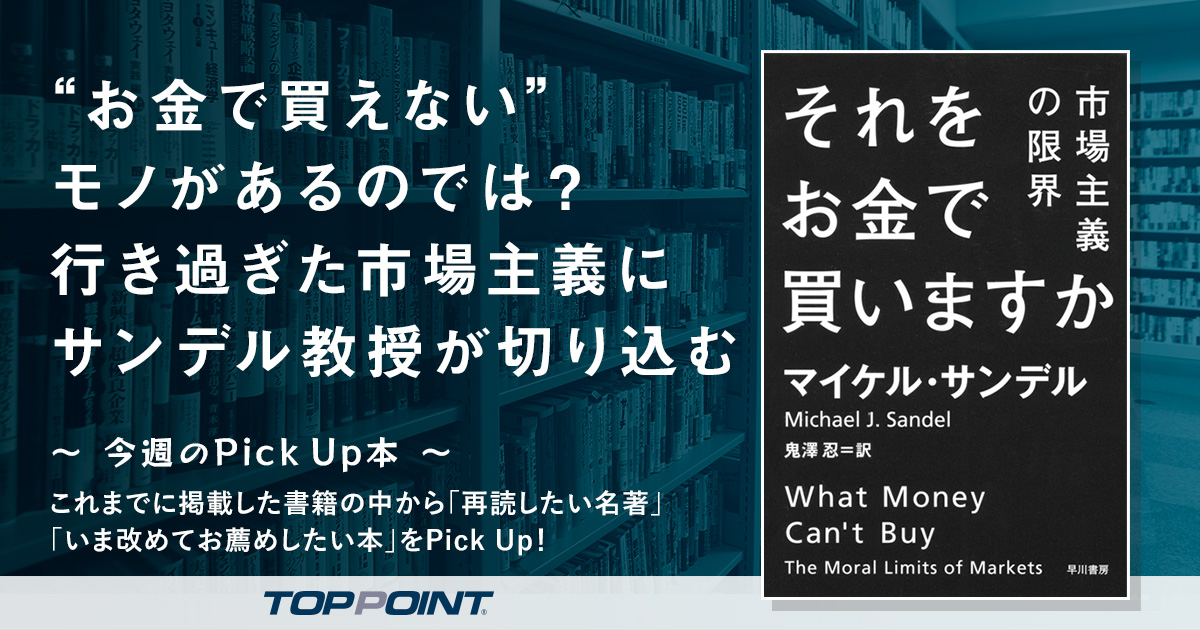
スーパーマリオブラザーズの帽子をかぶった海外の観光客、ハリー・ポッターの衣装を着た日本の学生たち…。夜、仕事帰りにJR大阪駅の構内を歩いていると、USJ(ユニバーサル・スタジオ・ジャパン)帰りと思しき人たちと出会います。
調査によれば、2022年のUSJの来園者数は1235万人。前年から2.2倍に増え、コロナ禍前の19年比では85%まで回復しています(「USJ、世界3位の集客力 日本のアニメを起爆剤に」/日本経済新聞電子版2023年8月2日)。これだけ入場者が多いと、アトラクションに並ぶのも一苦労です。先述の日経新聞の記事では、ジェットコースターは待ち時間が3時間以上の時もあるそうです。
このPick Up本を読んだ方は、
他にこんな記事にも興味を持たれています。
-
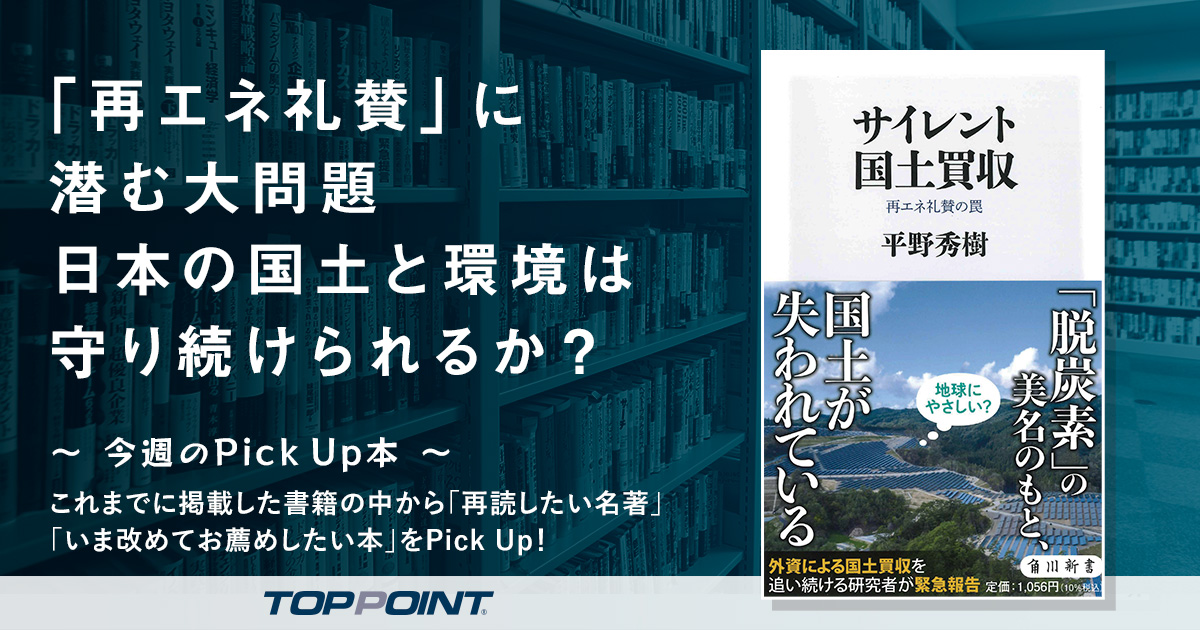
「再エネ礼賛」に潜む大問題 日本の国土と環境は守り続けられるか?
-
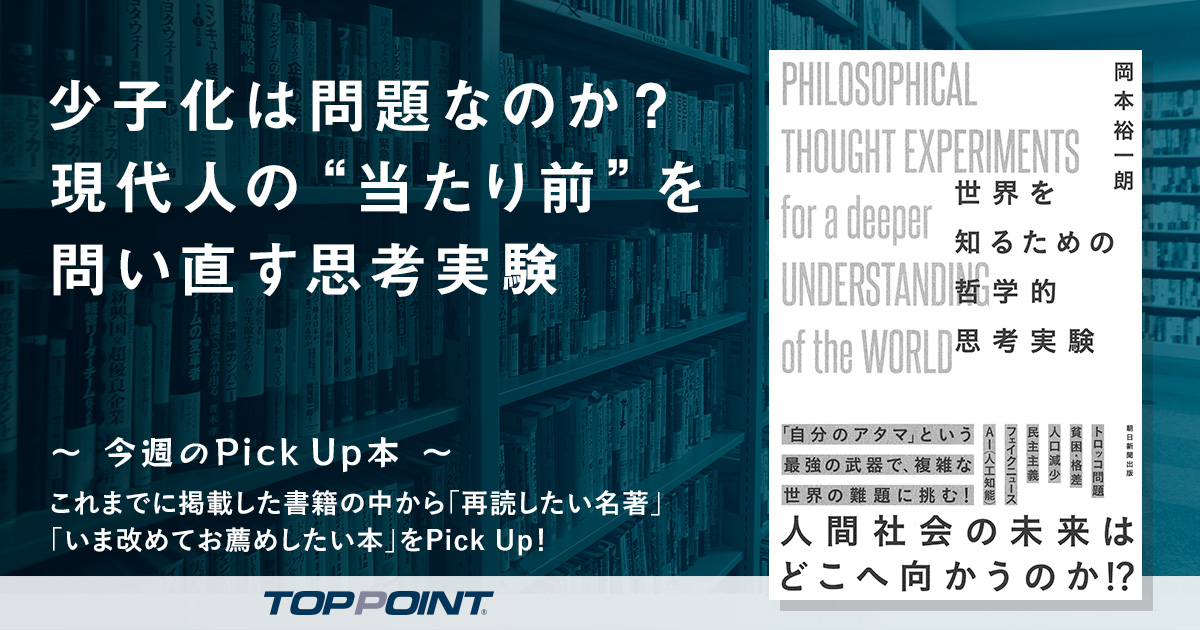
少子化は問題なのか? 現代人の“当たり前”を問い直す思考実験
-
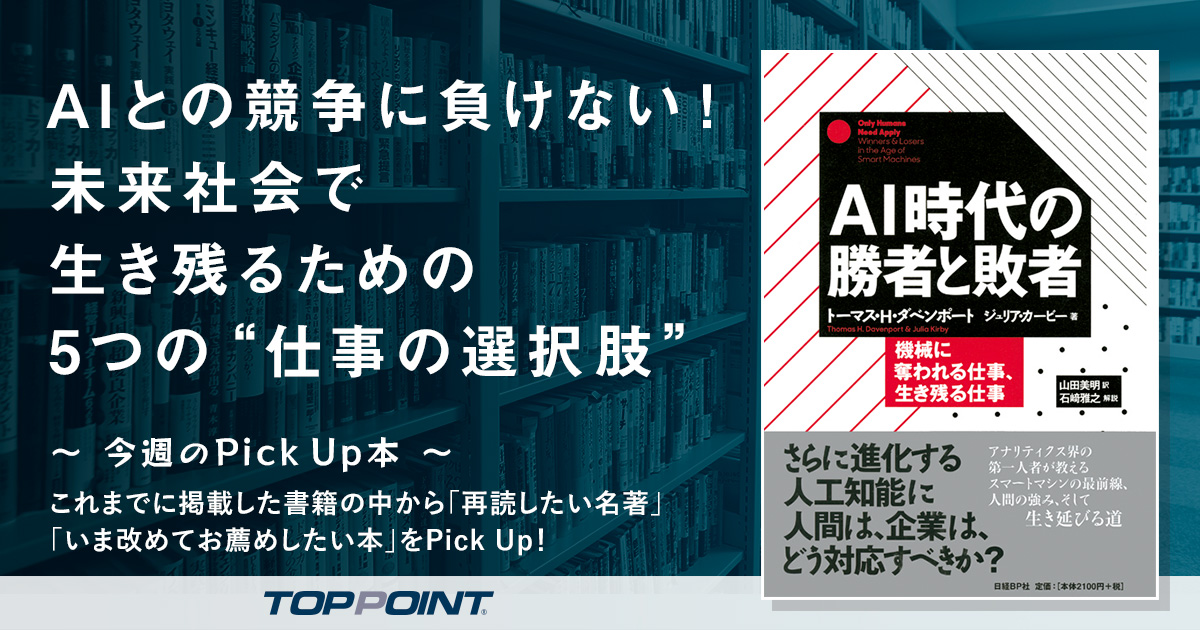
AIとの競争に負けない! 未来社会で生き残るための5つの“仕事の選択肢”





