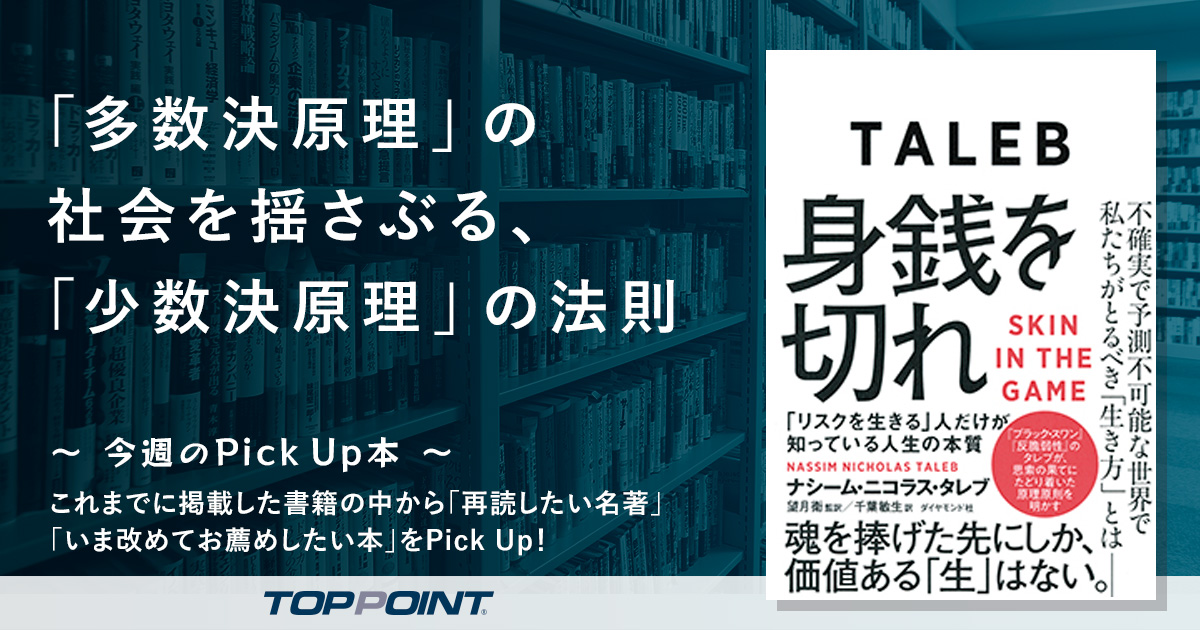
先日、自宅でカレーを食べていた時の話です。
我が家には小学生の子どもがいるのですが、辛い食べ物が苦手です。そのため、カレーを作る時には甘口のルーを使います。親は辛さが欲しい時には、自分の皿に盛られたカレーにガラムマサラや七味唐辛子を振りかけて調整しています。
辛さが苦手な子どもに合わせておけば、家族が同じものを食べられる。他の家でもそうしているのかな…。そんなことを考えているうちに、ふと思いました。このシチュエーション、どこかで読んだことがあるな、と。
思い出した本というのは、今回Pick Upする『身銭を切れ 「リスクを生きる」人だけが知っている人生の本質』(ナシーム・ニコラス・タレブ 著/ダイヤモンド社 刊)です。
このPick Up本を読んだ方は、
他にこんな記事にも興味を持たれています。
-
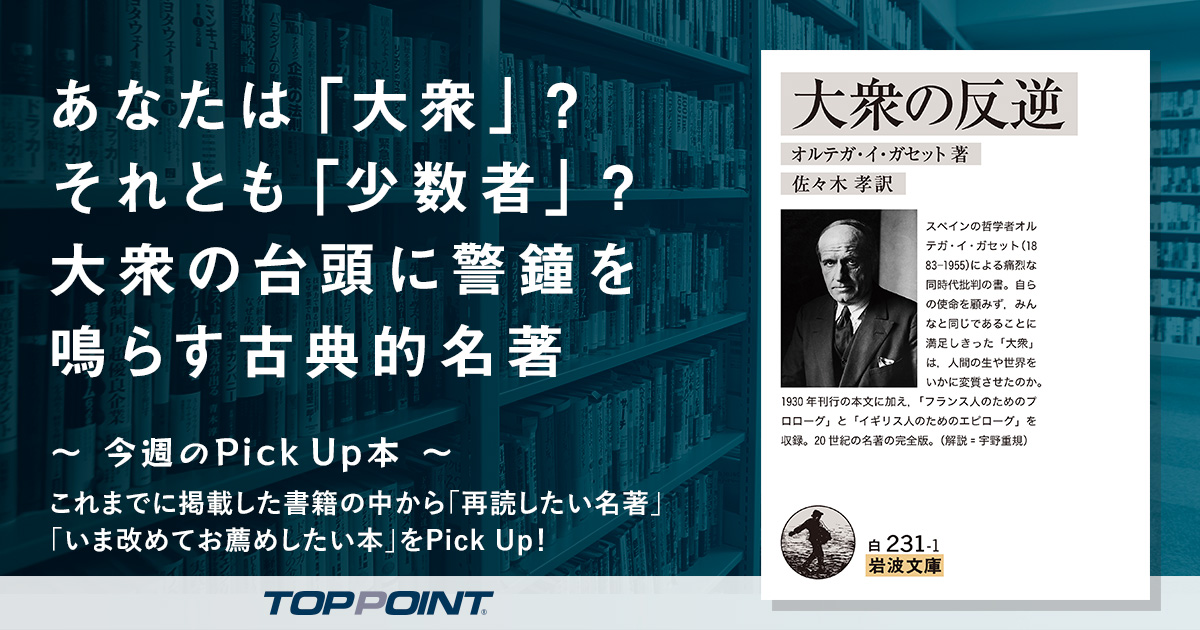
あなたは「大衆」? それとも「少数者」? 大衆の台頭に警鐘を鳴らす古典的名著
-
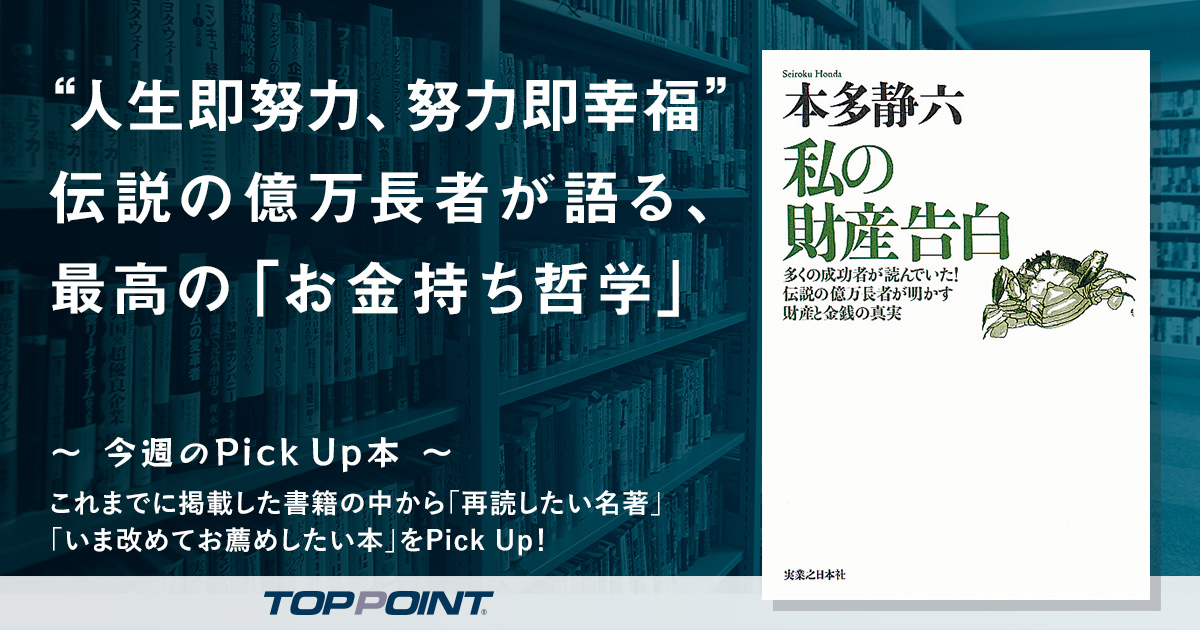
“人生即努力、努力即幸福” 伝説の億万長者が語る、最高の「お金持ち哲学」
-
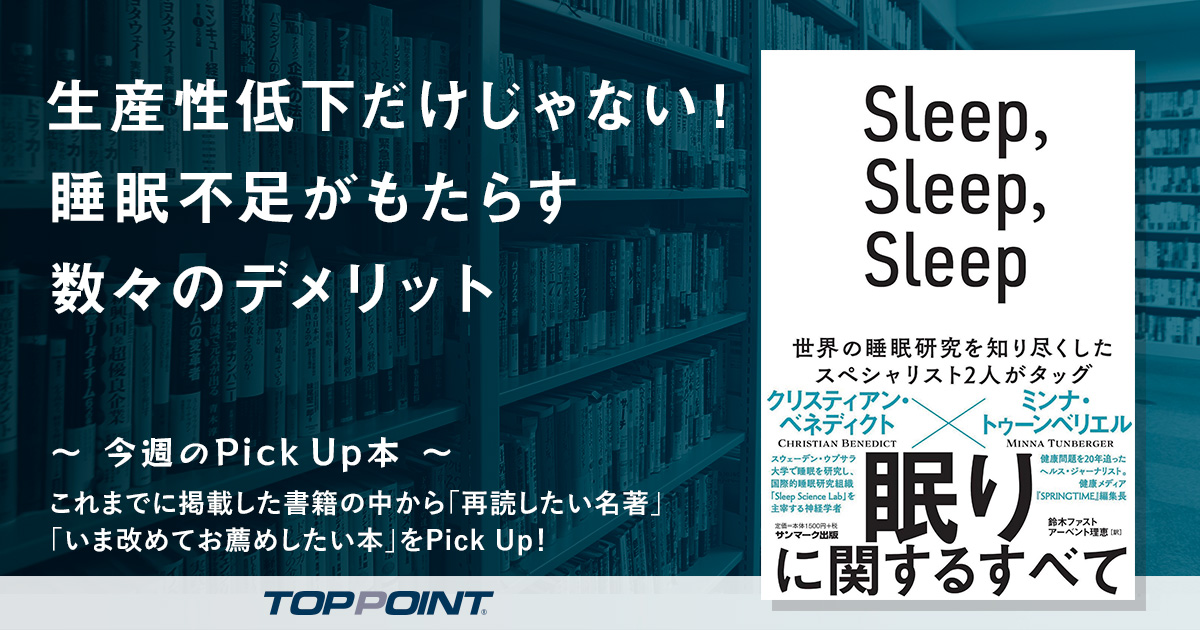
生産性低下だけじゃない! 睡眠不足がもたらす数々のデメリット





