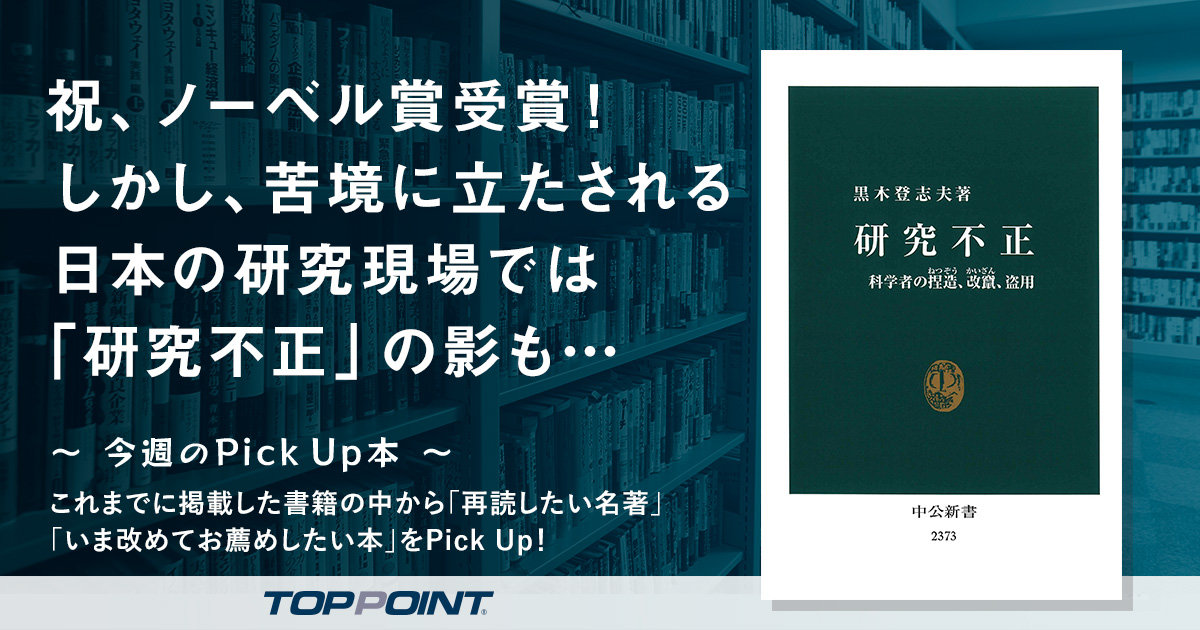
2025年10月、ノーベル賞が発表され、大阪大学の坂口志文特任教授が生理学・医学賞を、京都大学の北川進特別教授が化学賞を受賞しました。
これにより、21世紀に入ってから自然科学3部門(生理学・医学賞、物理学賞、化学賞)の日本出身受賞者は22人となりました。これは米国に次ぐ第2位です(「日本の科学者のノーベル賞受賞、ラッシュいつまで 研究力には陰り」/日本経済新聞2025年10月11日)。
一見すると、日本の科学界は安泰のように思えます。しかし実際には、日本の研究界は近年、苦境に立たされており、その中で「研究不正」に手を染めてしまう研究者も少なくないそうです。今回は、そんな“不都合な真実”を明らかにした本、『研究不正』(黒木登志夫 著/中央公論新社 刊)を取り上げます。
このPick Up本を読んだ方は、
他にこんな記事にも興味を持たれています。
-
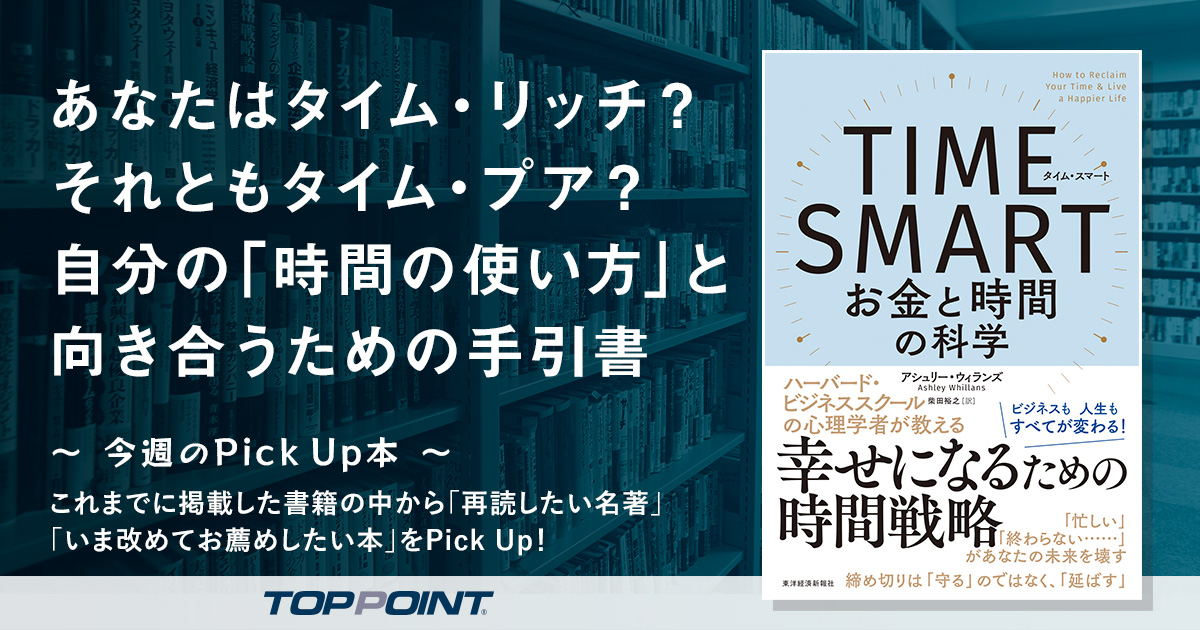
あなたはタイム・リッチ? それともタイム・プア? 自分の「時間の使い方」と向き合うための手引書
-
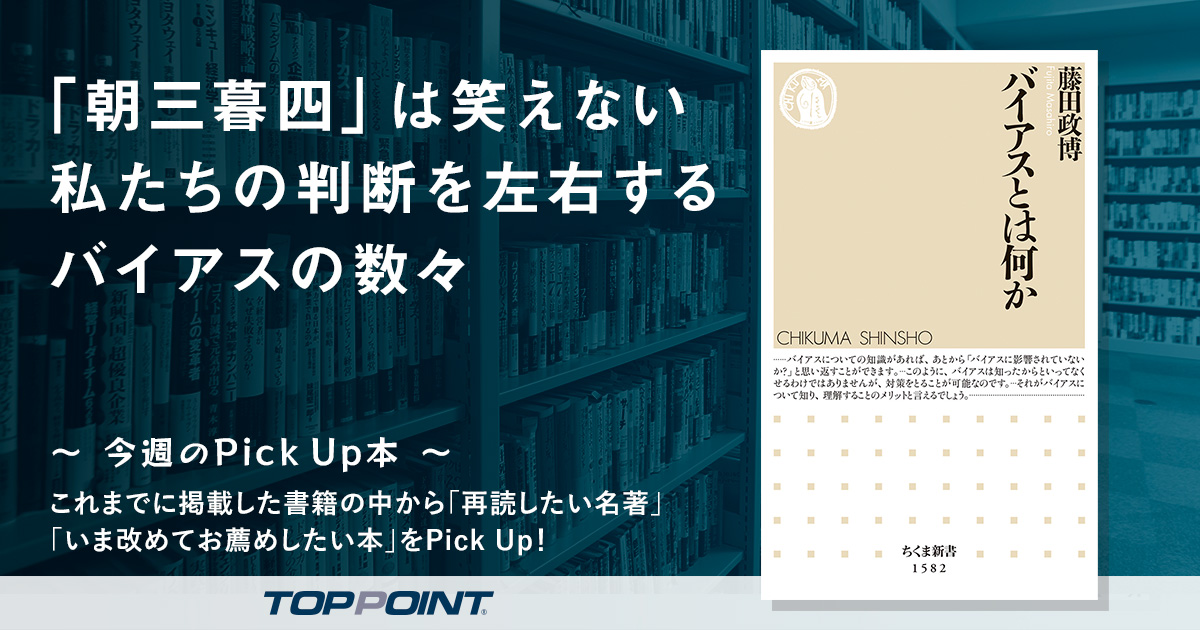
「朝三暮四」は笑えない 私たちの判断を左右するバイアスの数々
-
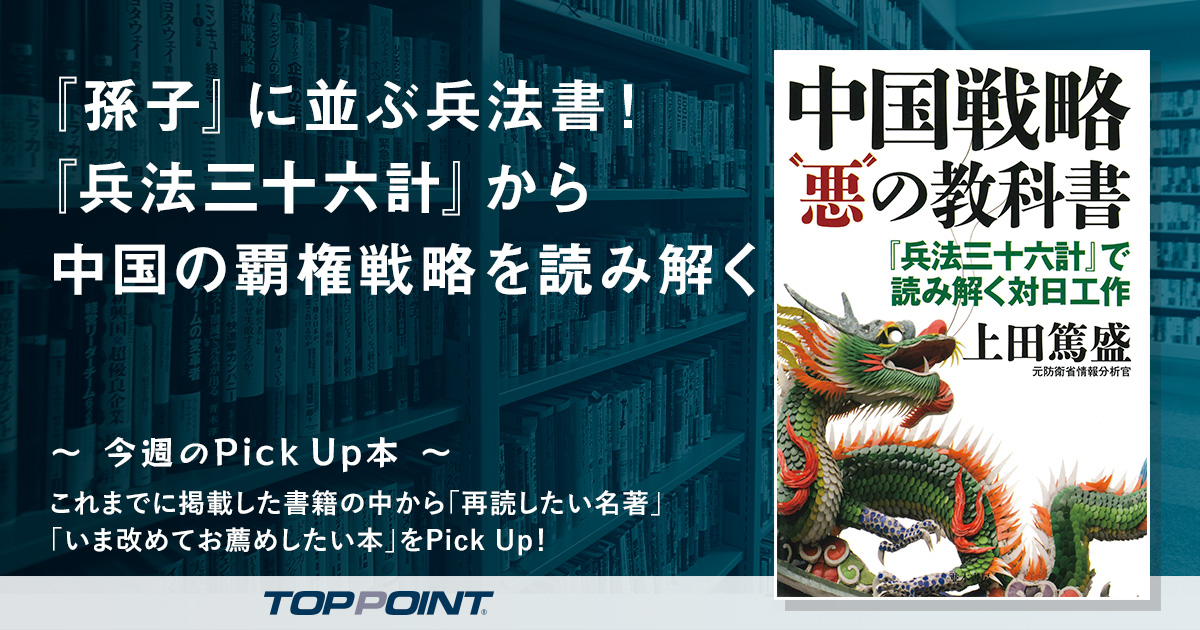
『孫子』に並ぶ兵法書! 『兵法三十六計』から中国の覇権戦略を読み解く





