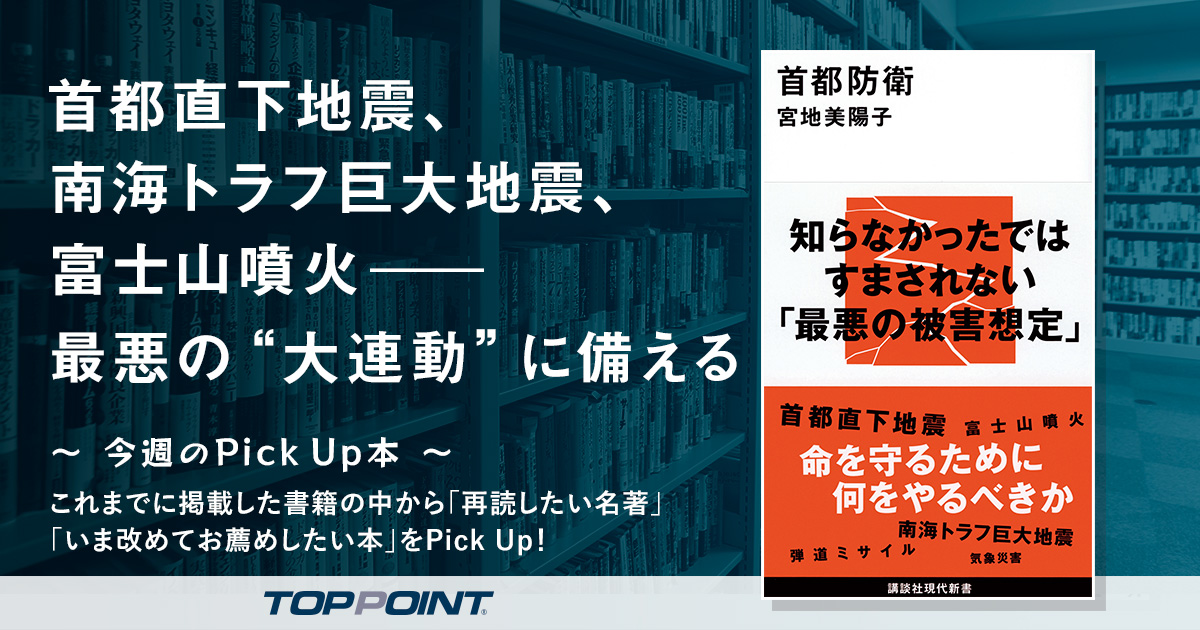
7月30日の早朝、ロシア・カムチャッカ半島付近でマグニチュード(M)8.7の巨大地震が発生しました。これは1900年以降、世界で8番目に大きな地震とされ、津波も発生(「カムチャツカ半島地震、太平洋沿岸の広範囲で津波警戒 規模歴代8位」日本経済新聞2025年7月30日)。
日本列島の広範囲で津波警報や注意報が発表され、テレビやスマホから流れた警報音に肝を冷やした人も多いのではないでしょうか。
そして8月3日には、同じくカムチャツカ半島のクラシェニンニコフ山が噴火。ロシア通信は、この噴火が約600年ぶりであり、7月30日の地震と関連している可能性があると報じました(「カムチャツカで火山噴火 600年ぶり、地震関連か」Yahoo!ニュース2025年8月3日)。
このPick Up本を読んだ方は、
他にこんな記事にも興味を持たれています。
-
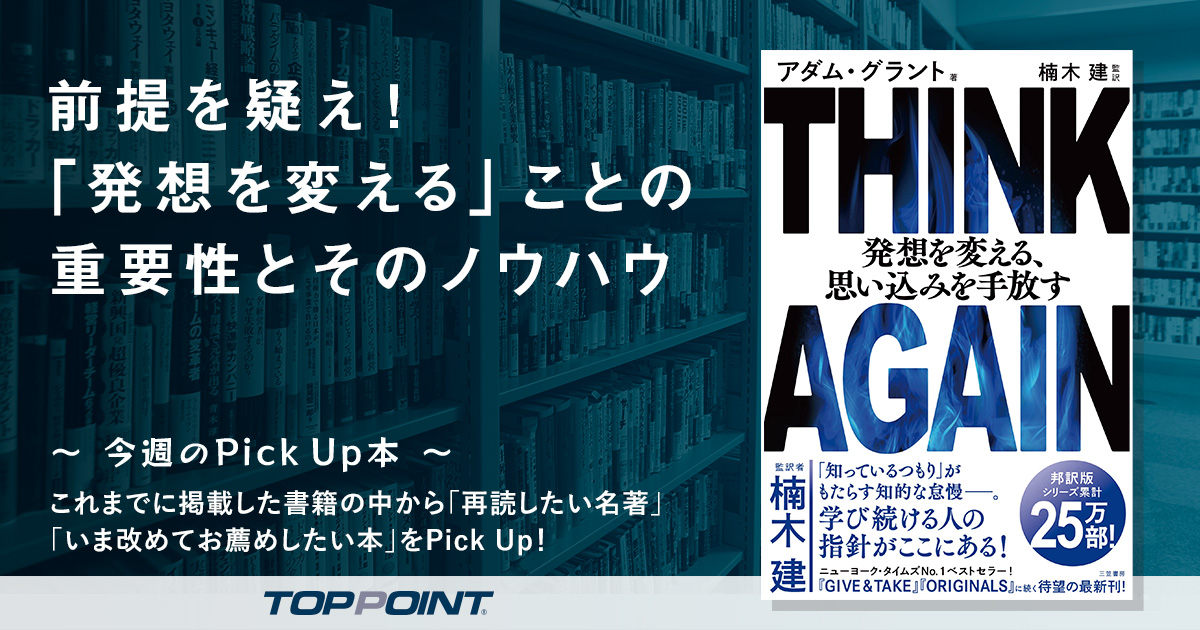
前提を疑え! 「発想を変える」ことの重要性とそのノウハウ
-
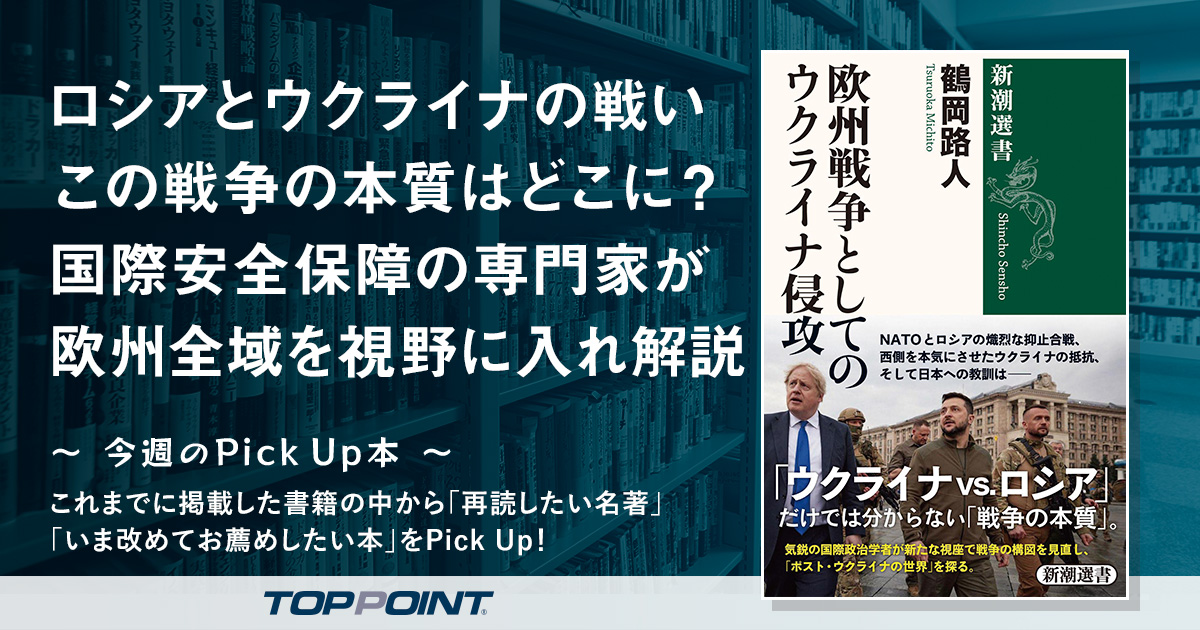
ロシアとウクライナの戦い この戦争の本質はどこに? 国際安全保障の専門家が欧州全域を視野に入れ解説
-
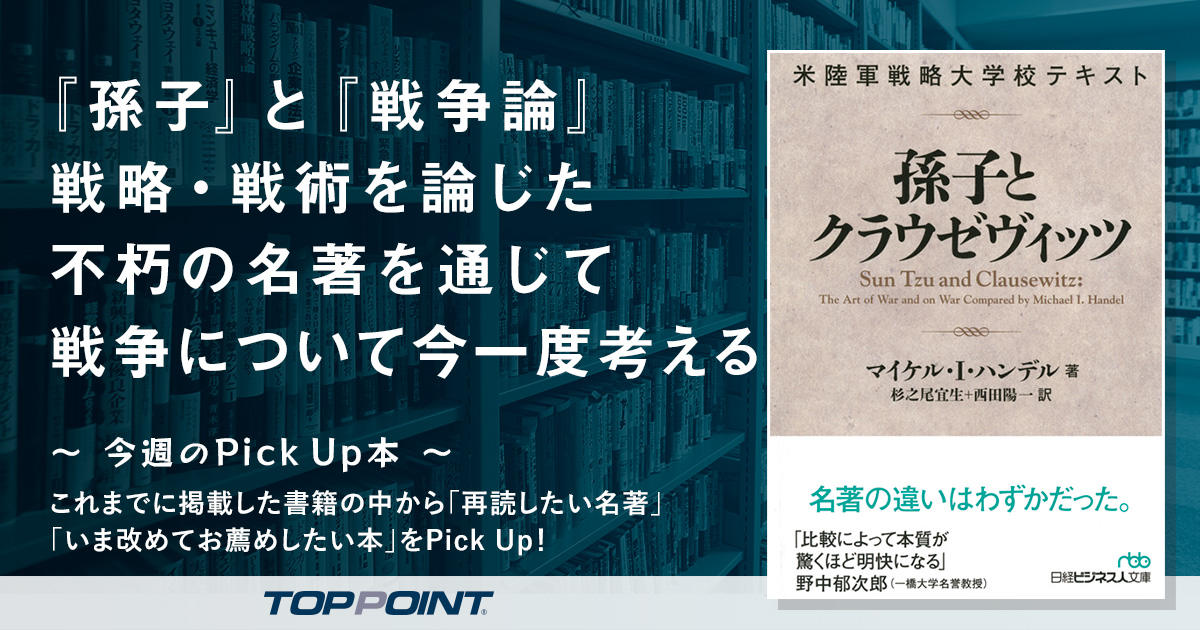
『孫子』と『戦争論』 戦略・戦術を論じた不朽の名著を通じて戦争について今一度考える





