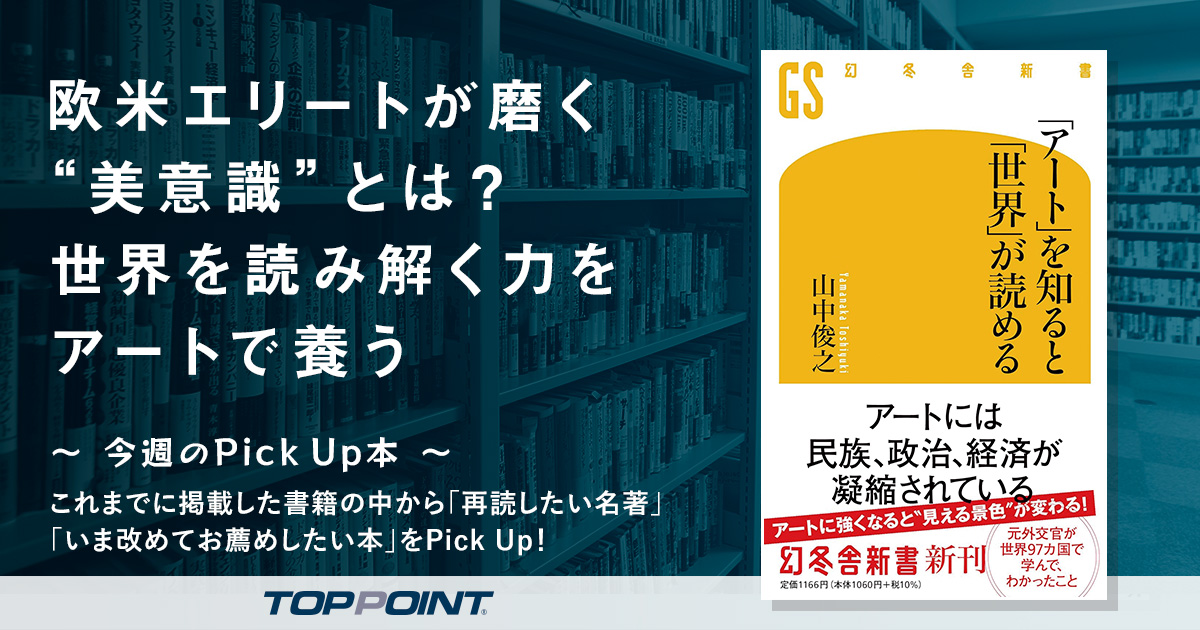
ゴールデンウィークが始まりました。連休中、皆さまはどんなふうに過ごされますか? 旅行に出かける方、自宅で読書や映画を楽しむ方も多いでしょう。もし、予定がまだ決まっていないなら、アートを巡る時間を加えてみてはいかがでしょうか。
今年は、注目の「大阪・関西万博」をはじめ、各地で大規模な芸術祭が目白押しの“アートイヤー”です。例えば——
-
- ・Study:大阪関西国際芸術祭(開催中〜10月13日)
- ・瀬戸内国際芸術祭(開催中〜11月9日)
- ・京都国際写真祭(開催中〜5月11日)
- ・千葉国際芸術祭(9月〜11月)
- ・国際芸術祭あいち(9月13日~11月30日)
- ・東京ビエンナーレ(10月17日~12月21日)
このPick Up本を読んだ方は、
他にこんな記事にも興味を持たれています。
-
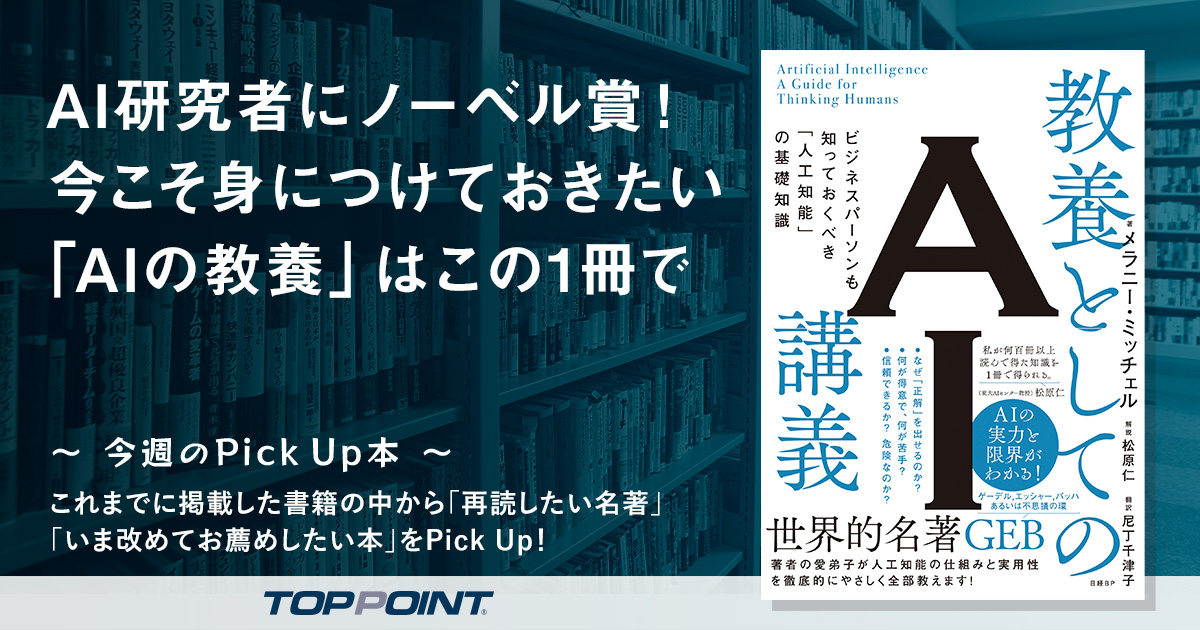
AI研究者にノーベル賞! 今こそ身につけておきたい「AIの教養」はこの1冊で
-
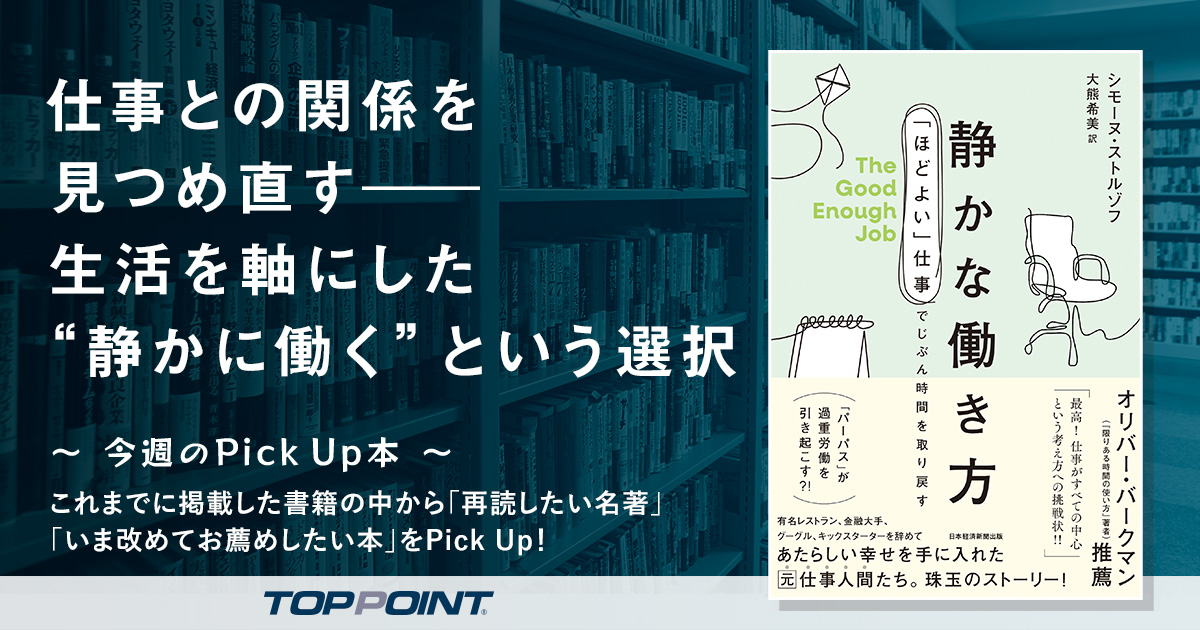
仕事との関係を見つめ直す―― 生活を軸にした“静かに働く”という選択
-
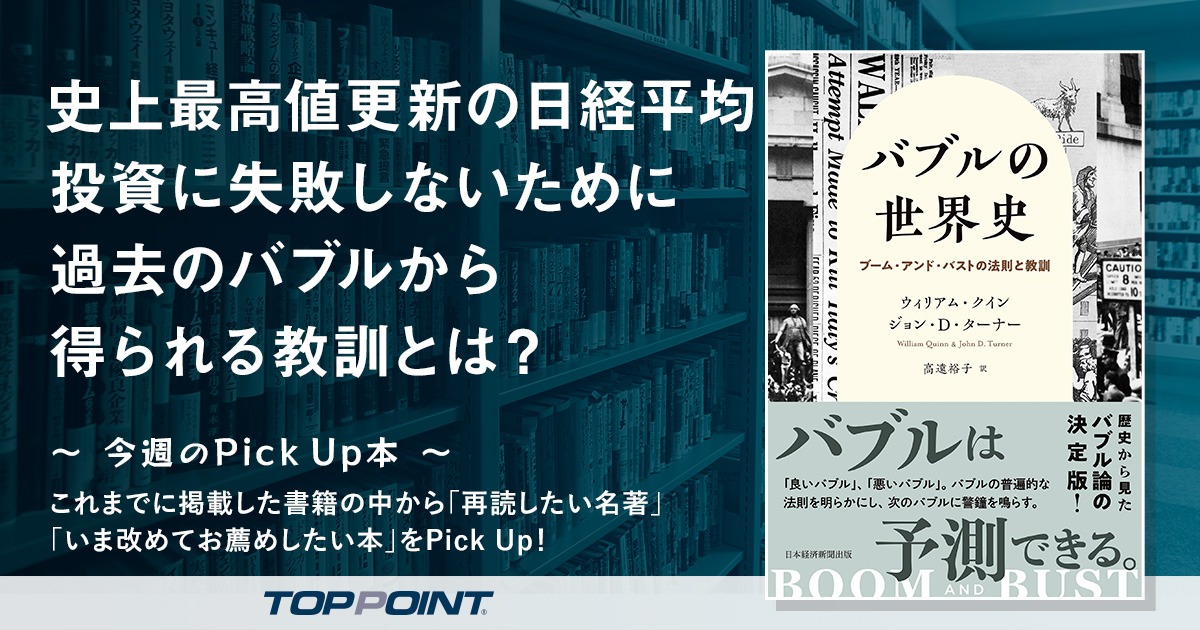
史上最高値更新の日経平均 投資に失敗しないために過去のバブルから得られる教訓とは?





