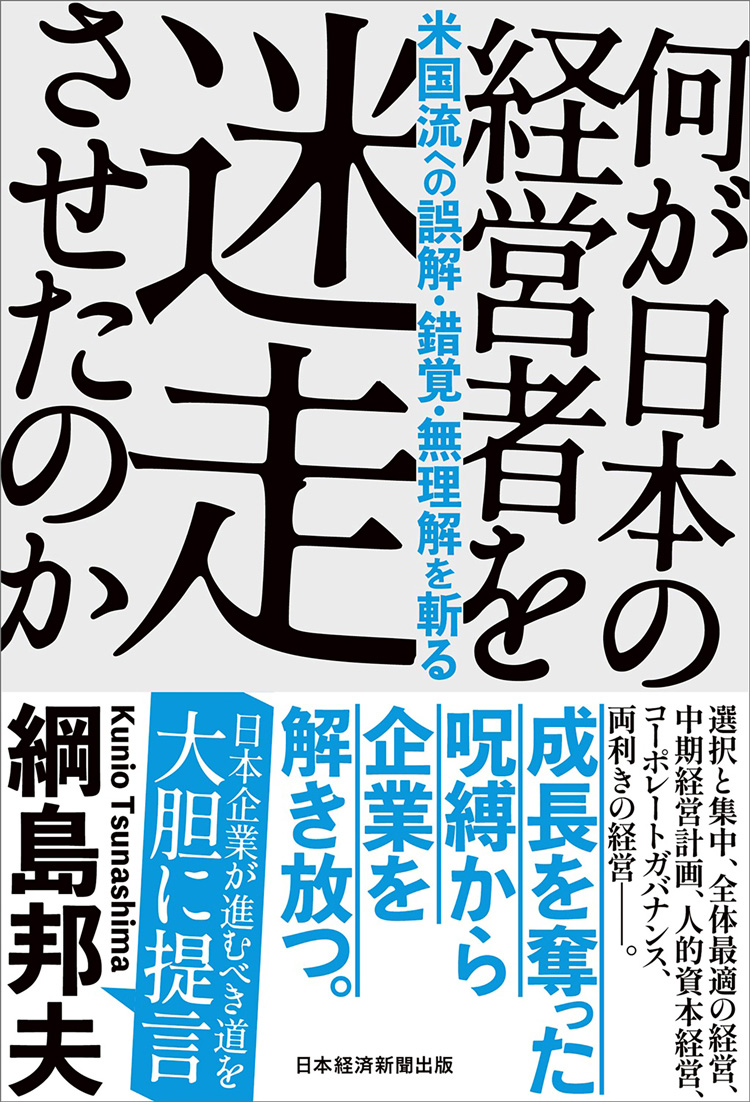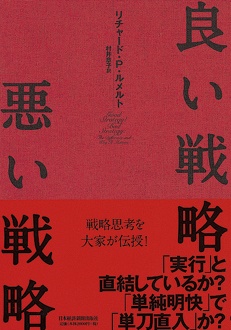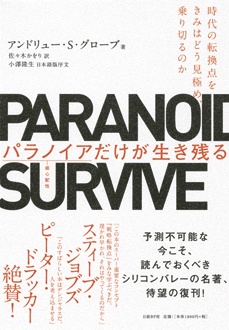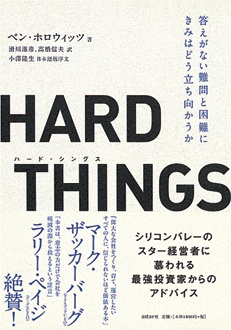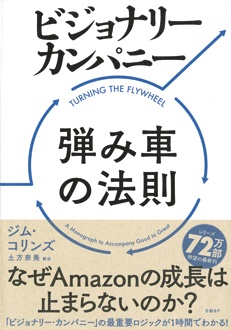2025年12月号掲載
何が日本の経営者を迷走させたのか
- 著者
- 出版社
- 発行日2025年9月24日
- 定価2,750円
- ページ数254ページ
※『TOPPOINT』にお申し込みいただき「月刊誌会員」にご登録いただくと、ご利用いただけます。
※最新号以前に掲載の要約をご覧いただくには、別途「月刊誌プラス会員」のお申し込みが必要です。
著者紹介
概要
リストラ、選択と集中、コーポレートガバナンス…。今や日本では、米国流の経営手法が広く取り入れられている。だが、本来の趣旨を外れ、誤った使われ方をしているものも少なくない。本書は、そんな「米国由来の流行」を取り上げ、日本企業にもたらされる弊害を説く。そして、日本企業が真に行うべき改革を提示する。
要約
捨てるべき米国由来の流行
平成後期に始まり、日本の実業界に広く浸透した米国流の経営。これは、私たちの誤解、錯覚と無理解に基づくものが多く、表層的な導入は日本企業を破滅に導く可能性がある。例えば ――
カタカナ言葉が蔓延している
今日、DXやCEOなどの略語や、米国発のカタカナ言葉が蔓延している。コーポレートガバナンスやサステナビリティ、ウェルビーイングなどだ。
だが、カタカナで表記すると元の言語の意味を理解することなく、表面だけをなぞることになる。
例えば「リストラ」は「リストラクチャリング」を短縮した言葉で、1980年代の米国企業の衰退の原因だった重層的な組織構造と官僚組織という、企業運営の構造を変革する取り組みであった。
しかし、日本ではリストラを構造改革ではなく、単なる人員削減と認識した。そのため、構造は変わらず、新規採用の停止と早期退職制度の導入による人員削減だけが多くの企業で行われた。
米国伝統企業の失われた40年
また、「米国が繁栄している」という見方は誤解である。繁栄しているのはGAFAM(グーグル、アマゾン、フェースブック、アップル、マイクロソフト)など限られた企業だけだ。米国の伝統企業の大半、GEやGMをはじめ、かつて世界を席巻した企業の多くは失われた40年を経験している。
「失われた40年」というのは、米国の伝統企業は1980年代から低迷期に入ったからである。彼らは1990年代に先述したリストラなどに取り組み、部分的には復活の兆候を見せるが、21世紀に入ると一貫して長期衰退の歴史を歩んでいる。
例えば、ゼネラル・エレクトリック(GE)。GEは1981年にジャック・ウェルチ氏が社長に就任すると大改革を実行する。世界1位、悪くても世界2位になる事業に資源を集中するというもので、M&Aで100の事業を入れ替え、従業員の大量解雇を行う。そして、GEの業績は2000年に頂点を迎える。時価総額は世界1位、同氏は賞賛された。
しかし、21世紀のGEを取りまく環境は大きく変貌した。1つは、工業化社会からデジタル社会への急激な移行。もう1つは、20世紀には存在感がなかった中国やアジア諸国の爆発的な成長だ。GEはこの大きな波に乗れなかった。
そして、21世紀のGEは投資家の圧力を受けるようになり、財務偏重の傾向が高まっていく。GEは多くの事業から撤退し、今では航空宇宙事業だけを行う小さな会社になっている。2000年の時価総額は6820億ドル(約100兆円)だったが、2020年には480億ドル(約7兆円)に激減した。