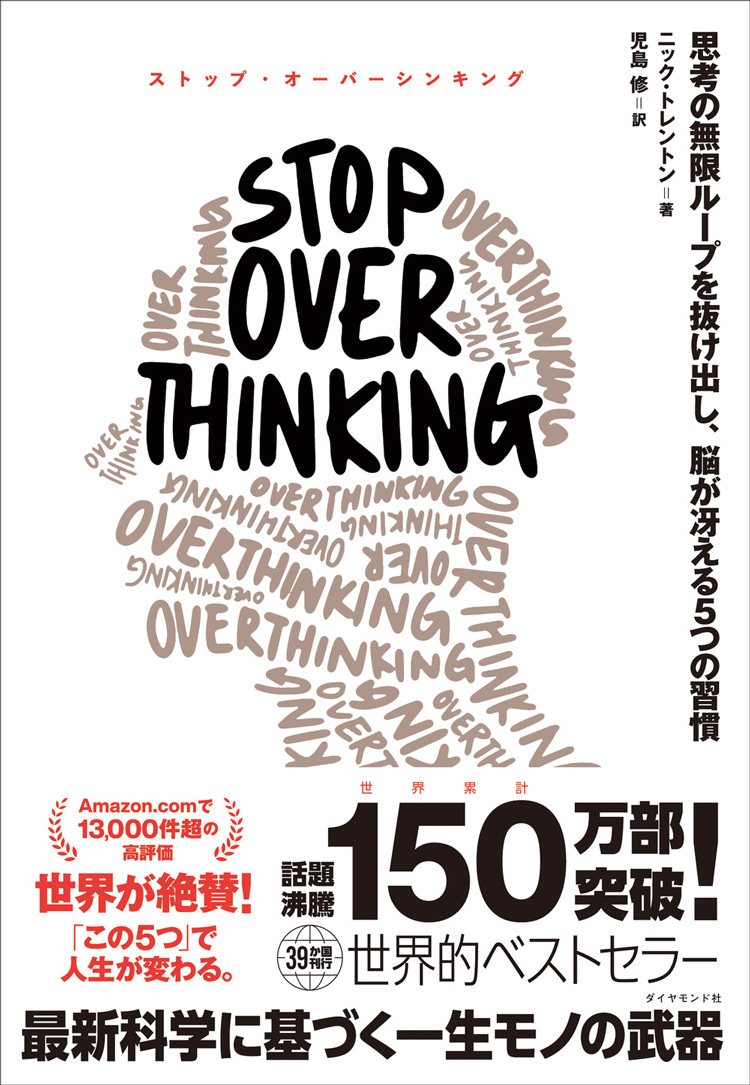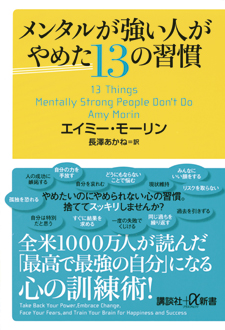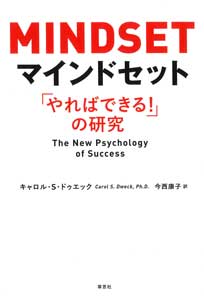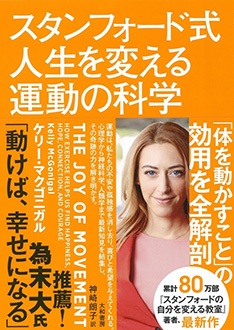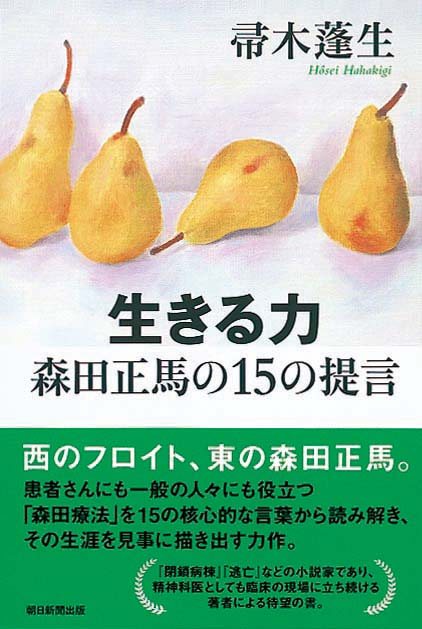2025年11月号掲載
STOP OVERTHINKING ――思考の無限ループを抜け出し、脳が冴える5つの習慣
Original Title :STOP OVERTHINKING (2021年刊)
著者紹介
概要
「OVERTHINKING(オーバーシンキング)」とは「考えすぎ」のこと。心配事が頭から離れず、夜よく眠れなかった、という経験をお持ちの方も多いのでは。そんなネガティブ思考を断つための習慣を紹介。「認識」と「不安」を区別する、心配を先のばしする等々、最新科学に基づく具体的なテクニックの数々が披露される。世界39カ国刊行のベストセラー。
要約
「考えすぎ」の恐ろしさ
ある若者が、肩にあざのようなものがあることに気づいた。気になってネットで調べていくうちに「これは重大な病気では?」と不安になる。そして、延々と考え続け、泥沼にハマる ―― 。
「考える」ことは、問題を解決するための行為だ。だが、「考えすぎる」と逆に問題が生まれる。
「考えすぎ」が問題となるケース
考えすぎが問題になるのは次のようなケースだ。
- ・次から次へと湧いてくる考えに気を取られる。
- ・「考えている自分」について考えている。
- ・自分の考えを常に疑い、分析し、評価している。
考えすぎ(オーバーシンキング)の本質は、その名に示されている。つまり有益なレベルを超え、過度(オーバー)に考え込んでしまうことなのだ。
人間の思考には素晴らしい力がある。思考は自らの思考すら考える対象にし、分析し、問いかけができる。だからこそ、人類はこれまで多くを成し遂げてきた。
だが考えすぎると、その力が損なわれてしまう。
考えすぎを甘く見る人が見逃す3つの影響
大半の人は、考えすぎは大した問題ではないと考えている。だが、それは大間違いだ。考えすぎを甘く見る人は、次の3つの甚大な影響を見逃す。
①長期的・短期的な影響
動悸、頭痛、吐き気、筋肉の緊張、震えや痙攣、記憶力の低下など。
②精神的・心理的な影響
疲労感、神経過敏、イライラ、集中力や意欲の低下、抑うつなど。
③社会的・環境的な影響
親密な人間関係への悪影響、仕事でのパフォーマンス低下など。
そして、考えすぎが常態化すると、体内にはコルチゾールなどのストレスホルモンが大量に分泌される。するとイライラが募り、さらに考えすぎ、ストレスが増し、ネガティブな気分になる。