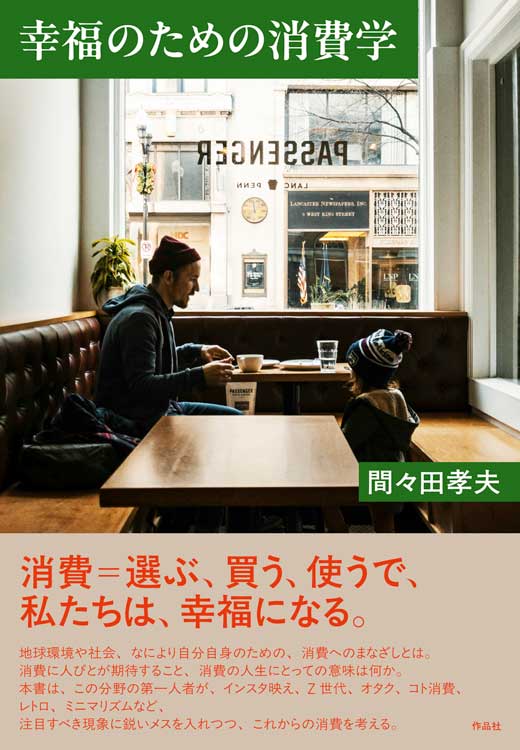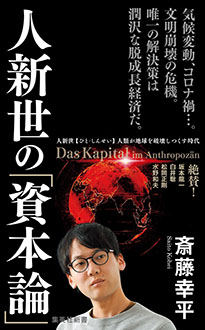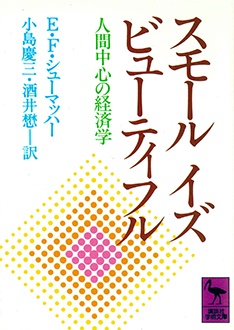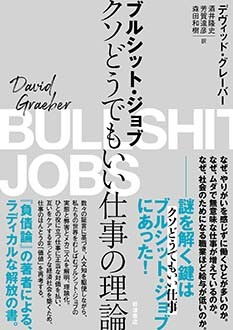2025年10月号掲載
幸福のための消費学
著者紹介
概要
幸福をもたらす消費とはどのようなものか? 消費研究の第一人者が、近年のトピックスをもとに考察した。昭和レトロブーム、ミニマリズム…。様々な現象から導き出したのは、「文化」の豊かさを求めることと、「社会」に悪影響を及ぼさないこと。これらを両立させることが幸福のカギだとし、目指すべき消費のあり方を示す。
要約
ノスタルジーでもレトロでもなく
「幸福のための消費」
このテーマに対する反応の1つは、消費は好きなものを買って使うのだから幸福をもたらすに決まっている、というものだろう。
しかし、そうではない。消費はただ量を増やせばいいというものではなく、何を目指し、どんなものをどう消費するかということを真剣に考えなければ、より幸福な段階には進んでいかない。
こうした考えに基づき、現在の消費社会で起きている注目すべき現象を読み解いてみよう ―― 。
消費社会と古いもの
消費社会は、限りなく新しいものを追い求める社会だ。毎年流行が変わって、今年売っているものは、来年にはたちまち古いものとして扱われる。
このように新しさを求める社会では、新しいものが作られる分だけ、古いものがどんどん増えていく。そしてその多くは見捨てられる。
しかし、一度見捨てられながら復活するものも少なくない。20世紀末以降、その動きは特に強まっている。例えば、昭和時代の街並みを再現する動きが多数あること、昭和歌謡が人気であることなど、古いものの見直しの動きは数知れない。
ノスタルジー消費の意味
このような動きについて、社会学などでは「ノスタルジー」の心理が注目されてきた。この言葉は、過去を懐かしむ感情として広く用いられる。
学問上、ノスタルジーは社会が大きく変化する時に現れるものとされた。幸福で安定した状態から不安定な状態になった時、精神の安定を保つ働きをするのがノスタルジーだと考えられたのだ。
この考え方を現在の日本に当てはめることは一応可能だろう。日本では長く続いた産業発展と経済成長がストップし、閉塞感が強まっている。だからこそ、活気があり発展を謳歌していた高度成長期やバブル期が懐かしがられるのだ、という仮説が立てられている。
しかし、昨今の古いもの消費のブームを観察する限り、私にはこの説明が妥当だとは思えない。