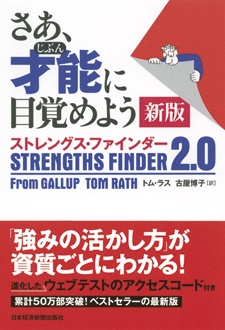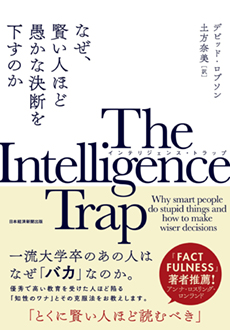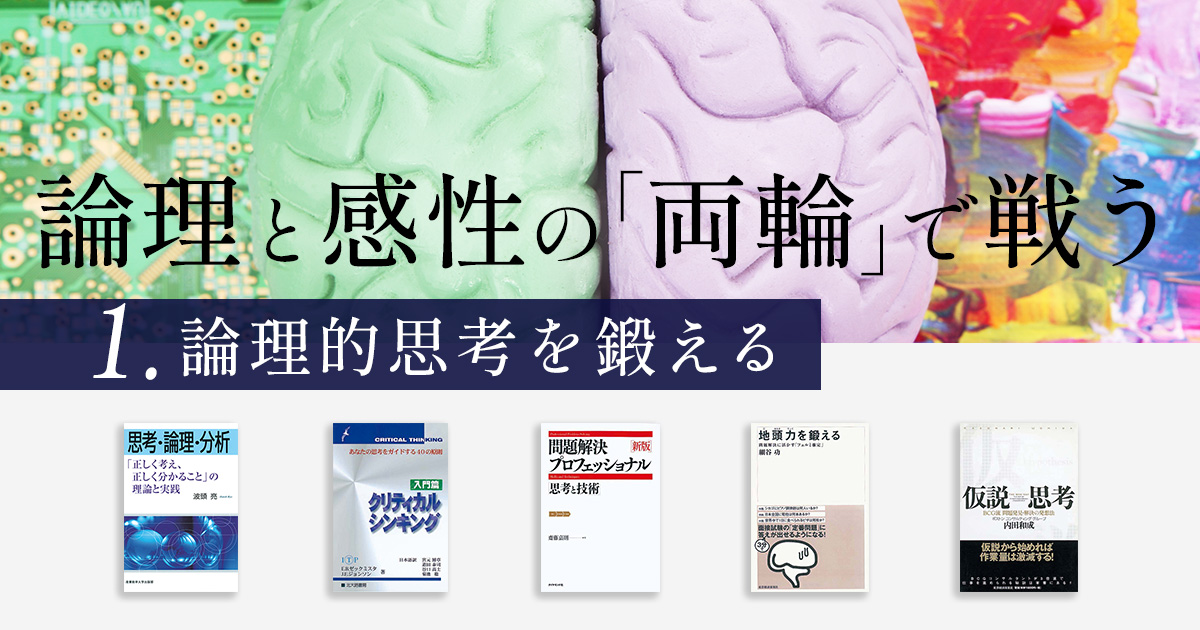2019年8月号掲載
思考・論理・分析 「正しく考え、正しく分かること」の理論と実践
著者紹介
概要
論理的思考の本質や方法論を、体系的に学ぶことができる“教科書”だ。「思考とは何か」「論理とは何か」といった基本的な定義や、物事を理解するための要件、正しい論理展開の仕方など、理論から実践までを丁寧に解説。単なるマニュアル本ではない、人間の基礎的能力である思考の力を徹底して強化できる1冊である。
要約
思考とは
論理的思考 ―― 。この能力を身につけるには、どうすればよいのか。
それは「思考」の力を強化することに尽きる。
論理的思考は、「論理」と「思考」に分けて学ぶことができる。思考することの本質と方法論を理解し、それを論理的に行えば、論理的思考が可能になる。まずは、思考について説明しよう。
思考の定義
思考とは、「思考者が、思考対象に関して何らかの意味合いを得るために、頭の中で情報と知識を加工すること」と定義できる。
ここでいう情報とは、情報収集によって得られた外からの情報と、思考者がもともと持っている知識の両方を含む。思考とは、頭の中で行われるこれら2種類の情報を加工する作業なのである。
思考のメカニズム
情報の加工は、“情報と情報を突き合わせる”作業から成り立つ。「突き合わせる」とは、「比べる」こと。思考者は比べることによって、「同じ部分」と「違う部分」を見極めているのだ。
つまり、思考とは、ある情報と別の情報とを“突き合わせて比べる”プロセスを通して、同じ部分と違う部分の認識を行うことなのである。このメカニズムを別の角度から表現すると、「分かる」こととは「分ける」こと、ということになる。
そして、この思考作業を経て、思考対象を構成する要素が、同じと違うに正しく分け尽くされた状態に辿り着くことが、「分かる=判る=解る」ということなのである。
「分ける」ための3要件
正しく分かるためには、正しく分ける必要がある。そのために必要な要件は、次の3つである。
①ディメンジョンの統一
ディメンジョンとは、“抽象水準”“思考対象・思考要素が属する次元”のことを指す。適切に分けて比べるためには、比べようとしている事象や要素が同一抽象水準上・次元上になければならない。
例えば、「野菜とりんごはどちらが好きか」という質問があったとする。この比較は、2つの対象の抽象水準が揃っていない。“野菜”と比べるのなら“果物”であるべきだ。“りんご”と比べるのなら“にんじん”などの個別の野菜でなければならない。ディメンジョンが異なるもの同士を比べても、正しく分かることには繋がらない。