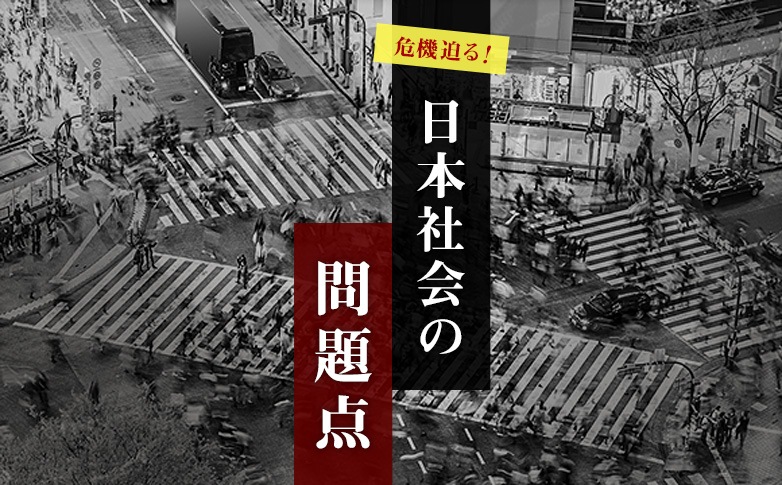男女ともに今後も延び続けると予測される、日本人の平均寿命。
2016年に男性80.98歳、女性87.14歳だった平均寿命は、推計によると、2065年は男性84.95歳、女性91.35歳になり、やがて “人生100年時代”が到来すると見られています。
「一定の年齢を迎えたら退職し、趣味を謳歌したい」「培ったスキルを活かして働き続けたい」等々、“第2の人生”に対する思いは人それぞれでしょう。
とはいえ、どのような生き方を選ぶにしても、心身ともに健康でなければ、思い通りに過ごせません。
そこで今回の特集では、
2016年に男性80.98歳、女性87.14歳だった平均寿命は、推計によると、2065年は男性84.95歳、女性91.35歳になり、やがて “人生100年時代”が到来すると見られています。
「一定の年齢を迎えたら退職し、趣味を謳歌したい」「培ったスキルを活かして働き続けたい」等々、“第2の人生”に対する思いは人それぞれでしょう。
とはいえ、どのような生き方を選ぶにしても、心身ともに健康でなければ、思い通りに過ごせません。
そこで今回の特集では、