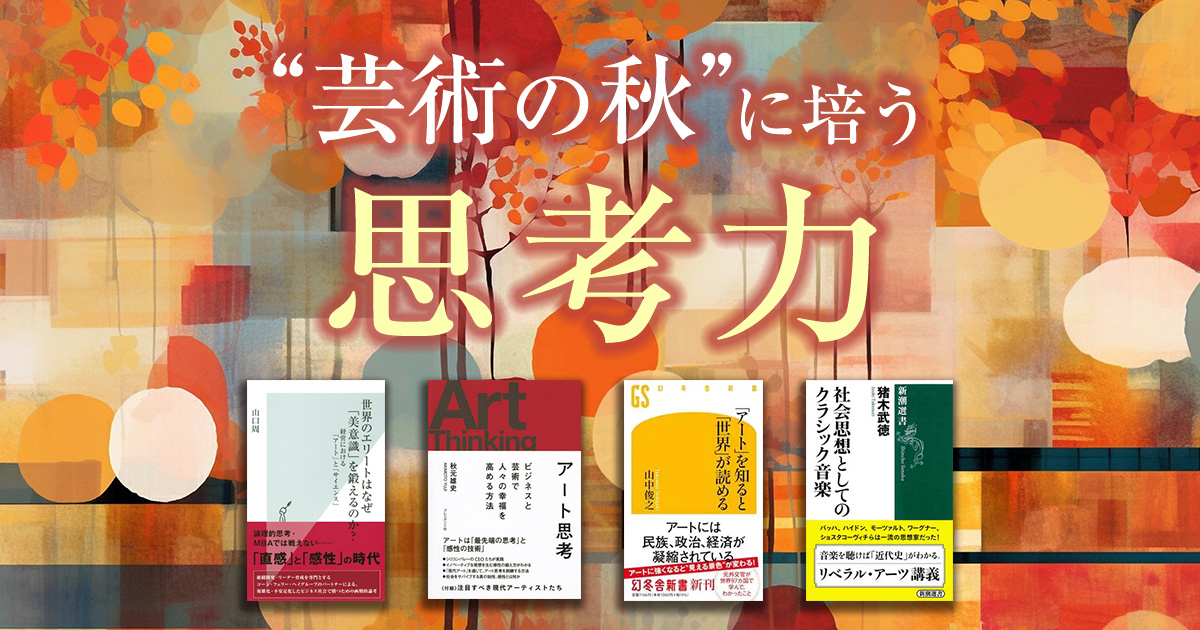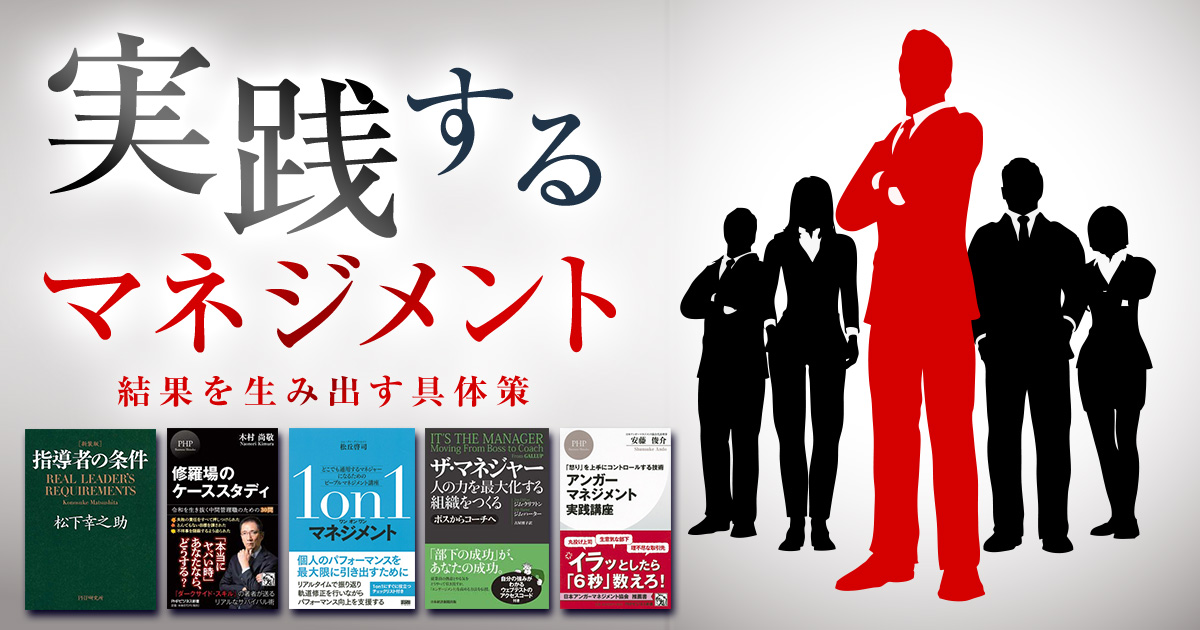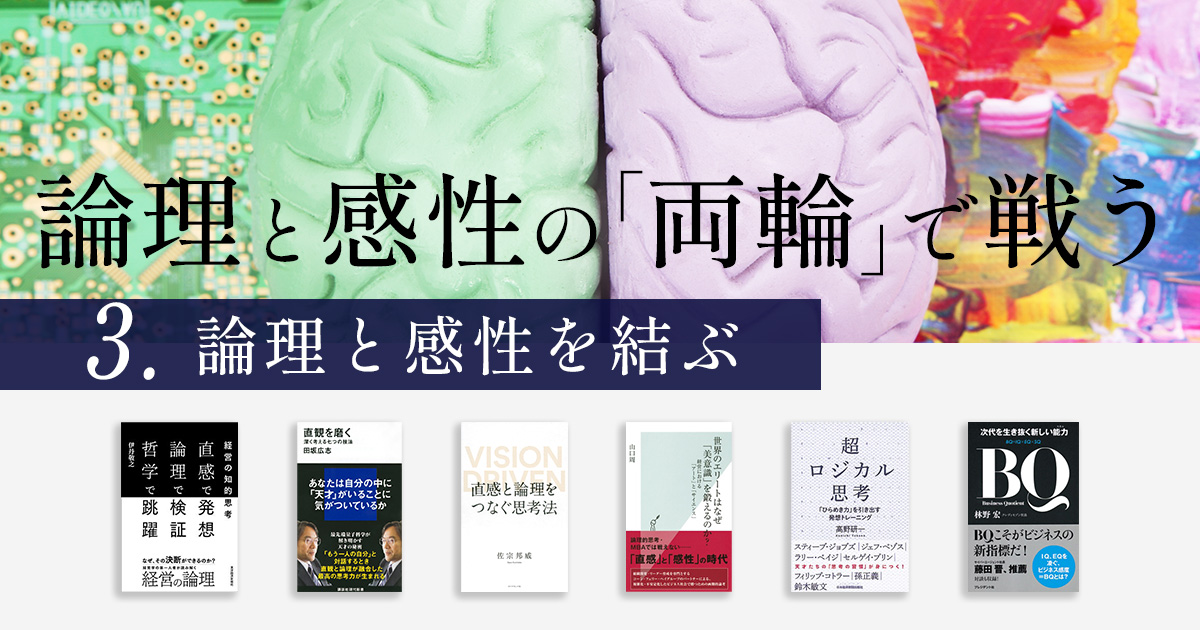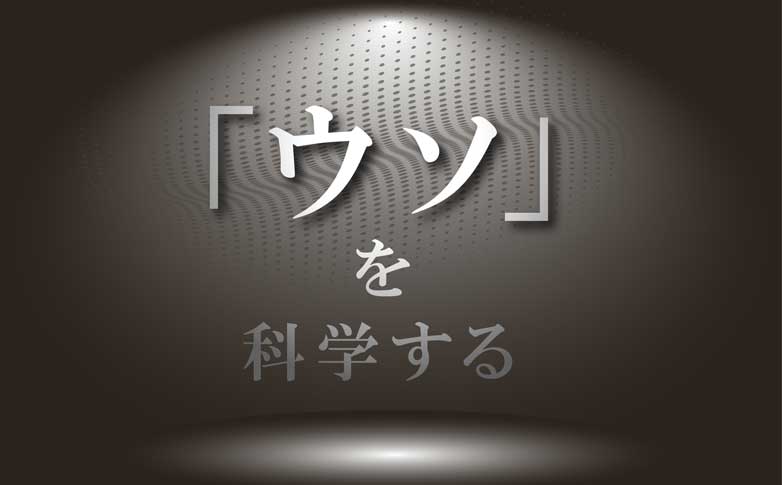
「嘘には3種類ある。普通の嘘と、真っ赤な嘘と、統計だ」
19世紀イギリスの首相ベンジャミン・ディズレーリが語ったとされるこの言葉。数字の説得力を支えるために統計が使われることを表したものとして知られています。裏を返せば、人がいかに数字に騙されやすいかを示した言葉とも言えるでしょう。
では、なぜ人は数字に惑わされ、「ウソ」を信じてしまうのか? そうしたウソに騙されないためにはどうすればよいのか?
今回は、ウソと人間の心理について科学的に分析した5冊を選書しました。
記憶の不確かさから、ウソを誤信する脳の働き、
19世紀イギリスの首相ベンジャミン・ディズレーリが語ったとされるこの言葉。数字の説得力を支えるために統計が使われることを表したものとして知られています。裏を返せば、人がいかに数字に騙されやすいかを示した言葉とも言えるでしょう。
では、なぜ人は数字に惑わされ、「ウソ」を信じてしまうのか? そうしたウソに騙されないためにはどうすればよいのか?
今回は、ウソと人間の心理について科学的に分析した5冊を選書しました。
記憶の不確かさから、ウソを誤信する脳の働き、