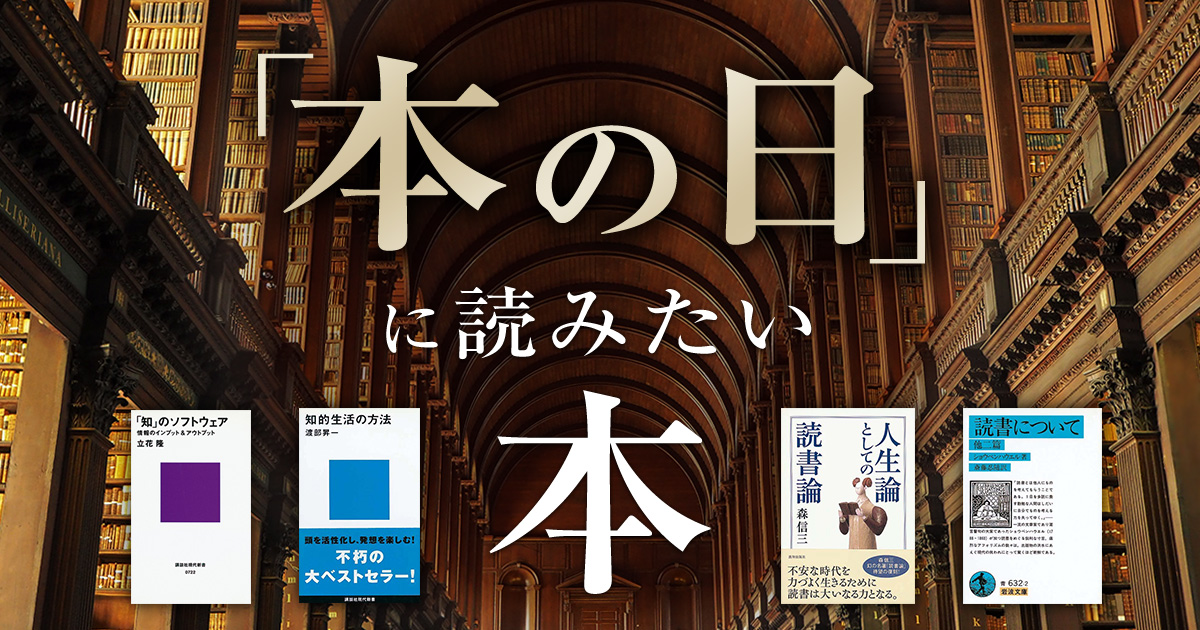
11月1日は「本の日」です。日付が「11」と「1」で本棚に本が並ぶ姿に見える。想像・創造の力は「1」冊の本から始まる。こうしたことから、記念日に認定されたのだそうです。
今回は、そんな「本の日」にちなんで、読書をテーマとする良書4冊をセレクトしました。
各書籍には、読書をより知的なものにする優れたヒントが詰まっています。情報のインプット・アウトプットの仕方、本の選び方や読み方、読書を日々の習慣にするための訓練…。「知の巨人」らが実践していた読書術は大いに参考になることでしょう。
これらの書籍との出合いが、本か
今回は、そんな「本の日」にちなんで、読書をテーマとする良書4冊をセレクトしました。
各書籍には、読書をより知的なものにする優れたヒントが詰まっています。情報のインプット・アウトプットの仕方、本の選び方や読み方、読書を日々の習慣にするための訓練…。「知の巨人」らが実践していた読書術は大いに参考になることでしょう。
これらの書籍との出合いが、本か








